AI問診は業務効率化のため、採用には関係ないのでは?
院長先生や看護部長、人事担当の方とお話ししていると、時々こんなご質問をいただきます。WEBやAIを活用した問診システムは、あくまで日々の業務を効率化するためのもので、看護師の採用や定着といった人事面の課題とは直接結びつかないように感じられるかもしれません。私の考えとしては、これらのツールをうまく活用し、運用を工夫することで、看護師の働きやすさが向上し、結果として採用や定着にも良い影響を与えうると感じています。
本稿では、代表的なWEB/AI問診システムであるユビーAI問診、メルプ、SymView(シムビュー)の3つを取り上げます。そして、主に小規模の病院やクリニックで公開されている具体的な導入事例をもとに、これらのシステムがどのように看護師の働きやすさにつながり、離職の抑制や応募者の増加に結びついていくのか、その道筋を一つひとつ丁寧に、淡々と整理していきたいと思います。途中では、現場で実践して「これはやってみてよかった」と感じられるような、具体的な運用の工夫についても触れていきます。
この記事は、あくまで診療現場の方々が、新しいツールの導入に対して理解を深め、安心して検討を進めるための材料となることを目指しています。そのため、詳細なシステム仕様や投資対効果(KPI)の分析に深く立ち入ることはしません。価格や具体的な数値については、一般に公開されている情報の範囲で引用し、参照元へのリンクを併記する形をとっています。
なぜ「問診の質と運用」が看護師の働きやすさに影響するのか
外来で働く看護師が「今日も疲れたな」と感じる負担の多くは、実は一つひとつの大きな業務よりも、細かな業務の積み重ねによって生じていることがあります。例えば、ひっきりなしにかかってくる電話への対応、受付での患者さんへの説明、紙の問診票の内容をヒアリングし直す作業、それを電子カルテに手で入力する時間、そして会計前後のこまごまとした案内などです。これらは一つひとつは小さな作業かもしれませんが、次から次へと発生し、看護師が本来集中したいケア業務の時間を圧迫していきます。
特に、従来の紙の問診票や口頭でのヒアリングが中心の運用では、いくつかの課題が生じがちです。まず、患者さんが書いた内容を電子カルテに転記する手間が発生します。走り書きで読みにくい文字を解読したり、内容を要約したりする作業は、思いのほか時間を要します。また、問診票だけでは情報が足りず、診察前に再度同じような質問を繰り返す「聞き直し」も頻繁に起こります。これにより、患者さんを待たせてしまうことも少なくありません。さらに、必要な情報が漏れてしまったり、聞き忘れたりすることで、診察がスムーズに進まない原因にもなります。
こうした状況は、患者さんからの不満にもつながりやすくなります。「待ち時間が長い」「同じことを何度も聞かれる」「説明が足りない」といったご意見は、多くの場合、看護師が直接受け止めることになります。これが続くと、看護師の心理的な負担は少しずつ大きくなっていきます。また、転記や聞き直しといった作業に時間がかかれば、それが積み重なって残業の原因にもなりかねません。
逆に、もし来院前から受付、診察、そして会計までの一連の流れがスムーズに整っていたら、どうでしょうか。患者さんが来院する前にWEBで問診を済ませてくれていれば、受付での手間が減ります。問診内容が自動で電子カルテに連携されれば、転記作業は不要になります。診察前に必要な情報が整理されていれば、医師も看護師も効率的に動くことができ、結果として患者さんの待ち時間も短縮されるかもしれません。
このような環境では、残業が自然と減り、患者さんからのクレームも少なくなる傾向があります。業務の流れが仕組み化されているため、新しく入ったスタッフでも比較的早く仕事に慣れることができるでしょう。これこそが、求職中の看護師が「この職場なら、落ち着いて長く働けそうだ」と感じる、いわゆる「求人で選ばれる職場」の具体的な姿に近いのではないかと思います。
この文脈において、AIやWEBを活用した問診システムは、単なる業務効率化ツールにとどまらず、外来全体の業務フローを支える「骨格」のような役割を果たす可能性を秘めているのです。
WEB/AI問診がもたらす変化:3つのツールの具体例から
それでは、実際にこれらの問診システムを導入したクリニックや病院では、どのような変化が起きているのでしょうか。ユビー、メルプ、SymViewそれぞれの公開されている事例から、看護師の働きやすさにどうつながるのかを見ていきましょう。
ユビーAI問診:診察前の情報収集を効率化し、患者との対話を豊かに
ユビーAI問診は、患者さんがタブレットやスマートフォンで症状に関する質問に答えていくと、AIが関連する病気の可能性などを分析し、医師向けの電子カルテ用サマリーを生成するシステムです。この「診察前」のプロセスを効率化することに大きな特徴があります。
- 竜王みついクリニック(山梨県)の事例
- このクリニックでは、以前は紙の問診票を運用しており、その内容を電子カルテに転記する作業が大きな負担となっていました。ユビーを導入した結果、患者さんが入力した問診内容が自動でカルテ形式に整理されるため、この転記作業がほぼゼロになったといいます。導入後の効果として、公式サイトの事例紹介では「実質的な勤務時間を毎日2時間削減できた」という具体的な声が紹介されています。これは、看護師だけでなく医師の負担軽減にもつながり、結果として生まれた時間を、問診データの精査や患者さんとのコミュニケーションに充てられるようになったとのことです。看護師にとっては、単調な入力作業から解放され、より専門性を活かせる業務に集中できる環境が整った例と言えるでしょう。
- 複数のクリニックで見られる導入のねらい
- ユビーの導入事例ページを見ると、多くのクリニックが共通して「外来業務の効率化」と「患者さんの待ち時間短縮」を目的として挙げています。業務効率化は多くの医療機関にとっての課題ですが、特に問診業務は改善の余地が大きい部分です。ユビーの導入によって、診察が始まる前に質の高い情報が揃うため、診察そのものがスムーズに進み、結果として外来全体の流れが改善されたという声が多く見られます。
- 患者さんの主観的な待ち時間を減らす工夫
- ある事例では、「待ち時間と感じさせない時間をつくる」という考え方が紹介されています。患者さんは待合室でただ待っていると15分が長く感じられますが、その時間にタブレットでユビーの問診に回答してもらうことで、集中して取り組むため、体感時間を短くできるというのです。これは、看護師が「お待たせして申し訳ありません」と繰り返し謝る心理的な負担を軽減する効果も期待できます。
これらの事例から見えてくるのは、ユビーAI問診が、カルテ転記や情報の聞き直しといった「診察前の非効率」を解消することで、看護師の業務負担を直接的に減らす可能性です。残業が常態化しにくい環境は、働きやすさの基盤となります。また、診察に必要な情報が事前に整理されていることで、看護師は患者さんとのコミュニケーションやケアといった、本来の業務により多くの時間を割けるようになります。こうした日々の業務における満足度の向上は、職場見学や面接の際に、施設の雰囲気として自然と求職者に伝わる重要なポイントになり得ます。
メルプ:カルテ連携と口コミ運用で、外来業務の全体像を整える
メルプは、クリニックが独自の問診を柔軟に作成できるWEB問診システムです。多くの電子カルテとの連携に対応している点や、問診後の患者さん向けアンケート機能が充実している点が特徴です。
- 市川すずき消化器・内視鏡クリニック(千葉県)の事例
- このクリニックは、1日に内視鏡検査が約20件、外来患者さんが約80名と、非常に多忙な現場です。メルプを導入し、受付から問診、そして電子カルテへの連携までをスムーズに行えるようにしたことで、業務効率が大幅に改善されたと報告されています。導入事例の中では、「人件費の代替」という表現を用いて、その効果を説明している部分もあり、システムが業務の一部を担うことで、スタッフの負担を大きく軽減している様子がうかがえます(ベンダーの自社サイトでの事例紹介のため、表現の解釈には幅がありますが、現場の体感として参考になります)。
- Googleビジネスプロフィール(口コミ)との連携機能
- メルプのユニークな機能の一つに、問診回答後の患者さんに対してアンケートを送り、その結果をもとにGoogleビジネスプロフィールへの口コミ投稿を促す仕組みがあります。患者さんの満足度が高かったタイミングで口コミを依頼することで、良い評価が集まりやすくなります。これは、クリニックの評判をオンライン上で高めることにつながります。採用の観点から見ると、求職中の看護師は、応募前に必ずと言っていいほどクリニックの評判をインターネットで調べます。その際に、患者さんからのポジティブな口コミが多ければ、「患者さんから信頼されている、雰囲気の良いクリニックなのだろう」という良い印象を抱きやすくなります。
- 小児科や在宅医療など、多様な現場での活用
- メルプの導入インタビューページを見ると、様々な診療科での活用事例が共有されています。例えば、小児科では保護者の方が入力しやすいように、質問の言葉遣いをやさしくしたり、専門用語を避けたりといったカスタマイズを行っています。また、紹介状の情報を問診内容から自動で作成する機能などもあり、これまで看護師や事務スタッフが行っていた「二度手間」になりがちな作業を減らす工夫が紹介されています。
メルプの事例から考えられるのは、問診を起点として、外来業務全体の流れを可視化し、改善していくアプローチです。看護師にとって、患者さんが来院前にきちんと情報を入力してきてくれる状態は、受付での案内や説明の負担を大きく減らします。これにより、クレーム対応に追われる時間が減り、心穏やかに業務に集中できます。業務フローがシンプルになることは、新しく入職したスタッフへの教育もしやすくなるため、早期離職を防ぐ効果も期待できるでしょう。
SymView:順番管理や決済との連携で、待ち時間のストレスを減らす
SymViewは、WEB問診機能に加えて、他のシステムとの連携に強みを持つサービスです。特に、受付の順番管理システムや決済システムと連携することで、患者さんの「待ち時間」に関する課題解決を目指しています。
- 受付・順番管理アプリ「Airウェイト」との連携
- 多くのクリニックで導入されているリクルートの「Airウェイト」とSymViewは連携が可能です。これにより、患者さんは自宅や外出先からスマートフォンのAirウェイトで順番を取り、その待ち時間にSymViewでWEB問診を済ませることができます。クリニック側からすると、患者さんが来院する前に順番受付と問診の両方が完了しているため、来院後の受付業務が非常にスムーズになります。待合室での滞在時間を短縮し、紙の問診票を記入してもらう手間を省くという、明確な目的を持った連携です。
- 小児科での高い入力率を達成した事例
- ある導入事例の記事では、小児科クリニックでWEB問診の入力率が80%を超えたケースが紹介されています。小児科では、お子さん本人ではなく保護者が入力するため、いかに簡単で分かりやすいかが重要になります。このクリニックでは、シンプルな院内案内や、家族が代理で入力しやすい操作性が、高い利用率につながったと分析されています。
- 自由診療におけるスマート決済との連携
- SymViewは、自由診療の分野で、クレジットカード情報を事前に登録してもらうことで、診察後に会計窓口に寄らずに帰れる「スマート決済」の仕組みも提供しています。保険診療と自由診療が混在する外来では、会計待ちの行列がボトルネックになることが少なくありません。この仕組みを使えば、自由診療の患者さんは診察が終わればそのまま帰宅できるため、会計窓口の混雑を緩和できます。看護師にとっては、会計待ちの患者さんへの声かけや呼び出しといった業務が減り、外来全体の流れがスムーズになります。
SymViewの事例が示唆するのは、問診を単体で捉えるのではなく、受付から会計までの一連の患者体験と業務フローの中で捉え直す視点です。順番管理や決済との連携は、患者さんだけでなく、スタッフにとっても「イライラがたまりやすいポイント」を解消する効果があります。特に、会計前の行列や、患者さんを何度も呼び出す作業は、看護師にとって地味ながらもストレスのたまる業務です。一日の業務の「終わりが見える」外来、つまり、おおよその退勤時間が予測しやすい職場は、看護師にとって勤務終了後の予定が立てやすく、働き心地が良いと感じられます。こうした日々の働きやすさが、結果的に定着率の向上や、求人応募時の良い評判につながっていくと考えられます。
採用につながるWEB/AI問診の導入・運用の工夫
ここまで見てきたように、問診システムはただ導入するだけでなく、その運用を工夫することで、より大きな効果を発揮し、看護師の働きやすさ、ひいては採用力の向上へとつなげることができます。ここでは、そのための具体的な4つのアプローチをご紹介します。
1. 「来院前に7割の準備が終わる」流れをつくる
- 来院前の入力を徹底して案内する
- 理想は、患者さんの多くが来院する前に問診入力を済ませてくれている状態です。そのためには、予約や順番受付をした患者さんに対して、WEBサイト、予約完了時の自動返信メール、SMS(ショートメッセージサービス)、あるいはLINE公式アカウントなどを通じて、事前問診への協力を丁寧に案内することが重要です。院内の掲示物でも「ご自宅で問診を済ませていただくと、院内での待ち時間が短縮できます」といったメリットが伝わるような案内を心がけましょう。先に紹介したSymViewとAirウェイトの連携のように、「順番を待ちながら問診を入力してもらう」という流れも、患者さんにとって自然で受け入れやすい方法です。
- 最初のうちはスタッフが丁寧に伴走する
- 特に導入初期は、操作に不慣れな患者さんもいらっしゃいます。例えば、午前中の特定の時間帯を「タブレット問診サポートタイム」のように設定し、初診の患者さんや高齢の患者さんには、受付スタッフや看護師が付き添って一緒に操作を手伝う時間を設けるのも一つの方法です。一度体験して便利さを感じてもらえれば、次からは自宅で入力してくれるようになる可能性が高まります。
2. 職種ごとに「見るべき情報」の焦点を決めておく
- 役割分担で情報の見落としを防ぐ
- WEB/AI問診で得られる情報は非常に豊富ですが、全員がすべての情報を同じように読み込む必要はありません。あらかじめ、職種ごとにチェックするポイントを決めておくと、効率的かつ安全に情報を共有できます。
- 医師
- 重症度を示唆するサインはないか、鑑別診断のヒントになる情報はないか、といった医学的な判断に関わる部分を重点的に確認します。
- 看護師
- バイタルサインの情報、感染症の兆候(発熱や咳など)、アレルギー歴、来院時の移動で介助が必要かなど、ケアや院内での案内に必要な情報を中心に確認します。
- 受付スタッフ
- 保険証の種類や変更の有無、連絡先の確認など、事務手続きに必要な情報をチェックします。
- このように役割分担を明確にすることで、情報の見落としを防ぎ、それぞれの専門性を活かした対応が可能になります。ユビーの事例にもあったように、診察室での機械的な質問が減ることで、医師や看護師は患者さんとのより本質的な対話に時間を使えるようになります。
3. 会計やクレームといった「滞りやすい部分」を先回りして解消する
- 会計待ちの時間をできるだけなくす
- 外来の最後に発生しがちな会計待ちの行列は、患者さんにとってもスタッフにとってもストレスの原因です。SymViewの事例で紹介した自由診療のオンライン決済や事後決済は、この課題に対する有効な解決策の一つです。保険診療が中心の場合でも、自動精算機を導入したり、クレジットカードや電子マネーなど多様な決済手段に対応したりすることで、会計窓口の混雑を緩和することができます。会計がスムーズになることは、看護師が最後の案内にかける時間を減らし、結果として退勤時間にも良い影響を与えます。
- 患者さんの声を早めに把握し、対応する
- メルプのアンケートからGoogle口コミへ連携する機能は、患者さんの満足度を可視化する良い仕組みです。満足度の高い声はスタッフの励みになりますし、万が一、不満の声があった場合でも、それが大きなクレームになる前に早期に把握し、改善策を検討することができます。看護師が直接厳しい意見を受ける場面が減ることは、心理的な安全性の確保につながります。
4. 「私たちの外来で働く魅力」を言葉にして採用活動に活かす
- 日々の働きやすさを具体的に伝える
- これらの取り組みによって生まれた働きやすさを、採用活動の場で積極的に伝えていくことが大切です。求人票やクリニックの採用サイトに、単に「業務効率化を進めています」と書くだけでなく、もっと具体的に、働く人の目線で表現します。
- 例1
- 「多くの患者様が来院前に問診を済ませてくださるので、受付での情報の聞き直しやカルテ入力の手間が少なく、落ち着いて患者様と向き合えます。」
- 例2
- 「順番管理システムと連携しているので、待合室の混雑が少なく、患者様への声かけやご案内がスムーズに行えます。」
- 例3
- 「日々の残業時間が予測しやすくなったので、仕事終わりの予定も立てやすいとスタッフから好評です。」
- ユビー、メルプ、SymViewのいずれを導入した場合でも、それによって看護師が体感しているメリットを、見学や面接に来た求職者に自分の言葉で伝えることが、何よりも説得力のあるアピールになります。
まとめ:自院に合った問診システムを選び、働きやすい環境づくりへ
ここまで、3つのWEB/AI問診システムと、それらが看護師の採用・定着に与える影響について見てきました。どのシステムを選ぶかという点ももちろん重要ですが、それ以上に「どのように運用し、外来全体の流れを整えるか」が、働きやすい職場づくりの鍵となります。
- ユビーAI問診
- AIによる詳細な問診と、それによる「待ち時間と感じさせない時間」の創出が特徴です。カルテ転記などの直接的な作業時間を削減したという具体的な事例もあり、日々の業務負担を軽減したい場合に適していると考えられます。
- メルプ
- 柔軟な問診作成機能や多くの電子カルテとの連携、そしてアンケートから口コミへつなげる仕組みまで含めた、外来の評判づくりを得意としています。多忙な外来の業務を効率化しつつ、クリニックの評価も高めていきたい場合に有効な選択肢です。
- SymView
- 順番管理システムや決済システムとの連携に強みを持ち、受付から会計までの「滞り」を解消することで、患者さんとスタッフ双方のストレスを軽減します。待合室の混雑や会計業務の負担が課題となっている場合に、特に効果を発揮しやすいでしょう。
いずれのシステムも、小規模の病院やクリニックでの活用事例が数多く公開されています。大切なのは、システムを導入して終わりにするのではなく、それをきっかけとして、患者さんが来院する前から診察を終えて帰宅するまでの一連の流れを、スタッフにとって無理のない、スムーズなものへと見直していくことです。これこそが、採用や定着に良い影響を与える「働きやすい外来」を実現するための、最も確実な道のりと言えるのではないでしょうか。
看護師採用の次の一手として
このようにして、問診システムの導入によって外来業務の「土台」が整い、スタッフが落ち着いて働ける環境ができてきたら、次はいよいよ、新しい仲間を募集する段階です。その際には、募集の方法も工夫したいところです。
現場の業務が落ち着いたタイミングは、新しい看護師を迎え入れ、丁寧に業務を教えることができる絶好の機会です。急な欠員補充で慌てて採用するのではなく、計画的に応募者の母集団を広げ、自院の文化に合った人材をじっくりと見極めたい、とお考えでしたら、短期のお試し勤務から始められるような募集媒体の活用が非常に有効です。
実際に数日間一緒に働いてみることで、履歴書や面接だけでは分からない人柄や仕事への姿勢を確認でき、採用後のミスマッチを大きく減らすことができます。詳しくは、看護師の登録者数が多く、お試し勤務のマッチングに強みを持つ「クーラ(施設向け)」(https://business.cu-ra.net/)のウェブサイトをご覧ください。
お試し勤務を活用することで、現場の看護師も新しい候補者と実際にコミュニケーションを取ることができ、「この人となら一緒に働けそうだ」という納得感を持って採用プロセスに進めます。これは、新しい仲間が職場にスムーズに溶け込み、長く定着してくれる上で非常に重要な要素です。
また、募集から面談の日程調整、契約手続きといった労務まわりの手間は、採用担当者にとって大きな負担です。クーラのようなサービスは、お試し勤務に関連する一連のプロセスをデジタル化(DX)することで、こうした負担を軽減するサポートも行っています。外来の業務フローの「滞り」を問診システムで解消した次のステップとして、採用活動の「滞り」を解消するために、クーラ(https://business.cu-ra.net/)のようなサービスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
よくあるご質問
- Q1. 導入にかかる費用は、おおよそどれくらいですか?
- ユビー
- 料金は施設の病床数や利用するタブレットの台数、オプション機能の有無などによって変動します。公式サイトでは料金表のダウンロードを案内しており、個別の見積もりを取ることが確実です。小規模なクリニック向けのプランも用意されています。
- メルプ
- こちらも公式サイトでは資料ダウンロードでの案内が基本ですが、外部の医療系情報サイトなどでは、参考価格として初期費用が165,000円から、月額費用が16,500円から、といった情報が掲載されていることがあります(導入時期や契約内容によって変動する可能性があります)。
- SymView
- 初期費用と月額費用で構成されているようです。標準で用意されている公式問診の利用は無制限ですが、オリジナルの問診票を11枚以上作成する場合は追加費用が発生する、といった料金体系の解説が外部記事で見られます(正確な価格は、資料請求や問い合わせでご確認ください)。
- ユビー
- Q2. 高齢の患者さんが多いのですが、スマートフォンやタブレットでの入力は可能でしょうか?
- 導入初期に、スタッフが付き添って操作をサポートする時間帯を設けるといった工夫で、多くの場合、スムーズに移行できます。SymViewの導入事例では、保護者が代理入力する小児科で80%を超える高い入力率を達成した例も紹介されており、家族のサポートや、分かりやすい院内案内によって、年齢に関わらず利用率を高めることは十分に可能です。
- Q3. 導入すれば、患者さんの待ち時間は本当に短くなりますか?
- 診察時間そのものが劇的に短くなるわけではありませんが、問診情報の転記や聞き直しにかかる時間が削減されることで、外来全体の流れはスムーズになります。また、ユビーが提唱するように、問診入力に集中してもらうことで、患者さんの主観的な「待たされている感覚」を和らげる効果も期待できます。さらに、決済システムとの連携などで会計待ちの行列を解消することも、体感時間の短縮に大きく貢献します。
- Q4. 導入にあたって、スタッフからの抵抗はありませんでしたか?
- 新しいシステムを導入する際には、一時的に業務のやり方を変更する必要があるため、多少の戸惑いが生まれることはあります。大切なのは、導入の目的を事前に丁寧に説明することです。「なぜ導入するのか(目的)」「導入すると、日々の業務がどう楽になるのか(メリット)」「操作で困ったときは、誰がどうサポートするのか(支援体制)」を明確に共有することで、スタッフの不安を和らげ、前向きな協力を得やすくなります。
さいごに
AIやWEBを活用した問診システムは、単に業務を効率化するだけの道具ではありません。それは、看護師が日々の細かな非看護業務から解放され、本来の専門性を発揮して患者さんと向き合うための「土台」を整えるための投資であると考えることができます。
情報の聞き直しやカルテへの転記、待合室の混雑対応や会計の行列といった、日々の業務のボトルネックが一つひとつ解消されていくほど、外来は落ち着きを取り戻し、多くのスタッフが定時で帰れる職場へと近づいていきます。そこで働く看護師が感じている、その素直な「働きやすさ」こそが、何よりの口コミとなり、求職者にとっての「このクリニックで働いてみたい」という魅力につながっていくのではないでしょうか。
まずは、ご自身のクリニックや病院の業務フローに合ったツールを見つけ、来院前から会計までの一連の流れをスムーズにつなげることから始めてみてください。そして、職場環境が整ったタイミングで、クーラ(https://business.cu-ra.net/)が提供する「お試し勤務」のような仕組みを掛け合わせる。これこそが、無理なく着実に、採用力の強化につながる進め方であると、私は考えています。
参考資料
- ユビーAI問診 導入事例・クリニック向け案内
- メルプ 導入インタビュー・機能紹介
- SymView 活用事例・連携・料金関連情報
- 料金に関する外部参考情報
- 目利き医ノ助 (メルプ価格参考)
- CLINICS (ユビー、SymView料金解説)







.avif)
.avif)

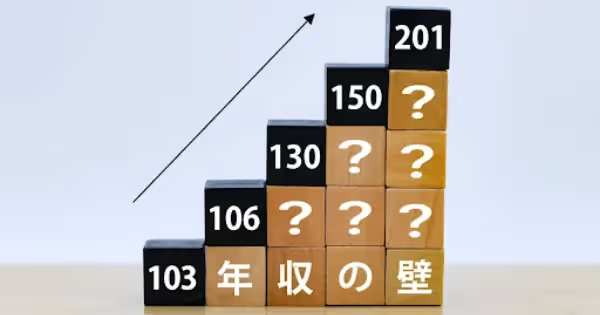
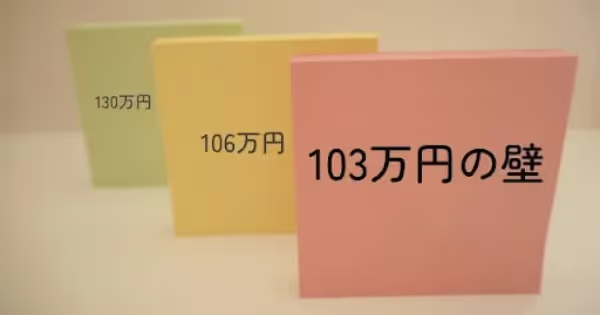







.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
