地方で看護師を採用するとき、「交通費はどこまで支給すべきか」「住宅手当はいくらが妥当か」「寮や社宅は用意したほうが良いのか」といった点で迷う場面は少なくないかもしれません。これらの費用は決して小さなものではなく、設計を誤ると支出だけが増え、期待した効果が得られないという結果につながる可能性もあります。この記事では、一般に公開されている医療機関の情報を参考にしながら、交通費・住宅手当・社宅(寮)の総額をどのように組み合わせ、その投資をいかにして「回収」していくかという視点で、情報を整理していきます。
この記事の途中では、費用対効果を高めるための一つの現実的な方法として、クーラの「お試し勤務」を何度かご紹介します。これは無理におすすめするものではなく、採用のミスマッチを減らし、かけた費用を無駄にしないための自然な選択肢としてご理解いただければ幸いです(リンク先:https://business.cu-ra.net/)。
地方採用で“お金をかける場所”がぶれやすい理由
地方の医療機関にとって、看護師の確保は共通の課題とされています。その理由の一つに、そもそも地域の人口が少なく、採用の対象となる母集団が限られていることが挙げられます。そのため、多くの場合、通勤できる範囲外、時には県外や全国から人材を迎え入れる必要が出てきます。
しかし、遠方からの応募者にとって、転居を伴う就職は金銭的にも精神的にも大きな負担です。その負担を少しでも軽くするために、多くの医療機関が交通費や住宅に関する手当を用意しています。
ところが、求人情報を見てみると、「交通費全額支給」「住宅手当あり」「寮・社宅完備」といった言葉が並んでいるだけで、具体的な金額や条件、対象となる範囲がはっきりと書かれていないケースが見受けられます。
例えば、「住宅手当あり」とだけ書かれていても、
- 毎月いくら支給されるのか
- 世帯主でも単身者でも同じ金額なのか
- 寮に入った場合も支給されるのか
- いつまで支給されるのか
といった情報がなければ、応募者は自分の生活を具体的にイメージすることができません。結果として、魅力的な制度であっても応募の動機づけとしては弱くなり、せっかく内定を出しても、生活費の不安から辞退されたり、入職後に「思っていたのと違った」という理由で早くに離職してしまったりする原因の一つになり得ます。
離職は、目に見えにくいコストを発生させます。公益社団法人日本看護協会が公表した「2023年 病院看護実態調査」によると、2022年度の正規雇用看護職員の離職率は11.3%でした。特に、既卒採用者の1年未満の離職率は16.1%にのぼるというデータも示されており、採用活動がいかに難しいかを物語っています。地方への採用は、応募者本人にとって転居という大きな決断が伴うため、この離職のリスクをより慎重に考える必要があると言えるでしょう。
このような状況を避けるためには、採用側がまず、交通費や住宅に関する支援制度を具体的で分かりやすい形で提示し、応募者の不安を一つひとつ取り除いていく姿勢が大切になります。
実例で見る:交通費・住宅手当・寮(社宅)の“現実的な水準”
では、他の医療機関は実際にどのような条件を提示しているのでしょうか。ここでは、インターネット上で公開されている求人情報や募集要項から、具体的な事例をいくつか拾い上げてみます。これらの事例はあくまで一例ですが、自院の制度を検討する上での参考になるかもしれません。
交通費の明示例:「全額支給」のわかりやすさ
交通費は、毎日の通勤に関わる重要な費用です。特に地方では、公共交通機関が限られ、自動車通勤が中心となることも多いため、応募者はガソリン代や駐車場の費用を気にします。
- 社会医療法人社団森山医会 行徳総合病院(千葉県)の事例
- 新卒採用の募集要項において、住宅手当と並んで「交通費:全額支給」とはっきりと記載されています。応募者からすると、自宅から病院までの距離や定期代の上限などを心配する必要がなく、安心して応募できる一つの材料になります。特に都市部やその近郊では、複数の路線を乗り継ぐことも想定されるため、「全額支給」という言葉は強い安心感を与えるようです。
- 自動車通勤の上限設定例
- 地方の病院では、自動車通勤者に対して距離に応じた上限額を設けている例が多く見られます。例えば、ある病院の規定では「2km以上、上限24,500円まで」のように、具体的な金額が示されています。これは、無制限の支給を避けるための現実的な対応ですが、応募者にとっては「自分の場合はいくらになるのか」が明確になるため、曖昧な表現よりも親切と言えるでしょう。
住宅手当の目安:月額1万円台後半から2万円台が中心か
住宅手当は、支給額が生活設計に直接影響するため、応募者が特に注目する項目の一つです。
- 医療法人社団哺育会 さいたま記念病院(埼玉県)の事例
- こちらの病院では「住宅手当:20,000円(世帯主)、15,000円(単身者)」と、対象者別に具体的な金額を明記しています。さらに「※賃貸・本人契約に限る」といった条件も付記されており、誰がどのような場合に対象となるのかが非常に分かりやすくなっています。
- 社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院(東京都)の事例
- こちらでは「住宅手当:15,000円(世帯主)、12,000円(単身者)」と提示されています。寮に入る職員も対象となるのか、ならないのか、といった点も明記されていると、応募者はさらに検討しやすくなります。
これらの事例から、住宅手当の金額は1万円台後半から2万円台あたりが一つの目安になりそうですが、大切なのは金額の多寡だけでなく、「誰に、いくらを、どのような条件で支給するのか」を具体的に示すことにあると考えられます。
寮(社宅)の補助割合:家賃の半額以上を負担する例も
遠方からの採用では、寮や社宅の存在が決め手になることも少なくありません。その際、単に「寮完備」と書くだけでなく、本人負担額がどれくらいになるのかを示すことが重要です。
- 医療法人財団川崎病院(兵庫県)の事例
- 「ワンルームマンションタイプの寮(オートロック・バス・トイレ・エアコン完備)」を用意し、「寮費:30,000円(別途、住宅手当13,000円支給のため実質負担17,000円)」という形で、実質的な家賃負担額を提示しています。月々の手取り額からいくら住居費として引かれるのかが明確になるため、応募者は入職後の生活を具体的に計算することができます。これは、内定後の辞退を防ぐ上でも有効な伝え方とされています。
- 公益財団法人東京都医療保健協会 代々木病院(東京都)の事例
- 借り上げ寮制度を導入しており、「家賃の約6割を病院が負担」することを明記しています。例えば家賃6万円の物件であれば、本人の負担は約2.4万円になるという計算ができます。さらに、この病院では寮に入居している職員にも別途、住宅手当を支給する例が公表されており、手厚い支援体制がうかがえます。
赴任旅費・引越費用の支給:遠方採用の鍵
県外など、長距離の移動を伴う採用において、初期費用である引越代や交通費の支援は非常に重要です。この支援の有無が、内定を承諾するかどうかの最終的な判断に影響することも少なくありません。
- 地方独立行政法人 長野県立病院機構の事例
- 採用試験の案内の中で、「採用に伴い転居する場合には、規定に基づき交通費、宿泊費、移転料(引越費用)を支給します」と明記しています。公的な機関ではこうした規定が整備されていることが多いですが、民間病院でも同様の制度を設けることで、遠方からの応募のハードルを下げることができます。
- 医療法人徳洲会グループの「トラベルナース」制度
- 全国各地の病院へ期間限定で応援に行く「トラベルナース」の仕組みでは、赴任先での宿舎(家具・家電付き)が提供されることに加え、赴任時の旅費や移転料(引越費用)が規定に基づいて支給されることが明示されています。短期の勤務であっても、移動に伴う本人負担をなくすことで、人材が流動しやすくなるという考え方は、地方での採用戦略を考える上で参考になります。
これらの事例は、北海道や沖縄といった「移住」を前提とすることが多い地域で特に多く見られ、求人サイトなどでも「住宅補助あり」「寮・借上社宅あり」といった条件で検索すると、多くの実例を見つけることができます。
設計の基本:3つの費用を“組み合わせて”説明する
これまで見てきたように、交通費や住宅に関する支援には様々な形があります。地方からの採用を成功させるためには、これらの支援をバラバラに提示するのではなく、応募者が転居してから新しい生活を始めるまでの一連の流れを想定し、必要な費用をセットで示すことが伝わりやすさの鍵となります。
具体的には、以下の3つの費用項目に分けて、それぞれの制度を整理し、分かりやすく説明することが考えられます。
1. 通勤・赴任にかかる費用
これは、新しい勤務地へ移動し、日々の通勤を始めるまでにかかるお金です。
- 通勤交通費
- 公共交通機関を利用する場合、全額支給なのか、上限額があるのか(例:月額50,000円まで)。
- 自動車通勤の場合、距離に応じた規定があるのか、駐車場代は自己負担か、病院が一部補助するのか。
- 赴任旅費
- 遠方から赴任する際の、本人分の交通費(新幹線、飛行機代など)を支給するのか。
- 精算方法は実費か、あるいは一律で金額を決めて支給するのか(例:一律5万円)。
- 家族を伴う場合、家族分の旅費も対象になるのか。
- 移転料(引越費用)
- 引越業者の費用を病院が負担するのか。
- 負担する場合、上限額はいくらか(例:単身者10万円、世帯20万円まで)。
- 費用の精算には領収書の提出が必要か。
- 赴任時の一時金など
- 一部の公的機関などでは、赴任時の支度金として「着後手当」のような一時金が支給される制度もあります。
2. 住居にかかる費用
新しい生活の基盤となる住まいに関するお金です。
- 住宅手当
- 毎月の支給額はいくらか。
- 単身者と世帯主で金額に違いはあるか。
- 寮や社宅に入居している場合も支給対象か。
- 支給期間に上限はあるか(例:入職後10年間まで)。
- 寮・社宅
- 寮費(自己負担額)は月額いくらか。
- 病院が家賃の何割を負担するのか(例:家賃の50%を補助)。
- 光熱費や水道代、駐車場代は寮費に含まれるのか、別途自己負担か。
- 家具や家電は備え付けか。
- 借り上げ社宅制度
- 自分で選んだ物件を病院が法人契約してくれる制度か。
- 家賃の上限額はいくらか。
- 上限を超えた場合の差額は自己負担か。
3. 初期負担の緩和に関する支援
転居時には、敷金・礼金や仲介手数料など、まとまった初期費用が必要になります。この負担を軽減する支援も、応募者にとっては大きな魅力となります。
- 敷金・礼金・仲介手数料の負担
- これらの初期費用を病院が負担、あるいは一部補助する制度はあるか。
- 病院が一時的に立て替え、給与から分割で返済する制度はあるか。
- 提携不動産業者の紹介
- 地域の事情に詳しい不動産業者を紹介してくれるか。
- 病院の提携業者を利用することで、仲介手数料の割引などが受けられるか。
- 一部の看護師紹介会社では、提携不動産業者を通じて「仲介手数料半額」や「最初の1ヶ月の家賃無料」といったサービスを提供している例もあります。
これらの項目について、自院では「何ができて、何ができないのか」を整理し、求人票や採用サイトで明確に伝えることが、応募者の不安を取り除き、信頼感を得ることにつながります。
金額感の目安(制度設計の出発点として)
これから制度を設計、あるいは見直す際に、どのくらいの金額を設定すればよいか迷うかもしれません。以下に示すのは、これまでに紹介した公開事例や一般的な求人情報から見られる水準を基にした、あくまで設計を検討する上での出発点となる目安です。最終的には、各地域の家賃相場や病院の経営状況に合わせて調整することが必要です。
回収シナリオ:投資した費用はどこで取り戻すのか
手厚い支援制度を導入するには、当然ながら相応の費用がかかります。その費用を「コスト」としてだけ捉えるのではなく、「投資」と考え、どのように回収していくのかをあらかじめ想定しておくことが、経営層への説明や制度の継続性を担保する上で重要になります。ここでは、3つの回収シナリオを考えてみます。
シナリオA:内定承諾率の改善で“採用活動の非効率”をなくす
福利厚生を具体的に、かつ魅力的に提示することは、内定辞退者を減らす効果が期待できます。
例えば、年間10名の看護師を採用する目標に対し、これまでの内定承諾率が50%だったとします。つまり、20名に内定を出して、ようやく10名の採用が決まる計算です。もし、住宅支援制度の魅力を高め、その伝え方を工夫することで内定承諾率が60%に改善したと仮定すると、約17名への内定通知で10名の採用が実現できることになります。
これは、面接に要する時間や労力、そして求人広告にかかる費用を圧縮できることを意味します。採用担当者や管理職の時間を他の重要な業務に充てることができ、病院全体の生産性向上にもつながります。
さらに、前述の日本看護協会のデータを参考にすると、既卒採用者の1年未満の離職率は16.1%とされています。もし、充実した住宅支援によって生活基盤が安定し、定着率が向上して、早期離職者が1人でも減ったとすればどうでしょうか。その1人を再び採用するためにかかる数十万から百万円単位の採用コスト(求人広告費や人材紹介手数料など)や、欠員中に発生する他の職員への業務負担、派遣看護師などを依頼する場合の追加費用を回避することができます。
シナリオB:人員の安定確保で“超過勤務や応援体制”を減らす
慢性的な人員不足に悩む病棟では、職員の超過勤務(残業)や、他の部署からの応援勤務が常態化しているケースも少なくありません。これらの超過勤務手当や応援出勤手当は、毎月の人件費を圧迫する大きな要因となります。
地方からの採用で1名の常勤看護師を確保でき、住宅支援によってその職員が1年間、安定して勤務してくれたとします。その結果、病棟の人員体制に余裕が生まれ、これまで恒常的に発生していた月数十万円規模の超過勤務手当を削減できる可能性があります。
この削減額は、年間にすれば百万円を超えることもあり得ます。これは、その職員に投じた住宅支援や赴任費用のコストを十分に回収できる計算になります。具体的な金額は、各病院の時間外勤務の実績などを基に試算してみると、より説得力のあるデータになるでしょう。
シナリオC:“採用広報”としての価値で、応募の質と量を高める
「寮費の実質負担1.7万円」「家賃の6割を病院が負担」「引越費用も支給」といった、具体的で分かりやすい数字は、それ自体が強力な採用メッセージになります。
求人サイトや病院の採用ホームページでこれらの情報を目にした求職者は、「この病院は職員の生活を大切に考えてくれている」という印象を持つかもしれません。結果として、求人広告のクリック率が上がったり、応募者の数が増えたり、あるいはより意欲の高い人材からの応募が集まったりする効果が期待できます。
ただし、ここで重要なのは、求人サイトに書かれている情報と、病院の公式サイトに書かれている情報に食い違いがないことです。両方の情報を一貫させ、誠実な姿勢で情報発信を続けることが、長期的な視点での「採用力」の強化につながります。
回収の確度を高めるための工夫
これらのシナリオの確度をさらに高めるための一つの方法として、「お試し勤務」の仕組みを導入することが考えられます。いきなり転居と正規雇用という大きなステップを踏むのではなく、まずは数日から数週間、短期のアルバイトとして働いてもらい、職場環境や人間関係、地域の雰囲気などを実際に体験してもらうのです。
この「お試し」の期間を通じて、応募者も病院側も、お互いの相性を確認することができます。その上で、双方が合意すれば、正規雇用と本格的な移住支援(住宅手当や赴任費用の支給)へと進む、という段階的なアプローチです。
この方法であれば、ミスマッチによる早期離職のリスクを大幅に減らすことができ、住宅支援などへの投資が無駄になる可能性を低く抑えることができます。クーラのようなサービスは、こうした「お試し勤務」から長期雇用へとつなげる仕組みと親和性が高く、費用を投入する前に、現場での適合性を見極めるための有効な手段となり得ます。https://business.cu-ra.net/
書き方・伝え方のコツ:応募前の“生活不安”を消し去る
制度を整えることと同じくらい大切なのが、その魅力を「どのように伝えるか」です。応募者が知りたい情報を、先回りして分かりやすく提供することで、応募前の不安を解消することができます。
ここでも、「まずはお試しで地域の雰囲気を見てみたい」というニーズに応えるために、短期勤務の受け入れを告知しておくことが有効です。「数回勤務してみて、この地域が自分に合うかどうかを判断してから、本格的な移住を決める」という選択肢を提示することで、応募の心理的なハードルを下げることができます。こうした自然な流れを作る上で、クーラの導入を検討することも一つの方法です。https://business.cu-ra.net/
モデル設計(初期案):3つのパターン比較
どのような支援制度が最適かは、病院の所在地、採用したい看護師の層(新卒か既卒か、単身か世帯かなど)、そしてかけられる予算によって異なります。ここでは、考えられる3つのモデルパターンを比較してみます。自院の状況に最も近いものはどれか、検討の参考にしてください。
特にパターンCのような「短期就業から継続を判断する」という仕組みは、投資の失敗を避ける上で非常に有効です。ここでも、クーラのようなサービスを併用することで、数回の勤務でお互いの不安を減らしてから、本格的な住宅投資に踏み切るという、より安全な採用プロセスを設計することができます。https://business.cu-ra.net/
ケース別Q&A(現場でよく出る迷い)
制度を具体的に検討していくと、細かな点で判断に迷うことが出てくるかもしれません。ここでは、採用担当者からよく聞かれる質問とその考え方をいくつか紹介します。
Q1:寮に入っている職員に、さらに住宅手当を出すべきでしょうか?
A:これは意見が分かれる点ですが、実際に「入寮者にも一律で少額の住宅手当を支給する」という設計を採用している病院は存在します。その背景には、寮に入らない職員との公平性を保つという考え方があります。住宅手当は給与の一部という側面もあるため、寮に入ったことで手当が全くもらえなくなると、「寮は家賃が安いけれど、トータルで見ると損をしている」と感じさせてしまう可能性があります。特に若い職員の納得感を得るための配慮として、検討する価値はあるかもしれません。
Q2:マイカー通勤の交通費、上限はいくらくらいが妥当ですか?
A:公共交通機関の場合は定期代の実費を全額支給するのが一般的ですが、マイカー通勤の場合は、公平性とコスト管理の観点から、距離や燃料価格の変動を考慮した上限設定が現実的とされています。国税庁が定める通勤手当の非課税限度額を一つの参考に、距離別の区分を設けている例が多く見られます。(例)
- 片道10km未満:月額 8,000円まで
- 片道10km以上20km未満:月額 12,000円まで
- 片道20km以上30km未満:月額 20,000円まで
大切なのは、求人票に「マイカー通勤可(規定により支給)」と書くだけでなく、こうした距離区分の目安を具体的に記載することです。「交通費全額支給」という表現が一般的な都市部の求人情報を見慣れている応募者は、「上限あり」という言葉に敏感になることがあるため、透明性の高い情報提供が信頼につながります。
Q3:引越費用の負担は、どこまでの範囲を対象にすればよいですか?
A:「赴任旅費(本人が移動するための交通費)」と「移転料(引越業者の費用など、荷物を運ぶための費用)」は、分けて規定化するのが一般的です。その上で、領収書に基づく実費精算を基本とするのがトラブルの少ない方法とされています。規定を作る際のポイントとしては、
- 対象者(本人だけでなく、帯同する家族も含むか)
- 上限額(単身か世帯かで上限を変えるか)
- 対象となる費用(梱包材やオプションサービスは含むかなど)を明確にしておくことが重要です。長野県立病院機構の例のように、公的機関の規程を参考にしたり、トラベルナースの制度でどのように運用されているかを調べたりすることも、自院のルールを作る上で役立ちます。
Q4:家族を伴って移住する職員向けの支援は、どう設計すればよいですか?
A:世帯向けの支援としては、「住宅手当の金額を加算する」方法と、「借り上げ社宅の家賃上限額を引き上げる」方法が考えられます。単身者よりも広い住居が必要になるため、それに合わせた配慮が必要です。また、お金の支援以上に重要になるのが、生活に関する情報提供です。
- 地域の保育園や幼稚園の空き状況、評判
- 小中学校の学区や特色
- 子どもが遊べる公園や、家族で楽しめる施設の情報
- 配偶者の就職先の情報提供や相談窓口の案内こうした情報を行政と連携して提供できる体制があると、家族での移住の決断を後押しすることができます。北海道の移住支援サイトの事例のように、暮らしの魅力や子育て環境に関する一次情報を発信することが、応募の動機に直接つながることもあります。
求人票の書き方テンプレート(抜粋・文例)
これまで解説してきた内容を踏まえ、求人票の福利厚生欄にそのまま使えるような文例を作成しました。これを基に、自院の制度に合わせて調整してみてください。
【福利厚生】当院では、遠方からご入職される方も安心して新生活をスタートできるよう、以下の支援制度を整えています。
■住宅支援ご自身のライフスタイルに合わせて、以下のいずれかを選択できます。
- 住宅手当
- 対象:ご自身で賃貸住宅を契約される方
- 支給額:単身者 月額15,000円/世帯主 月額25,000円
- 補足:寮に入居される方にも、一律で月額12,000円を支給します(支給期間:入職後最長8年間)。
- 寮・社宅(単身者用・ワンルームタイプ)
- 寮費:家賃の6割を病院が負担します(家賃上限60,000円)。自己負担は月額24,000円程度です。
- 設備:家具・家電付き、バス・トイレ別、オートロック完備
- その他:水道光熱費は実費、駐車場は月額3,000円で利用可能です。
■通勤支援
- 公共交通機関:交通費を全額支給します。
- 自動車通勤:通勤距離に応じて支給します(上限あり)。無料駐車場を完備しています。(支給例:片道10km未満 8,000円、20km未満 12,000円、30km未満 20,000円)
■赴任・引越支援
- 対象:採用に伴い、当院規定の遠隔地から転居される方
- 内容:ご本人の赴任交通費および引越業者の費用を、当院規定に基づき実費で支給します(領収書の提出が必要です)。
- その他:賃貸契約時の敷金・礼金など、初期費用の一時的な立替制度もありますので、ご相談ください。
■お試し勤務制度「まずは職場の雰囲気を知りたい」「地域の暮らしを体験してみたい」という方のために、短期のお試し勤務(アルバイト)も可能です。数回の勤務を体験した上で、移住や常勤でのご入職を判断いただけます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください(クーラ)。https://business.cu-ra.net/
まとめ:費用は“見せ方”と“段階的な導入”で回収できる
地方での看護師採用において、交通費や住宅に関する支援は不可欠な要素です。しかし、ただ費用をかけるだけでは、その効果を最大限に引き出すことは難しいかもしれません。大切なのは、その投資をどのように応募者に伝え、そしてどのように回収していくかという視点です。
1. 数字で安心感を与える
住宅手当の金額、寮の自己負担額、交通費の上限、赴任費用の対象範囲など、あらゆる支援制度について、「対象者」「条件」「期間」「金額」を具体的に明示することが基本です。応募者が入職後の生活を具体的にイメージでき、金銭的な不安が減ることで、内定承諾率の向上や入職後の定着率改善が期待できます。
2. “実質負担”で分かりやすく伝える
「寮費3万円から住宅手当1.3万円が引かれるので、実質負担は1.7万円です」といったように、応募者の手元から実際に出ていく金額を伝えることで、制度の魅力がより伝わりやすくなります。入職後の給与明細を見て「思っていたより手取りが少ない」といったギャップを防ぎ、早期離職のリスクを減らすことにもつながります。
3. “段階的な導入”で投資の無駄をなくす
いきなり正規雇用と移住支援という大きな投資に踏み切る前に、「お試し勤務」というワンクッションを置くことで、採用のミスマッチを大幅に減らすことができます。職場や地域との相性を確認し、双方が納得した上で定着支援へと進むことで、かけた費用の「回収確度」を格段に高めることが可能です。クーラのようなサービスは、この段階的な採用プロセスを設計する上で、親和性の高い選択肢の一つとなるでしょう。https://business.cu-ra.net/
最後に。採用にかかる費用をただ増やすのではなく、その「見せ方」を工夫し、「段階的な導入」でリスクを管理するという三つの視点を揃えることで、地方採用への投資は十分に回収可能であると考えられます。まずは、現在の求人票の表現を見直し、応募者の立場に立って、新しい生活の輪郭がはっきりと伝わるような書き方に整えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。必要に応じて、お試し勤務の受け入れフローを併設できるクーラの導入も検討することで、費用対効果はさらに安定したものになるかもしれません。
付記:参考情報(一部紹介)
この記事を作成するにあたり、以下の公開情報を参考にさせていただきました。
- 住宅手当・交通費の明記例:社会医療法人社団森山医会 行徳総合病院(住宅手当15,000円/入寮者12,000円、交通費全額支給など)
- 寮・住宅補助の手厚い例:公益財団法人東京都医療保健協会 代々木病院(家賃の約6割を病院負担、入寮者にも住宅手当を支給)
- 実質負担額の提示例:医療法人財団川崎病院(寮費30,000円から住宅手当13,000円を差し引き、実質負担17,000円と提示)
- 赴任旅費・移転料の明記例:地方独立行政法人 長野県立病院機構
- トラベルナースの宿舎・赴任費の規程化:医療法人徳洲会グループ
- 移住と暮らしの情報発信例:北海道ニセコ町への移住者インタビュー(くらしごと)
- 看護職員の離職率に関するデータ:公益社団法人日本看護協会「2023年 病院看護実態調査」







.avif)
.avif)

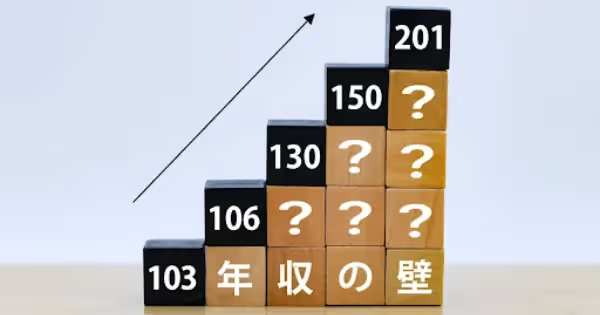
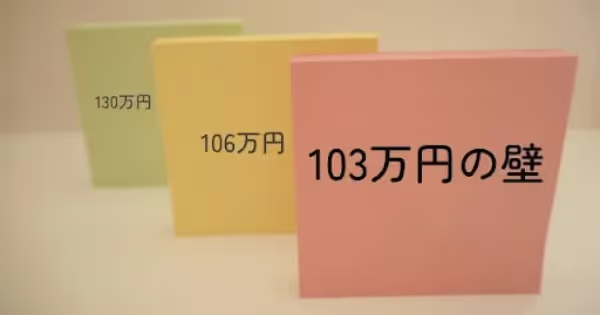







.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
