はじめに:なぜ今、採用戦略の見直しが不可欠なのか
多くのクリニックや病院の経営者様、人事・看護部門の管理者の皆様が、看護師の採用において深刻な課題に直面されていることと存じます。有効求人倍率が高い水準で推移し続ける中、多大なコストと時間をかけても応募が集まらない。あるいは、ようやく採用に至っても、数ヶ月で離職してしまう。この根深い悩みは、日々のオペレーションに支障をきたすだけでなく、中長期的にはクリニックの安定経営そのものを揺るがしかねない、極めて重要な経営課題です。
この状況は、単に「人手が足りない」という言葉で片付けられるものではありません。背景には、働き手の価値観の大きな変化、そして求職者が職場に求める要素が「給与や待遇」だけでなく、「働きがい」「良好な人間関係」「キャリア形成」「柔軟な働き方」など、より多岐にわたっているという事実があります。つまり、旧来の採用手法のままでは、現代の求職者の心に響かない時代になっているのです。
しかし、この厳しい採用環境は、見方を変えれば、自院の理念や文化、働きやすさといった本質的な魅力を再発見し、それを的確に発信することで、働き手から明確に「選ばれるクリニック」へと飛躍するための好機と捉えることができます。
この記事では、一時しのぎの採用テクニックを羅列するのではなく、看護師採用に継続的に成功している医療機関が、いかにして「ここで働きたい」という強い動機を候補者の中に創出しているのか、その根底にある本質的な取り組みを、具体的な事例と共に丁寧に解説してまいります。この記事が、皆様の採用活動に新たな視点と、明日から実践できる具体的な行動計画をもたらす一助となれば幸いです。
第1章:なぜ、従来の採用方法はうまくいかないのか?見落とされがちな3つの構造的課題
良かれと思って続けている、あるいは当たり前だと考えている採用活動が、実は知らず知らずのうちにミスマッチと早期離職を誘発していることがあります。まずは、多くの医療機関が陥りがちな3つの構造的な課題について、その本質を深く理解することから始めましょう。
課題1:『面接』という短時間勝負の限界
採用プロセスの中核をなす「面接」。しかし私たちは、このわずか30分から1時間程度の対話に、あまりにも多くを期待しすぎているのかもしれません。Google社がかつて自社の採用データを大規模に分析した結果、「特定の面接官が候補者を正確に見抜く能力は、基本的には偶然と大差ない」という結論に至ったことは、採用に関わる者の間では有名な話です。これは、採用のプロフェッショナル集団でさえ、短時間の対話で候補者の本質的な能力や適性を見抜くことが極めて難しいという事実を示唆しています。

- スキルは分かっても、「人柄」や「行動特性」までは分からない
- 職務経歴書の内容や、面接での受け答えの的確さから、「採血や注射が上手そうだ」「知識が豊富そうだ」といったテクニカルスキルを推測することは可能かもしれません。しかし、それが「他のスタッフと積極的に協力できるか」「患者様の些細な不安に寄り添い、温かい言葉をかけられるか」「忙しい時に率先して周囲を助ける行動がとれるか」といった、日々の業務品質やチームワークを左右する最も重要な人間性(ソフトスキル)や行動特性を保証するものではありません。これらの特性は、実際の業務環境というストレス下で初めて現れることが多いためです。
- 候補者も「自分を良く見せよう」というバイアス下にある
- 面接は、候補者にとっても人生を左右する重要な「試験」の場です。誰もが自分を最大限に良く見せようと、いわば「面接用のペルソナ」を被って臨んでいます。面接官の質問の意図を読み、模範的な回答を用意することは、事前準備である程度可能です。しかし、その完璧な受け答えの裏にある、予期せぬトラブルへの対応力、考え方の癖、価値観の細かなズレといった、素の部分を見抜くことはほぼ不可能です。面接官側もまた、「この候補者は優秀に違いない」といった第一印象に引きずられる「ハロー効果」や、自分の考えを支持する情報ばかりを集めてしまう「確証バイアス」といった認知バイアスの影響を免れません。
- 最も重要な「組織との相性」が測れない
- 特に、院長や看護師長との距離が近く、スタッフ間の連携が密なクリニックのような少人数の組織では、スタッフ同士の「相性」や、組織文化との適合度を示す「カルチャーフィット」が、個々の業務スキル以上に日々の運営や患者満足度に大きな影響を与えます。院長の診療方針や価値観、既存スタッフが大切にしている暗黙のルール、クリニック全体が持つ独特の空気感。これらは理屈ではなく感覚的なものであり、形式的な面接の場で正確に判断・評価することは極めて困難と言わざるを得ません。
【失敗談:Aクリニック院長のケース】
「先日、紹介会社経由で、大病院での経験も豊富な看護師Aさんを採用しました。面接では受け答えもハキハキと的確で、まさに即戦力だと確信したのです。しかし、いざ入職すると、自分のやり方に固執し、当院のやり方をなかなか受け入れてくれない。他のスタッフが助言をしても『前の病院ではこうでした』と不機嫌な態度を見せることが多く、徐々にチームから孤立していきました。患者様の前では完璧な対応をするのですが、スタッフルームでは他のスタッフへの不満を口にすることも。院内の雰囲気はみるみる悪化し、長年勤めてくれているスタッフの一人から『もう限界です』と相談を受ける事態になりました。結局、Aさんは周囲と馴染めないまま2ヶ月で退職。紹介会社に支払った高額な手数料と、この2ヶ月間のスタッフ全員の精神的な負担、そして失いかけた信頼関係を考えると、本当に大きな、そして無意味な損失だったと痛感しています。」
課題2:『人材紹介会社』への"丸投げ"に潜むリスク
多忙な院長や管理者にとって、候補者の募集からスクリーニング、面接調整までを代行してくれる人材紹介会社は、一見すると非常に便利で効率的なサービスです。しかし、そのビジネスモデルの特性を十分に理解せずに「丸投げ」の状態になってしまうと、意図せず採用の失敗を繰り返すことになりかねません。
紹介会社の収益源は、採用が決定した際に医療機関側から支払われる「成功報酬」です。もちろん、クライアントとの長期的な信頼関係を重視し、定着まで見据えて親身に紹介を行ってくれる優秀なコンサルタントも数多く存在します。しかし、ビジネスの構造上、彼らのインセンティブは、突き詰めれば「クリニックの理念に心から共感し、長く定着してくれる人材を紹介すること」よりも、「候補者を一人でも多くクリニックに入職させること」に強く働かざるを得ないという側面があることを理解しておく必要があります。
その結果、売上目標を優先するあまり、候補者の懸念点(例:「少し主体性に欠ける面もありますが、真面目な方です」といった表現でオブラートに包む)を十分に伝えなかったり、クリニックの理念や求める人物像の深い理解を欠いたまま、「とにかく経験年数とスキルが合致するから」と機械的に候補者を紹介してきたりするケースが後を絶ちません。Aクリニックの悲劇は、まさにこの構造が生み出した典型的なミスマッチ例と言えるでしょう。紹介会社を有効活用するには、丸投げにするのではなく、自院の理念や求める人物像を粘り強く伝え、パートナーとして連携していくという姿勢が不可欠です。
課題3:『求人票』という"一方通行"の情報発信
自院のウェブサイトや各種求人媒体に掲載する「求人票」。給与、勤務時間、業務内容、福利厚生といった「スペック」をいくら詳細に書き、クリニックの魅力を言葉巧みにアピールしても、それはあくまでこちら側からの「一方通行」の情報でしかありません。
現代の賢明な求職者は、その文字情報だけを鵜呑みにはしません。彼らは、その情報を読みながら、常に以下のような不安や疑念を抱いていると考えるべきです。
- 「"アットホームな職場です"って、どこの求人にも書いてある常套句だけど、本当のところはどうなんだろう?」
- 「"残業ほぼゼロ"とあるけど、実際はタイムカードを切ってからのサービス残業があるのではないだろうか?」
- 「院長先生は、写真だと優しそうだけど、実際はワンマンで厳しい人かもしれない…」
採用活動における、この**「情報の非対称性」**こそが、入職後に「こんなはずじゃなかった…」という残念なギャップを生み出す根本的な原因です。求人票は、いわば不動産情報サイトに掲載された「間取り図」のようなものです。間取り図や美しい内装写真をどれだけ眺めても、日当たりの良し悪し、近隣の騒音、そこに住む人々の雰囲気といった、本当に大切な「住み心地」は分かりません。それと同じように、求人票だけでは、実際に働いてみないと分からない「職場のリアルな空気感」の壁を越えることはできないのです。
第2章:【実例20選】採用成功クリニックが実践する「脱・一発勝負」の取り組み
では、採用における失敗とミスマッチをなくすためには、具体的にどうすれば良いのでしょうか。その答えは極めてシンプルです。「面接だけの一発勝負」という考え方を捨て、採用プロセスの各段階に「お互いの素顔を理解し、見極めるための機会」を意図的に設けることです。ここでは、全国の採用に成功しているクリニックが実践している、大きなコストをかけずに今日からでも始められる具体的な取り組みを、詳細な解説付きで20個ご紹介します。
【フェーズ1:魅力を伝え、応募の母集団を形成する】
- 院長の「物語」を語る(東京都A内科)
- 取り組み: Webサイトに「院長の想い」というページを新設。なぜ自分が医師を目指したのか、研修医時代に経験した一人の患者様との出会いが原点になったエピソード、この地域でどのような医療を実現したいのか、その想いを専門用語を一切使わず、自身の言葉で正直に綴った。
- 結果: サイトリニューアル後、応募者数が3倍に増加。何より、「先生のブログを読んで、こういう医療がしたいと強く思いました」と語る、理念に深く共感した熱意ある候補者が応募者の大半を占めるように。結果として、採用後のミスマッチが劇的に減少した。
- この取り組みのポイント: これは「理念採用」の最も効果的な手法の一つです。スペックではなく、院長の価値観や人柄という「物語」に共感した人材は、エンゲージメントが高く、定着しやすい傾向にあります。カッコつける必要はなく、不器用でも正直な言葉こそが人の心を動かします。
- 自院で始めるには: まずは「なぜこの地で開業したのか」「どんな患者様を笑顔にしたいか」「スタッフにどんな働き方をしてほしいか」といった問いについて、ご自身の言葉で書き出してみることから始めてみましょう。
- スタッフの「本音」を載せる(神奈川県B皮膚科)
- 取り組み: 採用ページに「先輩スタッフの1日」と、匿名で本音を語る「ぶっちゃけ座談会」というコンテンツを作成。「1日」では、タイムスケジュールと共に、仕事で工夫している点や休憩中の過ごし方を写真付きで紹介。「座談会」では、「院長の意外な一面は?」「仕事で一番大変なことは?」といった求職者が本当に知りたい質問に、スタッフが赤裸々に回答した。
- 結果: 「スタッフさんの雰囲気が良さそう」「正直な情報開示に信頼が持てる」という理由での応募が増加。面接時にも「座談会を読んで、〇〇さんの意見に共感しました」といった会話が生まれ、候補者の人柄を深く知るきっかけになった。
- この取り組みのポイント: 求職者は「良いこと」ばかりが書かれた求人情報に食傷気味です。あえて大変なことや苦労話もオープンにすることで、逆に情報の信頼性が増し、誠実な組織であるという印象を与えます。
- 自院で始めるには: 既存スタッフにアンケートやヒアリングを実施し、「入職前に知りたかったこと」「今の仕事のやりがいと大変なこと」などを集めてみましょう。それを座談会形式でまとめるだけで、貴重なコンテンツになります。
- 「数字で見るクリニック」を公開(埼玉県C小児科)
- 取り組み: 「働きやすさを客観的に伝えたい」と考え、「数字で見るCクリニック」というインフォグラフィックページを作成。「平均年齢34歳」「ママさんナース比率80%」「有給消化率95%」「平均残業時間 月3.5時間」「育休からの復職率100%」といったデータを、親しみやすいイラストと共に公開した。
- 結果: 近隣の市からも「数字を見て、ここなら安心して長く働けると思った」という質の高い応募が来るように。採用コストは以前の半分以下になり、定着率も大幅に向上した。
- この取り組みのポイント: 「働きやすい」という主観的な言葉を、客観的なデータで裏付けることで、求職者の不安を払拭し、絶大な説得力を生み出します。特に、ライフイベントとの両立を重視する求職者には極めて有効です。
- 自院で始めるには: まずは勤怠管理システムや給与計算ソフトから、残業時間や有給取得日数といったデータを集計してみましょう。スタッフの年齢構成や勤続年数も、組織の安定性を示す良い指標になります。
- Instagramで「日常」を切り取る(大阪府D耳鼻咽喉科)
- 取り組み: 事務長が中心となり、Instagramアカウントを開設。①院内の季節の飾り付け、②スタッフの誕生日祝い、③近所の美味しいランチ情報、④院長が趣味で育てているメダカの様子、といった「ゆるい日常」を週に2〜3回投稿。「#〇〇市看護師」「#耳鼻科ナース」といったハッシュタグを研究し、地道に発信を続けた。
- 結果: 半年後にはフォロワーが500人を超え、DM経由で「見学したいです」という問い合わせが初めて入る。その後、Instagram経由で2名の採用に成功。採用コストはゼロ。
- この取り組みのポイント: 作り込まれた広報よりも、リアルな日常の発信が、職場の温かい雰囲気や人間関係の良さを何よりも雄弁に伝えます。求職者は、ここで働く自分の姿を具体的にイメージしやすくなります。
- 自院で始めるには: 担当者を一人決め、スマートフォンで撮影した写真を気軽に投稿することから始めてみましょう。完璧を目指す必要はありません。継続することが最も重要です。
- Googleマップの口コミに誠実に対応する(福岡県E眼科)
- 取り組み: 院長自らが、全てのGoogleマップの口コミに24時間以内に返信するルールを徹底。特にネガティブな口コミには、真摯に謝罪した上で、具体的な改善策(予約システムの導入、待ち時間表示モニターの設置など)を丁寧に説明した。
- 結果: その誠実な対応が他のユーザーにも評価され、「口コミへの返信を見て、信頼できるクリニックだと思った」という好意的な口コミが増加。採用面接でも、院長の患者と向き合う姿勢に共感したという応募者が現れるようになった。
- この取り組みのポイント: 口コミは、患者様からの貴重なフィードバックであると同時に、未来のスタッフ候補者を含む社会全体に対する「組織の姿勢を示すショーウィンドウ」です。真摯な対応は、最高のブランディング活動になります。
- 自院で始めるには: まずは自院の口コミを定期的にチェックする習慣をつけましょう。返信はテンプレートではなく、具体的な状況に触れながら、感謝や謝罪、改善の意志を自分の言葉で伝えることが大切です。
- 「採用専用LINE」で気軽に質問対応(愛知県F整形外科)
- 取り組み: Webサイトや求人票に、採用に関する質問や見学希望を受け付けるためのLINE公式アカウントのQRコードを設置。自動応答メッセージで担当者名を名乗り、どんな些細なことでも気軽に質問できる雰囲気を作った。
- 結果: 「子供の急な発熱などによるシフト変更には、柔軟に対応してもらえますか?」といった、電話やメールでは聞きにくいような質問がLINEで気軽に寄せられるように。候補者の不安を応募前に解消することで、選考途中での離脱率が大幅に低下した。
- この取り組みのポイント: 応募のハードルを極限まで下げることで、潜在的な候補者との接点を増やすことができます。丁寧で迅速な対応を心がけることで、応募前から候補者の信頼を獲得できます。
- 自院で始めるには: 無料で開設できるLINE公式アカウントを作成し、求人媒体や自院サイトにQRコードを掲載するだけですぐに始められます。担当者を決め、通知に気づける体制を整えておきましょう。
- 地域の看護学校で「出前授業」(千葉県G在宅クリニック)
- 取り組み: 在宅医療の認知度が低いという課題に対し、近隣の看護学校にアプローチ。「在宅医療のリアルとやりがい」というテーマで、院長と先輩看護師が出前授業を実施。教科書だけでは分からない現場のエピソードや、患者・家族との心温まる交流を語った。
- 結果: 授業をきっかけに在宅医療に興味を持つ学生が増え、実習希望者が殺到。その中から毎年1〜2名の新卒採用に安定して繋がっている。
- この取り組みのポイント: これは目先の採用だけでなく、未来の医療を担う若者への啓蒙活動という、長期的な視点に立った社会貢献活動です。自院の専門分野の魅力を伝えることは、地域におけるブランディングにも繋がります。
- 自院で始めるには: 近隣の看護学校のカリキュラム担当者や就職課に連絡を取り、協力できることがないか相談してみましょう。最初はキャリア相談会のブース出展など、小さな関わりから始めるのも有効です。
【フェーズ2:ミスマッチを防ぎ、確信を持って採用する】
- 「半日体験見学・勤務」を必須化(京都府H消化器内科)
- 取り組み: 書類選考と一次面接を通過した候補者全員に、半日(4時間)の体験見学・勤務を必須とした。白衣を貸与し、先輩看護師について実際の業務の流れを見てもらうだけでなく、簡単な補助業務も体験してもらう。終了後、候補者本人、指導した先輩スタッフ、院長の三者で振り返りの時間を設ける。
- 結果: 候補者側から「思っていたより業務スピードが速く、私にはついていけそうにないです」と辞退するケースも出たが、それはむしろ入職後の早期離職を防ぐポジティブなミスマッチ回避と捉えている。この制度導入後、採用後の定着率はほぼ100%になった。
- この取り組みのポイント: 「百聞は一見に如かず」を地で行く、ミスマッチ防止の切り札です。候補者は職場のリアルな空気を感じ取れ、クリニック側は候補者の実際の動きやスタッフとのコミュニケーションの取り方を確認できます。
- 自院で始めるには: まずは短時間(1〜2時間)の見学から始めてみましょう。受け入れ体制(誰が案内するか、何を見てもらうか)を事前に決めておくことがスムーズな運用の鍵です。
- 「お茶会面談」で本音を引き出す(兵庫県I心療内科)
- 取り組み: 患者とのコミュニケーション能力を重視するため、最終面接は診察室ではなく、近所の落ち着いたカフェで実施。「面接」という堅苦しい言葉は使わず、「お互いをよく知るためのお茶会」と位置づけ、院長も私服で参加。仕事の話だけでなく、趣味や休日の過ごし方など、雑談を交えながら候補者の価値観や人柄を深く理解するよう努める。
- 結果: リラックスした雰囲気の中で、候補者も本音を話しやすくなり、「実は前の職場の人間関係で悩んでいて…」といった深い話が出てくることも。採用の判断精度が格段に向上した。
- この取り組みのポイント: 面接場所や形式を変えるだけで、候補者との心理的な距離が縮まり、本音を引き出しやすくなります。対等な立場で対話するという姿勢が、候補者の信頼感に繋がります。
- 自院で始めるには: 院内に落ち着いて話せる応接室などがあれば、そこでお茶を飲みながら話すだけでも効果があります。重要なのは、評価する・されるという関係性ではなく、相互理解の場であるという雰囲気作りです。
- 「リファラル紹介カード」を配布(北海道J産婦人科)
- 取り組み: 口頭での依頼だけでは形骸化していた職員紹介制度を活性化させるため、クリニックのロゴ入り名刺サイズの「紹介カード」を作成。表面にはキャッチコピーと院内の写真を、裏面には募集要項、WebサイトのQRコード、紹介特典(紹介者・被紹介者双方に5万円ずつなど)を記載し、全スタッフに配布した。
- 結果: カードという「ツール」があることで、スタッフも友人や元同僚に紹介しやすくなり、実際に同窓会でカードを渡したことがきっかけで1名の採用に成功。紹介経由の採用は、事前に職場のリアルな情報を得ているため定着率が高いことを改めて実感した。
- この取り組みのポイント: 従業員エンゲージメントが高い組織ほど、リファラル採用は機能します。紹介は、スタッフが自院に誇りを持っている証拠でもあります。紹介してくれたスタッフへの感謝とインセンティブを明確にすることが重要です。
- 自院で始めるには: まずはシンプルな紹介制度のルール(対象者、紹介プロセス、特典など)を決め、スタッフに周知することから始めましょう。カード作成は、無料のデザインツールなどを使えば簡単にできます。
- 「ブランク歓迎」お仕事説明会を実施(東京都Kメンタルクリニック)
- 取り組み: 資格は持つが離職中の「潜在看護師」の復職支援をしたいと考え、ターゲットを「ブランク5年以上の方」に限定し、土曜の午後を使って院内でお仕事説明会を開催。「当院では高度な医療処置はほとんどありません」「患者様の話をじっくり聴くことが一番の仕事です」と、業務内容のハードルを意図的に下げて説明。復職経験のある先輩ナースが自身の体験談を語る時間も設けた。
- 結果: 1回の説明会に10名以上が集まり、そのうち3名がパートとして入職。これまでアプローチできていなかった層の掘り起こしに成功した。
- この取り組みのポイント: 採用ターゲットを明確に絞り込み、その層が抱える不安(「今の医療についていけないのでは」「家庭と両立できるか」など)を先回りして解消してあげることで、応募への心理的ハードルを大きく下げることができます。
- 自院で始めるには: 自院の業務内容を棚卸しし、どのような経験を持つ人なら活躍できそうか、ターゲット像を具体的に設定してみましょう。地域のハローワークやナースセンターに相談し、広報に協力してもらうのも有効です。
- パートからの「正社員登用制度」を明記(神奈川県L透析クリニック)
- 取り組み: 常勤での採用を希望していたが、家庭の事情などでフルタイム勤務が難しいという理由で、優秀な候補者を逃すことが多かった。そこで「まずは週3日のパートから、職場の雰囲気に慣れてみませんか?半年後の正社員登用実績多数!」という一文を求人票に大きく記載した。
- 結果: 応募のハードルが下がり、これまで獲得できなかった優秀なママさんナースの採用に成功。実際に入職1年後に常勤へ移行し、今ではリーダーとして活躍しているケースも生まれている。
- この取り組みのポイント: 働き方の柔軟性や、長期的なキャリアパスを提示することは、特にライフイベントの変化が大きい女性看護師にとって大きな魅力となります。一度にすべてを求めるのではなく、段階的なステップを用意する視点が重要です。
- 自院で始めるには: 実際にパートから正社員になった実績があれば、それを積極的にアピールしましょう。まだ実績がなくても、制度として明文化し、面接で「あなたのライフプランに合わせて、柔軟に働き方を変えていきましょう」と伝える姿勢が大切です。
- 「課題解決型」の面接を行う(大阪府M美容クリニック)
- 取り組み: 指示待ちではなく、自ら考えて行動できる主体性のある人材を求めていたため、面接の最後に「もし当院で働くとしたら、これまでのご経験を活かして、どんな改善提案ができますか?例えば、患者様の待ち時間を減らす工夫など、何でも結構です」という質問を投げかけるようにした。
- 結果: この質問に対する回答で、候補者の当事者意識や視座の高さが明確に分かるように。「特にありません」と答える人よりも、「前職では〇〇というツールを使って予約管理を効率化していました」といった具体的な提案ができる人材を採用することで、入職後の活躍度合いが大きく変わった。
- この取り組みのポイント: 過去の経験を聞くだけでなく、未来の貢献について質問することで、候補者が自院をどれだけ「自分ごと」として捉えているかを測ることができます。思考力や問題解決能力を見る上でも有効な質問です。
- 自院で始めるには: 事前にクリニックのウェブサイトや口コミサイトなどを見てきてもらうよう候補者にお願いし、その上で「何か気づいた点や、もっと良くできそうだと思った点はありますか?」と聞いてみるのも良いでしょう。
【フェーズ3:入職後の定着率を高め、組織を強くする】
- 「ウェルカムランチ」を恒例化(福岡県N歯科)
- 取り組み: 新人が入っても、既存スタッフが日々の忙しさから十分なコミュニケーションを取れず、新人が孤立しがちだった。そこで、入職初日は必ず診療時間を少し短縮し、院長と全スタッフでクリニック近くのレストランでウェルカムランチに行くことを恒例化した。
- 結果: 新人が心理的な壁を感じることなく、スムーズにチームに溶り込めるようになった。ランチでの雑談が、その後の業務中の円滑なコミュニケーションのきっかけにもなっている。
- この取り組みのポイント: 入職初日の印象は、その後の定着に大きく影響します。「組織としてあなたを歓迎している」というメッセージを明確に伝えることが、新人の安心感に繋がります。
- 自院で始めるには: ランチが難しければ、朝礼で少し時間を取って丁寧な自己紹介の時間を設けたり、終業時に院長や教育担当者が「初日どうだった?」と一声かけたりするだけでも効果があります。
- 「ナースシューズ購入補助」制度(埼玉県Oクリニック)
- 取り組み: スタッフの満足度を高める福利厚生を導入したかったが、大きなコストはかけられない。そこで、多くの看護師が自腹で購入し、消耗品でもあるナースシューズに着目。年1回、上限5,000円でナースシューズの購入費用をクリニックが補助する制度を開始した。
- 結果: 金額以上に、「スタッフの足元の健康まで気遣ってくれる」という院長の姿勢が伝わり、スタッフの満足度が非常に高まった。「次はどんな靴にしようかな」と選ぶ楽しみも生まれている。
- この取り組みのポイント: 小さなことでも「スタッフを大切にしている」という姿勢を示すことは、エンゲージメント向上に繋がります。高額な福利厚生よりも、現場のニーズに寄り添ったユニークな制度が心に響くこともあります。
- 自院で始めるには: スタッフに「あったら嬉しい福利厚生は?」とアンケートを取ってみるのも良いでしょう。書籍購入補助や、近隣のジムの利用補助なども比較的導入しやすい制度です。
- ユニークな「スキルアップ支援」(東京都P自由診療クリニック)
- 取り組み: 向上心のあるスタッフの成長を応援し、モチベーションを高めるため、看護業務に直接関係なくても、スタッフが希望する研修やセミナーの費用を年間3万円まで補助する制度を導入。接遇マナー研修、アロマテラピー資格、ペン字講座など、本人の興味関心を尊重した。
- 結果: スタッフが自律的に学ぶ文化が醸成された。また、アロマの知識を待合室の環境改善に活かすなど、思わぬ形でクリニックに還元されるケースも生まれている。
- この取り組みのポイント: 人材育成を「業務命令」ではなく「個人の成長支援」と捉えることで、スタッフの学習意欲を高めます。スタッフの成長は、巡り巡って必ず組織の力になります。
- 自院で始めるには: まずは院内勉強会の開催や、外部研修に参加したスタッフによる報告会の実施など、学びを共有する文化作りから始めてみましょう。
- 「サンクスカード」の導入(兵庫県Q訪問看護ステーション)
- 取り組み: 各自が一人で訪問することが多く、スタッフ同士のコミュニケーションが不足しがちで、お互いの頑張りが見えにくいという問題があった。そこで、日々の業務の中で感じた感謝を小さなカードに書いて投函する「サンクスカード」制度を開始。毎週のミーティングで院長がカードを読み上げる。
- 結果: 「〇〇さん、急な訪問交代ありがとうございました!」「△△さんの記録、すごく分かりやすくて助かりました」など、お互いの良いところを認め合う文化が生まれた。職場の心理的安全性が高まり、チームワークが格段に向上した。
- この取り組みのポイント: 感謝や称賛を可視化・言語化することで、ポジティブなコミュニケーションが活性化します。これは、離職の大きな原因となる人間関係の問題を未然に防ぐ効果的な施策です。
- 自院で始めるには: 大げさなものではなく、小さなホワイトボードやノートを用意し、「今週のありがとう」を自由に書き込めるようにするだけでも始められます。
- 「シフト交換アプリ」の活用(神奈川県R健診センター)
- 取り組み: 子供の急な発熱などによるシフト変更の連絡・調整が、すべて事務長の電話対応に集中し、大きな負担となっていた。そこで、スタッフのスマートフォンで使える、無料のシフト管理・交換アプリを導入。急な休みが必要になった際、まずはスタッフ間で交代を探せるようにした。
- 結果: 事務長の調整業務が8割以上削減。スタッフも、上長に気兼ねなく休みを相談できる雰囲気になり、働きやすさが向上した。
- この取り組みのポイント: テクノロジーを活用して、管理業務の効率化とスタッフの働きやすさを両立させる好例です。スタッフに一定の裁量を与えることが、自律的な組織文化の醸成にも繋がります。
- 自院で始めるには: 無料で使えるシフト管理アプリは多数あります。まずは少人数で試してみて、自院の運用に合うものを見つけるのが良いでしょう。
- 院長の「月イチ通信」を発行(千葉県S総合クリニック)
- 取り組み: スタッフ数が増えるにつれ、院長の考えやクリニックの方向性が末端まで伝わりにくくなっていた。そこで、院長がA4一枚の手書き通信「SクリTIMES」を毎月発行。内容は、先月の経営状況の簡単な報告、今後の目標、頑張ってくれたスタッフへの名指しの感謝、院長自身のプライベートな話題など。給与明細と一緒に手渡している。
- 結果: スタッフが経営に興味を持つきっかけになり、組織の一体感が向上。「院長が私たちのことを見てくれている」という安心感が、定着率の向上に大きく貢献している。
- この取り組みのポイント: 組織のトップが何を考え、どこを目指しているのかを共有することは、従業員のエンゲージメントを高める上で非常に重要です。特に、個々のスタッフの頑張りを認め、感謝を伝えることは効果絶大です。
- 自院で始めるには: 手書きが難しければ、メールやチャットツールでの定期的なメッセージ配信でも構いません。形式よりも、誠実な言葉で継続的に発信するという姿勢が大切です。
- 「卒業」を応援する文化(東京都T緩和ケアクリニック)
- 取り組み: 専門性が高い職場だからこそ、スタッフのキャリアアップや家庭の事情による退職は避けられない。その際の引き継ぎや、残るスタッフの士気低下が問題だった。そこで、退職を「裏切り」ではなく「卒業」と捉える文化を醸成。退職が決まったスタッフには、院長が面談で感謝と応援の言葉を伝え、最終日には花束を贈って全員で送り出す。
- 結果: 円満な退職が、スムーズな業務引き継ぎと、残るスタッフのポジティブなマインドに繋がっている。実際に、一度退職した看護師が、数年後に「やっぱりここが一番です」と復職してきたケース(アルムナイ採用)も複数ある。
- この取り組みのポイント: 去り際の対応こそ、組織の文化レベルが表れます。退職者を「元仲間」として大切にすることで、彼らが外部の応援団になってくれたり、将来的に復職に繋がったりする可能性があります。
- 自院で始めるには: 退職者との最終面談(エグジットインタビュー)を設け、感謝を伝えると共に、退職理由を真摯にヒアリングし、組織改善に繋げる仕組みを作ることが第一歩です。
第3章:新しい採用の選択肢。「お試し勤務」サービスという考え方
前章では、採用の各フェーズにおける具体的な20もの取り組みをご紹介しました。どれも有効な手段ですが、「すべてを実践するのは正直、大変だ」と感じられた管理者の方もいらっしゃるかもしれません。
そこで近年、新たな採用手法として注目されているのが、看護師専門の**「お試し勤務(スポットワーク)」サービス**です。これは単発のアルバイトを探すためのサービスではなく、採用のミスマッチを根本から解決するための戦略的なツールとして活用できます。
この仕組みは、第1章で述べた「採用の3つの課題」をまとめて解決できる可能性を秘めた、新しい採用の形です。
- 「面接」の限界を超え、実際の"働きぶり"や"人柄"で判断できる。
- 「紹介会社」に依存せず、比較的低コストで候補者と直接出会える。
- 「求人票」だけでは伝わらない"職場のリアル"を、候補者が体感し、相性を確かめ合える。
「お試し勤務」サービスの仕組みとメリット
単なる短期的な人手不足を補うヘルプスタッフを探すだけでなく、**「正規採用を前提とした、候補者と職場とのお見合い期間」**として戦略的に活用できるのが最大の特徴です。
- 1日〜数日単位で、実際の業務を依頼できる
- まずは1日、あるいは数日間、実際のメンバーの一員として働いてもらうことで、面接では決して分からない候補者の臨床スキル、学習意欲、コミュニケーションの取り方、既存スタッフとの相性を、院長や現場スタッフ自身の目で見極めることができます。これは、第2章で紹介した「半日体験見学」を、より実践的かつ双方向的に行える仕組みと言えます。
- 応募者のプロフィールを見て、依頼前に選考できる
- サービス上では、応募者の職務経歴や保有資格、希望する働き方などを事前に確認できます。その情報をもとに、自院の求める要件と合わないと感じた場合は、面接を設定する時間的・心理的コストをかけることなく、お断りすることも可能です。
- 双方が合意すれば、直接雇用へ
- お試し勤務を経て、クリニック側が「この人にぜひ仲間になってほしい」と感じ、看護師側も「この職場でなら長く働けそうだ」と確信できた場合、双方の合意のもとで常勤やパートといった直接雇用契約に移行します。実際に数日間、同じ職場で汗を流した上で判断できるため、「こんなはずじゃなかった」という入職後のギャップを限りなくゼロに近づけることが可能です。
人材紹介会社とのコスト比較
お試し勤務サービスは、採用の「質」を高めると同時に、「コスト」の面でも大きなメリットをもたらす可能性があります。一般的な人材紹介会社では、採用決定時に理論年収の25%〜35%(例えば年収400万円の看護師なら100万円〜140万円)が手数料として発生します。
一方、お試し勤務サービス経由で直接雇用に至った場合の手数料は、サービスによって様々ですが、紹介会社よりも低額な固定料金(例えば30万円〜60万円)に設定されているケースが多く見られます。
このように、お試し勤務サービスを戦略的に活用することは、採用のミスマッチという最大のリスクを低減させ、かつ採用コストも大幅に抑制できる可能性を秘めています。そして、そこで抑制できたコストを、既存スタッフの待遇改善や教育研修、あるいは新たな医療機器への投資に振り向けることで、クリニック全体の価値をさらに高めるという、好循環を生み出すことができるのです。
第4章:よくある質問(FAQ)
新しい採用の形だからこそ、導入にあたっては様々な疑問や不安があるかと存じます。ここでは、管理者の方々から実際に寄せられることが多い質問に、Q&A形式でお答えします。
Q1. お試し勤務の看護師さんに、どこまで仕事を任せていいのですか?
A1. 安全性を最優先し、段階的に業務をお任せするのが基本です。初日はオリエンテーションを中心に、院内のルールや電子カルテの操作方法などを説明し、まずは見学や簡単な診療補助から始めてもらうのが一般的です。その上で、「採血・注射・バイタル測定」といった基本的な看護業務を、本人のスキルや経験を確認しながら徐々にお願いしていくと良いでしょう。事前に「当日お任せしたい業務リスト」と「初日のタイムスケジュール」を作成し、受け入れ側も準備を整えておくことが、お互いの安心に繋がります。
Q2. 個人情報や院内の機密保持は大丈夫でしょうか?
A2. 看護師には、保健師助産師看護師法第42条の2により、職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないという厳格な守秘義務が課せられています。これは、常勤・非常勤・お試し勤務といった雇用形態に関わらず、すべての看護師に適用されます。より万全を期すためには、お試し勤務を開始する前に、改めて院内のルールとして機密保持に関する誓約書を取り交わすことをお勧めします。これは、通常のパート・アルバイト採用時に行う手続きと同様であり、特別なことではありません。
Q3. 既存のスタッフから、人が頻繁に来ることへの反発はありませんか?
A3. 事前の丁寧な説明と、目的の共有が極めて重要です。「場当たり的に人を呼ぶ」のではなく、「採用のミスマッチをなくし、本当に私たちと長く一緒に働ける最高の仲間を、現場のみんなの意見も聞きながら見つけるために、こういう新しい方法を試したい」と、院長や管理者の方から導入の目的とメリットを真摯に説明することが不可欠です。「変な人が入ってきて、自分たちが後で苦労するよりずっと良い」「自分たちの意見も採用に反映されるなら歓迎だ」と、むしろポジティブに受け入れてくれるケースがほとんどです。お試し勤務の方への評価に、既存スタッフの意見を積極的に取り入れることも、チームの一体感を高める上で非常に効果的です。
Q4. どのような看護師さんが登録しているのですか?
A4. 多様な背景を持つ看護師が登録しています。具体的には、本格的な転職活動を始める前に、いくつかのクリニックの雰囲気を実際に見てみたいと考えている現役看護師。育児などで一度現場を離れたが、復職に向けて勘を取り戻したいと考えている潜在看護師。あるいは、特定の組織に縛られず、フリーランスとして様々な職場でスキルを磨きたいと考えている意欲の高い看護師などです。「いきなり面接を受けて転職するのは不安だが、まずは実際の職場を体験してみたい」という、慎重かつ質の高い候補者と出会える可能性が高いのが、これらのサービスの特徴です。
Q5. 万が一、お試し勤務中に物損やトラブルがあった場合の補償は?
A5. 多くのサービスでは、プラットフォームとして、勤務中の対人・対物事故を補償する損害賠償保険に加入しています。万が一の事態にも備えがあるため、医療機関側も安心して受け入れていただくことが可能です。ただし、補償の範囲や内容はサービスによって異なりますので、利用を開始する前に、どのようなケースが補償対象となるのか、規約を詳細に確認しておくことが重要です。
結論:クリニックの未来は、「採用の質」で決まる
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
これからのクリニック経営において、看護師採用は単なる「人員補充」という短期的なタスクではありません。どのような価値観を持ち、どのような強みを持った看護師がチームに加わるかで、日々の診療の質、患者様の満足度、既存スタッフの士気、そしてクリニックの未来そのものが大きく変わる、極めて重要な「経営戦略」です。
だからこそ、「誰でもいいから早く来てほしい」という場当たり的な採用から、私たちは卒業しなければなりません。
面接だけの一発勝負に頼るのではなく、お互いの価値観や本当の相性を、時間をかけてじっくり見極める。高額な紹介手数料を払い続けるのではなく、そのコストをスタッフの待遇改善や教育、働きやすい環境づくりに投資する。
この記事でご紹介した20の取り組みや、新しい選択肢である「お試し勤務」サービスは、その「採用の質」を劇的に高め、理想のチーム作りを実現するための具体的なヒントです。すべてを一度に実行する必要はありません。まずは自院の課題に照らし合わせ、できそうなことから、一つでも試してみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、貴院の採用活動、ひいてはクリニックの未来を大きく変えるきっかけになるかもしれません。
皆様の採用活動の成功を、心より応援しております。







.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)





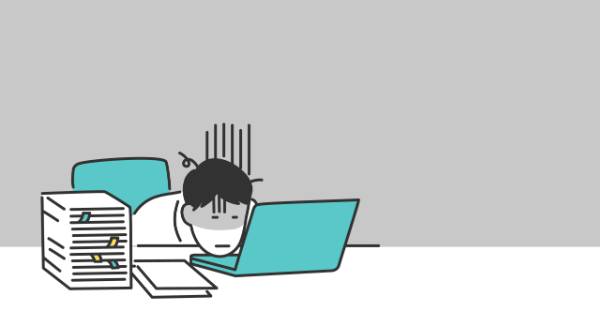
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
