はじめに
予約システムは、導入して終わり、というものではありません。日々の電話や窓口での対応、患者さんの院内での動き、そして患者さんが抱く待ち時間への期待、これら全てがうまく連携して初めて、その真価を発揮します。この記事では、CLINICS予約を中心に据えつつ、ドクターキューブ、EPARKを現場での運用の視点から比較し、小規模な病院やクリニックで起こりがちな課題を乗り越えるためのヒントをまとめました。
先にお伝えしたい大切なポイントは、「院内の混雑の特性に合った予約方式(時間帯予約か、順番待ちか、あるいはその両方か)を見極めること」「初診や予防接種といった、性質の異なる来院目的を分けること」「院内の表示とスタッフからのアナウンスを丁寧に行うこと」の三点です。これらが運用の成否を左右するといっても過言ではないかもしれません。
記事の中でご紹介する事例は、公開されている情報をもとに、客観的な解説を心がけています。この記事を読み終えたら、まずはご自身のクリニックの混雑する時間帯や曜日を紙に書き出してみて、どこから改善の手をつけられそうか、具体的なイメージを膨らませてみてください。もし導入初期などで人手が足りない時間帯があれば、クーラの「お試し勤務」のようなサービスを併用し、無理なく運用を始める方法もあります(導入に関するご相談はこちらからどうぞ:https://business.cu-ra.net/)。
CLINICS予約の特長:時間帯予約とオンライン診療、カルテ連携のスムーズさ
時間帯予約を基本とした設計
CLINICSは、例えば「10:00から10:30」のように、30分単位の「時間帯」で予約を受け付ける方式を基本としています。患者さんはその時間帯の中で呼び出しを待つ、という心づもりで来院されるため、待ち時間に対する期待感が揃いやすく、落ち着いた院内環境の維持につながりやすいという利点があります。これにより、「時間ぴったりに始まらない」という不満が生じにくくなります。
24時間対応のウェブ予約と事前記入による受付業務の効率化
クリニックごとに専用の予約ページを作成でき、診療メニューの設定、ウェブ問診、保険証画像の事前登録、必要に応じた予約料の設定まで、柔軟なカスタマイズが可能です。診療時間外であっても、患者さんは空いている時間帯を選んで手軽に予約を入れられます。これにより、受付での煩雑なやり取りや、書類の不備による手戻りを減らす効果が期待できます。
CLINICSカルテとの円滑な連携
CLINICSカルテを併用している場合、予約情報が自動的にカルテに取り込まれ、患者情報の一元管理がスムーズになります。外部のウェブ問診ツール、例えば「メルプ」などとも公式に連携実績があり、患者さんが事前に記入した問診内容がそのままカルテに反映される流れを構築しやすい点も、現場の負担軽減に貢献します。
小規模クリニックにおける導入のイメージ
実際にCLINICSを導入している「おひさま 子ども・ファミリークリニック」のような小児科では、患者さん向けにオンライン診療の利用手順や予約の考え方を説明した案内資料を公開しています。このように、院内での掲示や紙のチラシ、ウェブサイトなどを通じて、患者さん側の操作に対する心理的なハードルを下げていく工夫が、運用の定着には欠かせません。
このような現場におすすめです
- 時間帯ごとに来院数をならし、院内の混雑を平準化したい
- 対面診療だけでなく、オンライン診療も同じシステムで一元的に管理したい
- 予約情報とカルテを一体化させ、情報管理の手間を減らしたい
ドクターキューブの特長:時間予約と順番待ちの柔軟な併用、きめ細やかな院内表示
時間予約と順番受付を混在させて運用できる柔軟性
ドクターキューブの大きな特長は、日時を指定する「時間予約」と、来院した順番に受付を行う「順番待ち」の両方の方式に対応しており、これらを自由に組み合わせて運用できる点です。例えば、午前中は順番待ちを中心に、午後は時間予約のみにする、といった設定が可能です。混雑の波が大きい耳鼻咽喉科や小児科など、日や時間帯によって患者さんの流れが大きく変わる診療科にとって、この設計の自由度は大きな魅力となります。
院内表示ディスプレイによる情報提供
現在の待ち人数やおおよその待ち時間、そして「診療の遅れ時間」など、院内のディスプレイ(サイネージ)に多様な情報を表示できる機能が充実しています。特に「現在、約◯分遅れています」といった具体的な遅れ時間を表示するだけでも、待合室での患者さんの不満やストレスは大きく軽減されることが知られています。情報を可視化することで、漠然とした不安が安心感に変わります。
多くの患者さんが来院するクリニックでの活用事例
公式サイトで紹介されている千葉県八千代市の「やちよ総合診療クリニック」の事例では、1日に500人規模の患者さんが来院する中で、時間予約と順番予約を両立させることで、多くの患者さんをスムーズに受け入れる体制を構築しています。ウェブ予約を導入したことで患者さんが時間に合わせて来院するようになり、駐車場の混雑緩和にもつながったといいます。このような工夫は、多くの患者さんを抱えるクリニックにとって参考になる点が多いでしょう。
このような現場におすすめです
- 予約なしで当日来院される患者さんが多く、順番待ちの仕組みが不可欠である
- 診療の遅れ時間を表示することで、待合室の患者さんの不満を和らげたい
- 診療科や時間帯、曜日ごとに異なる予約ルールで運用したい
EPARKの特長:多くの人が利用するポータルサイトからの集患とネット受付の連携
「見つけてもらう」仕組みと受付システム
EPARKは、飲食店の順番待ちなどで広く知られていますが、医療分野でも大きな会員基盤を持っています。「EPARKクリニック・病院」というポータルサイトを入り口として、患者さんは病院やクリニックを検索し、そのままネット受付や順番待ちの状況確認ができます。検索から詳細ページの閲覧、そして予約へと続く流れがスムーズに設計されており、自院のウェブサイトだけでは届きにくい新しい患者さんに知ってもらうきっかけを作りやすいのが魅力です。
自治体や大規模な予防接種などでの活用実績
新型コロナウイルスのワクチン接種事業では、多くの自治体でEPARKのシステムが活用されました。ネットでの予約受付、キャンセルや日時変更の手続きがオンラインで完結し、ワクチンの在庫(受付可能な枠数)管理まで含めた大規模な運用実績があります。これは、システムの安定性や信頼性の高さを物語っており、現場での手入力や人為的なミスを減らすための仕組みが整っていることを示しています。
医科・歯科の小規模なクリニックでも豊富な導入事例
歯科領域では特に導入事例が多く、EPARKへの掲載やネット受付機能を通じて、新規の患者さん獲得や24時間予約受付による業務効率化の効果を報告する記事が多数見られます。医科のクリニックでも、各院のネット受付ページが公開されており、診療時間中の電話応対の数を減らし、窓口業務の負担軽減につながっている様子がうかがえます。
このような現場におすすめです
- まずは新しい患者さんにクリニックを知ってもらうための入り口を増やしたい
- 24時間対応のネット受付を導入し、電話応対の業務負荷を下げたい
- ポータルサイトからの集患と、自院のウェブサイトからの予約、両方を強化したい
比較早見:どのシステムが、ご自身のクリニックの混雑のしかたに合うか
院内の状況は様々です。「どのシステムが一番優れているか」という視点ではなく、「自院の患者さんの流れや混雑の特性に、どのシステムが合っているか」という基準で選ぶことが、導入後のスムーズな運用につながります。
実例から学ぶ、現場での運用のヒント
1. 患者さんの流れが速い診療科(耳鼻科・小児科など)での「順番」と「時間」の組み合わせかた
ドクターキューブの導入事例では、予防接種や一部の専門外来など、あらかじめ予定が決まっているものはウェブでの時間予約を基本とし、当日の急な体調不良などで来院する患者さんは順番受付で対応する、という使い分けが見られます。さらに、院内ディスプレイで診療の遅れ時間を具体的に知らせることで、待合室での不満を抑える工夫をしています。「時間通りに診てもらいたい人」と「今日中に診てもらいたい人」、両方の要望に応えるための仕組みづくりが運用の鍵となります。
- 運用のヒント
- 初診や予防接種、健診はウェブでの時間予約にできるだけウェブ予約に誘導し、電話での問い合わせには予約ページの案内を基本とすることで、受付の負担を減らします。
- 当日の一般診療は順番受付を中心に来院された方から順番にご案内し、診療の遅れはディスプレイでこまめに情報提供します。
- 「来院時刻」と「診察開始の見込み」を分けて伝える「すぐにご案内できるわけではない」ことを丁寧に伝え、待ち時間への期待を調整します。
2. オンライン診療を日常的な選択肢にするための情報提供
CLINICSは、患者さん向けにアプリの操作手順や時間帯予約の考え方を分かりやすく解説したサポートページを用意しています。これらを参考に、自院のウェブサイトや院内掲示、配布物などで、「アプリのインストール方法」「オンラインでの呼び出しの仕組み」「オンラインでの服薬指導の流れ」といった情報を繰り返し案内することが、患者さんの不安を取り除き、問い合わせを減らすことにつながります。
- 運用のヒント
- 「時間帯予約」の意味を明確に伝える「10:00予約」ではなく「10:00〜10:30の間にご案内」という考え方であることを明記します。
- オンライン診療のメニューには注意事項を先に同意事項や、事前に準備が必要な書類(保険証など)を予約ページで先に案内し、当日の混乱を防ぎます。
- 予約料を設定する場合はその目的を説明するもし予約料を設定する際は、「無断キャンセルを防ぎ、本当に必要な方が予約できるようにするため」といった目的を丁寧に説明することが、理解を得る上で大切です。
3. まずは「入口」を増やしたいクリニックでのEPARKの活用法
EPARKは多くの会員数を背景に、検索からクリニックの詳細ページ、そしてネット受付へと続く流れが整っています。自院のウェブサイトを充実させると同時に、EPARKのようなポータルサイトを「もう一つの入口」として活用することで、これまでクリニックの存在を知らなかった新しい患者さんに見つけてもらえる機会を増やすことができます。
- 運用のヒント
- ネット受付の枠は少しずつ開放する最初から全ての枠を開放するのではなく、まずは少なめに設定し、院内の状況を見ながら徐々に増やしていくと、過度な負担なく運用を始められます。
- 初診枠と再診枠を分ける初診の患者さんには問診などで時間がかかるため、再診の方とは別の枠を設けると、全体の流れがスムーズになります。
- 口コミへの返信は丁寧に行う口コミへの返信は、他の患者さんも見ています。感謝の言葉とともに、「また何かお困りの際はご相談ください」といった形で、次の来院につながるようなメッセージを添えると、安心感につながります。
失敗の少ない導入と設定のために確認したい5つのチェックポイント
スタッフの体制も同時に整えましょう
システムの導入直後は、スタッフも患者さんも新しい運用に慣れていないため、一時的に問い合わせが増えたり、混乱が生じたりすることがあります。最初の1〜2ヶ月は、特に混雑が予想される時間帯のスタッフを厚めに配置するなど、無理のない体制でスタートすることが、運用の揺れを最小限に抑えるコツです。短期やスポットでの看護師確保には、クーラの「お試し勤務」のようなサービスも役立ちます(お問い合わせはこちら:https://business.cu-ra.net/)。
よくある質問と、運用のヒント
- Q1:ウェブ予約を導入したのに、電話がなかなか減らないのですが…
- A: 受付スタッフが電話口でウェブ予約の空き状況をすぐに確認し、案内できる体制を整えましょう。EPARKの管理画面には、電話を受けながら空き状況を照会する手順の解説もあります。また、予約完了後の自動返信メールやSMSに「お電話よりもウェブサイトからの予約変更がスムーズです」といった一文を添えるだけでも、次回の予約からウェブを利用してくださる方が少しずつ増えていきます。
- Q2:待合室での患者さんの不満が、以前より強くなった気がします…
- A: まずは診療の遅れ時間を掲示することを最優先で検討してみてください。ドクターキューブの院内ディスプレイは、この「遅れ時間」の表示機能が細かく設定でき、運用しやすいと評判です。また、「お名前をお呼び出しして3回お返事がない場合は、次の方を先にご案内することがあります」といった呼び出しに関するルールも、紙に印刷して掲示しておくと、無用なトラブルを避けやすくなります。
- Q3:オンライン診療に関する質問が多く、受付が対応に追われています…
- A: CLINICSが提供している患者さん向けの手順説明を参考に、自院専用の簡単な図解を作成し、院内での掲示や配布を試してみてください。特に、時間帯予約の考え方(「予約は〇時ちょうどではなく、〇時〜〇時の間のご案内です」という点)を少し大きめの文字で記載しておくと、問い合わせが減る可能性があります。
まとめ:選ぶ基準は「最も優れたシステム」ではなく「自院の混雑に合ったシステム」
どのシステムを導入しても、最初の数ヶ月は必ず「運用を学び、慣れる期間」が発生します。この期間を乗り切るためには、特に混雑する時間帯の人員を少し厚めに確保し、電話、窓口、ウェブサイトでの案内メッセージを、できるだけ「同じ言葉遣い」に統一することが大切です。これだけでも、患者さんが感じる安心感は大きく変わります。人手の調整という点でも、クーラのような短期シフトを活用することは、無理なく運用を軌道に乗せるための一つの方法です(導入に関するご相談はこちらからどうぞ:https://business.cu-ra.net/)。
付録:小さな現場ですぐに使える、ひと言案内の文例
- 予約確認のSMSやLINEで
- 「ご予約は『時間帯』でのご案内です。診察の順番が近づきましたらお呼び出しいたしますので、院外でお待ちの方は〇分前までにお戻りください。」(CLINICSなどで採用されている時間帯予約の考え方を、事前に共有しておく)
- 受付での声かけに
- 「現在、診察は予定より約〇分遅れております。待合室のディスプレイに最新の目安時間が表示されますので、そちらもご確認ください。」(ディスプレイでの表示と、口頭での案内を組み合わせる)
- 電話での問い合わせに
- 「ありがとうございます。ただいまお調べします。ちなみに、ウェブサイトからですと空き状況が一覧でご確認いただけますので、お急ぎの際はそちらが最も早くご予約いただけます。」(ウェブ予約の利便性を伝え、次回の利用を優しく促す)
最後に
この記事でお伝えしたかったことは、とてもシンプルです。
- まず、ご自身のクリニックの混雑パターンを書き出してみる。
- 「予約方式」「目的別の分離」「情報表示」の3点について、改善できそうなところから整える。
- 導入初期は人員を少し厚めにし、スタッフ間の案内の言葉遣いを揃える。
ここまで準備ができれば、どの製品を選んだとしても、きっと以前よりスムーズに回る状態に近づけるはずです。導入に伴う現場の負担を少しでも減らしたい、短期的に人手を確保したい、といったお悩みがあれば、クーラの「お試し勤務」で小さく始めてみるのも一つの手です。まずは、クーラ導入のご相談から、どのような始め方ができるか、情報収集だけでもしてみてはいかがでしょうか。







.avif)
.avif)

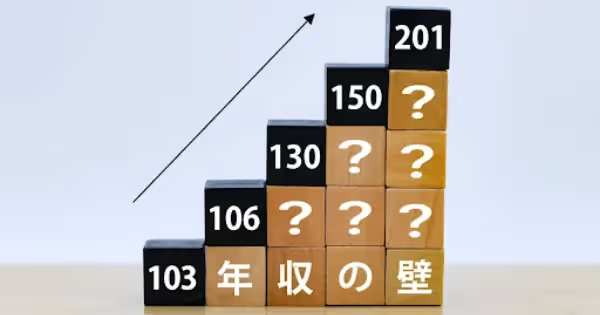
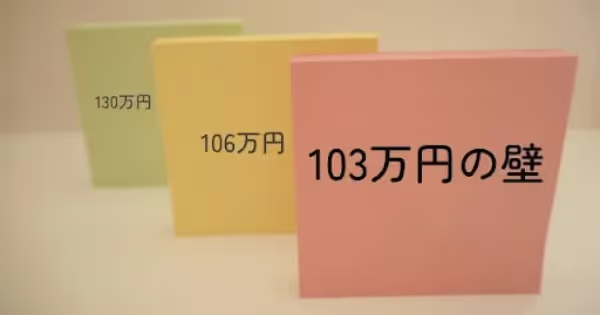







.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
