はじめに:なぜ、推薦文だけでは心もとないのでしょうか
看護師の採用場面で手元に届く推薦文や紹介状、あるいは人材紹介会社からの推薦コメント。目を通すと、「真面目な人柄です」「周囲とのコミュニケーションも良好です」「勤怠も安定していました」といった言葉が並んでいることが多いかもしれません。これらの言葉は、もちろん大切な情報の一つです。
しかし、採用を担う院長先生や看護部長、人事担当者の皆さまが本当に知りたいのは、もう少し具体的な場面での動きではないでしょうか。例えば、「週明けで最も忙しい月曜午前の外来で、20件の採血をどのように工夫して終わらせたのか」「予期せぬインシデントが起きた時、最初に何をして、どのように報告したのか」といった、現場の状況が目に浮かぶような「行動の事実」です。
人柄を表す言葉だけでは、その方が自院のチームに加わった後、日々の業務の中でどのように動き、どのように貢献してくれるのかを具体的にイメージするのは、少し難しいかもしれません。
この記事では、推薦文に書かれた人物評を、より確かで、現場の判断材料として活用できる情報に変えていくための具体的な方法を整理します。小規模な病院やクリニック、訪問看護ステーション、介護施設など、さまざまな現場ですぐに試せるような工夫を、実際の取り組み事例を交えながらご紹介します。また、個人情報保護などの法律面で注意すべき点にも触れ、安心して採用活動を進められるよう配慮しました。
記事の最後には、採用候補者と事業所の双方にとって負担が少なく、入職後のミスマッチを減らすための実務的な方法として、クーラの「お試し勤務」という仕組みの活用もご提案します。採用における不安を少しでも解消し、「この人と一緒に働きたい」と心から思える出会いを増やすための一助となれば幸いです。
背景にある課題:形式的な推薦文から生まれる、三つのすれ違い
推薦文を参考にしつつも、それだけに頼った採用活動には、いくつかの課題が潜んでいることがあります。ここでは、現場でしばしば聞かれる三つの「すれ違い」について、少し掘り下げて考えてみたいと思います。
これらの課題を乗り越えるための一つの考え方として、推薦文を「絶対的な評価」ではなく「参考情報の一つ」と捉え、それを行動事実の確認、現場での様子の観察、そして短期間の試用期間という三つの要素で補っていく、という発想の転換が有効かもしれません。
特に、短期間の試用、いわゆる「お試し勤務」を、法律や労務管理の負担を抑えながらスムーズに導入したい場合には、そのための仕組みが整ったサービスを併用することが現実的な選択肢となります。クーラのようなプラットフォームは、そうしたニーズに応える一つの方法です。ご興味があれば、クーラの事業者向け案内ページ( https://business.cu-ra.net/ )をご覧ください。
他の現場ではどうしてる?「見える化」の工夫事例
推薦文の内容を補うために、他の医療機関や介護施設ではどのような工夫をしているのでしょうか。ここでは、公表されている情報の中から、特に小規模な事業所で参考になりそうな「見える化」の取り組みをいくつかご紹介します。
1. 訪問看護:「見学」や「同行体験」で、現場への適応を事前に確認
訪問看護の現場では、院内とは異なる独自の動き方や判断が求められます。そのため、多くの事業所が、採用選考の段階で実際の業務に触れてもらう機会を設けています。
- 訪問看護ステーションけせら(岩手県)の例
- こちらでは、1日だけの「職場見学」から、3日間から5日間の「同行体験」まで、候補者の希望や状況に応じて選べる段階的なプログラムを用意しています。候補者は、実際に先輩看護師の訪問に同行し、利用者さんとの関わり方、移動のスムーズさ、記録の付け方といった一連の流れを肌で感じることができます。これにより、入職してから「思っていた仕事と違った」と感じることを減らす工夫をされています。
- 社会医療法人大道会 在宅事業部(大阪府)の例
- こちらの採用ページでは、「訪問看護の体験」が可能であることが明記されているだけでなく、入職後の研修体制についても詳しく説明されています。eラーニング(インターネットを通じた学習)や、先輩看護師がマンツーマンで指導するプリセプター制度など、業務に慣れるまでをどのようにサポートするかが具体的に示されています。これにより、候補者は安心してキャリアをスタートできるイメージを持つことができます。
2. 在宅クリニック:「職場体験」の実施を明記し、お互いの目線を合わせる
在宅医療を専門とするクリニックでも、同様の取り組みが見られます。
- 若狭クリニック(埼玉県所沢市)の例
- こちらの看護師募集要項には、「本院に限り、職場体験を実施」という一文がはっきりと記載されています。在宅医療では、医師の訪問に同行したり、必要な物品を準備したり、他の事業所と連絡を取り合ったりと、院内業務とは異なる多様なタスクが発生します。こうした在宅ならではの業務への適性を、書類や面接だけで判断するのではなく、実際の現場で一緒に動いてみることで確認する、という姿勢がうかがえます。
3. 美容皮膚科:選考フローの中に「業務体験」を組み込む
専門性の高いクリニックでも、業務体験は有効な手段です。
- 天神みきクリニック(福岡県福岡市)の例
- こちらのクリニックでは、選考プロセスの中に「実際の業務を体験していただくことがあります」と明記されています。美容皮膚科では、患者さんへの丁寧な説明やご案内、スムーズな動線の確保、専門的な医療機器の準備など、接遇と正確な作業の両方が求められます。こうした細やかな動きや所作は、推薦文を読むだけでは分かりません。短時間でも業務を体験してもらうことで、現場の雰囲気や仕事の流れに馴染めるかどうかを、お互いに見極めることができます。
4. 推薦文だけでは分からなかった経験からの学び
ある企業調査機関が紹介している事例では、面接での印象も推薦文の内容も非常に良かったにもかかわらず、入職後に他のスタッフへの情報伝達がうまくいかなかったり、コミュニケーションの行き違いが頻繁に発生したりしたケースが報告されています。結局、再度、候補者の経歴や働きぶりについて調査(バックグラウンドチェック)をやり直すことになったそうです。これは、人柄の評価だけでは見抜けない部分があることを示す典型的な例であり、やはり実際の現場での観察とセットで判断することの重要性を示唆しています。
こうした「見える化」の取り組みは、推薦文の情報を補い、その信頼性を高める上で非常に有効です。さらに、数日間といった単位での「お試し勤務」を制度として導入することができれば、採用の判断材料の質はもう一段階上がると考えられます。お試し勤務の導入にあたって、煩雑な手続きや労務管理の負担をできるだけ軽くしたいとお考えの場合は、クーラの事業者向け案内( https://business.cu-ra.net/ )をご参照ください。
解決へのアプローチ:推薦文を「検証できる情報」に変える五つの手順
では、具体的にどのようにして、推薦文の内容をより信頼できる情報へと変えていけばよいのでしょうか。ここでは、明日からでも始められる五つの手順を、順を追ってご説明します。
これらの手順をすべて完璧に行うのは大変だと感じるかもしれません。特に、3番目の「業務体験」や4番目の「ミニ試用」の労務管理や書類の準備は、日々の業務に追われる中で大きな負担になりがちです。そうした運用面の負担を軽減し、安全に試用期間を設けたい場合には、クーラ( https://business.cu-ra.net/ )のような、お試し勤務の運営が整ったサービスを活用するのも有効な手段です。
参考:行動の事実を確認するための質問票設計
手順の2番目で触れた「行動を聞く質問」とは、具体的にどのようなものでしょうか。人柄ではなく、過去の具体的な行動や状況判断について尋ねるための質問例を、カテゴリ別にいくつかご紹介します。これらの質問を、以前の上司や同僚、合わせて2名から3名の方に同じ内容で尋ねてみると、回答の一致点や相違点から、候補者の働きぶりを多角的に理解するヒントが得られることがあります。
まとめ:推薦「文」から、検証できる「事実」へ
ここまで、推薦文だけに頼らない採用の進め方について見てきました。大切なポイントを改めて整理します。
- 推薦文は出発点
- 推薦文は、あくまで人物理解の一つのきっかけと捉えましょう。そこに書かれた内容を鵜呑みにするのではなく、これからご紹介する方法で、検証可能な情報へと変えていく視点が大切です。
- 合法的な手順を踏むこと
- 前職照会を行う際は、ご本人の同意を得ること、そして質問内容を業務適性に関連するものに限定することが大前提です。法律やルールを守ることが、信頼関係の第一歩となります。
- 小規模な現場でも工夫は可能
- ご紹介したように、職場見学や業務体験、同行訪問といった取り組みは、事業所の規模に関わらず導入できます。すでに取り組んでいる医療機関の事例も、そのヒントになるはずです。
一歩進んだ実務のイメージ
これまでの内容をまとめると、採用の精度を高めるための具体的な流れは、次のようにイメージできるかもしれません。
「この方は、忙しい時間帯に、どのような業務を、どのくらいの量こなせるのだろうか?」という疑問を確かめるために、まず半日から数日間の現場体験の機会を設けます。同時に、ご本人の同意を得た上で、以前の職場の上司や同僚に、設計した質問票を使って同じ内容を問い合わせます。
この二つの情報(現場での実際の動きと、第三者からの客観的な行動事実)を照らし合わせ、その上で短期間の「ミニ試用期間」に進む。この流れを築くことができれば、採用後のミスマッチを大幅に減らし、現場の誰もが安心して新しい仲間を迎え入れることにつながるのではないでしょうか。
クーラのご案内:低負担で「お試し」を制度化するために
この記事で触れてきた「現場体験」や「ミニ試用」といった仕組みは、採用の精度を高める上で非常に有効ですが、その一方で、募集の告知、応募者とのやりとり、賃金計算、保険の手続きといった事務的な負担が伴うことも事実です。
「クーラ」は、こうした課題を解決するために作られた、看護師専門の募集媒体です。多くの看護師が登録しており、スピーディーな募集が可能なだけでなく、「お試し勤務」の仕組みがパッケージ化されている点が大きな特徴です。
数日間の短期シフトで、まずは現場の雰囲気や業務との相性を見てもらい、お互いに「ここでなら続けられそう」と感じれば、その後の長期的な勤務へとスムーズに移行できます。求人票の作成から、採用後の労務管理に至るまでの事務的な負担を軽減する機能(業務のデジタル化)も備わっています。
こんな時に、クーラの活用をご検討ください
- 推薦文の内容を、実際の現場での行動で確かめたい
- 候補者の方に、まずは短時間でも現場に入ってもらい、安全への意識、患者さんへの接し方、記録の正確さなどを直接確認したい場合に役立ちます。
- 忙しい時期の助っ人を探しつつ、良い人がいれば長く働いてほしい
- 繁忙期やスタッフの休暇が重なる時期に、スポットで人員を補充しながら、その中から自院の理念やチームに合う方を見つけ出し、長期的な採用につなげたい、というニーズにも応えられます。
- 採用プロセス全体の事務負担を減らしたい
- 求人掲載から採用決定、給与支払いまでの流れをシンプルにし、本来の業務である医療・ケアに集中できる環境を整えたいと考えている事業所にも適しています。
まずは、どのようなサービスなのか、下記の事業者向け案内ページからお気軽にご確認ください。
推薦文に書かれた情報を、より確かな「事実」へと変えるための最短ルートとして、クーラの「お試し勤務」を、ぜひ皆さまの現場の新たな一手としてご検討いただければと思います。
付記:この記事を作成する上で参考にした公開情報
- 法律やガイドラインについて
- 厚生労働省が公開している「公正な採用選考の基本」や、採用選考時に配慮すべき事項に関する資料。これらは、採用時に不適切な質問をしたり、不必要な身元調査を行ったりすることを避けるための基本的な指針となります。
- 同意の必要性について
- 弁護士が監修するウェブサイトなどで解説されている、前職照会(リファレンスチェック)は本人の同意が前提であるという法的解釈。
- 看護職員の離職の現状について
- 公益社団法人日本看護協会が2024年に公表した「2023年 病院看護実態調査」における、正規雇用看護職員の離職率11.3%というデータ。
- 現場体験の事例について
- 各医療機関が公式ウェブサイトで公開している採用情報(訪問看護ステーションでの見学・同行プログラムや、クリニックの選考過程における業務体験の明記など)。
この記事が、院長先生、看護部長、事務長、そして人事ご担当の皆さまにとって、「納得のいく採用」を実現するための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。現場の安心を守るために、推薦「文」の確認から、推薦「事実」の確認へ。そして、その確認作業を賢く、負担なく進めるための仕組みを、ぜひ取り入れてみてください。その選択肢の一つとして、クーラの「お試し勤務」がお役に立てる日を心待ちにしております。







.avif)
.avif)

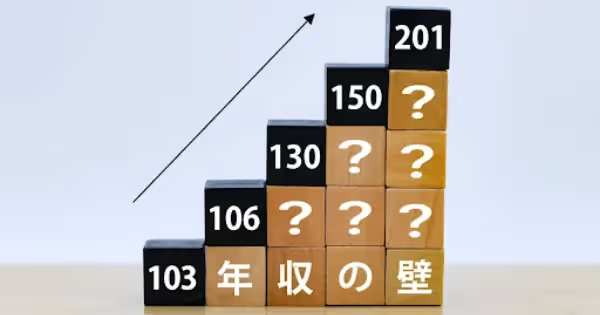
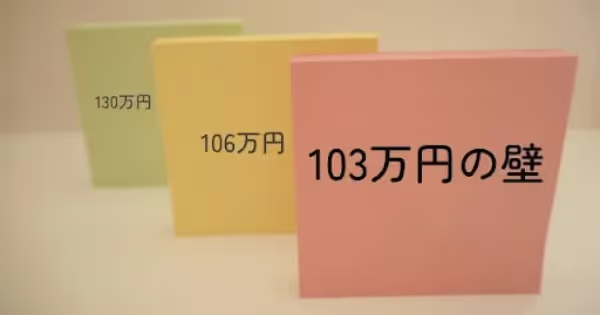







.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
