はじめに:あるクリニックの昼下がりの出来事
「事務長、ちょっといいですか。急で申し訳ないのですが、来週のワクチン外来、どうしてもあと一人、看護師さんが必要でして。知り合いのクリニックを退職された方に、3日間だけスポットでお願いできないか打診しているところです。」
看護部長からの急な相談。クリニックの事務長であるあなたは、「分かりました、手配をお願いします」と答えながらも、頭の中では様々な懸念が渦巻いているのではないでしょうか。
(1日や数日だけの方の給与計算って、常勤と同じで良いのだろうか…)(源泉徴収のルールが違うと聞いたことがある。「丙欄」とかいう言葉だったか…)(マイナンバーは、さすがに数日の勤務の方から頂くのは気が引けるな。でも法律的にはどうなのだろう?)(雇用契約書は?タイムカードは?もし、万が一残業が発生したら…?)
この記事は、看護師の採用や管理に携わる院長、看護部長、理事長、事務長、人事ご担当者の皆様が、スポット・日雇い採用における労務管理のポイントを体系的に理解し、自信を持って実務にあたれるようになることを目指して作成しました。
第1章:源泉所得税のキホン -「丙欄」を正しく理解する
スポット採用の労務管理で、最初につまずきやすいのが税務、特に「源泉所得税」の扱いです。給与から天引きする所得税の金額は、国税庁が発行する「給与所得の源泉徴-徴収税額表」に基づいて決定しますが、スポット勤務の方には特別なルールが適用される場合があります。その鍵となるのが「丙欄(へいらん)」です。
1-1. そもそも「丙欄」とは何か?
「丙欄」とは、給与所得の源泉徴収税額表のうち、「日額表」に設けられている区-分の一つです。これは、日雇いではたらく方や、ごく短期間の雇用契約ではたらく方を対象とした、特別な税額計算ルールとご理解ください。
なぜこのような特別な区分があるのでしょうか。それは、短期的な収入に対して、月給制の常勤スタッフと同じ方法で税金を計算すると、税額が高くなりすぎることがあるためです。丙欄は、そうした短期雇用の方の納税額が過大にならないよう配慮された制度です。
ただし、誰にでも使えるわけではなく、適用できる条件は厳密に定められています。
- 日雇い賃金(日々雇い入れられる人のその日の労働に対して支払う給与)であること
- 雇用契約の期間があらかじめ2か月以内と定められていること
このどちらかの条件に当てはまる場合に、丙欄を使用することができます。
1-2.「甲欄」「乙欄」「丙欄」の違いを整理する
給与計算の実務では、「甲欄(こうらん)」「乙欄(おつらん)」という言葉も頻繁に登場します。この3つの違いを明確に理解しておくことが、正しい給与計算の第一歩です。
以下の比較表は、それぞれの特徴と対象者をまとめたものです。
1-3.【実例で学ぶ】スポット看護師の源泉徴収税額計算
では、実際のケースでどのように計算するのか見ていきましょう。国税庁が公開している「令和7年分 源泉徴収税額表」を参考にします。(税額は近年変動がありませんが、常に最新のものを確認する習慣が大切です)
- ケース1:単発1日、ワクチン接種応援の看護師Aさん
- 勤務条件:1日間のみ
- 給与:日給 25,000円
- 交通費:実費 1,500円を別途支給
- 扶養控除等申告書:提出なし
- まず、交通費は非課税ですので、給与の25,000円のみを課税対象として考えます。
- 国税庁の日額表で「丙欄」の「その日の給与等の金額」の列を見ます。
- 25,000円は、「17,900円以上 25,800円未満」の範囲に含まれます。
- 対応する「税額」の列を見ると、「655円」と記載されています。
- したがって、Aさんに支払う金額は、給与25,000円から源泉所得税655円を差し引いた24,345円、それに非課税の交通費1,500円を加えた、合計25,845円となります。
- ケース2:2か月間の期間限定、週2回勤務の看護師Bさん
- 勤務条件:毎週月・木曜の週2回、8週間の契約(合計16回勤務)
- 給与:1勤務あたり 18,000円
1-4. 最も注意すべき「2か月の壁」と実務対応
スポット採用で最も間違いが起こりやすいのが、この「2か月の壁」です。
- シナリオ:ケース2のBさんの働きぶりが良く、契約満了後、さらに3か月間の契約延長を依頼した
この瞬間、Bさんは「2か月以内の短期契約者」ではなくなります。契約を延長した日から、丙欄は一切使えなくなります。
- 延長後の正しい手続き
- 本人への説明と書類依頼: 契約延長を打診する際に、「長期契約に切り替わるため、税金の計算方法が変わります。つきましては、『扶養控除等(異動)申告書』をご提出いただけますか」と伝えます。
- 申告書の提出があった場合: Bさんが貴院を主たる勤務先とするなら、申告書を提出してもらい、その日以降の給与からは「甲欄」で源泉徴収を行います。
- 申告書の提出がなかった場合: Bさんに別の主たる勤務先がある場合など、申告書の提出がない場合は、「乙欄」で源泉徴収を行います。
- 給与計算システムの更新: 使用している給与計算ソフトがあれば、Bさんの従業員情報を「丙欄適用」から「甲欄適用」または「乙欄適用」に必ず変更します。
この切り替えを怠ると、年末調整や本人の確定申告の際に、追加で多額の税金を納めなければならない事態になりかねません。
煩雑な給与計算・労務管理はシステムで効率化しませんか?
日々の給与計算、特にスポット採用における丙欄と甲乙欄の切り替え管理は、手作業では漏れやミスが発生しやすいポイントです。 看護師に特化した採用・労務管理システム「クーラ」なら、事務長や人事ご担当者様が本来のコア業務に集中できる環境づくりをサポートします。 ご興味のある方は、ぜひこちらのサイトをご覧ください。
第2章:マイナンバーの取り扱い - 収集・保管・廃棄の全手順
「たった数日の勤務の方から、大切なマイナンバーを預かるのは気が重い…」このように感じるのは、ごく自然なことです。しかし、マイナンバーの収集は、事業者の法律上の義務を果たすために、避けては通れない手続きです。
2-1. なぜスポット勤務でもマイナンバーが必要なのか?
結論から言うと、市区町村へ提出する「給与支払報告書」に、従業員のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があるためです。
- 給与支払報告書とは?
- 事業者が、前年中に支払った給与の額などを、従業員が住んでいる市区町村に報告するための書類です。
- 市区町村は、この報告書に基づいて、翌年度の住民税の額を決定します。
- この提出は、給与の支払額の大小や、雇用期間の長短に関わらず、給与を支払った全ての従業員について行うのが原則です。(例えば、横浜市や大阪市などの主要都市でも、同様の案内がなされています。)
つまり、たとえ1日の勤務で支払う給与が少額であっても、事業者はその実績を市区町村に報告する義務があり、その際にマイナンバーが必要となるのです。
2-2. 正しい収集方法と本人確認のステップ
マイナンバーを収集する際は、「番号法(マイナンバー法)」で定められた厳格なルールに従う必要があります。ポイントは「番号確認」と「身元確認」を必ずセットで行うことです。
- 利用目的の明示: まず、なぜマイナンバーが必要なのかを本人に明確に伝えます。「市区町村へ提出する給与支払報告書の作成など、法律で定められた社会保障および税に関する手続きのために利用します」といった形で、口頭または書面で説明しましょう。
- 番号確認と身元確認の実施: 以下のいずれかの方法で確認を行います。
- パターンA(マイナンバーカードを持っている場合): マイナンバーカード1枚で、「番号確認(裏面)」と「身元確認(表面)」が同時に完了します。
- パターンB(マイナンバーカードを持っていない場合):
- 番号確認書類: 「通知カード」または「マイナンバーが記載された住民票の写し」
- 身元確認書類: 「運転免許証」「パスポート」などの顔写真付き身分証明書1点。(もし顔写真付きがない場合は、「健康保険証」と「年金手帳」など、2点以上の書類が必要になります。)
実務上は、これらの書類のコピーを預かるか、番号を正確に書き写すことになります。
2-3. やってはいけない保管・廃棄のNG例
マイナンバーは、その取り扱いに細心の注意が求められる「特定個人情報」です。万が一の漏洩は、事業者の信-用を大きく損なうことになります。
- 保管時のNG例
NG:収集したマイナンバーのコピーを、誰でもアクセスできる共有フォルダに保存する。NG:書類のコピーを、鍵のかからないキャビネットや机の引き出しに無造作に保管する。NG:業務に不要な職員まで、マイナンバー情報にアクセスできる状態にしておく。OK:アクセス制限をかけた特定のフォルダにパスワード付きで保存する。担当者を限定し、鍵のかかる書庫で厳重に管理する。
- 廃棄時のNG例
NG:退職後、不要になったマイナンバーのコピーを、シュレッダーにかけずに一般ゴミとして捨てる。NG:データファイルを、PCのゴミ箱に入れるだけで完全に削除したと思い込む。OK:給与支払報告書の提出など、法律で定められた保存期間が過ぎたものは、速やかにシュレッダーで裁断するか、データ復元ソフトでも復元できない方法で完全に消去する。- 実務上のヒント: 院内で「スポット勤務者のマイナンバー関連書類は、翌々年の3月末に一括してシュレッダー廃棄する」といったルールを定めておくと、管理がしやすくなります。
2-4. もし提出を拒否されたら?
従業員にはマイナンバーを提出する義務まではありません。しかし、事業者には、社会保障や税の手続きのためにマイナンバーの提供を求め、それを記録・管理する義務があります。
もし、従業員から提出を拒否された場合は、以下の対応をとります。
- 再度、利用目的を丁寧に説明し、提供を依頼します。
- それでも提供を得られない場合は、強制することはできません。
- その代わり、事業者として「提供を求めたが、本人の意思により提供されなかった」という経緯を記録として残しておきます。メールでのやり取りや、面談の記録メモなどで構いません。この記録を残すことで、事業者は義務を果たそうと努力した、という証明になります。
「クーラ」について、詳しくは、こちらのサイトでご確認いただけます。
第3章:36協定と労働時間 - 残業ルールの落とし穴
スポット勤務の方にお願いする業務は、基本的に時間内で完結するよう調整するのが理想です。しかし、医療現場では予測不能な事態が常に起こり得ます。「外来が長引いてしまった」「急患の対応が入った」など、やむを得ず所定の時間を超えて勤務をお願いする可能性はゼロではありません。
このような「法定労働時間」を超える労働、いわゆる残業をさせるためには、事前に「36(サブロク)協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。これは、常勤・パート・スポットといった雇用形態に関わらない、すべての労働者に適用される絶対的なルールです。
3-1. 36協定の基本と「全従業員」を対象とすることの重要性
36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定書」の通称です。法律では、労働時間は原則として「1日8時間・1週40時間」以内と定められており、これを超えて労働させること、また、法定休日に労働させることは認められていません。
この法定労働時間を超えて労働させる必要が生じた場合に、事業者と、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで、はじめて時間外労働や休日労働が法的に認められます。
ここで重要なのは、協定の対象となる「労働者の範囲」です。協定書を作成する際に、「対象となる労働者の範囲」を「常勤職員」や「〇〇部の職員」のように限定してしまうと、その範囲に含まれないスポット勤務の方に残業をお願いすることは、たとえ36協定を届け出ていたとしても違法となります。
したがって、協定を結ぶ際には、対象者を「臨時職員、パートタイマー、アルバイト等を含む全ての従業員」といった形で、雇用形態を問わない包括的な範囲で設定しておくことが、いざという時のリスク管理として極めて重要です。
3-2. 医療現場における時間外労働の上限規制
働き方改革関連法により、36協定で定めることができる時間外労働には上限が設けられています。原則として、月45時間・年360時間です。
臨時的な特別な事情がある場合には、労使の合意を経て「特別条項付き36協定」を結ぶことで、この上限を超えることが可能ですが、それでも「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」「月100時間未満」といった厳しい上限が課せられます。
医療現場では、医師の働き方改革も進められている通り、労働時間の管理はますます重要になっています。スポット勤務の方も、この上限規制の対象となります。例えば、ある月に複数の医療機関でスポット勤務をされている方の場合、労働時間は通算されます。貴院での残業が、その方の全体の労働時間上限を超えるきっかけにならないよう、配慮が求められます。
3-3. スポット採用における安全な労務設計
トラブルを未然に防ぐためには、そもそも残業が発生しない業務設計が最も安全です。
- 業務範囲の明確化: 労働条件通知書や雇い入れ時の説明で、「ご担当いただく業務は〇〇です。原則として時間外労働はありません」と明確に伝えておきます。
- 引継ぎ時間の確保: 勤務終了時刻の15分前には、常勤スタッフへの引継ぎを完了してもらうよう、業務フローに組み込みます。
- 緊急時の役割分担: 勤務終了間際に緊急事態が発生した際は、常勤スタッフが対応を引き継ぐ体制をあらかじめ整えておきます。
こうした配慮は、労務リスクを回避するだけでなく、スポットで働く方が安心して勤務できる環境づくりにも繋がり、今後の協力関係を良好に保つ上でも有効です。
第4章:社会保険・労働保険 - 加入義務の境界線
スポット勤務の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険の対象となることは少ないですが、契約条件や更新の状況によっては加入義務が発生します。一方で、労災保険は雇用形態に関わらず、すべての労働者が対象です。これらの違いを正確に把握しておくことが重要です。
4-1. 労災保険:すべての労働者を守る、必須のセーフティネット
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度です。
- 加入対象: 労働者を一人でも使用するすべての事業所に、加入が義務付けられています。雇用形態、勤務時間、賃金額に関わらず、すべての労働者が対象です。つまり、1日だけのスポット勤務の看護師さんも、勤務を開始した瞬間から労災保険の保護対象となります。
- 保険料: 全額事業主負担です。
- 具体例:
- 業務災害: 勤務中に院内で足を滑らせて転倒し骨折した。患者さんの介助中に腰を痛めた。採血時に誤って自分の指に針を刺してしまった(針刺し事故)。
- 通勤災害: クリニックへ向かうため自宅から最寄り駅まで歩いている途中で、自転車にはねられ負傷した。
もしもの事態が発生した場合、事業者は速やかに所轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出するとともに、被災した本人が適切な保険給付を受けられるよう、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」などの必要書類の準備をサポートする必要があります。
4-2. 雇用保険:「31日以上の雇用見込み」の判断基準
雇用保険は、労働者が失業した場合などに給付を行うための保険です。スポット勤務の方が加入対象となるかは、以下の2つの要件を両方満たすかで判断します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
週1日・8時間勤務のような典型的なスポット契約では、1.の要件を満たさないため対象外です。
問題は2.の「31日以上の雇用見込み」の解釈です。これは、契約期間が31日未満であっても、実質的に31日以上雇用が継続する可能性がある場合には、加入義務が生じるという考え方です。具体的には、以下のようなケースが「見込みあり」と判断される可能性があります。
- 契約書に「契約を更新する場合がある」旨の記載がある場合。
- 同様の雇用契約で、過去に31日以上にわたって雇用された実績がある場合。
- 明確な規定はなくても、同様の立場の他の従業員が31日以上雇用されている実態がある場合。
例えば、「1か月の短期契約」で採用したものの、状況により契約更新の可能性を伝えているような場合は、当初から加入手続きが必要となる可能性がありますので、注意が必要です。
4-3. 社会保険:契約更新時に特に注意が必要な「2か月の壁」
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、常勤の従業員と比較して労働時間・日数が概ね4分の3以上の場合に加入義務が生じます。スポット勤務でこの基準を満たすことは稀ですが、ここでも契約期間が重要な判断基準となります。
特に注意したいのが、当初「2か月以内の期間を定めて雇用」した場合の扱いです。法律上、当初の契約期間が2か月以内であれば、社会保険の適用除外となります。しかし、その契約が更新され、結果として2か月を超えて雇用されることになった場合は、当初の契約期間の初日から遡って社会保険の被保険者資格を取得することになります。
- シナリオ:
- 4月1日から5月31日までの「2か月契約」で看護師Dさんを採用。この時点では社会保険は適用除外。
- 5月末、Dさんの勤務を継続してもらうことになり、6月1日以降も契約を更新。
- この瞬間、Dさんは4月1日に遡って社会保険の被保険者となります。
この場合、事業者は遡及分の保険料(事業者負担分と本人負担分)をまとめて納付する必要があり、本人にも保険料の負担が発生します。短期契約から長期契約への切り替えを検討する際は、この社会保険の遡及適用について、事前に本人へ十分な説明を行い、理解を得ておくことが不可欠です。
第5章:法定帳簿と書類 - 作成・保管の義務
労働基準法では、事業者に「法定三帳簿」と呼ばれる3つの重要な帳簿を作成し、保管することを義務付けています。この義務は、日雇いやスポット勤務の方にも等しく適用されます。
5-1. 法定三帳簿の基本
- 労働者名簿:
- 従業員の氏名、生年月日、履歴、住所、従事する業務の種類などを記載した書類です。
- 労働基準法第107条で作成が義務付けられています。
- 賃金台帳:
- 氏名、性別、賃金の計算期間、労働日数、労働時間数、基本給や手当の種類と額、控除した項目と額などを記載した書類です。給与明細の元となる重要な情報です。
- 労働基準法第108条で作成が義務付けられています。
- 出勤簿(タイムカードなど):
- 従業員の出退勤時刻や休憩時間など、労働時間を客観的に記録したものです。賃金台帳に労働時間数を記入する際の根拠となります。
これらの帳簿は、労働基準法第109条により、従業員の退職、解雇または死亡の日から5年間(ただし、当分の間は経過措置として3年間)の保存が義務付けられています。
5-2. 日雇い向け様式の活用で効率化
「たった1日の勤務の方のために、これらの帳簿を全て揃えるのは大変だ」と感じるかもしれません。その負担を軽減するため、厚生労働省は「日雇い労働者名簿兼賃金台帳」という、労働者名簿と賃金台帳を一枚にまとめた便利な様式を提供しています。
この様式を活用すれば、必要事項を漏れなく記録でき、書類管理の手間も省けます。
5-3.【院内掲示用】スポット採用の業務フロー
採用が決まってから、給与支払い、そして退職後の手続きまでの一連の流れを可視化しておくことは、担当者が変わっても業務品質を維持するために有効です。以下に、その流れをタイムライン形式でまとめました。
5-4.【保存版】提出・作成書類の完全チェックリスト
手続きの漏れを防ぐために、以下のチェックリストをご活用ください。
第6章:よくあるご質問(FAQ)
ここでは、スポット採用の実務において、特にお問い合わせの多い質問とその回答をまとめました。
- Q1. 丙欄と乙欄の違いが、今ひとつ分かりにくいです。
- A1. 勤務期間で使い分けるとシンプルです。「2か月以内の短期契約」であれば「丙欄」を適用します。一方で、契約期間の定めがない、あるいは2か月を超える契約で、かつ「扶養控除等申告書」の提出がない方(主に他でメインの勤務先がある方)には「乙欄」を適用します。「丙欄」は短期雇用向けの特別な区分、と覚えておくと分かりやすいです。
- Q2. 「業務委託契約」にして、個人事業主として働いてもらえば、これらの手続きは不要になりますか?
- A2. 形式的に「業務委託契約」を結んでいても、実態として「指揮命令関係」があると判断されれば、労働基準法上の「労働者」とみなされ、雇用契約と同様の義務が発生します。例えば、「勤務時間や場所が指定されている」「業務の進め方について具体的な指示がある」といった場合は、労働者性が高いと判断される可能性が高いです。看護業務のように、院内のルールや医師の指示のもとで行われる業務は、一般的に業務委託には馴染みにくいと考えられます。安易な判断はせず、実態に即して契約形態を選ぶことが重要です。
- Q3. スポット勤務の方にも、源泉徴収票の発行は必要ですか?
- A3. はい、必要です。所得税法により、給与を支払ったすべての従業員に対して、源泉徴収票を発行する義務があります。年の途中で退職したことになるため、退職後1か月以内に本人に交付するのが原則です。本人が確定申告をする際に必要となる大切な書類です。
- Q4. 給与を現金で手渡しする場合の注意点はありますか?
- A4. 現金で支払うこと自体は問題ありません。ただし、必ず「給与明細」を交付し、総支給額、控除額、差引支給額を本人が確認できるようにしてください。また、本人が給与を受け取った証として、受領印やサインをもらっておくと、後の「払った・払わない」といったトラブルを防ぐことができます。賃金台帳への記録も忘れずに行いましょう。
- Q5. スポット勤務の方に、休憩時間は必要ですか?
- A5. はい、必要です。労働基準法第34条で定められた休憩時間は、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。
- Q6. 交通費の非課税限度額とは何ですか?
- A6. 電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、所得税法上、1か月あたり15万円までは非課税と定められています。スポット勤務で日払いの場合も、このルールに準じ、合理的な運賃の実費であれば非課税として扱って問題ありません。ただし、この非課税枠を超える高額な交通費や、マイカー通勤で規定を超える額を支給した場合は、超えた分が給与として課税対象になります。
おわりに:スポット採用を、貴院の強みに変えるために
ここまで、スポット・日雇い看護師を採用する際の税務、マイナンバー、労働時間、保険、そして帳簿管理といった多岐にわたるテーマについて、具体的な実例を交えながら解説してきました。情報量が多く、複雑に感じられた部分もあったかもしれません。
しかし、これらの手続きの一つひとつは、特別なものではなく、法律で定められた基本的なルールに則ったものです。そして、その根底にあるのは、働く人を守り、事業者との間で公正な関係を築くという考え方です。
スポット採用は、もはや「緊急時のイレギュラーな対応」ではありません。多様な働き方を望む看護師が増えている現代において、常勤採用と並ぶ、戦略的な人材確保の重要な柱です。適切な労務管理体制を整え、安心して働ける環境を提供することは、優秀な人材に「またこのクリニックで働きたい」と思ってもらうための、何よりの投資と言えるでしょう。
この記事でご紹介した知識やツールが、貴院の労務管理体制を見直し、よりスムーズで確実なスポット採用を実現するための一助となれば幸いです。
クーラ導入でさらにラクに
- 労働条件通知書・名簿・台帳を自動作成
- 短期→継続採用へのスムーズな移行をシステムで誘導
「スポット雇用=煩雑そう」を「むしろシンプル」に変えられる。
クーラなら、労務事故の不安を最短で解消できます。
→ 詳しくはこちら:https://business.cu-ra.net/

.jpeg)





.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)





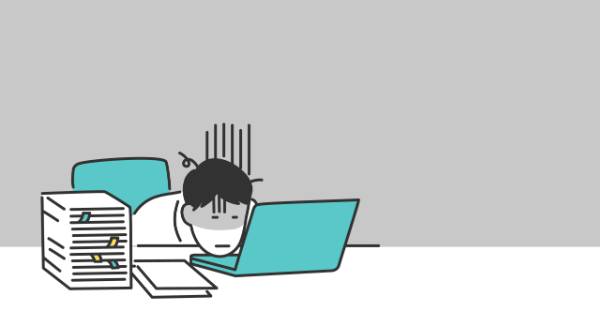
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
