いま「多言語予約」の仕組みを整える理由
日本の社会で暮らす外国籍の方々の数は、年々増加傾向にあります。法務省の発表によると、在留外国人数は2023年末時点で約341万人に達し、過去最多を更新しました。この数は今後も増えていくと見込まれています。このような状況の中、日々の診療の現場でも、日本語を母語としない患者さんを受け入れる機会は、規模の大小を問わず、あらゆる医療機関で増えているのではないでしょうか。
特に、患者さんとの最初の接点となる「予約」の段階から多言語に対応できる体制を整えることは、多くの利点をもたらします。予約がスムーズに進むことで、受付での待ち時間を短縮でき、情報の聞き間違いや勘違いといったトラブルを未然に防ぐことにつながります。そして何よりも、言葉の壁に不安を感じている患者さんご本人に、大きな安心感を与えることができます。
しかし、多くのクリニック、特に限られた人員で運営されている小規模な医療機関にとって、常に多言語対応が可能なスタッフを配置し続けることは、現実的に難しい面もあるかもしれません。だからこそ大切なのは、「できること」と「できないこと」の線引きをあらかじめ明確にしておくことです。全ての場面で完璧な通訳を目指すのではなく、機械翻訳を手軽に活用できる場面と、専門の医療通訳サービスに頼るべき場面を賢く使い分ける。そのような現実的な運用設計を考えることが、持続可能な多言語対応の第一歩となります。
この記事では、小規模なクリニックや病院が、外国人患者さんの予約対応を円滑に進めるための具体的な方法や工夫、そして便利なツールや公的サービスについて、実際の事例を交えながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。
新しい体制を導入する際、特に立ち上げ期や繁忙期には、受付や電話対応の一次対応スタッフが一時的に不足することもあるかもしれません。そのような場合に備えて、短期間からでも人材を募集できるサービスをあらかじめ知っておくと、心強い備えになります。例えば、看護師の登録者が多く、一日単位の「お試し勤務」という仕組みでミスマッチのリスクを抑えながら迅速に募集ができる「クーラ」のようなサービスを併用することで、人員面の不安を和らげながら、新しい運用のテストや導入を進めることが可能になります。https://business.cu-ra.net/
予約の段階で起こりやすい、多言語対応のつまずき
外国人患者さんの対応において、問題が起きやすいのは、実は診察室の中だけではありません。最初の入り口である「予約」の時点で、いくつかの典型的なつまずきのパターンが見られます。事前にこれらの課題を把握しておくことで、対策が立てやすくなります。
予約情報の取り違え
最も頻繁に発生するのが、予約の基本情報に関する行き違いです。日付や時間の聞き間違いは、特に電話予約で起こりがちです。例えば、「しちじ(7時)」と「いちじ(1時)」の聞き間違いや、日本独自の元号表記、午前と午後の混同などが原因となります。また、どの診療科を希望しているのか、初診なのか再診なのかといった基本的な情報の確認も、言葉の壁があるとスムーズにいかないことがあります。
さらに、患者さんが伝えたい症状を自由に記述してもらう欄では、文章が長くなればなるほど、機械翻訳の精度が落ち、誤訳が生じる可能性が高まります。翻訳ツールが症状を実際よりも軽く訳してしまったり、あるいは全く異なる意味で伝わってしまったりすると、来院時の対応に遅れや混乱が生じる原因にもなりかねません。
本人確認と支払いの不安
次に、本人確認と医療費の支払いに関する説明の難しさがあります。日本の医療保険制度は複雑で、国民健康保険、社会保険、あるいは旅行者保険など、患者さんが加入している保険の種類によって、窓口での手続きや自己負担額が変わってきます。これらの違いを口頭で、しかも不慣れな言語で正確に説明することは非常に困難です。
こうした場面では、「やさしい日本語」、つまり簡単な単語や文法を使い、一文を短くして話す工夫と、あらかじめ多言語で用意された定型の案内文を見せることが有効です。しかし、自己負担の上限額や、保険適用外の費用に関する但し書きなど、細かなニュアンスが求められる説明は、こうした工夫だけでは十分に伝わらないことも多く、後の会計トラブルにつながる可能性が残ります。
予約時に“説明し過ぎる”ことの危険性
患者さんを安心させたいという思いから、予約の段階で治療内容や考えられるリスク、同意事項の詳細まで踏み込んで説明しようとすることがあります。しかし、これはかえって危険を伴う場合があります。専門的な医療用語を含むインフォームド・コンセント、つまり「十分な情報を得た上での同意」に関する説明は、極めて正確性が求められます。
機械翻訳や、医療知識のないスタッフによる自己流の通訳を介してこれらの説明を行うと、情報が不完全、あるいは不正確に伝わってしまう恐れがあります。その結果、患者さんは内容を十分に理解しないまま同意したことになってしまい、万が一の際に重大な問題に発展しかねません。インフォームド・コンセントのような重要な説明は、予約時に不完全な形で行うのではなく、必ず来院していただいた上で、医療通訳の専門家を介して、時間をかけて確実に行うのが安全な運用です。
院内の対応リソース不足
多くの小規模クリニックでは、英語やその他の言語に堪能なスタッフが常駐しているわけではありません。特定のスタッフ一人の語学力に依存してしまうと、その人が不在の日に対応ができなくなってしまいます。そのため、院内にいるスタッフだけで全てを解決しようとするのではなく、外部の力を上手に借りる視点が重要になります。
例えば、自治体が提供している無料または安価な医療通訳サービスや、NPOなどが作成・公開している多言語の問診票、厚生労働省が提供する説明資料など、すでに存在する便利なリソースは数多くあります。これらをいかに自院の運用フローの中に「つないで」いくか。その仕組みを構築する力が、限られた人員で多言語対応を実現するための鍵となります。
小さな医療機関の、賢い取り組み事例
多言語対応というと、特別な設備や多額の費用が必要だと感じられるかもしれません。しかし、日本全国の小規模な病院やクリニックでは、すでにあるものを活用したり、少しの工夫を加えたりすることで、外国人患者さんが安心して受診できる環境を整えています。ここでは、具体的な事例をいくつかご紹介します。
1. 静岡県・森町家庭医療クリニックの取り組み(小規模・町立)
静岡県周智郡森町にあるこのクリニックは、地域に暮らす外国人患者さんのために、費用を抑えながら通訳体制を構築した好例です。
- 無料の遠隔医療通訳をフル活用
- 当初、クリニックが契約していた保険会社を通じて、無料で利用できる電話通訳サービスを活用していました。ただし、利用には回数や時間の上限がありました。そこで、より安定した運用を目指し、静岡県が提供する24時間対応の医療通訳事業へと移行しました。これにより、費用を気にすることなく、必要な時にいつでも専門の通訳を介して患者さんとコミュニケーションが取れる体制を整えました。
- 地域への積極的な情報発信
- クリニックが目指しているのは、単に言語の壁を解消するだけではありません。「予約がなくても診察は受けられるが、予約をした方が待ち時間は短くなること」や、「言葉の心配はしなくても大丈夫です」というメッセージを、地域の外国人コミュニティに積極的に周知したいと考えています。これにより、患者さんが受診をためらうことなく、適切なタイミングで医療にアクセスできる環境づくりを進めています。
- 現場でのリアルな運用
- 実際に、このクリニックでは月に約40人ほどの外国人患者さんが受診しますが、そのうち電話通訳を利用するケースは月に4〜5回程度だといいます。全ての会話に通訳を入れるのではなく、本当に必要な場面、例えば症状の詳細な聞き取りや、医師からの重要な説明の際に限定して活用することで、効率的な運用を実現しています。町の規模の公立クリニックでも、既存の公的サービスを起点にすることで、着実に体制づくりを前進させられることを示唆する事例です。
2. 徳島県・松永病院の現在進行形の取り組み(小規模病院)
徳島県にある松永病院では、デジタルツールを積極的に活用し、予約から診察までの流れをスムーズにするための仕組みを構築しています。
- 多言語ウェブ問診とホームページの多言語化
- 来院前に患者さん自身のスマートフォンやパソコンから症状などを入力できる「ウェブ問診システム」を導入し、英語、中国語、韓国語に対応させました。患者さんが母国語で入力した内容は、院内の電子カルテシステムには日本語で連携されるため、スタッフはスムーズに情報を把握できます。また、病院の公式ホームページも多言語化し、診療時間やアクセス方法などの基本情報を分かりやすく提供しています。
- LINE公式アカウントを問い合わせ窓口に
- 多くの外国人にとって日常的なコミュニケーションツールであるLINEを活用し、公式アカウントを開設しました。院内に掲示したQRコードから簡単に友達登録ができるため、電話をかけることに抵抗がある人でも、気軽に問い合わせができる一次窓口として機能しています。
- 役割分担の明確化
- デジタルツールで効率化を図る一方で、安全性が最優先される場面での線引きを明確にしています。特に、医師による診察やインフォームド・コンセントの場面では、ウェブ問診の内容だけで判断するのではなく、必ず電話医療通訳サービスを利用することを必須のルールとして定めています。その際、医師は「やさしい日本語」を使い、「はい(Yes)」か「いいえ(No)」で答えられるような短い質問を心がけることで、通訳を介したコミュニケーションの精度を高めています。予約から来院までの利便性と、診察の厳密な運用を両立させている実践的な例です。
3. “すでにある”リソースの賢い流用術
特別なシステムを導入しなくても、公的機関やNPOが提供している無料のリソースを上手に活用することで、多言語対応の基盤を築くことができます。
4. 予約システム側の“多言語”機能を上手に使う
近年、多くのオンライン診療予約システムには、基本的な多言語対応機能が備わっています。自院で現在利用しているシステムに、言語切り替えのオプションがないか、まずは確認してみることをお勧めします。
これらの機能を使えば、予約画面の日付や時間、診療科といったラベルを多言語で表示させることができます。また、休診日の案内や、来院時の注意事項といった、クリニック独自のメッセージを多言語で設定できるシステムもあります。
多言語対応の予約システムを活用する際のコツは、患者さんの入力をできるだけ「選択式」にすることです。自由記述の欄を多用すると、前述の通り誤訳のリスクが高まります。主な症状や来院目的などを選択肢としてあらかじめ用意し、自由記述は補足的な情報(例えば「その他、特に伝えたいことがあれば短く書いてください」など)に限定する設計にすることで、情報の正確性を高め、誤解を減らすことができます。小規模なクリニックの導入事例を紹介する記事などでも、こうした予約システムの多言語機能の有用性がたびたび取り上げられています。
(人手の確保について)受付や電話の一次対応、あるいは多言語対応のテスト運用を行う期間だけでも、スタッフを増員したいと考えることがあるかもしれません。そのような時には、短期間のお試し勤務で人材を確保できるサービスを並行して利用すると、立ち上げがスムーズに進みます。「クーラ」は看護師の登録者数が多く、募集から労務管理までの負担をデジタル技術で軽減できるため、実務の特に忙しい時期を乗り越えるための一つの選択肢として有効です。https://business.cu-ra.net/
解決へのアプローチ:機械翻訳の限界を踏まえた「線引き」と運用ルール
多言語対応を安全かつ持続可能なものにするためには、「この場面では機械翻訳で十分」「この場面では必ず専門の通訳を使う」という明確なルール、つまり「線引き」を院内で共有することが不可欠です。ここでは、具体的な場面ごとに、その線引きと運用のポイントを解説します。
A. 予約段階(ウェブ、電話、メッセージ)での線引き
- 機械翻訳を使っても差し支えのない範囲
- 予約画面の基本的な項目:日時、診療科、初診か再診か、支払い方法の選択肢など、定型的で誤解の生じにくい部分の表示。
- 自動返信メッセージ:予約が受け付けられたことを伝える完了通知や、来院時の持ち物、キャンセルに関する規定など、あらかじめ決まった内容の定型文。
- 「やさしい日本語」を使った定型的な質疑応答:「遅刻しそうな場合はどうすればいいですか?」「当日のキャンセルはできますか?」といった、よくある質問に対する回答。これらの文章は、鳥取県などが公開している「やさしい日本語」のガイドラインを参考に作成すると、より伝わりやすくなります。
- 専門の通訳を要する、あるいは特に注意が必要な範囲
- 症状に関する詳細な聞き取り:特に、使用中の薬剤、アレルギーの有無、妊娠の可能性など、患者さんの安全に直結する重要な情報に関する聞き取り。
- 検査や処置に関する同意説明(インフォームド・コンセント):検査や治療の目的、内容、伴う可能性のある副作用やリスク、代替となる治療法の選択肢、そしてそれに伴う費用などの説明。
- 特別な配慮が必要な場面:未成年者の受診で保護者の同意が必要な場合や、精神科、産婦人科の診療など、患者さんの自己決定を慎重に支援する必要がある場面。
これらの重要事項については、予約の段階では「概要の把握」に留めるという運用ルールを徹底することが賢明です。そして、患者さんが来院された際に、電話やビデオを通じた医療通訳サービスを利用して、改めて正確なインフォームド・コンセントを実施する。この二段階の運用が、医療安全を守る上で極めて重要です。
B. ツールの使い分け(一次受付から診察まで)
来院された患者さんをスムーズに診察へとつなぐため、複数のツールを役割分担させて組み合わせることが有効です。
- 「やさしい日本語」と多言語問診票で“聞き漏れ”を減らす
- 予約時にはウェブの選択式フォームで大枠を掴み、患者さんが来院されたら、受付で紙の多言語問診票を渡して詳細を記入してもらいます。そして、特に重要だと考えられる項目(アレルギーや持病など)については、医療通訳を介して口頭で再確認する。この多段階の確認プロセスを踏むことで、情報の聞き漏れや誤解を最小限に抑えることができます。
- 電話やビデオの医療通訳を“要所”で活用する
- 通訳サービスは、全ての会話で利用する必要はありません。コストと時間を効率的に使うためにも、利用する場面を限定することが重要です。インフォームド・コンセント、処方する薬の変更、外科的な処置に関する説明、あるいは万が一医療上の問題が発生した際の報告など、法的な責任が伴う重要な説明の場面では、必ず医療通訳を介在させるというルールを徹底します。
- AI電話やチャットボットによる一次受け
- 最近では、人工知能(AI)を活用した電話自動応答や、ウェブサイト上のチャットボットサービスも進化しています。これらを活用して、休診日の案内、再診の予約、予約時間の変更といった定型的な用件の“最初の受け皿”を用意することができます。そして、AIが対応できない複雑な問い合わせや、緊急性が高いと判断されるキーワードを含む用件については、人間のスタッフと専門の通訳へと自動的に引き継ぐ(エスカレーションする)仕組みを構築することで、24時間対応の窓口を効率的に運用できます。
C. 誤訳を起こしにくい予約フォームの作り方の工夫
オンライン予約フォームの設計を少し工夫するだけで、機械翻訳による誤訳のリスクを大幅に減らすことができます。
- 自由記述欄は短く、一問一答の形式に分割する
- 「症状を詳しく書いてください」のような大きな自由記述欄を一つ設けるのではなく、「痛いのはどこですか?」「いつから痛いですか?」「熱はありますか?」のように、質問を細かく分割します。これにより、患者さんは短い単語や一文で答えられるようになり、翻訳の精度が向上します。
- 単位、数字、時刻の表記を統一する
- 温度は「37.8℃」のように摂氏で、期間は「3 days」のように具体的な数字で、時刻は「AM/PM」ではなく「14:30」のような24時間表記に誘導するなど、世界的に誤解されにくい表記(ISO表記に近い形)を促します。
- 画像やイラストで補助する
- 人体のイラストを提示し、「痛い場所を指してください」と促すなど、視覚的な補助を用いることで、言葉だけに頼らないコミュニケーションが可能になります。
- 自動返信メールは二言語併記を基本とする
- 予約完了後に送る自動返信メールには、「やさしい日本語」とその下に英語を併記するのが親切です。そして、「来院された際に、通訳を介して詳しくお伺いしますのでご安心ください」といった一文を必ず添えることで、患者さんの不安を和らげ、予約段階での過度な情報伝達を避けることができます。
D. 電子カルテやウェブ問診との“つなぎ”
予約時や来院時に得た多言語の情報を、いかに効率的かつ正確に院内の診療録(カルテ)に反映させるかも重要なポイントです。
- ウェブ問診からカルテへの自動連携
- 先述の松永病院の事例のように、多言語ウェブ問診システムと電子カルテシステムが連携可能であれば、それが最も理想的です。患者さんが母国語で入力した情報が、スタッフの画面では日本語に自動変換されて表示されるため、受付での転記作業がなくなり、ミスを防ぐことができます。
- 連携が難しい場合の代替案
- システムの連携が難しい場合は、次善の策として、記入済みの多言語問診票(ウェブの場合は画面キャプチャやPDF)をスキャナーで取り込み、画像データとして電子カルテに添付する方法があります。その上で、受付スタッフや看護師が、その内容の要点のみを日本語で要約してカルテに記載します。この際、要約する項目をあらかじめ定めた「要約文のひな形」を用意しておくと、スタッフによる記載内容のばらつきを防ぎ、品質を均一に保つことができます。
E. 夜間や時間外の対応に関する線引き
診療時間外の問い合わせにどう対応するかも、あらかじめルールを決めておく必要があります。
- 自動応答システムによる一次受け
- 夜間や休診日は、AI電話や予約システムの多言語自動応答メッセージで一次対応を行います。そして、もしメッセージの中に「胸が痛い」「呼吸が苦しい」「妊娠中の出血」といった緊急性が高いと疑われる危険なキーワードが含まれていた場合に、自動的に「救急車(119番)を呼ぶか、救急相談センターに連絡してください」という案内や、「翌日の診療開始後に、通訳を付けてこちらから折り返し連絡します」といった指示に切り替える設定をしておくと、リスク管理につながります。
- 緊急連絡先を常に明記する
- 留守番電話のメッセージや、ウェブサイトの問い合わせフォームには、「緊急の場合は、119番に電話するか、救急案内を利用してください」という定型文を、複数の言語で常に表示しておくことが重要です。この際の文言は、厚生労働省が提供している多言語資料の用語を参考に、公的に使われている表現に統一することで、より正確に意図が伝わりやすくなります。
(人手が足りない場合の現実的な解決策)こうした新しい仕組みを導入する初期段階では、どうしても一時的に業務負担が増えることがあります。その期間だけ、受付補助や院内案内のためのスタッフを短期で確保するのも、現実的な解決策の一つです。ミスマッチが生じにくい「お試し勤務」の仕組みがある「クーラ」のような募集サービスを活用すれば、必要な日数だけ人員を増やし、導入の山を乗り越えるといった柔軟な運用がしやすくなります。https://business.cu-ra.net/
まとめ:予約は“軽やかに”、診察は“慎重に”。役割分担で安全な運用を
外国人患者さんの多言語対応を、全て自院のスタッフだけで完璧に行おうとすると、負担が大きくなり、長続きしません。大切なのは、それぞれの場面やツールが持つ役割を明確に分け、それらを上手に組み合わせることです。
- 予約の役割は「日時・目的・持ち物の確認」
- この段階では、完璧な意思疎通を目指す必要はありません。オンライン予約システムの選択式項目や短い文章での入力を中心に据え、機械翻訳で誤解が生まれにくい設計を心がけます。「やさしい日本語」と、あらかじめ用意した多言語の定型文をうまく活用しましょう。
- 診察の役割は「評価・説明・同意」
- ここは、医療の安全と質に直結する最も重要な場面です。インフォームド・コンセントや、薬剤の変更、治療方針に関する重要な説明など、責任の重いコミュニケーションは、自己流の判断をせず、必ず専門の医療通訳を介して慎重に行うことをルールとします。
- 既存の公的リソースを積極的に組み合わせる
- 多言語問診票、厚生労働省の多言語説明資料、自治体が提供する通訳事業など、無料で利用できる優れたリソースがたくさんあります。これらを“知っている”だけでなく、自院の業務フローの中に“組み込む”ことで、小規模なクリニックでも、費用を抑えながら多言語対応の体制を構築することが可能です。
- 予約システムとAIの一次受けで、24時間迷わせない導線をつくる
- 診療時間内外を問わず、患者さんがいつでも最初のアクセスポイントを見つけられるように、予約システムの多言語機能やAIによる自動応答を活用し、「迷わない」導線を設計することが、患者さんの安心につながります。
(最後に)新しい体制の立ち上げに際して、もし人員面での不安が少しでも残るようであれば、「必要な日だけスタッフを増やす」という柔軟な選択肢があることを、ぜひ覚えておいてください。看護師の登録者数が多く、迅速な募集が可能で、ミスマッチを減らす「お試し勤務」の仕組みを持つ「クーラ」は、求人から労務管理までの負担をデジタル技術で軽減できる募集サービスです。多言語予約という新しい体制づくりの最初の一歩を、より安全に、そして安心して進めるための後ろ盾として、一度検討してみてはいかがでしょうか。https://business.cu-ra.net/
付録:導入時に最低限そろえておきたいチェックリスト
何から手をつければ良いか分からない、という場合は、まず以下のリストを参考に、一つずつ準備を進めてみてください。これらを順番に整えるだけでも、多言語予約の“安全な運用”へと大きく踏み出すことができます。
- 予約画面の多言語表示と自動返信文の準備
- 見出し行現在使用している予約システムの多言語設定を確認し、日時、診療科、初診・再診、支払い方法といった基本的なラベルを、少なくとも英語で表示できるように設定します。また、予約完了時に自動送信されるメールの文面を、「やさしい日本語」と英語を併記した形で見直します。
- 「やさしい日本語」での質疑応答集(FAQ)の作成
- 見出し行「遅刻」「当日キャンセル」「持ち物」「保険証の確認」など、頻繁に受ける問い合わせについて、簡潔で分かりやすい「やさしい日本語」での回答集を作成し、院内スタッフ間で共有しておきます。順天堂大学などが公開している医療分野のやさしい日本語の事例も参考になります。
- 多言語問診票の印刷と配置
- 見出し行かながわ国際交流財団などが提供する23言語対応の多言語問診票を、自院の診療科目に合わせて数種類、あらかじめ印刷して受付にストックしておきます。そして、どのスタッフでも外国人患者さんにスムーズに渡せるよう、配布の手順を確認しておきます。
- 医療通訳サービスの利用手順と院内ルールの策定
- 見出し行地域の自治体や契約している保険会社などが提供する電話・ビデオ医療通訳サービスについて、「誰が、どの電話機やタブレット端末を使い、どの番号にかけるのか」という具体的な接続手順をマニュアル化します。同時に、「インフォームド・コンセントの際は必ず通訳を利用する」という院内ルールを明確にし、全スタッフに周知徹底します。
- 危険なキーワードへの対応ルールの設定
- 見出し行夜間や休診日にAI電話やチャットボットを運用する場合、どのようなキーワード(例:胸痛、呼吸困難)を検知したら、人への引き継ぎや救急案内へ誘導するのか、そのエスカレーションのルールをあらかじめ設定しておきます。
- 利用可能な公的通訳サービスの登録状況の再確認
- 見出し行自院が所在する自治体の通訳事業や、加入している賠償責任保険などに付帯する通訳サービスについて、最新の登録状況や利用条件を改めて確認し、すぐに使える状態になっているかチェックしておきます。
これらの準備を小さなステップで進めていくことで、過度な投資や急な人員増を行うことなく、外国人患者さんを安全に受け入れるための体制を築いていくことができます。そして、必要になったタイミングで、「クーラ」のようなサービスを活用して、機動的に短期の人員補強を行うことも検討してみてください。https://business.cu-ra.net/







.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)





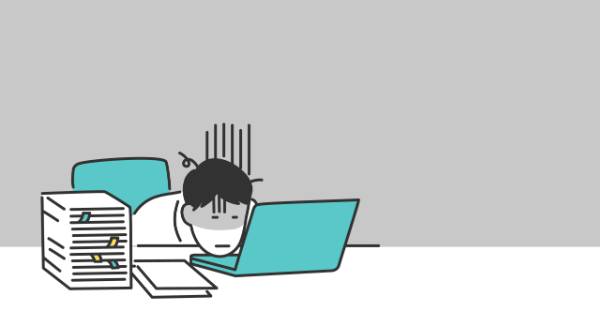
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
