入力が二度になる、締めが止まる。現場で本当に起きていること
クリニックや小規模な病院の日常の中で、スタッフの方々が静かに、しかし確実に疲弊していく原因の一つに「情報の二重入力」があります。受付で患者さんの情報をシステムに登録し、診察室で医師や看護師が電子カルテに診療内容を記載し、そして会計で金額を確定させる。この一連の流れのどこか一箇所でも、システム同士がうまくつながっていないと、現場ではすぐに同じ情報を何度も入力し直すという作業が発生してしまいます。
例えば、受付で受け取った紙の問診票の内容を、改めて電子カルテに入力し直す。あるいは、電子カルテに入力した診療行為を、会計のためにレセプトコンピューター(レセコン)にもう一度入力する。こうした作業は、一つひとつは些細なものに思えるかもしれません。しかし、一日に何十人、何百人と患者さんが訪れる現場では、この積み重ねが大きな時間的負担となり、スタッフの集中力を削いでいきます。
さらに深刻なのが、日次や月次の「締め処理」への影響です。会計データが正確に、そして遅滞なくレセコンに集約されないと、その日の売上を確定させる締め処理が完了しません。データが揃わない、金額が合わないといった理由で、診療時間後もスタッフが残って原因調査や差額の調整に追われる。こうした状況が常態化してしまうと、残業が増えるだけでなく、現場の雰囲気も重くなってしまいがちです。
これは決して特別な話ではありません。実際に、紙カルテから電子カルテへ移行したある診療所では、「レセプトを作成するための二重入力が不要になり、作業時間が大幅に短縮された」という実例が公開されています。このような具体的な声は、この課題が多くの医療現場にとって「ありふれた現実」であることを示しています。
この記事では、そうした現場の負担を少しでも軽くするために、公開されている情報や実際の事例をもとに、クリニックや小規模病院、訪問看護や介護の現場でも応用できる、システム連携をうまく機能させるための運用の考え方をまとめました。難しい専門用語や実装の技術的な手順書ではなく、この記事を読んでくださる院長先生や看護部長、事務長の方々が「なるほど、そういうことか」と理解し、納得して、安心して次のステップを考えられるようになることを目指しています。
もし、日々の運営や採用活動に追われ、こうした業務改善にまで手が回らないと感じていらっしゃる場合は、看護師の短期的な応援勤務などを活用して、まずは現場に時間と気持ちの余力を作るという選択肢も有効です。https://business.cu-ra.net/
背景・課題:どこで二重入力が生まれ、なぜ締め処理が止まるのか
なぜ、あれほど手間のかかる二重入力がなくならないのでしょうか。また、なぜ月末や一日の終わりに締め処理で慌てることがあるのでしょうか。その根本的な原因は、院内の様々な場所で情報が生まれているのに、それらが自動的につながっていない、というシンプルな構造にあります。
「入力元が複数」になると、必ずどこかが手入力になる
現代のクリニック運営では、実に多くのデジタルツールが使われています。患者さんがスマートフォンから利用する予約サイト、来院前に記入してもらうWeb問診、受付で使う電子カルテやレセコン、そして会計で利用する在庫管理システムやPOSレジ。これらはそれぞれが便利な機能を持っていますが、一つでも他のシステムと自動で情報を受け渡す「連携」ができていないと、その隙間を人間が手作業で埋めることになります。
例えば、予約サイトで入力された患者さんの氏名や連絡先が、電子カルテに自動で取り込まれない場合、受付スタッフは予約画面を見ながら、電子カルテに手で打ち直さなければなりません。これが「患者IDの付け替え」や「氏名の再入力」といった作業です。また、Web問診で詳細に回答してもらった内容がカルテに反映されなければ、看護師や医師がその内容を転記する必要が出てきます。
これはシステムの提供者側も認識している課題です。ある電子カルテのベンダーは、周辺のシステムを電子カルテと連携させずに運用すると「患者IDの二重登録が発生しうる」という点を資料の中で整理しています。つまり、それぞれのシステムが別々に患者情報を管理している状態では、情報の重複や不一致が起こりやすいのです。
電子カルテの画面操作ミスも「入力事故」に直結
システムの連携が不十分なことに加え、日々の操作におけるヒューマンエラーも、情報の不整合を引き起こす大きな要因です。特に、似た名前の患者さんを選択してしまうといった「患者間違い」は、医療安全の観点からも非常に注意が必要な事象です。
全国の医療機関からインシデント(ヒヤリ・ハット)情報を収集している公的なレポートでも、「患者間違い」に関連する事故は継続的に報告されています。その原因として、複数の患者さんの情報を画面に同時に表示させて作業していたり、選択操作を急いでしまったりすることがリスク要因になりうると指摘されています。こうした操作ミスによって誤った情報が入力されてしまうと、後続の会計処理やレセプト請求にも当然影響が及び、後から修正するために多大な労力が必要となります。
「締め処理」は“連動の穴”が露呈する瞬間
そして、日々の業務で蓄積されたこれらの小さなズレや入力漏れが、最も顕著に現れるのが「締め処理」のタイミングです。締め処理とは、その日一日の、あるいはその一月分の診療報酬を正確に集計し、会計を確定させるための重要な作業です。
例えば、日本医師会が提供するレセコン「ORCA」では、日々の締め処理として「仮締め」と「本締め」という運用が明確に定義されています。仮締めは、その日の診療が概ね終わった段階で一度集計を行うもので、本締めはすべての会計処理が完了した後に最終的な確定を行うものです。しかし、診察は終わったものの会計がまだ済んでいない患者さんがいたり、入力が遅れていたりすると、データが揃わずに本締めができません。結果として、その日の売上を翌日に繰り越すといった対応が必要になり、日々の会計管理が煩雑になります。
月次の締め処理も同様です。レセプト(診療報酬明細書)は、診療を行った月(診療年月)単位で作成されるため、入力の遅延や計上漏れがあると、翌月の請求に回さなければならなくなります。これは「月遅れ請求」と呼ばれ、クリニックの資金繰りに影響を与える可能性もあります。また、保険証の確認ミスや病名の入力漏れなどがあれば、保険者からの支払いが一時的に保留される「返戻」となり、再請求の手間も発生します。
このように、締め処理がスムーズに進まない背景には、システム間の連携不足や日々の入力ミスといった、業務プロセスの「穴」が隠れていることが多いのです。
実例紹介:小規模現場の“実在する”改善とつまずき
理論だけではなく、実際に他のクリニックがどのようにシステム連携に取り組み、どのような成果を上げているのか、あるいはどのような点に苦労しているのかを知ることは、自院の取り組みを考える上でとても参考になります。ここでは、公開されているいくつかの事例をご紹介します。
1)皮膚科クリニック:レセコン・電子カルテ連携と自動釣銭機で会計ミスと待ち時間を削減
ある皮膚科クリニックの事例です。このクリニックでは、会計時の現金の取り扱いミスや、患者さんの待ち時間が課題となっていました。そこで、レセコンと電子カルテを連携させたPOSレジシステムと、自動で釣銭を計算して排出する「自動釣銭機」を導入しました。
これにより、会計担当者がレセコンで確定した金額は、自動的にレジに反映されます。患者さんから預かったお金を機械に入れれば、正確な釣銭が自動で出てくるため、金額の打ち間違いや釣銭の渡し間違いといったヒューマンエラーが構造的に起こらなくなりました。結果として、会計の正確性が向上し、スタッフの精神的な負担が軽減されただけでなく、会計処理そのものがスピードアップしたことで、患者さんの待ち時間短縮にもつながりました。さらに、一部をセルフレジとして運用することで、混雑時の受付周りの人員配置にも柔軟性が生まれたといいます。これは、システム連携によって業務の正確性と効率性を同時に高めた好例です。
2)都心の眼科:レセコン連動の自動精算機・POSで業務を平準化
都心部で開業したある眼科クリニックでは、開業当初の混乱を避けるため、当初から業務の効率化と平準化を重視していました。そこで、レセコンと連動する自動精算機およびPOSレジを導入しました。この事例のポイントは、単に機器を導入するだけでなく、ベンダーが開業時の設置や操作説明、さらには稼働開始日の立ち会いまで手厚くサポートしてくれた点です。
新しいクリニックでは、スタッフも新しい環境と業務に慣れていないため、開業直後は特に会計業務が滞りがちです。しかし、このクリニックでは、専門のサポートを受けながらシステムを導入したことで、開業初日からスムーズな会計運用を実現できました。スタッフの誰が対応しても同じ品質で会計が行えるため、特定のスタッフに業務が偏ることを防ぎ、チーム全体の業務負担を平準化することに成功しています。
3)内科クリニック:ORCA連動型のカルテを選ぶことで移行をスムーズに
多くのクリニックで利用されているレセコン「ORCA」からのデータ移行は、システムを入れ替える際の大きな課題の一つです。ある内科クリニックでは、既存のORCAに蓄積された患者情報や過去の診療データを無駄にしないため、「ORCAとの連携」を最優先事項として新しい電子カルテを選定しました。
このクリニックでは、院内にサーバーを置くオンプレミス型のORCAから、インターネット経由で利用するクラウド型のORCAへの移行と同時に、クラウド型の電子カルテを導入しました。ORCAとスムーズに連携できる電子カルテを選んだことで、従来のデータをスムーズに引き継ぐことができ、運用開始後の入力の二度手間も抑制することができました。これは、既存の資産を活かしながら、賢くシステム移行を実現した事例と言えます。
4)美容・自由診療系の落とし穴:保険診療のレセコンに非対応だと“二重入力”に逆戻り
一方で、システムの特性を見誤ると、かえって手間が増えてしまうケースもあります。例えば、美容皮膚科やAGAクリニックなど、自由診療を中心に扱っているクリニック向けの電子カルテは、予約管理やコース契約、顧客管理(CRM)といった機能に強みを持っています。しかし、これらのクリニックでも、一部で保険診療を行っている場合があります。
過去の事例では、ある自由診療に強い電子カルテが、当初は保険診療のレセプトを作成する機能やORCAとの連携機能が弱かったため、保険診療を行った分だけ、結局スタッフが手作業でORCAに情報を入力し直さなければならない、という状況が発生していました。せっかく電子カルテを導入したにもかかわらず、保険診療のたびに二重入力が発生してしまったのです。この問題は、後にベンダー側がWeb版ORCAとの連携機能を実装することで解消されましたが、導入を検討する際には、自院で行う診療内容(保険・自由診療の割合など)と、システムの対応範囲を事前にしっかりと照らし合わせることの重要性を示唆する事例です。
日々の業務改善は、現場に余裕があってこそ進められるものです。締め処理やシステムの移行期など、特に忙しくなる時期の人員繰りに悩んでしまうと、こうした改善活動も止まりがちになります。いざという時に短期の看護師シフトを柔軟に補えるような選択肢を持っておくと、落ち着いて院内の連携体制の検証や定着に取り組むことができます。https://business.cu-ra.net/
解決アプローチ:今日からできる「二重入力ゼロ/締めが止まらない」ための要点
では、具体的にどのような点に気をつければ、二重入力や締め処理の混乱を防ぐことができるのでしょうか。ここでは、明日からの運用を考える上で土台となる、いくつかの重要なポイントを整理します。
レセコン・電子カルテ・予約/問診の「一次入力点」を1か所に定める
情報の混乱が起こる最大の原因は、あちこちでバラバラに情報が入力されていることです。これを防ぐ最も効果的な方法は、情報の「源泉」、つまり最初に患者情報を登録する場所(一次入力点)を、院内でただ一つに決めてしまうことです。
- 患者IDの“源泉”を決めて、他システムへ受け渡す
- 多くのケースでは、電子カルテが情報の中心的な役割を担うのが合理的です。まず電子カルテで新しい患者さんのIDを発行し、その情報を予約システムやWeb問診システム、会計のPOSレジへ連携機能を使って同期させます。こうすることで、どのシステムで見ても同じ患者さんは同じIDで管理され、情報の重複を防ぐことができます。もし、システム間の直接連携が難しい場合でも、諦める必要はありません。例えば、電子カルテで発行した患者番号のバーコードを診察券に印刷し、会計時にそのバーコードを読み取るだけでも、手入力を大幅に減らすことが可能です。市販のバーコードリーダーと連携できるレセコンやPOSシステムも多く存在します。大切なのは、「手で打ち直す」という作業をいかにしてなくすか、という視点です。
- 自由診療と保険診療の“系統分離”を明文化
- 特に、自由診療と保険診療の両方を行っているクリニックでは、情報の流れを明確に文書化しておくことが有効です。例えば、「自由診療に関する会計情報は、〇〇という電子カルテから直接POSレジに連携する」「保険診療に関する情報は、必ずORCAと連携する電子カルテの□□という機能を使って入力し、ORCA経由でレセプトを作成する」といったルールを定めます。先述の事例のように、過去には自由診療に強いカルテの保険機能が十分でなく、二重入力が発生したケースもありました。導入を検討している、あるいは現在使用しているシステムの仕様を確認し、どの情報が、どちらのシステムに「自動で反映される」のか、そして「手動での対応が必要」なのはどの部分なのかを一覧にしておくと、スタッフ間の認識のズレを防ぐことができます。
「締め処理」を運用設計に組み込む(仮締め→本締めの型化)
締め処理は、一日の業務の終わりに行う単なる作業ではなく、院内の情報連携が正しく機能しているかを確認するための重要なプロセスです。これを円滑に進めるためには、あらかじめルールを定めておくことが不可欠です。
- 日次の締め:「仮締めで確定スコープ」を固定する
- レセコン「ORCA」の公式マニュアルにも記載があるように、日々の締め処理は「仮締め」と「本締め」のステップを踏むのが基本です。重要なのは、これを日々の運用ルールとして定型化することです。「診療終了時刻の15分後、18時45分に一度、事務の〇〇さんが仮締めを行う」といった具体的なルールを決めます。この仮締めによって、その時点で会計が完了している範囲が一旦固定されます。もし、その後に会計が遅れて発生した場合は、どう対応するのか(当日の本締めに含めるのか、翌日処理とするのか)という再開条件も決めておきましょう。そして、最終的な「本締め」を行う責任者を明確に定めておくことで、日々の作業がスムーズに進みます。
- 月次の締め:「診療年月単位」でデータを整える
- 月次のレセプト作成は、「診療年月」という単位でデータが正確にまとまっていることが大前提となります。そのため、月末の締め処理の際には、その月に発生した診療データに漏れや誤りがないかを確認する作業が重要になります。もし、当月中に処理しきれなかった差額の調整や、保険者から差し戻された返戻レセプト、あるいは前月以前の診療分で未請求だった「月遅れ」のデータなどを、翌月の請求でどのように扱うのか(当月分に合算するのか、別で処理するのか)を、院内の運用ガイドとして文書化しておくと、担当者が変わっても処理方法がブレることがなくなります。
会計・決済は“ヒトを介さない”経路を用意する
会計業務は、お金を直接扱うためミスが許されず、スタッフにとって精神的な負担の大きい作業の一つです。この部分をできるだけ自動化し、人の手を介さない仕組みを作ることは、業務効率化とリスク軽減の両面で大きな効果があります。
- 自動釣銭機・セルフレジで入力箇所を減らす
- 先の皮膚科や眼科の事例でもあったように、レセコンと連携した自動精算機や自動釣銭機は、会計業務を大きく変える力を持っています。レセコンからの請求金額データに基づいて機械が自動で処理を行うため、スタッフが現金の受け渡しや計算をする必要がなくなります。これにより、会計ミスが劇的に減少するだけでなく、スタッフは患者さんへの説明や次の案内といった、よりコミュニケーションが求められる業務に集中できるようになります。
- POS/レセコン連携の可視化(“どの項目が同期されるか”)
- POSレジを導入する際には、「どのデータがレセコンと自動で同期されるのか」を一覧にして、スタッフ全員で共有することが大切です。例えば、患者さんの氏名やID、診療行為のコード、金額はもちろんのこと、領収済みの情報や、一部未収があるといったステータスまで連携されるのか。こうした同期項目を事前にリストアップし、ベンダーに確認しながら、院内の壁などに掲示しておくと、「誰が、いつ、何の情報を入力したか」が分かりやすくなり、トラブル発生時の原因究明も迅速に行えます。あるクラウド型カルテの提供元も、予約や会計データが連携されることによる業務効率化のメリットを明確に示しています。
移行・切替は“併用期間の検証”でリスクを潰す
新しいシステムを導入したり、既存のシステムを入れ替えたりする際には、一斉に切り替えるのではなく、準備期間を設けることが成功の鍵を握ります。
- お試し導入で“連携の当日運用”を実地確認
- ベンダーによっては、本格導入前にお試しでシステムを利用できる期間を設けている場合があります。この期間を最大限に活用し、実際の業務の流れに沿って、データの連携がうまくいくかを徹底的に確認しましょう。例えば、受付での患者登録から、診察、会計、そして日々の締め処理まで、一連の作業をテストデータで行ってみるのです。あるクリニックでは、このお試し期間中にORCAとの連携を入念に検証し、同時に入力した場合の挙動などを細かく詰めたことで、本格導入の初日は朝のわずかな微調整だけで乗り切れたという声もあります。
- 操作ミスの“型”に対応:患者取り違え対策
- システムの機能だけでなく、それを使う人間の操作ミスを想定したルール作りも重要です。先の「患者間違い」の例で言えば、患者さんを呼び出す際には必ずフルネームと生年月日で確認する、電子カルテの画面は一度に一人の患者さんのものしか開かないようにする、といった具体的なルールを定めておくと、入力事故のリスクを減らすことができます。
システムの連携切り替えや、月末の締め処理前後は、どうしても現場の負荷が高くなりがちです。そうした時期に、短期の増員などで一時的にでも人員的な余裕を作っておくと、安全かつ着実に新しい運用へ移行することができます。https://business.cu-ra.net/
まとめ:二重入力を“仕組みで不可能”に、締めを“型で自動的”に
ここまで見てきたように、クリニックの日常業務に潜む二重入力や締め処理の混乱は、個々のスタッフの注意力や頑張りだけで解決できる問題ではありません。むしろ、仕組みそのものに目を向け、人の手に頼らなくても業務が回るような環境を整えることが、根本的な解決につながります。
今回ご紹介したアプローチの要点を、改めて整理してみましょう。
- 一次入力点を決める(患者IDの源泉を明確化)最初に情報を登録するシステムを一つに定め、そこから他のシステムへ情報が流れるようにすることで、データの重複と不一致をなくします。
- 連携の抜けを見える化(同期項目・非同期項目を一覧化)どの情報が自動で連携され、どの情報が手動での対応が必要なのかをリストにして共有し、認識のズレを防ぎます。
- 日次/月次の締めを運用に埋め込む(仮締め→本締め、診療年月単位の統計)締め処理の手順と責任者を明確にルール化し、日々の業務の中に定型的な作業として組み込みます。
- 会計は非接触・自動化を軸に(自動精算機・釣銭機・POS連携)自動精算機などを活用してヒューマンエラーが発生する余地をなくし、スタッフと患者さん双方の負担を軽減します。
- 併用期間で“実運用テスト”(お試し導入で当日の詰まりを解消)本格導入の前にテスト期間を設け、実際の業務の流れの中で問題点を洗い出し、スムーズな移行を実現します。
これらはどれも、どこかの天才的な経営者が考え出した特別な施策というわけではありません。多くのクリニックが試行錯誤の中でたどり着いた、公開事例にも裏付けのある、いわば「普通の手順」です。だからこそ、早めに院内の運用ルール、つまり「型」に落とし込んでしまえば、その後はスタッフが入れ替わっても、日々の業務が大きく揺らぐことなく、現場は安定した運用に集中することができるようになります。
現場に“余力”を——締めや切替の週を、余裕で乗り切るために
クーラは、多くの看護師が登録しており、急な募集にも迅速に対応しやすい採用媒体です。特に「お試し勤務」の仕組みがあるため、本格的な採用の前に、院の雰囲気や業務内容との相性を見極めることができ、採用後のミスマッチを抑えることにもつながります。
システムの連携を切り替える週や、月末月初の締め処理で業務が集中する時期に合わせて、短期やスポットで人員を確保することで、既存のスタッフが過度な負担を抱えることなく、新しい業務フローの定着に集中できる環境を作ることができます。求人票の作成や労務関連の手続きといった採用活動に伴う負担も、デジタルツールで軽くすることが可能です。
この記事で触れたような、システム連携や締め処理の運用を整理する取り組みと合わせて、「忙しい日を、もう忙しくしない」ための体制をつくる。それが、スタッフ一人ひとりの安心感、そしてクリニック全体の安定した運営につながっていくのではないでしょうか。
まずは、どのような形で協力を得られるのか、施設の紹介ページをご覧になってみてください。https://business.cu-ra.net/
参考にした公開情報(抜粋)
- 診療所における紙カルテから電子カルテへの移行と、それに伴うレセプト二重入力作業の省力化に関する事例。 (healthcareconnectiveplace.humanbridge.net)
- 日本医師会ORCA管理機構による、日次締め(仮締め/本締め)の操作と月次統計作成に関する公式マニュアル。 (orcamanual.orca.med.or.jp)
- 皮膚科および眼科クリニックにおける、レセコンと連携したPOSシステムや自動精算機の導入効果に関する事例。 (株式会社ポスコ)
- 美容医療向け電子カルテにおける、保険診療レセプトへの対応とWeb ORCA連携機能の実装に関する情報。 (自由診療のすべてを実現する電子カルテ | メディカルフォース)
- 電子カルテの操作時における患者取り違えのリスク要因に関する医療機能評価機構の分析記事。 (GemMed | データが拓く新時代医療)
- 本格導入前のお試し期間を利用してORCA連携を入念に検証し、スムーズな移行を実現したクリニックのケーススタディ。 (エムスリーデジカル株式会社)
(本記事に記載した各社の製品名、サービス名、およびその仕様は、将来的に更新される可能性があります。最終的なシステムの導入判断にあたっては、必ず自院の運用要件と照らし合わせ、各ベンダーの最新情報をご確認くださいますようお願いいたします。)







.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)





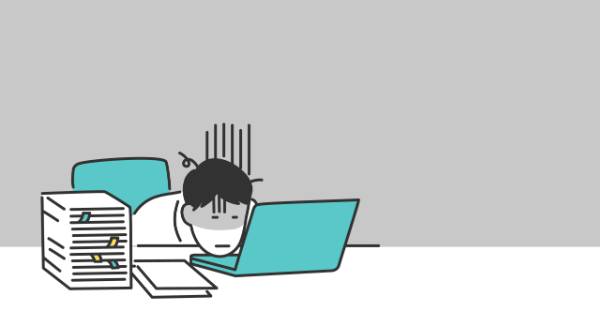
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
