いちばん“紹介”が生まれやすいのは、実は面接直後
「熱意のある応募は時々あるのに、そこから職員の紹介にはなかなかつながらない」「職員紹介制度を導入してみたものの、ほとんど活用されていない」。多くの医療機関で聞かれるこれらの悩みは、その原因をたどると、面接が終わってから候補者が帰宅し、翌日を迎えるまでの、わずか24時間のコミュニケーション設計に潜んでいることが少なくありません。
看護師という職業は、その専門性と責任の重さから、職場選びにおいて極めて慎重になります。面接で受けた印象、感じた期待、そして拭いきれなかった不安。そうした感情のすべてを、候補者は面接室を出た瞬間から、自身の日常へと持ち帰ります。帰りの電車の中でのスマートフォン検索、家族との夕食での会話、親しい同僚とのLINEでのやり取り、そして何気ないSNSの閲覧。この生活導線のあらゆる場面で、面接での体験は反芻され、評価され、そして他者へと語られていきます。
この面接後24時間という極めて重要な時間帯に、候補者の心の中に「この職場のことを、誰かに話してみたい」「友人にも教えてあげたい」と思えるような、具体的でポジティブな理由を一つでも提供できるかどうか。これが、候補者自身の入職意欲を高めるだけでなく、その先にいる潜在的な候補者、つまり同僚や友人への自然な口コミ、紹介へとつながるかどうかの分岐点となります。
本稿では、この「面接後24時間」を、候補者との関係を築くための「5つの具体的な接点」と、その中で伝えるべき「3つの魅力的な話題」というフレームワークで再構築する方法を解説します。単に制度の有無を伝えるのではなく、候補者が思わず誰かに語りたくなるような体験を設計し、それが入職、再来訪、そして友人や同僚を伴っての見学へとつながっていく。そのための実践的なアプローチを、実際に成果を上げている医療機関の具体的な事例を交えながら、詳しく見ていきます。
背景・課題:制度だけでは紹介は増えない
看護師採用における「紹介(リファラル)」の伸びしろ
看護職員の離職率は、新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着きを見せる中で、全体としては改善の傾向にあります。しかし、その内訳を詳しく見ると、特に既卒で中途採用された看護師の年度内離職率が依然として高い水準で推移しているという現実があります。これは、多くの医療機関が抱える根深い課題を示唆しています。採用活動においては、スキルや経験のマッチングだけでなく、入職後の「こんなはずではなかった」というミスマッチをいかに防ぎ、新しい環境に対する不安をいかに早い段階で安心感に変えていくかが、これまで以上に重要な鍵を握っています。
この「ミスマッチの回避」と「安心感の早期醸成」という二つの課題に対して、最も効果的な解決策の一つが、身近な人からの信頼できる情報、すなわち口コミや紹介(リファラル採用)です。実際にその職場で働く友人や元同僚からの「ここの教育体制はしっかりしているよ」「子育て中のシフトに理解があるから働きやすい」といった生の声は、求人広告のどの美辞麗句よりも強く、候補者の心を動かします。
公益社団法人日本看護協会が公表した「2023年 病院看護実態調査」によると、2022年度の正規雇用看護職員全体の離職率は11.3%でした。このうち、新卒採用者の離職率は8.8%であるのに対し、既卒採用者の離職率は16.1%にものぼります。この数字は、経験を持つ看護師であっても、新しい職場環境への適応には多くの困難が伴うことを示しており、いかに現場の不安を迅速に解消し、信頼関係を築ける職場環境であるかが、定着率、ひいては紹介の生まれやすさに直結していると言えるでしょう。紹介が増える職場とは、すなわち、現役の職員が自信を持って他者に薦められるだけの安心と納得感がある職場なのです。
よくある“紹介が回らない病”の原因
多くの病院や施設で職員紹介制度は設けられていますが、その多くが十分に機能しているとは言えない状況です。その背景には、いくつかの共通した原因、いわば「紹介が回らない病」が存在します。
- 制度存在の周知不足最も基本的でありながら、最も多く見られる原因です。制度が院内のイントラネットの片隅に掲載されているだけ、あるいは入職時の説明で一度触れられたきり、といったケースは珍しくありません。職員自身が制度の存在を忘れていたり、知っていても「どうやって使えばいいのか」「誰に申請すればいいのか」といった具体的な利用方法を把握していなかったりします。これでは、紹介したい友人が現れても、行動に移すことができません。
- 推す理由の欠落面接を受けた候補者が、面接直後に「この病院、すごく良かったよ」と誰かに話す時、その「良かった」という感想を裏付ける具体的なエピソードや情報がなければ、言葉に説得力が生まれません。面接官の人柄が良かった、という漠然とした印象だけでは、友人の心を動かすには不十分です。教育体制の具体的な内容、初日のサポート体制、シフトの柔軟性など、候補者が「自分の言葉で語れる具体的な魅力」を面接の場で提供できているかどうかが問われます。
- 連絡の間延び面接が終わった後、候補者の関心と熱意が最も高いのは、言うまでもなく面接当日です。しかし、多くの医療機関では、合否の連絡が数日後、場合によっては一週間以上経ってからということも少なくありません。面接後、丸一日(24時間)何の連絡もなければ、候補者の期待感は急速に薄れていきます。その間に他の医療機関から連絡があれば、そちらに気持ちが傾いてしまうのも自然なことです。この「沈黙の時間」は、紹介の機会を失うだけでなく、入職意欲そのものを削いでしまう大きな要因となります。
- 紹介のハードルが高いいざ友人に紹介しようと思っても、そのプロセスが煩雑であれば、職員は躊躇してしまいます。「友人に渡せるような、分かりやすい病院の資料がどこにあるか分からない」「紹介用のウェブページのURLが長くて送りにくい」「正式な応募の前に、まずは気軽に見学に誘いたいが、そのための窓口が不明確」といった状況では、善意の紹介活動も途中で頓挫してしまいます。招待リンク一つ、同伴見学の案内一つあるだけで、紹介のハードルは劇的に下がるのです。
- 「金銭インセンティブ依存」紹介制度というと、多くの場合は「紹介者と被紹介者に一時金を支給する」という金銭的なインセンティブが中心に据えられます。もちろん、これは有効な動機付けの一つです。しかし、金額の多寡だけに頼った制度は、持続的な紹介文化を育む上では限界があります。「お金のために紹介する」という雰囲気が院内に広がることは、必ずしも望ましいものではありません。それよりも先に、職員が自発的に「この職場の魅力を語りたい」と思えるような、働きがいや良好な人間関係といった「体験価値」を設計し、それを伝える努力が不可欠です。インセンティブは、あくまでその感謝の印として機能するのが理想的な形です。
実例紹介:病院・訪問看護の“うまくいった”工夫
院内認知を高めただけで動き出したケース
静岡県熱海市に拠点を置く、医療法人社団熱海所記念病院の事例は、制度の「使い方」を明確に示すことの重要性を教えてくれます。同院では、職員紹介制度を活性化させるために、外部のコンサルティング会社の支援を受けながら、院内の情報伝達の仕組みを見直しました。その中心的な取り組みが、制度の概要、紹介の手順、インセンティブの内容などを分かりやすく一枚にまとめた「職員紹介制度説明カード」を作成し、全職員に配布したことです。
このカードには、「誰が、誰を、どのように紹介すれば、どのようなメリットがあるのか」が一目で理解できるように工夫されていました。それまでは、制度の存在は知っていても、具体的な利用方法が分からずに行動に移せなかった職員たちが、このカードを手にしたことで、「こうすればいいのか」と納得し、すぐに行動に移せるようになりました。結果として、それまでほとんど利用されていなかった制度が活発に動き出し、実際に紹介からの採用につながるケースが生まれたのです。この事例は、制度はただ「あります」と宣言するだけでは機能せず、「このように使えます」という具体的なナビゲーションが示された時に、初めて職員の行動を促す力を持つことを示しています。
ボーナスだけに頼らない紹介文化を育てた例
採用活動において、金銭的なインセンティブに頼らないアプローチで成功を収めているのが、えん訪問看護ステーションです。同社の代表は、自身の公開ノート(note)を通じて、会社の理念や職場環境、スタッフへの想いなどを積極的に発信しています。その中で、一時期は採用の3割から5割が、金銭的なインセンティブを設けずとも、職員からの紹介で占められていた時期があったことを明らかにしています。
この背景にあるのは、「この職場で働くことの価値」そのものを磨き上げ、それを外部に真摯に伝え続けるという姿勢です。例えば、スタッフ一人ひとりの成長を支援する教育体制、ワークライフバランスを重視した柔軟な働き方の許容、そして何よりも代表自身の言葉で語られる組織のビジョンや文化。こうした「語りたくなる中身」が豊富にあるからこそ、職員は金銭的な見返りがなくても、自然と自分の職場を誇りに思い、友人や知人に薦めたくなるのです。この事例は、採用費を抑制しながら質の高い人材を確保するという、多くの医療機関が目指す理想的な形であり、紹介制度の本質が「報酬」ではなく「共感」にあることを示唆しています。
院内で明確な金額設計を打ち出す例
一方で、インセンティブの仕組みを明確化し、それを職員に分かりやすく提示することで、制度の利用を促進している例もあります。愛知県名古屋市にある名古屋西病院(医療法人純正会)では、職員紹介制度のインセンティブについて、非常に具体的で透明性の高い設計をウェブサイト上で公開しています。
例えば、看護師を紹介した場合、紹介者と被紹介者の双方に、総額で20万円が支給される仕組みになっています。重要なのは、この金額が一度に支払われるのではなく、入職後の定着期間に応じて段階的に支給される点です。例えば、「入職1ヶ月後に5万円、3ヶ月後に5万円、6ヶ月後に10万円」といった形で分割支給することで、紹介した職員にも、新しく入った仲間が職場に定着するまでサポートしようという意識が芽生えます。単なる人材の「紹介」で終わるのではなく、その後の「定着」までを視野に入れた、伴走型のインセンティブ設計と言えるでしょう。このように、金額と支給条件、そしてそのタイミングを一覧表などを用いて明確に「見える化」することは、職員にとっての制度の分かりやすさと納得感を高め、積極的な利用へとつながります。
金銭は“感謝の額”で十分という見立て
紹介制度のインセンティブを高額に設定する動きもありますが、それに警鐘を鳴らす声も存在します。診療所の開業支援などを行う専門家の中には、リファラル採用が、時に100万円以上にもなる人材紹介会社の成功報酬を節約できるという側面から、過度に高額なインセンティブを設定しがちであると指摘しています。
しかし、あまりに高額な報酬は、かえって院内の人間関係に「お金の匂い」を持ち込み、全体の雰囲気を損なうリスクもはらんでいます。紹介することが目的化し、職場の実態以上に良く見せようとする職員が現れる可能性も否定できません。こうした観点から、インセンティブは5万円から10万円程度の「紹介してくれてありがとう」という感謝の気持ちを示す範囲で十分機能するという考え方も、有力な見方として提言されています。各医療機関の文化や風土に合わせて、院内の空気を壊さず、持続可能で、誰もが気持ちよく利用できる制度を設計することが重要です。
解決アプローチ:面接後24時間の“5接点×3話題”設計
紹介を増やすための本質は、面接を終えた候補者が、帰宅後から翌日にかけての最も記憶が新しく、感情が動きやすい時間帯に、「この職場のことを誰かに話したい」と思えるような具体的な情報やきっかけを、こちらから能動的に提供することにあります。この24時間という限られた時間の中で、候補者が抱えるであろう「不安の穴」を先回りして埋め、誰かに自慢したくなるような「誇れる小ネタ」を手渡し、そして実際に紹介という行動に移すための「物理的な導線」を用意する。この3つを体系的に設計することが、成功の鍵となります。
接点① 面接後30分以内——サンキューメールは“安心の箇条書き”
目的は、面接を終えた候補者が帰路につく中で、面接の記憶を反芻し、漠然とした不安が膨らみ始める前に、こちらからの具体的なメッセージでポジティブな印象を確定させることです。長文である必要はありません。感謝の気持ちと、要点をまとめた箇条書きで構成された、簡潔で誠実なメールが効果的です。
本文の型(要旨)
- 本日はありがとうございました:単なる定型文で終わらせず、「〇〇様が以前の職場で経験された〇〇についてのお話、当院の〇〇病棟でも大いに活かせると感じ、大変興味深く伺いました」のように、面接中の具体的な会話内容を一点引用することで、パーソナライズされた特別なメッセージであることを伝えます。
- 当日のメモ(決定事項の再確認):口頭で伝えた重要な情報を、改めてテキストで残します。これにより、候補者は「聞き間違いではなかった」と安心できます。例:「配属先の候補は、ご希望を伺った〇〇病棟です」「勤務イメージとしては、最初の2週間は日勤のみで、3週目から先輩看護師の夜勤にオリエンテーションとして同行する形を考えています」
- 次の動きの明示:候補者が最も気になる「いつ連絡が来るのか」を具体的に伝えます。例:「選考結果につきましては、48時間以内、つまり〇月〇日の午後までには、改めてご連絡いたします」「それまでの間、もしご不明な点や追加の質問がございましたら、このメールに直接ご返信いただくか、採用担当〇〇の直通電話(XXX-XXXX-XXXX)まで、いつでもお気軽にご連絡ください」
- 同僚への共有を促す情報:このメールが、友人との会話のきっかけになるように設計します。例:「本日お話しした当院の概要については、こちらの紹介ページ(URL)でも詳しくご覧いただけます。もしご家族やご友人に当院のことをお話しされる機会がございましたら、ご自由にお使いください。また、改めて院内を見学したいというご希望がございましたら、こちらの見学予約フォーム(URL)からお申し込みいただけます」
看護師向けの転職情報メディアなどでも、面接後の御礼連絡は、可能であれば当日中に送ることが、丁寧な印象を与え、次のステップへ進むためのマナーとして推奨されています。この基本的なアクションに、紹介活動へと自然につながるリンクを一つ添える。この小さな工夫が、大きな違いを生み出す第一歩となります。
接点② 面接当日夜——“2つの不安”の先回りメッセージ
面接を終えた看護師が自宅で落ち着いて考えた時に、最も心に浮かびやすい不安は、大きく分けて二つあります。一つは「配属先の具体的な業務内容についていけるだろうか」という業務への不安。もう一つは「新しい機器や電子カルテの操作を覚えられるだろうか」という技術的な初期負荷への不安です。これらの不安に対して、こちらから先回りして具体的な情報を提供することで、大きな安心感を与えることができます。
メッセージのテンプレート(抜粋)「本日は面接にお越しいただき、重ねてお礼申し上げます。ご自宅でゆっくりされている頃かと思います。少しでも入職後のイメージが湧くよう、本日お話しした〇〇病棟での、看護師の典型的な1日の流れを写真付きの資料にまとめましたので、お送りします(URL)。ご覧いただくと、午前中は〇〇のケアが中心で、午後は〇〇カンファレンスがある、といった雰囲気がお分かりいただけるかと思います。また、多くの方が心配される電子カルテや医療機器の操作については、入職初日に必ず20分程度のミニ研修の時間を設けています。その後も、慣れるまでは必ず先輩職員が隣で操作をサポートしますので、ご安心ください。もしこの資料を、ご家族やご友人の看護師さんに見せて相談したい、ということがあれば、ご自由にご共有いただいて構いません。」
ここでのポイントは、候補者が「そのまま転送できる素材」を用意しておくことです。病棟の紹介や1日の流れをまとめた、スマートフォンで見やすいシンプルなウェブページ(ミニページ)を作成し、そのURLを送るのが効果的です。候補者は、友人に「今日面接に行った病院、こんな感じらしいよ」と、そのURLを送るだけで、職場の雰囲気を正確に伝えることができます。これは、候補者自身の入職意欲を高めるだけでなく、その友人からの「私も見学してみたい」という再来訪や、同僚の関心を喚起する強力なツールとなります。
接点③ 翌朝9時——“1問だけ”のリアクション確認
面接翌日の朝、候補者が一日を始めるタイミングで、簡潔なフォローアップの連絡を入れることは、丁寧な印象をさらに強めます。しかし、ここで長々とした質問を送ると、相手の負担になりかねません。重要なのは、相手が指一本、ワンタップで返信できるような、極めてシンプルな問いかけをすることです。
メッセージ例:「おはようございます。昨日の面接後、何か新しく気になったことや、不安に感じた点はありましたでしょうか?もしよろしければ、以下のうち最も近い番号だけで構いませんので、お返事をいただけますか?① 配属先の具体的な業務内容について② 勤務時間やシフトについて③ 教育・研修体制について④ その他(もしよろしければ、内容をお聞かせください)」
このように選択式の質問にすることで、返信率は格段に上がります。そして、候補者からの返信(例えば「②」という一言)は、私たちが気づけなかった、紹介への障壁となっている「隠れた不安」を早期に発見するための貴重なシグナルとなります。返信があった場合は、それに対して「ご連絡ありがとうございます。勤務時間に関するご質問をまとめたFAQページをお送りしますね(URL)」といった形で、さらに詳しい情報を提供します。このやり取りを通じて、候補者の手元には「誰かに職場のことを説明しやすい、公式の文章」が蓄積されていくことになります。
接点④ 翌昼12時——“同伴見学”の誘い
人は、一人で職場を見学するよりも、信頼できる友人と一緒に見ることで、より客観的に、そしてリラックスしてその場の雰囲気を感じ取ることができます。また、一緒に働く同僚のイメージが具体的に湧くことで、入職への意欲、そして他者への紹介意欲は飛躍的に高まります。
メッセージ例:「もしご興味があれば、実際に働く現場の雰囲気をより深く知っていただくために、30分程度の短時間での同伴見学も可能です。ご友人や元同僚の方など、どなたとでもお越しいただけます。見学に来てくださった方には、院内にあるカフェで使えるドリンクチケットをお渡ししています。現在、毎週土曜日の午前10時と、火曜日の午後2時に、見学の固定枠を設けておりますが、ご都合はいかがでしょうか?」
ここでのポイントは、ただ「見学もできます」と伝えるだけでなく、「同伴可能」であること、「カフェ券」のような小さなインセンティブがあること、そして何より「具体的な曜日と時間枠」を明示することです。これにより、候補者は友人を誘う際に「火曜の午後なら空いてる?病院見学に行くとカフェでお茶できるらしいんだけど、一緒に行かない?」と、極めて具体的に、そして気軽に声をかけることができます。候補者が「良かったよ」という感想と共に、この見学枠の情報をそのまま転送できる形を作ることが、紹介の連鎖を生むきっかけとなるのです。
接点⑤ 翌夕18時——“共有しやすい1枚画像”
LINEのグループトークやSNSのダイレクトメッセージなど、日常的なコミュニケーションの場では、長文のテキストよりも、一枚の画像の方がはるかに拡散されやすく、人の目を引きます。面接後24時間の締めくくりとして、職場の魅力を凝縮した、共有しやすい画像を候補者に提供しましょう。
画像に盛り込む内容:
- 魅力的な写真:ナースステーションで談笑するスタッフの様子や、明るく清潔感のある休憩室など、職場のポジティブな雰囲気が伝わる写真を1枚、大きく配置します。
- 安心を誘うキーワード:「初日は先輩がマンツーマンで並走します」「夜勤は業務に慣れてから、本人の希望を聞いて開始します」「月間の平均残業時間は〇分です」といった、候補者の不安を解消する具体的な情報を、短いキャッチコピーとして加えます。
- 次のアクションへの導線:院内見学の予約フォームに飛ぶQRコードや、採用情報のLINE公式アカウントへ友だち追加するためのQRコードを配置します。
- 紹介制度の要点:インセンティブの金額、支給条件、支給時期などを、複雑な文章ではなく、シンプルな図や表で示します。「紹介者・被紹介者にそれぞれ10万円!」「入職3ヶ月後・6ヶ月後に支給」のように、直感的に理解できるデザインが理想です。
実際に、前述の熱海所記念病院の事例でも、制度の概要を一枚のカードに「見える化」したことが、認知度と利用率を一気に押し上げるきっかけとなりました。このアプローチを応用し、デジタル版の共有カードとして候補者に渡すことで、情報が候補者の友人関係のネットワークの中で、自然に広がっていくことを期待できます。
話題設計——“3つの語りネタ”を面接直後に渡す
語りネタ1:「研修が整ってる」——初期負荷の見える化
多くの看護師、特にブランクがある方や新しい診療科に挑戦する方にとって、最大の不安は「新しい環境の業務を覚えられるか」という点です。この不安を解消し、「あそこは教育体制がしっかりしているから、最初の負担が少なそうだよ」と語ってもらうための情報を提供します。
- 入職初日の流れを具体的に示す:「8:30 更衣室でユニフォームに着替え → 8:45 端末とIDカードの発行 → 9:00 電子カルテのミニ研修(20分) → 9:20 配属先の病棟でスタッフに挨拶 → 9:30 先輩看護師に同行し、業務の流れを見学」というように、タイムスケジュールで示すと、一日の見通しが立ち、安心感につながります。
- つまずきポイントを先回りして提示する:電子カルテの操作や、特定の医療機器(輸液ポンプなど)の取り扱いで、新人が戸惑いがちな点をリストアップし、「これらの点については、最初の1週間、毎日先輩が隣について一緒に操作します」と明示します。
- 30秒のミニ動画で動線を紹介する:プロの撮影は不要です。スマートフォンで、職員用の更衣室からナースステーションまでの道のりを撮影するだけでも、職場の雰囲気や物理的な距離感が伝わります。「ロッカーが広くてきれい」「ステーションが明るい」といった小さな発見が、ポジティブな口コミの種になります。
これらの情報提供を通じて、候補者は「ここなら、初日から一人で放り出される心配はなさそうだ」「教育が丁寧で、最初の立ち上がりが楽そうだ」と具体的に言語化できるようになり、同僚や友人に自信を持って薦めることができます。
語りネタ2:「生活と両立できる」——シフトの柔らかさ
給与や業務内容と同じくらい、あるいはそれ以上に看護師が重視するのが、プライベートの生活と仕事をいかに両立できるか、という点です。特に子育て中の方や、自身の健康、家族の介護など、様々な事情を抱える看護師にとって、シフトの柔軟性は職場選びの決定的な要因となります。
- 具体的な働き方の選択肢を提示する:「夜勤は入職後3ヶ月が経過し、本人の希望を確認してから開始します」「お子さんが小さい間は、週に1回、4時間だけの短時間パートとして働くことも可能です」「オンコール当番は、担当者を複数名で設定し、負担を分散させています」など、多様な働き方を許容する制度があることを具体的に伝えます。
- シフト例を画像化して共有可能にする:例えば、「子育て中の看護師Aさんの、とある一週間のシフト例」として、具体的な勤務時間を図示します。これを画像データとして候補者に渡すことで、「この病院、こんな働き方もできるみたいだよ」と、友人にLINEで簡単に転送できるようになります。
「ここでは無理なく働き続けられそうだ」という実感は、同じような悩みを抱える友人への、極めて説得力の高い推薦理由となります。
語りネタ3:「人が良い」——顔とストーリー
最終的に、人が職場を選ぶ決め手となるのは「人」です。どんなに設備が新しく、給与が高くても、人間関係に不安があれば、人は定着しません。「あそこは、人が温かくて雰囲気が良い」という口コミほど、強力なものはありません。
- 師長や教育担当者の顔を見せる:採用担当者だけでなく、実際に入職後に関わることになるキーパーソンの顔写真と、短い自己紹介メッセージ(例:「趣味は週末のガーデニングです。皆さんと一緒に、患者さんだけでなく、私たちの職場もより良く育てていきたいです」)を共有します。顔が見えるだけで、心理的な距離はぐっと縮まります。
- 先輩の「最初の1週間」の体験談を伝える:「入職したばかりの頃は不安でいっぱいでしたが、先輩たちが毎日『何か困ったことはない?』と声をかけてくれて、すぐに馴染むことができました。特に、初めての夜勤明けに師長さんが『お疲れ様』と差し入れてくれたお菓子が、本当に嬉しかったです」といった、200字程度の短い、しかし具体的なエピソードは、職場のリアルな人間関係を伝えます。
- 病棟の「好きなところベスト3」を募る:現役のスタッフにアンケートを取り、「①休憩時間にみんなでお菓子を食べる和やかな雰囲気、②分からないことを何度聞いても嫌な顔せず教えてくれる先輩たち、③窓から見える景色が綺麗で癒される」といった声を、吹き出しを使った親しみやすい画像にまとめます。
こうした「人の顔」と「個人のストーリー」が見える情報は、候補者にとって単なる求人情報ではなく、共感を伴う物語として受け取られます。そして、その物語こそが、最も人の心を動かし、口コミや紹介の起点となるのです。
院内運用——紹介制度は“金額×空気×手間”で設計する
紹介制度を院内で効果的に機能させるためには、「インセンティブの金額設定」「院内の雰囲気づくり」「紹介者の手間を省く工夫」という三つの要素をバランス良く設計することが不可欠です。
金額——段階支給で“定着”まで伴走
インセンティブは、紹介してくれたことへの感謝であると同時に、新しく入った仲間が職場にスムーズに溶け込み、長く活躍してくれることへの期待の表れでもあります。そのために有効なのが、支給を複数回に分ける「段階支給」の仕組みです。
- 双方に支給する:紹介者だけでなく、紹介されて入職した被紹介者にもインセンティブを支給することで、「一緒に頑張ろう」という連帯感が生まれます。
- 定着のマイルストーンを設定する:例えば、「入職1ヶ月後(初期のサポート完了)」「3ヶ月後(試用期間満了)」「6ヶ月後(独り立ち)」「12ヶ月後(1年間の貢献)」といった節目で支給額を分割します。これにより、紹介者の関心が「採用決定」の瞬間だけでなく、その後の「定着」まで持続します。
前述の名古屋西病院のように、看護師の紹介であれば総額20万円といった具体的な金額と、その支給タイミングを明記した表を作成し、院内の誰もが見える場所に掲示したり、デジタルデータとしていつでも共有できるようにしておくことが、制度の利用促進につながります。
空気——“感謝の額”で続けやすく
インセンティブの金額は、高ければ高いほど良いというわけではありません。前述の提言にもあるように、あまりに高額な報酬は、かえって職員間の関係性をぎくしゃくさせたり、「お金目当て」というネガティブな印象を与えたりする可能性があります。
大切なのは、その金額が「紹介してくれてありがとう」という純粋な感謝の気持ちとして、職員に受け止められる範囲であることです。多くの専門家は、5万円から10万円程度でも、制度としては十分に機能すると指摘しています。各医療機関の給与水準や文化に合わせて、過度な負担にならず、かつ職員のモチベーションを維持できる、持続可能な金額感を見つけることが、健全な紹介文化を育む上で重要です。
手間——職員側の“紹介コスト”をゼロに
職員が友人に職場を紹介しようとする時、そのプロセスにおける心理的・時間的な負担(紹介コスト)を、限りなくゼロに近づける努力が求められます。
- 共有素材をパッケージで用意する:紹介用の「1枚画像」「ミニページのURL」「招待リンク」などを、いつでも誰でも取り出せる共有フォルダなどにまとめておきます。「友人に送りたいんだけど、何か良い資料ない?」と聞かれた時に、すぐに渡せる状態が理想です。
- 同伴見学のハードルを下げる:見学の申し込みを、紹介者自身が調整するのではなく、「毎週火曜の午後と土曜の午前」といった固定枠を設けることで、紹介者は友人に「この時間ならいつでも見学できるらしいよ」と伝えるだけで済みます。
- 申請フォームを極限までシンプルにする:紹介制度の申請フォームは、入力項目を最小限に絞り込み、30秒程度で完了するように設計します。最低限、「紹介者の氏名・連絡先」と「被紹介者の氏名(またはニックネーム)と連絡先」さえあれば十分です。
- 申請後のプロセスは人事が引き受ける:申請があった後は、すべて人事(採用担当者)が主導して、被紹介者(候補者)への連絡や面接日程の調整を行います。「申請さえしてくれれば、あとは全部こちらでやります」というスタンスを示すことで、紹介者は「友人に迷惑をかけるかもしれない」という心配から解放され、気軽に紹介しやすくなります。
チャネル別——“面接後24時間”の配布物リスト
これまでに述べたアプローチを、具体的なコミュニケーションチャネルごとに整理し、すぐに使える配布物のリストを作成しました。
LINE(候補者個人との連絡用)
- 御礼メッセージ+不安解消の3点セット:配属先のイメージ、教育体制の具体例、入職初日の動線を伝えるテキストやURLを送ります。
- 同伴見学の予約フォーム:Googleフォームなどで作成した、日時を2〜3つの候補から選ぶだけのシンプルなフォームのURLを共有します。
- 共有OKの素材:友人・知人への転送を許可した「1枚画像」と、より詳しい情報が載った「病棟紹介ミニページ」のURLを送ります。
LINEオープンチャット/既存職員向けの院内ツール(Slack, Teamsなど)
- 今週の同伴見学枠の告知:毎週決まった曜日に、「今週の見学枠、まだ空きがあります!ご友人といかがですか?」といった定型文と、魅力的な写真を組み合わせた画像を投稿します。
- 紹介制度の図解:インセンティブの金額や支給時期をまとめた表画像を、定期的にリマインドとして共有します。
- 新入職者の「最初のひとこと」:新しく入った職員に、入職後1週間の感想を200字程度で書いてもらい、本人の許可を得て共有します。「皆さんが温かく迎えてくれて、安心してスタートできました」といった生の声は、他の職員が紹介する際の強力な後押しになります。
院内掲示・ロッカールーム
- QRコード付きのA4ポスター:職員が最も頻繁に目にする場所に、「同伴見学」「紹介制度申請フォーム」「病棟紹介ミニページ」の3つのQRコードをまとめたポスターを掲示します。
- 素材庫の明示:「友人への紹介に使える写真や資料は、このQRコードから自由にダウンロードして使ってください」といった案内を掲示し、職員が自律的に紹介活動を行える環境を整えます。
“語ってもらう”ためのコピー例(転載・利用可)
これらの言葉を、前述の「1枚画像」や各種メッセージに盛り込むことで、候補者や職員が、職場の魅力を誰かに伝えやすくなります。
- 「入職初日は、まず20分間の電子カルテのミニ研修からスタートします。その後は、先輩が必ず隣について一緒に業務を回るので安心してください。」
- 「夜勤は、日勤業務に十分に慣れてから、ご本人の希望を聞いた上で始めていきます。最初は週1回の短時間勤務から体を慣らしていきたい、といった相談も可能です。」
- 「ご家族やご友人と一緒に、まずは30分、院内の雰囲気をのぞきに来ませんか?同伴見学も大歓迎です。」
- 「院内カフェのドリンクチケット付き見学会を実施中です。選考ではないので、まずは気軽に、私たちの職場の空気を確かめに来てください。」
- 「友人紹介は、30秒で入力が終わる専用フォームから申請するだけ。その後の候補者の方へのご連絡は、すべて人事が引き継ぎますので、ご負担はありません。」
これらのコピーを組み合わせて一枚の画像にまとめ、面接の翌日夕方に候補者へ送付することで、情報が自然に拡散していく可能性を高めることができます。
外部発信を“口コミの受け皿”に——検索・地図・SNS
院内での取り組みと並行して、外部に向けた情報発信の基盤を整備することも、口コミや紹介の効果を最大化する上で不可欠です。
近隣に住む看護師が、友人から「〇〇病院、良いらしいよ」と聞いた時、次に行う行動は、スマートフォンでその病院名を検索することです。その際、Googleマップ上の情報が古かったり、施設の公式ウェブサイトがスマートフォンに対応していなかったりすると、せっかくの興味も薄れてしまいます。実際に、介護経営の分野では、Googleマップの情報を充実させ(院内の写真を追加、口コミへの返信など)、ウェブサイトの理念や働く環境を明確に打ち出すことで、地図検索から理念への共感、そして質の高い応募へとつながった成功例が報告されています。地図情報とウェブサイトは、口コミや紹介を受け止めるための重要な「受け皿」なのです。
また、採用サイトに、実際に働く看護師のインタビューや、1日の仕事の流れを紹介する体験談を掲載することも非常に効果的です。これは、紹介者が友人に「ここの雰囲気、良いでしょう?」と、具体的なURLを送って示すことができる「証拠」となります。実際に、採用サイトのデザインや内容を見直し、看護師の顔が見えるコンテンツを増やし、応募フォームを簡素化したことで、応募の質と量の両方が向上したというウェブ制作会社の成功事例もあります。候補者がいつでも参照でき、紹介者が自信を持って共有できるオンライン上の拠点を作ることが、紹介文化を根付かせるための土台となります。
まとめ:24時間で“語られる職場”に変える
職員からの紹介を増やし、リファラル採用を活性化させるための鍵は、遠いどこかにあるわけではありません。それは、面接を終えた一人の候補者が、帰路につき、自宅で過ごし、翌日を迎えるまでの、わずか24時間のコミュニケーションの中にあります。
- 面接後30分以内の迅速な御礼連絡で、ポジティブな第一印象を確定させる。
- 面接当日の夜、候補者が抱えるであろう不安を先回りして解消し、「この職場は信頼できる」という安心感と共に、「推せる理由」を一つ提供する。
- 翌朝のシンプルな1問アンケートで、言葉にしにくい不安の残りを丁寧に拾い上げる。
- 同伴見学という具体的な選択肢と、LINEなどで共有しやすい画像を提供することで、候補者からその友人へと情報が「転送」されるきっかけを作る。
- 紹介制度そのものは、インセンティブの段階支給設計と、申請の手間を極限まで省く「見える化」された仕組みによって、誰もが使いやすいものにする。
紹介は、単に制度を設けて、あとは職員の自発性に任せる、というだけでは決して活性化しません。候補者が、自分の言葉で、誰かにその職場の魅力を語りたくなるような、具体的で、共感を呼ぶ小さな材料を、最も効果的なタイミングである「面接後24時間」のうちに、一つのパッケージとして手渡すこと。これが、紹介を増やすための最も確実で、効果的な道のりです。
クーラ導入誘導:まずは“お試し勤務”で安心を可視化する
この記事で解説したアプローチをさらに一歩進め、候補者の安心感を決定的なものにする方法があります。それは、1日から数回程度の短期アルバイト、すなわち「お試し勤務」の機会を提供することです。実際に職場で働いてみるという体験は、どんな説明や資料よりも雄弁に、職場のリアルな魅力を伝えます。候補者は、自身の体験に基づいて家族や同僚に「あの職場、実際に働いてみたらすごく雰囲気が良かったよ」と、熱量を持って語ることができるようになり、紹介の質が格段に向上します。
面接直後の24時間のフォロー動線の中に、この短期勤務の予約枠を組み込むことで、面接から再来訪(見学)、そして体験勤務(お試し)、さらには友人への紹介という、理想的な循環を生み出すことができます。
忙しい医療現場であっても、今回ご紹介した「御礼メールのテンプレート」「共有用の1枚画像」「見学の固定枠」「段階支給の図解」などを、一度「使い回せるパッケージ」として整備してしまえば、日々の運用負荷を最小限に抑えながら、今日からでも実践を始めることが可能です。
次の一手(すぐにできること)
- 面接後の御礼メールのテンプレートを作成し、当日中の送信を院内でルール化する。
- 「毎週火曜日の14時」「毎週土曜日の10時」など、同伴可能な30分間の見学枠を2コマ設定する。
- 紹介制度の概要をまとめたA4一枚の図解資料を作成・配布し、QRコードから30秒で申請できるフォームを用意する。
- 候補者に共有してもらうための「1枚画像」(配属先の雰囲気、教育体制の安心ポイント、見学案内のQRコードを記載)を作成し、面接後に送付する。
- 面接の翌日に、クーラのようなサービスを活用して確保した短期勤務の空き枠を提示し、実際の職場体験から本格的な紹介へとつなげる。
クーラは、「働いてみてから決める」という、候補者と医療機関双方にとってミスマッチの少ない採用スタイルを前提とした、採用導線づくりを支援するサービスです。見学から短期勤務、そして本格的な入職まで、看護師さんにも、受け入れる現場にも無理のない形で、口コミや紹介が自然に生まれる流れを共に作り上げます。
まずは、貴院の「面接後24時間」のフォローアップ用テンプレートを整備することから始めてみませんか。本稿でご紹介したような、御礼の文面、共有画像のテキスト案、紹介制度の図解フォーマットなど、そのまま現場でお使いいただける形の雛形をご提供することも可能です。詳細はこちらからご覧ください: https://business.cu-ra.net/
(参考資料:日本看護協会「2023年 病院看護実態調査」、その他、リファラル採用に関する各種メディア記事、医療機関の公式ウェブサイト、経営コンサルタントによる公開情報などを基に作成。)







.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)





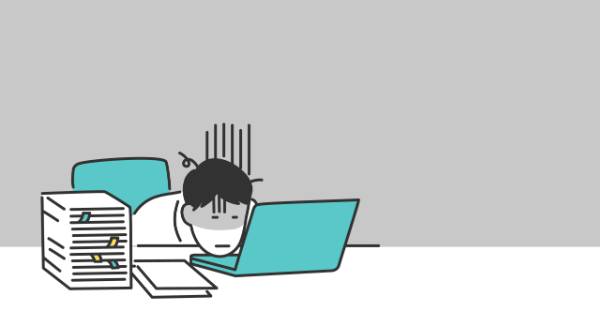
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
