はじめに:その成功報酬は、“痛みを先送り”にしているだけかもしれません
「成功報酬型だから、採用が決まるまで費用はかかりません。初期費用ゼロで安心ですよ」
人材紹介会社から、このような説明を受けることは多いかもしれません。確かに、採用活動の初期段階で費用が発生しないのは、多くの医療機関にとって魅力的に映ります。しかし、その一方で、採用した看護師が数か月で離職してしまい、高額な紹介手数料だけが手元に残ってしまった、というお悩みもまた、現場でよく耳にする声です。
私自身も、多くの院長先生や看護部長の方々からご相談を受ける中で、手数料率の設定、支払いのタイミング(分割)、そして返金(返戻金)に関する規定の作り方一つで、院内の採用に関する意思決定や、現場のスタッフの動き方が大きく変わることを目の当たりにしてきました。
この記事では、特定のサービスを一方的に推奨したり、複雑な理屈を並べたりするのではなく、公にされている情報や、比較的小規模な医療機関、在宅医療の現場で実際に起きている事例をできるだけ多く引用しながら、この「成功報酬」という仕組みと、どうすれば上手に付き合っていけるのか、その着地点を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
なお、本採用の前に、まずは短期のお試し勤務から始めて、お互いの相性をじっくり見極めたい、というご意向でしたら、「クーラ」のようなサービスも一つの選択肢になるかもしれません。(詳しくはこちらのサービス案内をご覧ください:https://business.cu-ra.net/)
私たちの意思決定を左右する、手数料の「率・タイミング・条件」
看護師の採用に人材紹介サービスを利用する際、契約書には必ず手数料に関する項目が記載されています。この手数料が、私たちの採用活動における判断や行動に、どのような影響を与えているのでしょうか。まずは基本的な仕組みや数字について、いくつかの公開情報を基に整理してみましょう。
看護師紹介の手数料率はどのくらい?
一般的に、看護師の人材紹介における成功報酬の手数料率は、採用する看護師の理論年収の20%から35%程度が目安とされています。例えば、医療機関向けのウェブサイト制作などを手掛ける企業の解説記事では「30%から35%」が一つの典型例として挙げられています。一方で、別の調査や情報源に目を向けると「20%前後」でサービスを提供している会社も存在します。
この割合は、募集するポジションの専門性(例えば、認定看護師や専門看護師など)や、採用の難易度、また都市部か地方かといった地域性によっても変動します。仮に、年収450万円の看護師を一人採用した場合、手数料が年収の25%だとすると112.5万円、35%であれば157.5万円という具体的な金額になります。この金額が、採用の意思決定において決して小さくない影響力を持つことは、想像に難くないでしょう。
早期離職時にどうなる?返金(返戻金)規定の一般的なかたち
採用した看護師が、残念ながら早期に離職してしまうケースも想定しておく必要があります。その際に重要になるのが、返金(返戻金)に関する規定です。多くの人材紹介会社では、入職後の在籍期間に応じて、支払った手数料の一部が返金される仕組みを設けています。
そのパターンは様々ですが、在籍期間が短いほど返金割合が高く、時間とともに減少していく「逓減(ていげん)方式」が一般的です。例えば、インターネット上で公開されている情報を見ると、以下のような例が見られます。
- 入職後1か月以内の離職:手数料の80%から100%を返金
- 入職後1か月から3か月以内の離職:手数料の50%から20%を返金
- 入職後6か月経過後の離職:返金対象外、または10%程度の返金
こうした条件は、契約を結ぶ前に必ず確認しておくべき重要なポイントです。この規定があることで、医療機関側は早期離職のリスクをある程度軽減できますし、紹介会社側にも、定着しやすい人材を慎重に紹介しようという意識が働きやすくなります。
手数料に関する情報の透明性
職業安定法では、職業紹介事業者は手数料に関する定めを事業所に掲示するなど、情報を公開することが求められています。これには、紹介手数料の具体的な料率や、万が一の際の違約金に関する規定などが含まれます。サービスを利用する側としては、これらの情報が明確に開示されているかどうかを事前に確認することが、複数の会社を比較検討し、院内で採用方針の合意を形成する上での大前提となります。もし情報が見当たらない場合は、各都道府県の労働局に問い合わせることも可能です。
全ての前提となる「離職率」という現実の数字
採用戦略を考える上で、看護職員の離職率という基礎的なデータを無視することはできません。公益社団法人日本看護協会が公表しているデータによれば、正規雇用看護職員の離職率はおおむね10%前後で推移しています。特に、新卒で採用された看護師の場合、入職した年度内に離職してしまう割合は、既卒者よりも高い傾向にあることが示されています。
これはつまり、「採用した職員のうち、一定の割合は早期に離職する可能性がある」という現実を直視し、それを前提として人材紹介会社との契約条件を検討する必要がある、ということを意味しています。この現実から目を背けてしまうと、いざ離職が起きた時に、想定外の費用負担に頭を悩ませることになりかねません。
さまざまな現場からの声:具体的な事例に学ぶ
抽象的な数字やルールだけでは、なかなか実感しにくいかもしれません。ここでは、小規模な病院や訪問看護ステーション、介護施設など、様々な現場で実際に聞かれる声や、公開されている事例をいくつかご紹介します。
1. 小規模病院であった事例:返金条項がなく、費用が全額負担に
ある法律事務所が医療機関向けに公開しているコラムで、このような事例が紹介されていました。ある病院が人材紹介会社経由で看護師を採用したものの、その看護師はわずか1か月で退職してしまいました。病院側は当然、手数料の返金を期待しましたが、残念ながら契約書には返金に関する条項が一切記載されていなかったのです。結果として、病院は高額な紹介手数料を全額負担することになり、返金を受けることはできませんでした。この事例は、契約内容の事前確認がいかに重要であるかを物語っています。どんなに急いでいる採用であっても、契約書の隅々まで目を通し、不明な点は必ず確認するという基本的な行動が、将来の不要な支出を防ぎます。
2. 訪問看護の現場:返金規定を明確に示している紹介会社の例
一方で、利用者である医療機関側が安心してサービスを使えるよう、配慮している紹介会社も存在します。例えば、訪問看護の分野に特化したある人材紹介会社では、自社のウェブサイト上で返金規定を具体的に公開しています。そこには、「入職後1か月未満での退職の場合は80%返金」「1か月以上2か月未満の場合は50%返金」「2か月以上3か月未満の場合は20%返金」といったように、期間と割合が明確に定められています。このように条件がはっきりしていると、採用する側も「最初の3か月は特に注意深くフォローしよう」「試用期間中に、お互いの相性をしっかりと見極めよう」といった、入職後の具体的な計画を立てやすくなります。
3. 在宅医療・小規模事業所のコスト感覚
訪問看護ステーションを含む、比較的小規模な事業所における採用コストについて言及した、あるウェブメディアの記事も参考になります。その記事によると、成功報酬が年収の25%から35%に達することも珍しくなく、場合によっては半年で離職しても返金の対象外となる契約も存在する、と指摘されています。特に、採用担当者が他の業務と兼務しているような小規模な事業所では、採用活動を自前で行う(内製化する)リソースが不足しがちです。その結果、人材紹介会社への依存度が高まり、コストが高い水準で固定化してしまう、という状況に陥りやすい傾向があるかもしれません。
4. 介護分野での動き:手数料ルールの明確化
医療と密接に関連する介護の分野でも、サービスの透明性を高める動きが見られます。例えば、有料老人ホームなどの紹介事業者団体が、利用者保護や事業者間のトラブル防止を目的として、ガイドラインを策定している例があります。その中では、短期間で契約が終了した場合の手数料の返金ルールや、複数の事業者が同じ入居者を紹介してしまった場合の取り扱いなど、具体的なルールが定められています。このように、サービスの条件を明確に「見える化」することが、利用者との信頼関係を築き、健全な業界の発展につながるという考え方が広がっています。
契約を見直すための具体的なアプローチ
これまで見てきたような背景や事例を踏まえ、人材紹介会社との契約条件を検討する際に、どのような点に注意すればよいのでしょうか。「手数料率」「分割払い」「返金規定」という3つの視点から、具体的なアプローチを考えていきます。
1. 手数料率の「意味」を院内で言葉にする
まず、手数料率についてです。相場とされる「20%から35%」という数字を、ただ漫然と受け入れるのではなく、その率が自分たちの組織にとってどのような意味を持つのかを、院内で言語化するプロセスが大切です。
例えば、看護師が一人欠員となることで、病床の稼働率が下がり、一日あたりどれくらいの収益が失われるのか(機会損失)。あるいは、残されたスタッフの残業時間が増え、時間外手当がどれだけ増加するのか。外部の看護補助スタッフを臨時で依頼した場合のコストはいくらか。こうした二次的に発生するコストも考慮に入れた上で、「この金額までなら、手数料を支払ってでも採用する価値がある」という、院内での共通認識、つまり合理的な上限ラインを設定することが第一歩です。
複数の紹介会社から相見積もりを取り、それぞれの料率を比較することも重要ですが、その際に注意したいのは、率の数字だけで交渉を進めないことです。例えば、「手数料率を引き下げる代わりに、返金規定の条件を厳しくする」「とにかく早く採用を決めることを優先し、候補者の質に関するスクリーニングが甘くなる」といった、こちらが望まない副作用が生じる可能性も考えられます。手数料率は、あくまで支払いのタイミングや返金の条件とセットで、総合的に判断することが、より安全な進め方と言えるでしょう。
2. 「分割払い(段階払い)」で“定着”と支払いを連動させる
次に、支払いのタイミングについてです。多くの契約では、採用した看護師が入職した時点で手数料を一括で支払う形式が取られています。これを、例えば「入職時に50%、3か月後の在籍確認をもって20%、6か月後の在籍確認で残りの30%を支払う」というように、分割払いの形式にできないか交渉してみる、というアプローチが考えられます。
この方法には、いくつかのメリットがあります。まず、採用する医療機関側にとっては、万が一の早期離職が発生した場合でも、初期の支出を抑えることができます。一括で全額を支払った後に返金を待つよりも、キャッシュフローの観点から負担が軽くなります。
もう一つの大きなメリットは、紹介会社側にも、採用後の「定着」までをサポートする動機(インセンティブ)が生まれやすくなる点です。支払いが完了するまでの期間、定期的に採用者と面談を行ったり、配属先の部署との間に立って人間関係の調整をしたりと、より手厚いフォローが期待できるかもしれません。
もちろん、分割払いに対応してくれるかどうかは紹介会社の方針によりますので、まずは契約前の段階で、複数社に対してこうした支払い方法が可能かどうかを打診してみることが重要です。その際は、後々のトラブルを避けるためにも、各回の支払いがいつ発生するのか(日付)、そして在籍をどのように確認するのか(例えば、給与明細の写しや在籍証明書など)といった判定基準を、契約書に明確に記載しておく必要があります。
3. 返金(返戻金)規定を「制度」として点検する
最後に、返金規定です。これは、組織を守るための重要なセーフティネットの役割を果たします。先ほど紹介した一般的な逓減パターンの例(1か月以内で100%、3か月以内で50%、6か月以内で10%など)を参考にしつつ、自院の状況に合わせて、より具体的な条件を詰めていく作業が求められます。
具体的には、以下の点を確認し、文書化しておくことが望ましいでしょう。
- 対象期間:いつまでの離職が返金の対象になるのか(例:入職後6か月以内)。
- 返金割合:在籍期間に応じて、割合がどのように変動するのか。
- 除外事由:返金の対象外となるのは、どのようなケースか。例えば、試用期間中に本人の責に帰すべき事由で解雇した場合や、採用時に提示した労働条件(給与、勤務地、業務内容など)を、入職後に施設側の都合で変更したことが離職の原因となった場合など、細かな点まで双方で認識を合わせておくことが重要です。
前述の通り、契約書に返金条項がなければ、たとえ入職後すぐに退職してしまっても、返金を求めることは法的に困難になる場合があります。契約を結ぶ前には、必ずこの条項の有無とその内容を精査する習慣をつけましょう。
契約条件が現場の「行動」に与える影響
契約条件は、ただの紙切れではありません。それは、採用に関わる人々の「行動」を変化させる力を持っています。ここでは、手数料の条件が変わることで、採用側の私たちと、紹介会社側の担当者の行動に、どのような変化が生まれやすいかを考えてみましょう。
手数料率が高いと…
採用側としては、一人あたりの採用にかかる費用が大きくなるため、選考の目が自然と厳しくなります。「絶対に失敗できない」というプレッシャーから、面接での質問が深くなったり、スキルチェックをより入念に行ったりするでしょう。また、入職前に職場見学の機会を設けるなど、できるだけ早い段階でミスマッチの可能性を潰しておきたい、という意識が強くなります。
一方で、紹介会社側としては、一般論として、早く採用を決定させたいというインセンティブが働きやすくなる可能性があります。その結果として、選考プロセスを短縮する提案(例:「面接は1回で決めましょう」)をしたり、内定を出すかどうかの決断を急がせたりするようなコミュニケーションが増えるかもしれません。
分割払いだと…
採用側にとっては、分割金の支払日がマイルストーンとして機能します。例えば「3か月後の支払日」がカレンダーに見えていると、「その日までに、新しいスタッフが職場に馴染めるように、しっかりとサポートしよう」という意識が自然と生まれます。配属先の決定や、教育担当(プリセプター)の選定、引継ぎの計画などが、より丁寧で慎重になる傾向があります。
紹介会社側も、支払いが完了するまでは関係が続くため、入職後のフォローが手厚くなることが期待できます。採用者との定期的な面談に同席したり、現場で起きがちな人間関係の摩擦や、シフトに関する不満などを早期に察知し、解決に向けて介入してくれる場面が増えるかもしれません。
返金規定が手厚いと…
採用側では、「万が一、どうしても合わない場合は、早めに申し出れば金銭的なダメージは少ない」という心理的な安全性が生まれます。これは、採用担当者だけでなく、現場の看護師長や同僚にとっても同じです。無理に引き留めるのではなく、「このまま続けてもお互いのためにならない」と判断した場合に、正直な意見を言いやすい雰囲気が醸成されることがあります。
紹介会社側は、返金のリスクを避けるために、何よりもマッチングの精度を高めることに注力するようになります。ただ単に「経験年数」や「保有資格」といった条件面だけでなく、「貴院の理念に共感できるか」「この病棟のチームワークに馴染めるか」といった、より定性的な部分まで深く掘り下げて、候補者を探そうとするでしょう。
もちろん、これらはあくまで一般的な傾向です。しかし、こうした「人の行動の変化」をあらかじめ想像した上で、自院の求人票の書き方や面接での質問内容、入職後のフォロー体制といった一連の流れを、「早期の見極め」と「入職後の丁寧なケア」という二つの軸で最適化していくことで、採用活動全体の無駄を減らしていくことができる、と私は考えています。
今日から始められる小さなチェックリスト
ここまで様々な観点から成功報酬の仕組みを見てきましたが、最後に、院長先生や看護部長、事務長の方々が、すぐに実践できる確認項目をリストアップしました。
看護師採用の成功報酬で確認すべき5つの項目
- 率年収の何パーセントが手数料になるか。その「年収」には、基本給だけでなく、夜勤手当や賞与などがどこまで含まれるのか。提示された料率が、市場の相場(一般的に20%から35%程度)と比べてどのような位置づけにあるか、複数の情報源を基に再確認しましょう。
- 分割支払いを分割にすることは可能か。もし可能な場合、入職後、何ヶ月在籍した時点で、何パーセントを支払うことになるのか。在籍していることの確認は、どのような方法(例:勤怠記録や給与明細の写しの提出など)で行うのか、具体的な手順まで合意しておきましょう。
- 返金早期離職の際に返金が適用される期間(例:1か月、3か月、6か月など)と、その期間に応じた返金の割合(例:100%、50%、10%など)。そして、返金の対象から外れる「除外事由」には、どのようなケースが記載されているか(例:施設側の都合による配置転換や労働条件の変更など)を、一つひとつ確認します。
- 公開情報利用を検討している紹介会社が、手数料率や違約金に関する規定を、自社のウェブサイトや事業所内で適切に明示しているか。契約を結ぶ際は、その最新の掲示内容をお互いにデータとして保存しておくと、後々の認識の齟齬を防ぐのに役立ちます。
- 事後フォロー紹介会社の担当者が、入職後のフォロー(定期的な面談、人間関係の調整、シフトに関する相談対応など)に、どこまで関与してくれるのか。このフォロー体制は、分割払いや返金規定の設計と密接に関連していることが多いため、合わせて確認するとよいでしょう。
採用“依存”の悪循環を断つヒント
まとめ:大切なのは率よりも「設計」、そして「関係性」
成功報酬という仕組みは、「初期費用がかからないからリスクが低い」と一見すると感じられるかもしれません。しかし、これまで見てきたように、手数料の率、支払いの分割、そして返金の規定という「契約の設計」次第で、現場の行動(候補者の見極め方、入職後のフォローの濃さ、そして採用活動に対する組織全体の内省の深さ)は、良くも悪くも大きく変わります。
手数料の「率」については、市場の相場を参考にしつつも、自院にとって「意味のある上限」はどこなのかを、機会損失などの観点からしっかりと議論して決めることが大切です。
支払いの「分割」は、採用後の「定着」と費用負担を連動させ、紹介会社と医療機関が同じ目標に向かって伴走するための仕組みとして機能する可能性があります。
そして「返金」は、万が一の際に組織を守るための保険です。条件の明示と、特に返金の対象外となるケース(除外事由)の整理を丁寧に行うことで、解釈の違いから生じるトラブルの芽をあらかじめ摘んでおくことができます。
最終的に目指すべきは、採用する側、紹介する側、そして入職する看護師の三者間で、期待値が大きくずれることのない、良好な「関係性」を築くことではないでしょうか。この関係性が、結果として早期離職を防ぎ、無駄な採用コストの発生を抑制します。
そして、その良好な関係性をじっくりと育む時間を作るためにも、いきなり長期雇用を目指すのではなく、まずは短期のお試し勤務から始めて本採用へとつなげるような、段階的な設計を取り入れることも、これからの時代において非常に有効な手段の一つだと考えられます。
もし、こうした採用のミスマッチを減らしつつ、スピーディーな募集も両立したいとお考えでしたら、ぜひ一度「クーラ」のようなサービスも選択肢の一つとしてご検討いただければ幸いです。
クーラのご案内
- ミスマッチを根本から減らしたいとお考えの方へ短期のお試し勤務を通じて、お互いの相性をしっかりと確認してから、長期的な関係へとステップアップする。私たちはそんな採用の形を支援しています。全国に多くの登録看護師がおり、募集開始までがスピーディーなのも特長です。クーラのサービス案内はこちら
- 採用や労務管理の負担を少しでも軽くしたいとお考えの方へお試し勤務に関わる求人票の作成から、煩雑になりがちな労務手続きまで、デジタル技術(DX)を活用してサポートし、現場の皆様の手間をできるだけ抑える工夫をしています。詳細はこちらからご覧ください
参考(読みもの・公開情報)
- 手数料率・返金パターンの公開例
- 様々な企業や個人が、手数料や返金規定に関する情報を公開しています。期間は1週間から6か月、返金方法は逓減式が一般的です。(例:note記事、訪問看護向けサービスの規程、業界解説メディアなど)
- 相場に関する情報
- 手数料率は年収の20%から35%が目安とされ、年収400万円から500万円の看護師を採用した場合、100万円から175万円規模の費用感となる可能性があります。(例:メディカルリンク、セカンドラボなど医療系サービスの情報)。クーラを利用することで、看護師採用手数料を、従来の主要業者比で約半額に抑えることも見込めます。
- 離職率に関するデータ
- 公益社団法人日本看護協会の調査では、病院に勤務する正規雇用看護職員の離職率は約1割強で推移しており、特に新卒者の年度内離職率はより高い傾向が見られます。
- トラブルに関する事例
- 契約書に返金条項がなかったために、採用した職員が早期に退職したにもかかわらず、手数料が一切返金されなかったという事例が、法律事務所のウェブサイトなどで紹介されています。
- 情報の公開義務について
- 職業紹介事業者は、職業安定法に基づき、手数料や違約金などに関する規定を明示する義務があります。詳細は各都道府県の労働局のウェブサイトなどで確認できます。







.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)





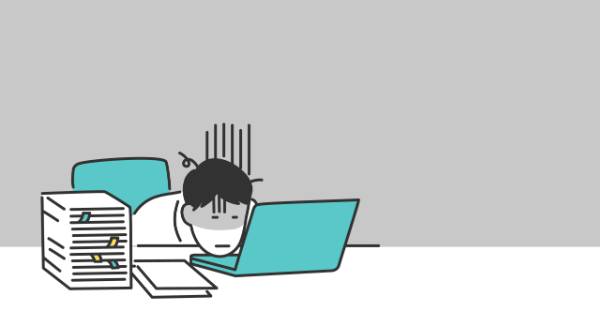
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
