10分の遅れが「日々の暮らしの崩れ」につながる理由
「私たちの職場は、残業がほとんどありません。発生したとしても、せいぜい毎日10分程度です。」
採用面接や求人票で、このように伝えているにもかかわらず、なぜか応募者が集まらなかったり、せっかく入職した方がすぐに辞めてしまったりする。そうしたご経験をお持ちの採用担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
実は、この「毎日10分」の退勤の遅れは、看護師一人ひとりの生活設計にとって、決して小さな影響ではありません。例えば、ある看護師さんの1日を想像してみてください。定時は17時。もし10分遅れて17時10分に職場を出ると、いつも乗るはずだった電車に間に合わず、次の電車を待つことになります。たった1本乗り過ごしただけかもしれませんが、その影響は連鎖的に広がっていきます。
駅に着く時間が遅れれば、保育園のお迎えが延長保育の時間にかかってしまい、追加の料金が発生するかもしれません。家に帰り着く時間も遅くなり、そこから慌ただしく夕食の準備を始めることになります。入浴の時間も、子どもを寝かしつける時間も、すべてが少しずつ後ろにずれていきます。そして最後に削られてしまうのが、自分自身の休息や睡眠の時間です。
この10分の遅れが、1ヶ月(勤務日数22日で換算)積み重なると、約3時間40分にもなります。年間では44時間、つまり丸2日近い勤務時間と同じくらいの時間が、予定外に失われている計算になります。
大切なのは、時間外手当が支払われるかどうかという問題だけではありません。わずかな遅れであっても、「毎日、確実に、予定通りに帰れない」という状況が続くこと。これが、実質的に勤務と勤務の間の休息時間、いわゆる「勤務間インターバル」が短くなっているという体感につながり、日々の暮らしの計画が立てられないことへの強いストレスや、職場に対する不信感へと発展していくことがあります。
採用を成功させ、職員に長く働き続けてもらうためには、この数字には表れにくい「体感の差」を深く理解し、求人での伝え方や日々の職場運営を丁寧に見直していくことが、とても重要になります。
この記事では、小規模な病院やクリニック、訪問看護ステーション、介護施設などの具体的な事例を交えながら、なぜ「たった10分」がこれほどまでに敬遠されるのか、その背景にある課題を掘り下げ、どのようにすればその状況を解消できるのか、具体的な方法を一緒に考えていきたいと思います。
※もし、採用のミスマッチを避けつつ、自院の働き方に合う人材かを見極めたいとお考えでしたら、短期のお試し勤務から始めてみるという方法もあります。募集や労務管理の負担を抑えながら、必要な時に必要な人材を素早く集める方法について、クーラの導入相談で詳しくご案内しています。よろしければご覧ください。https://business.cu-ra.net/
背景にある課題:勤務間インターバルと医療の安全、そして職員の定着
近年、日本国内で「勤務間インターバル制度」という考え方が、厚生労働省などを中心に広く周知されるようになりました。これは、仕事の終業時刻から次の始業時刻までの間に、一定時間以上の休息時間を確保するという考え方です。十分な休息は、働く人の心身の健康を守るために不可欠であるとされています。
特に医療や介護の分野では、人材を確保し、安全なケアを提供し続けるという観点から、この休息時間を確保することの重要性が繰り返し示されてきました。睡眠時間が不足すると、注意力が散漫になったり、判断力が低下したりすることが知られています。これが、医療現場で起こるヒヤリ・ハットやアクシデントの増加につながる可能性も指摘されています。したがって、たとえ1日10分という短い時間であっても、毎日のように退勤が遅れる状況が常態化してしまうと、それは職員の休息の質に直接影響を及ぼし、ひいては医療やケアの安全性を脅かすことにもなりかねません。
厚生労働省が開設している「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、勤務間インターバル制度の導入事例が紹介されています。ここで重要なのは、この制度を単に就業規則に「終業から次の始業まで11時間以上の休息を確保するよう努める」といった一文を書き加えるだけで問題が解決するわけではない、という点です。
制度が本当に意味を持つのは、時間外勤務そのものが発生しにくい業務の設計と、それを維持するための日々の運用が伴ってこそです。例えば、高齢者福祉施設の事例では、「時間外勤務はあくまで“異常事態”である」という意識を組織全体で共有し、勤怠管理の仕組みと業務プロセスの見直しを一体で進めたことで、職員の休息時間の確保と定着率の向上につながったという報告があります。形だけのルールではなく、実体を伴った取り組みが成果を生むのです。
小さな遅れを生まないための、現場の具体的な工夫
では、実際にさまざまな医療・介護の現場では、日々の小さな遅れの発生を防ぐために、どのような工夫が行われているのでしょうか。ここでは、具体的な施設名やサービスの事例をいくつかご紹介します。
- ケアプロ訪問看護ステーション(東京都足立区)の事例:訪問スケジュールの最適化
- 見出し行
- スケジュール作成をシステム化し、終業間際の停滞感を解消
- 説明文行
- 訪問看護の現場では、日々の訪問スケジュールの作成が大きな業務負担となることがあります。ケアプロでは、このスケジュール作成業務に専用のシステムを導入しました。これにより、これまで担当者が多くの時間を費やしていた作成業務が大幅に短縮され、効率化されました。その結果、職員間のコミュニケーションの質が向上し、終業前後に発生しがちだった「申し送りのための待ち時間」や「記録のためのちょっとした居残り」といった、わずかな時間の停滞が解消されたといいます。一つひとつの訪問スケジュールが無理なく組まれることで、1件あたりの数分の遅れが連鎖的に積み重なって終業時刻を圧迫する、という現象が起こりにくくなり、職員が退勤時刻の見通しを立てやすくなりました。
- 見出し行
- 特別養護老人ホーム エーデル土山(滋賀県甲賀市)の事例:「時間外は例外」というルールの徹底
- 見出し行
- 時間外勤務を「異常事態」として管理し、不要な残業を抑制
- 説明文行
- こちらの施設では、時間外勤務を「原則として行わない、やむを得ない場合は異常事態」として位置づけ、実施する際には必ず上司の明確な指示を必須とする運用を徹底しました。これにより、「キリが悪いからもう少しだけ」「他の人が残っているから帰りにくい」といった、明確な業務指示のない“なんとなくの10分残業”が抑制され、勤務間インターバルの確保が進みました。また、香川県のある有料老人ホームでは、助成金を活用してクラウド型の勤怠管理システムを導入し、制度の整備とシステムの導入を同時に行ったことが、働き方の改善を後押ししたという事例も報告されています。
- 見出し行
- 小規模病院での事例:申し送りの標準化とリアルタイム記録
- 見出し行
- 申し送り内容を見直し、記録方法を変えることで終礼時間を短縮
- 説明文行
- 日本看護協会の事業報告の中では、看護業務の効率化に関する多くの実践が紹介されています。その中には、日々の申し送りの内容を「必ず伝えるべき重要な項目」に絞って標準化したり、患者さんのケアをしながらその場でタブレット端末などに記録を行う「リアルタイム記録」に切り替えたりすることで、時間外勤務と申し送り時間が短縮されたという取り組みが複数あります。特に小規模な病院では、これまで慣習的に行われていた「始業前の情報収集」といった時間も、正式な業務時間内に組み込むなど、業務時間外とみなされがちだった数分間を、きちんと業務時間内に確保する工夫が有効であるとされています。
- 見出し行
- クリニック(外来)での事例:事務作業の自動化
- 見出し行
- 定型的な事務作業を自動化し、「最後の10分」を生み出さない工夫
- 説明文行
- クリニックの業務では、RPA(Robotic Process Automation)と呼ばれる、パソコンで行う定型的な作業を自動化するツールの導入事例が報告されています。例えば、診療時間終了後に行うレセプト関連の集計作業や、翌日の予約確認といった事務的な工程が自動化されると、職員が「最後の10分」を使って行っていた作業そのものがなくなり、毎日の退勤時刻の遅れを解消しやすくなります。外来業務は日によって患者さんの数が変動し、終業間際に業務が集中しがちですが、こうしたツールを活用することで、職員の負担を軽減し、定時退勤を促すことができます。
- 見出し行
これらの事例に共通しているのは、職員個人の努力や「早く帰ろう」という意識に頼るのではなく、「10分の遅れが常態化しない」ための仕組みや業務設計を、組織全体で構築しようとしている点です。看護師一人ひとりの頑張りで埋め合わせる余地を残してしまうほど、その職場は敬遠されやすくなるのかもしれません。
解決へのアプローチ:「10分の遅れ」を仕組みで無くすための5つの視点
日々のわずかな退勤の遅れを解消するためには、精神論ではなく、業務の仕組みそのものを見直すことが近道です。ここでは、そのための具体的な5つの視点をご紹介します。
なお、採用広報の場面では、「残業ほぼ無し」という曖昧な言葉よりも、退勤予定時刻と実績が一致するための具体的な運用を公開する方が、求職者からの信頼を得やすい傾向にあります。例えば、以下のような情報です。
- 「申し送りは、共有すべき3項目に絞ったテンプレートを使用し、5分で完了します」
- 「日計作業は日中に行うため、終業時は最終チェックのみです」
- 「時間外勤務を行う際は、必ず所属長からの事前指示が必要です」
このような、業務設計の中身を具体的に示すことが、応募を検討している方の安心感につながります。
よくあるつまずき:なぜか10分が消えない職場の特徴
仕組みを変えようと試みても、なかなか定時退勤が定着しない職場には、いくつかの共通した特徴が見られます。もし自院が当てはまっていないか、確認してみてください。
- 「最後にまとめてやればいい」という工程が多い
- 特徴
- 看護記録、物品の片付け、翌日の準備など、多くの作業を終業間際に集中させてしまう傾向があります。
- 対策
- 一日のタスクを洗い出し、日中の空き時間などに前倒しできる工程に細かく分割しましょう。終業時は「最終確認だけ」の状態を目指すことが理想です。
- 特徴
- 口頭での申し送りや、二重の記録が残っている
- 特徴
- 口頭で伝えた内容を、後からもう一度カルテに入力し直すなど、同じ情報を複数回扱う手間が発生しています。
- 対策
- 日本看護協会の報告にもあるように、リアルタイムで記録できる仕組みと、要点を絞ったテンプレートを活用することで、情報の再入力を無くすことができます。
- 特徴
- “善意による自発的な残業”が評価されてしまう雰囲気がある
- 特徴
- 「他の人のために」「時間内に終わらなかったから」といった理由で自主的に残ることが、熱心さの表れとして捉えられがちです。
- 対策
- 「働き方・休み方改善ポータルサイト」の事例にもあるように、時間外勤務はあくまで例外であり、指示があった場合のみ行うというルールに切り替え、文化そのものを変えていく必要があります。
- 特徴
- シフトと実際の業務量のバランスが合っていない
- 特徴
- 訪問看護で移動時間が見積もりより常にかかってしまったり、外来で最後の患者さんの対応がいつも受付時間を大幅に超えてしまったりします。
- 対策
- 訪問ルートや移動時間のデータを見直したり、外来の予約枠や受付の締め時間を調整したりするなど、現実の業務量に合わせてシフトや時間割を最適化することが求められます。訪問看護のスケジュール最適化事例は、この点で多くのヒントを与えてくれます。
- 特徴
採用活動での伝え方:言葉だけでなく「仕組みの証拠」を示す
求人票や面接の場で、単に「残業は少なめです」と伝えるだけでは、候補者は「本当だろうか?」と半信半疑に感じてしまう可能性があります。ここで効果的なのは、言葉による説明に加えて、その言葉を裏付ける「運用の証拠」を具体的に示すことです。
例えば、以下のような資料を面接時に見せたり、求人サイトに掲載したりすることが考えられます。
- 月ごとの「退勤予定時刻と実績時刻の差」を示した簡単なグラフ
- 実際に使っている申し送りのテンプレートや、日中に前倒しで行うタスクの一覧
- 時間外勤務が必要になった際の、申請から承認までの流れを示したフロー図
- 勤務間インターバルの実績時間を示した、勤怠管理システムの画面サンプル
「私たちの職場には、毎日10分遅れるような文化はありません」というメッセージを、こうした具体的な運用資料で見せること。これが、応募率の向上と入職後の定着率の両方に良い影響を与えます。制度面の背景として、厚生労働省の資料などを軽く添えておくと、より安心材料になるでしょう。
※もし、こうした職場全体の運用を整えていく過程で、一時的に人手が不足したり、欠員のリスクを下げたりしたい場合には、お試し勤務で職場との相性を確かめながら人材を受け入れる方法が安全です。人材が集まりやすい募集媒体を活用すれば、現場の負担を増やすことなく、新しい体制を試すことができます。参考までに、クーラの導入相談では、即戦力となる人材を短期間から確保できる仕組みをご案内しています。https://business.cu-ra.net/
まとめ:10分の遅れは“気持ち”の問題ではなく“仕組み”の問題
看護師が毎日の10分の遅れを不快に感じるのは、それが日々の生活設計の崩れや、大切な休息時間が少しずつ削られていくことを、毎日確実に実感するからです。この問題は、個人の気持ちや頑張りで解決するものではなく、業務の仕組みそのものの問題として捉えることが重要です。
この記事でお伝えしたポイントは、大きく3つにまとめられます。
- 終業前の工程を、できるだけ日中に前倒しすること
- 申し送りや記録、日計などの作業を細かく分解し、テンプレート化を進めます。
- “時間外勤務は例外である”という運用を徹底すること
- 実施には明確な指示を必須とし、休息時間を「見える化」して管理します。
- シフトと実際の業務量のバランスを常に見直すこと
- 訪問ルートや移動時間、外来の受付時間などを現実に合わせて調整します。
これらの取り組みは、小規模な病院、クリニック、訪問看護ステーション、介護施設など、どのような規模の職場でも実行可能であり、すでに多くの具体的な実践事例が報告されています。制度という土台の上に、日々の運用設計を丁寧に積み重ねていけば、あの「10分」は着実に無くしていくことができます。
今日からすぐにでも始められる、第一歩として、以下の項目を試してみてはいかがでしょうか。
- 今日からできる最初の一歩
- 申し送りのテンプレートを、重要な3項目・5分で完了できるものに固定してみる。
- 日計や翌日の準備作業を、日中に2回に分けて行うようにしてみる。
- 終業30分前は、緊急時を除き「重いタスクは入れない」というルールを試験的に導入する。
- 時間外勤務は、上長からの明確な指示がない限りは認められないことを改めて周知する。
- まずは1週間、職員の退勤予定時刻と実際の時刻の誤差を記録し、共有してみる。
現場の「10分の遅れを無くす」ためには、欠員を速やかに補充し、採用のミスマッチを回避することも、同時並行で進めていくと安全です。登録者数が多く、迅速に募集を開始でき、お試し勤務でミスマッチを防げるような募集媒体を活用すると、職場は業務改善そのものに集中しやすくなります。もしご興味があれば、クーラ(施設向け)のウェブサイトで、その仕組みをご確認いただければ幸いです。
また、お試し勤務に関連する求人から労務管理までの負担をデジタルツールで軽減できる点も、結果として終業間際の「最後の10分」を増やさないことにつながります。無理のない範囲で、まずは小さな一歩から試してみてください。
参考にした公開資料(抜粋)
- 厚生労働省「医療業における勤務間インターバル導入・運用マニュアル」
- 休息を確保することの意義や、具体的な導入手順、他院の事例などがまとめられています。(働き方・休み方改善ポータルサイトより)
- 厚生労働省「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル(高齢者福祉)」
- 介護施設での具体的な運用事例や、時間外勤務を「異常」として管理する考え方、助成金の活用方法などが紹介されています。(働き方・休み方改善ポータルサイトより)
- 日本看護協会「看護業務効率化先進事例収集・周知事業報告書」
- 申し送り時間の短縮や、始業前の情報収集といった業務の見直しによる時間外勤務削減の取り組みが多数掲載されています。
- 訪問看護のスケジュール最適化事例(ZEST導入事例)
- スケジュール作成時間の短縮が、結果として当日の業務の誤差を抑制することにつながるという示唆が得られます。
- クリニックのRPA活用事例(BizRobo!導入事例など)
- 診療後の締め業務などを自動化することによる、残業削減の効果が報告されています。
おわりに
毎日の10分は、制度の有無よりも、日々の業務設計と運用の問題として捉え直すことで、解決の糸口が見えてきます。まずは、職員の「退勤予定時刻が、実績と一致する」という当たり前の状況を作り出し、その事実をもって、働く人々の安心感を育んでいくことが大切です。
人員確保の一つの選択肢として、短期のお試し勤務から長期的な定着へとつなげる流れを柔軟に取り入れたいとお考えの場合は、クーラの導入相談から小さく始めてみることをお勧めします。https://business.cu-ra.net/

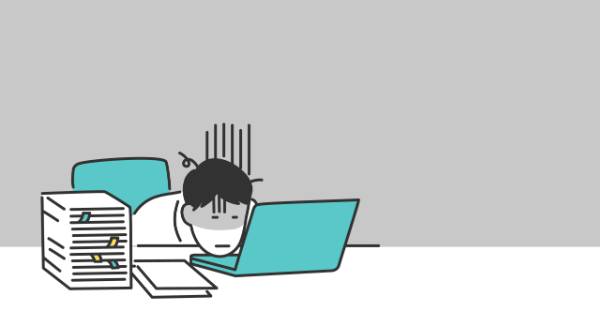





.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)






.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
