忙しさが採用を止める、大きな要因の一つ
「求人は出しているのに、なかなか面接が組めない」「応募者への対応が後手に回り、貴重な候補者を逃してしまった」。このようなお悩みは、全国各地の医療機関様からお話を伺う中で、頻繁に耳にするものです。その根底にある課題を丁寧に紐解いていくと、多くの場合、「現場の多忙さ」という共通の要因に行き着きます。
特に看護部門は、社会的な需要の高さと裏腹に、慢性的な人手不足や業務量の多さに直面しやすい環境にあります。看護職のニーズは高まる一方で、離職や急な欠員、配置転換などが続くと、採用活動は「重要ではあるものの、緊急ではない」タシューとして、日々の緊急業務の波にのまれてしまいがちです。
その結果として、応募者への返信が数日後になってしまったり、面接の日程調整が一向に進まなかったり、内定を出してから入職に至るまでのフォローが手薄になったり、といった事態が起こります。これらは、残念ながら「採用活動が思うように進まない病院」でしばしば見られる傾向と言えるでしょう。
日本看護協会が公表しているデータを見ても、看護職の離職率は依然として軽視できない水準で推移しています。例えば、「2023年 病院看護実態調査」によると、2022年度の正規雇用看護職員の離職率は11.8%でした。これは、約10人に1人が1年間で職場を去っている計算になります。特に新卒採用者に限っても8.9%、既卒採用者に至っては16.1%と、決して低いとは言えない数字です。このような状況が続く限り、新たな人材の確保と定着は、病院経営における最重要課題の一つであり続けるでしょう。
この複雑で根深い課題を解決に導くための一つの現実的なアプローチは、院内における採用業務の役割分担を一度見直し、プロセスを細かく「分解」することです。そして、分解した業務のうち、外部の専門家や他職種のスタッフに任せられる部分は積極的に「代行」してもらう体制を構築することにあります。
この記事では、実際の医療機関で見られる工夫や取り組みの事例を交えながら、「多忙な現場であっても、着実に前に進める採用活動」へと転換していくための具体的な方法を、順を追って解説していきます。また、その一つの有効なツールとして、当社が提供する「クーラ(Cura)」を活用した、「お試し勤務(短期アルバイト)」を起点とする新しい採用の形も、随所に織り交ぜてご紹介します。
背景・課題:なぜ採用活動は滞ってしまうのか(可視化すべき3つの摩擦)
採用活動が円滑に進まない背景には、いくつかの構造的な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、特に課題となりやすい3つの「摩擦」について、データを交えながら掘り下げていきます。
看護師の有効求人倍率と需給ギャップ:市場構造の逆風
まず、看護師採用の市場環境そのものが、採用側にとって厳しい状況にあることを認識する必要があります。厚生労働省が発表する「一般職業紹介状況」を見ると、看護師や准看護師を含む「保健師、助産師、看護師」の有効求人倍率は、長年にわたり全職業の平均よりも高い水準で推移しています。例えば、2024年に入ってからも、パートタイムを含む有効求人倍率は2倍を超えており、これは求職者1人に対して2件以上の求人がある、いわゆる「売り手市場」が続いていることを示しています。
さらに、厚生労働省の「医療従事者の需給に関する検討会」の報告書などでは、日本が迎える超高齢社会において、看護職員の需要は2025年に向けて、そしてその先もさらに増大していくと推計されています。つまり、「求人票を公開すれば自然に応募者が集まる」という時代は終わり、数多くの競合する医療機関の中から自院を選んでもらうための、戦略的な採用活動が不可欠となっているのです。
このような市場環境では、応募があった際の「初動の速さ」が決定的に重要になります。応募者は同時に複数の病院に応募しているケースがほとんどです。返信が早い、対応が丁寧、日程調整がスムーズといった初期対応の質が、応募者の心証を大きく左右し、その後の選考に進んでもらえるかどうかを分ける最初の関門となります。だからこそ、迅速な対応を可能にするための「分業設計」が、採用成果に直結するのです。
離職・欠員が“時間”を奪い、採用が後手に回る現実
次に、院内の事情に目を向けてみましょう。前述の通り、看護職の離職率が2桁台で推移する状況では、現場は常に人員の変動にさらされています。一人の看護師が離職すると、その穴を埋めるために、残されたスタッフの業務負担は増大します。夜勤回数の増加、シフトの再調整、新人や異動者へのOJT(On-the-Job Training)の負荷など、目に見える形、見えない形で現場の時間は奪われていきます。
看護部長や師長といった管理職は、こうした現場の混乱を収拾し、日々のオペレーションを維持することに忙殺されます。その結果、本来であれば優先的に取り組むべき採用活動に割く時間が物理的に確保できなくなってしまいます。日本看護協会の調査でも、多くの病院で看護職員の業務効率化やタスク・シフティング(業務の移管)が重要な経営課題として認識されていることが示されています。
つまり、日々の業務に追われる中で、新たに「採用のための時間」を生み出すことは極めて困難です。必要なのは、既存の業務を「入れ替える」こと、そして一部の業務を他者や外部サービスに「肩代わりしてもらう」という発想の転換です。現状の業務フローを変えずに、ただ「頑張って採用活動をしよう」と精神論に頼るだけでは、状況は改善しにくいのが現実です。
応募対応の遅延・面接調整の滞留・内定辞退の連鎖
市場が売り手市場であり、院内が多忙であるという二つの要因が重なることで、最も顕著な問題として現れるのが、応募者対応の遅れです。
考えてみてください。勇気を出して求人に応募したにもかかわらず、病院からの返信が3日後、あるいは1週間後だったとしたら、応募者はどう感じるでしょうか。「この病院は応募者を大切にしていないのかもしれない」「もっと対応の早い他の病院の選考を進めよう」そう考えるのが自然です。
応募者への最初の連絡が遅れること。面接日程の候補を提示するのに時間がかかること。面接の前日にリマインドの連絡がないこと。これらは一つ一つは小さなことのように思えるかもしれませんが、積み重なることで確実に「面接辞退」や「当日キャンセル(ドタキャン)」のリスクを高めます。
「ジョブメドレー」などの医療系メディアが発信する情報を見ても、選考のスピード感や、前日・当日のきめ細やかな連絡といった運用が、応募者の離脱率に直接的な影響を与えることは、業界の実務知見として繰り返し指摘されています。応募から面接、内定、そして入職までの一連のプロセスにおいて、一貫して迅速かつ丁寧なコミュニケーションを維持できるかどうかが、採用の成否を分ける重要な鍵となるのです。
実例紹介:忙しい院内でも回る“分業と代行”の小さな成功
ここでは、規模や地域の異なる医療機関で実際に見られ、効果を上げている役割分担や業務代行の工夫を、具体的な事例としてご紹介します。これらは、公開されている情報や専門メディアの知見などを基に、要点をまとめたものです。
実例1:応募一次対応を“非看護職”が担い、返信SLAを4時間に固定
- 狙い:応募者が最初に接する体験(レスポンスの速さ)の質を安定させ、機会損失を防ぐ。
- 型:
- 求人サイトや自院の採用ページからの応募に対する一次返信(応募受付の連絡、簡単な質問への回答、面接・見学候補日の提示など)は、医事課や総務課のスタッフが担当するルールを設けます。その際、誰が対応しても質がぶれないよう、詳細な対応ガイドラインや返信テンプレートを整備します。
- 応募者からの質問のうち、臨床経験や専門的な知識を要するものについては、その場で無理に回答せず、「担当の看護部門に確認の上、改めてご連絡します」と一次回答をします。そして、それらの質問をリストアップし、看護副部長など特定の役職者が「1日に1回、15分」といった時間を確保し、まとめて回答を作成する仕組みを作ります。
- この運用により、応募があってから4時間以内に何らかの形で応募者に最初の連絡を返す、というSLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)を院内の共通目標として設定し、実行します。
- 効果:応募者への一次返信の速度が劇的に向上することで、応募者が他の病院の選考に進んでしまう前に、自院との接点を確保し、選考への参加意欲を維持する効果が期待できます。一般の採用市場においても、応募への反応速度は、応募者のエンゲージメントに大きく影響することが知られています。特に、近年は求人広告のクリック単価や応募獲得単価が上昇傾向にあるため、広告費をかけて得た貴重な応募を無駄にしないためのレスポンス改善は、費用対効果の観点からも非常に重要です。例えば、採用管理に関する情報発信を行うnoteの記事などでも、初動の速さが採用コスト全体に与える影響の大きさが指摘されています。
- クーラ活用ポイント:クーラ(Cura)を通じて「お試し勤務」の希望者を募る場合に、この仕組みは特に有効です。お試し勤務は、正式な面接を経ずに短期の有給アルバイトとして働いてもらう形式のため、臨床的な判断を必要とする質問が少なく、事務スタッフ主導で日程調整までを進めやすいという利点があります。応募者に対して、「まずは1回から4回程度、職場の雰囲気を確かめながら働いてみませんか?」という提案を、事務スタッフからスムーズに行うことが可能になります。
実例2:面接前提をやめ“お試し勤務”を一次評価に—現場拘束を大幅削減
- 狙い:看護管理職や現場スタッフが、面接の同席、評価会議、日程調整などに費やしていた時間を大幅に削減し、本来の業務に集中できるようにする。
- 型:
- 看護師募集の際の最初のステップとして、従来の「面接」を原則として廃止し、「まず半日または1日のお試し勤務」に参加してもらうフローに統一します。応募者への案内や手続きは、前述の通り事務スタッフが中心となって完結させます。
- お試し勤務当日に、候補者と一緒に業務を行う現場の看護師は、指導役となるプリセプター1名に限定します。これにより、多くのスタッフが対応に追われる状況を避けます。評価も、特別な時間を設けるのではなく、通常のシフト業務の中で候補者の動きを見ながら行えるように設計します。
- 勤務終了後の評価プロセスを極限まで簡略化します。評価項目を「医療安全への意識」「チーム内での協働姿勢」「新しい知識や手順を学ぶ意欲」といった最も重要な3つの観点に絞り込み、それぞれについて「○(良い)」「△(普通)」「×(懸念あり)」で申告する形式とします。この評価結果を基に、翌日の午前中には採用可否の一次判断を下す、という迅速な意思決定フローを確立します。
- 効果:この取り組みにより、従来であれば30分から60分程度かかっていた面接を、応募者の数だけ実施する必要がなくなり、さらにその後の評価会議や関係者間のすり合わせといった時間も大幅に削減できます。採用可否を判断する根拠も、面接での短い会話から得られる情報よりも、実際の業務(ワークサンプル)に基づいた具体的な情報に一本化されるため、入職後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを減らす効果も期待できます。これは、日本看護協会が推進する看護現場の業務効率化やタスク・シェアリングの考え方にも合致する、合理的なアプローチです。
- クーラ活用ポイント:クーラは、最初から給与が発生する短期アルバEイト契約を前提として設計されています。そのため、医療機関側が労働条件通知書の準備や給与計算、労務管理といった法的な整理を気にすることなく、「面接なしで、まずは短期で働いてみる」という流れを標準的な採用プロセスとして安心して導入できます。候補者との相性を見極めた上で、双方の合意があれば継続雇用へとスムーズに移行できる点も大きなメリットです。
実例3:前日接触と代替スロットを“事務主導”で運用、当日キャンセルを防ぐ
- 狙い:多忙な応募者が面接やお試し勤務の日時を忘れてしまったり、他の予定と重複してしまったりすることによる、当日のキャンセル(ドタキャン)率を低減させる。
- 型:
- 面接やお試し勤務の前日の午前中に、事務スタッフから候補者へ最終確認の連絡を入れることを標準業務(SOP:Standard Operating Procedure)とします。連絡手段は、電話とSMS(ショートメッセージサービス)を組み合わせるのが効果的です。伝える内容は、日時、集合場所、持ち物、服装、緊急連絡先など、候補者が当日安心して来院できるための情報に絞ります。
- 急な体調不良や都合でキャンセルせざるを得なくなった候補者に対して、その場で提示できる「代替スロット表(予備の日程リスト)」を事務スタッフが常に手元に用意しておきます。これにより、「申し訳ございません」と連絡をくれた候補者に対し、「承知いたしました。よろしければ、来週のこの日時はいかがでしょうか?」と即座に次の機会を提案でき、関係性の断絶を防ぎます。
- 当日、予定時刻になっても候補者が現れない場合の連絡手順も、「まず電話→応答がなければSMS→最後にメール」といったように、多重化し、テンプレート化しておきます。
- 効果:医療系求人メディア「ジョブメドレー」などでも、選考離脱を防ぐための施策として、前日や当日のきめ細やかなコミュニケーションの重要性が強調されています。院内でこうした多重の接触ルールを設け、さらに代替日程を即座に提示できる体制を整えることで、一度は失いかけた機会を再びつなぎ留め、採用活動全体を安定させる効果があります。
- クーラ活用ポイント:クーラを利用すると、候補者とのコミュニケーションはプラットフォーム上のメッセージ機能に集約されます。これにより、事務スタッフが複数の候補者の状況を一元的に管理し、前日のリマインドなどを送りやすくなります。万が一、当日キャンセルが発生した場合でも、クーラのシステム上で公開している他の勤務シフトをすぐに提案し、同一週の別の日時などにスムーズに振り替えるといった柔軟な対応が可能です。
実例44:RPO(採用代行)で“上流の先着順勝負”に勝つ
- 狙い:競争が激しい母集団形成(応募者を集める段階)から、応募への一次対応、面接設定といった採用プロセスの「上流工程」を専門の外部パートナーに委託することで、院内スタッフの負担を軽減しつつ、採用の速度と量を確保する。
- 型:
- 看護師採用に特化した実績を持つRPO(Recruitment Process Outsourcing)サービスを提供する企業と契約し、求人原稿の作成や最適化、複数の求人媒体への出稿管理、スカウトメールの送信、応募者への一次対応、面接日程の調整といった一連の業務を包括的に委託します。
- 院内の採用担当者(看護部長や人事担当者)は、RPOパートナーが設定した面接やお試し勤務の評価、そして最終的な合否判断、入職後の定着支援といった、院内でしかできないコア業務に集中します。
- 効果:RPOを活用する最大のメリットは、応募に対する初動の「速度」と「量」を安定的に担保できる点です。多くの候補者は複数の求人に同時に応募しているため、「最初に声をかけてくれた病院」に好印象を抱きがちです。RPOは、その「先着順の勝負」に勝ちやすくなるための仕組みを外部に構築する、と考えることができます。近年では、医療・看護分野に特化したRPOサービスも増えており、例えばStockSun株式会社が紹介するような様々な企業が、料金体系や導入事例を公開しているため、自院の規模や課題に合わせて比較検討することが可能です。
- クーラ活用ポイント:RPOサービスとクーラを組み合わせて活用することも非常に有効です。RPOパートナーにスカウト活動を依頼し、興味を示した候補者に対して、「まずは面接ではなく、クーラを使った半日の短期勤務からいかがですか?」と提案する流れを定型化します。これにより、院内スタッフの面接稼働を最小限に抑えながら、実際の現場での働きぶりを評価する機会を最大化し、入職後の定着率向上につなげるという、効率的かつ効果的な採用モデルを構築できます。
解決アプローチ:院内役割分担の“正解パターン”と、代行の使い分け
ここからは、多忙な院内でも「止まらない採用」を実現するための、業務の分解と役割分担の標準的なモデルを提示します。もちろん、病院の規模や診療科の特性によって最適な形は異なりますので、自院の状況に合わせて調整しながらご活用ください。
代行の“3レイヤー”:どこまで外に出すか
採用業務を外部に委託する、いわゆる「アウトソーシング」を検討する際には、どの業務を院内に残し、どの業務を外に出すのか、その境界線を明確にすることが成功の鍵です。ここでは、業務の性質に応じて3つのレイヤー(階層)に分けて整理します。
コスト感と優先度:最小コストで“止めない仕組み”を先に
採用活動の改善を考える際、多くの方が広告費の増額や新たなシステムの導入といった「コスト」を心配されます。しかし、最も優先すべきは、大きな投資をせずとも始められる「仕組み化」です。
まずは“時間”を買う:一次返信と前日接触の仕組み化
改善効果が出やすく、かつコストをかけずに始められる施策は、以下の順番で考えるのがセオリーです。
- 一次返信のSLA(4時間以内)を設定し、事務部門主導で実行する。
- 前日接触の標準化(多重連絡と代替スロット表の準備)を徹底する。
- 従来の面接フローを、お試し勤務フローへ置き換えることを検討する。
なぜこの順番なのでしょうか。それは、多額の広告費を投じて応募者を集めても、応募後の対応プロセス(歩留まり)に問題があれば、ザルのように候補者がこぼれ落ちていってしまうからです。求人広告の単価が上昇している市場環境では、まず上流工程の歩留まりを改善し、貴重な応募を一つでも多く次のステップにつなげることの方が、費用対効果は圧倒的に高くなります。初動の速さこそが、現代の採用市場における最大の武器なのです。
RPO活用の勘所:上流の“速さ”を外部で担保する
院内のリソースだけではどうしても初動の速さを担保できない、という場合に、RPOの活用が有効な選択肢となります。RPOサービスを比較検討する際のポイントは以下の通りです。
- 医療業界、特に看護師採用に特化した実績が豊富か。
- どこまでの業務範囲をカバーしてくれるか(求人原稿作成、媒体運用、スカウト、日程調整など)。
- 料金体系は自院の予算に合っているか(月額固定型、成果報酬型、あるいはその組み合わせか)。
幸い、近年は看護師採用に特化したRPOの導入事例や料金に関する情報もオンラインで得やすくなっています。自院のどの業務に最も時間がかかっているのか(内製できる余力はどこにあるのか)を分析し、前述のA/B/Cレイヤーを参考に、外部に委託する業務の境界線を明確にすることが、RPOをうまく活用するコツです。
すぐ使える“標準オペ”一式(そのまま流用可)
以下に、明日からでもすぐに使える返信テンプレートや評価票の雛形をご用意しました。院内マニュアルとして、ぜひご活用ください。
一次返信テンプレート(事務用・お試し前提)
件名:ご応募ありがとうございます/まずは半日“お試し勤務”のご案内(医療法人〇〇会 △△病院)
本文:〇〇様
このたびは、当院の看護師募集にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。医療法人〇〇会 △△病院、採用担当の〇〇と申します。
当院では、ご応募いただいた方々に、まず半日または1日のお試し勤務(給与をお支払いする短期アルバイト形式です)にご参加いただき、実際の職場の雰囲気や業務内容を体験していただく機会を設けております。
つきましては、〇〇様のご都合のよい日程の候補を、いくつかお伺いできますでしょうか。大変恐縮ですが、以下の例を参考に、第3希望までご提示いただけますと幸いです。
(例)・第1希望:〇月〇日(月) 午前(9:00〜13:00)・第2希望:〇月〇日(水) 午後(13:00〜17:00)・第3希望:〇月△日(金) 終日(9:00〜17:00)
ご返信いただきましたら、折り返し担当者より、当日の詳しい流れや持ち物などについてご案内させていただきます。
その他、ご不明な点がございましたら、本メールにそのままご返信ください。いただきました日程候補につきまして、本日時点での仮押さえも可能でございますので、お気軽にお申し付けください。
〇〇様からのご連絡を、心よりお待ちしております。
※クーラ(Cura)のメッセージ機能をご利用の場合は、本テンプレートの内容をメッセージに貼り付けてご活用いただけます。
前日接触スクリプト(事務スタッフから候補者へ)
「もしもし、医療法人〇〇会 △△病院の〇〇と申します。〇〇様のお電話でよろしいでしょうか。明日のお試し勤務の件で、最終確認のためご連絡いたしました。今、1分ほどよろしいでしょうか。」
「ありがとうございます。明日は、午前〇時から〇時までのご勤務で、配属予定の部署は〇〇病棟です。集合場所は、本館〇階の〇〇番受付までお越しください。」
「当日は、制服と内履き、名札(お持ちでなければこちらで貸与します)、筆記用具をご準備いただけますでしょうか。」
「もし、電車遅延などで時間に遅れそうな場合は、このお電話番号(XXX-XXXX-XXXX)にご連絡いただくか、ショートメッセージをお送りいただけますと幸いです。」
「万が一、ご都合が悪くなられた場合でも、代替の候補日もいくつかご用意しておりますので、本日中でしたら日程の再調整も可能です。ご無理なさらず、何かあればいつでもご連絡ください。」
「それでは、明日お会いできることを楽しみにしております。お気をつけてお越しください。失礼いたします。」
お試し評価票(3項目・所要時間3分)
候補者氏名:____________実施日:202X年 〇月 〇日評価者:____________
以下の3つの観点について、該当する評価にチェック(✓)を入れてください。
- 安全への意識・行動(手技の丁寧さ、指差し確認、報告・連絡・相談の姿勢など)[ ] 〇:安心して任せられる[ ] △:概ね問題ないが、一部確認が必要[ ] ×:安全上の懸念が見られた(具体的所見:__________________________)
- 協働性・コミュニケーション(他スタッフへの声かけ、患者様や同僚への配慮、職場への適応姿勢など)[ ] 〇:円滑な関係を築けそう[ ] △:特に問題ない[ ] ×:コミュニケーションに課題が見られた(具体的所見:__________________________)
- 学習意欲・吸収力(未知の手順に対する質問の仕方、メモを取る姿勢、一度教わったことの再現度など)[ ] 〇:意欲が高く、成長が期待できる[ ] △:標準的[ ] ×:主体的な学習姿勢に課題が見られた(具体的所見:__________________________)
■ 総評(いずれかにチェック)[ ] ぜひ継続して勤務してほしい[ ] もう一度、別の日にお試し勤務で様子を見たい[ ] 今回は見送りとする
■ 総合的なコメント(30〜60字程度で理由を記載)______________________________________________________________________
よくある懸念と、運用での解き方
新しい仕組みを導入する際には、必ずと言っていいほど疑問や懸念の声が上がります。ここでは、想定される代表的な懸念と、それらに対する考え方や解決策をQ&A形式でまとめました。
まとめ:採用は“重要かつ緊急”な業務へ—忙しさの中で前に進める設計を
この記事でご提案してきたことを、改めて5つのポイントに集約します。多忙な現場であっても、採用活動を着実に前進させるための設計思想です。
- 役割分担の明確化:応募の一次対応は事務、臨床に関する判断は看護管理職、現場での評価はプリセプター、というように、それぞれのフェーズで誰が責任を持つのかを明確に定めます。
- 時間設計の具体化:応募があったら「4時間以内」に返信するSLA、キャンセルを防ぐための前日連絡の多重化、評価から「翌朝15分」で判定を下すスピード感、といったように、具体的な時間を目標に設定します。
- 代行の賢い使い分け:採用業務をA(広告・原稿作成)、B(運用事務)、C(評価・意思決定)のレイヤーに分解し、自院のリソースに合わせて、どこまでを外部に委託するかの境界線を引きます。
- 「お試し勤務」の前提化:従来の面接を原則としてお試し勤務に置き換えることで、現場の拘束時間を削減しつつ、実際の働きぶりを基にした評価を行うことで、入職後のミスマッチを低減させます。
- 「速さ」こそが武器であることの認識:看護師の有効求人倍率が高止まりし、需給ギャップが続く市場環境では、応募者への初動の速さが採用の成否を分ける、という構造的な背景を直視し、組織全体でスピードを重視する文化を醸成します。
現場が忙しいという現実は、すぐには変わりません。だからこそ、採用のやり方そのものを変える必要があります。業務を「分解」し、定型的な作業は院内の他部署や外部サービスに「逃がし」、とにかく「速く回す」。この発想の転換が、状況を好転させる第一歩です。
今日からでも始められることは、事務部門と協力して「一次返信のSLA」を宣言すること、そして「前日接触の標準化」のルールを作ることです。そして、その先にある「面接の置換」という大きな一歩を踏み出す際には、クーラがその「型」作りを一緒にサポートできます。必要であれば、今回の記事でご紹介したテンプレート群を、そのまま院内のマニュアルとして活用することから始めてみてください。
まずは“半日”から始める、新しい採用の形へ
- 面接ゼロで短期勤務へクーラは、給与ありの「お試し勤務(短期アルバイト)」を前提とした採用プラットフォームです。まずは半日、あるいは1日から、候補者に実際の現場で働いてもらい、お互いの相性を見極めることができます。これにより、面接や見学対応にかかっていた現場スタッフの貴重な時間を大幅に削減します。→詳しくはこちら
- 事務主導で回せる運用体制を応募者への一次対応、日程調整、前日のリマインドなど、これまで看護部長や師長が時間を取られていた「事務で代行可能な領域」を、クーラのプラットフォームに合わせて標準化できます。この記事で紹介した返信テンプレートや代替スロット表をそのまま流用し、スムーズな運用体制を構築してください。→クーラで始める
- 急な欠員にも即応できる仕組み急な欠員や繁忙期の波に合わせて、「まず数回だけ」働いてもらうことで、現場の負担を迅速に軽減できます。継続して雇用するかどうかは、実際の勤務実績を見てから慎重に判断できるため、採用後のミスマッチによるコストやリスクを最小限に抑えられます。→ご相談はこちらから
- 既存のRPO・代理店とも好相性すでにご契約中の広告代理店やRPOサービスとも、スムーズに連携が可能です。スカウト活動のゴールを「面接」ではなく「クーラでの半日お試し」に設定することで、応募のハードルを下げ、より効率的な採用フローを一体的に運用できます。多忙な院内でも“止まらない採用”の仕組みを、クーラと共に作り上げましょう。→お問い合わせ
参考にした公開情報(抜粋)
- 日本看護協会「2023年 病院看護実態調査 報告書」:看護職員の離職率、業務効率化、タスク・シェア/タスク・シフトに関する実態データとして参照。
- 日本看護協会 2023年度「ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析」報告書:既卒看護職の離職率などのデータとして参照。
- 厚生労働省「一般職業紹介状況」および「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会」関連資料:看護職員の有効求人倍率、将来的な需給見通しに関する構造的背景として参照。







.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.avif)





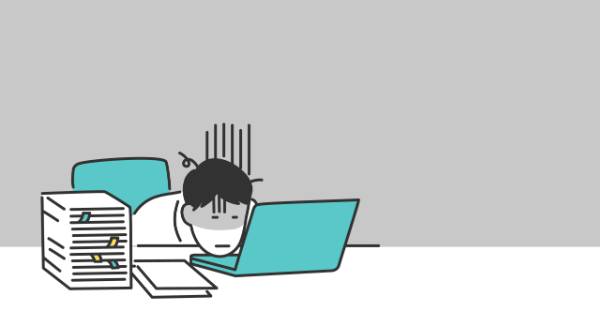
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
