はじめに:その求人票、10年前から更新されていますか?
「給与も休みも、地域の平均以上のはず。なのに、なぜか応募が来ない…」
「面接で『どんな研修制度がありますか?』と聞かれ、しどろもどろになってしまった…」
「研修は大事。でも、ただでさえ人手が足りないのに、勤務扱いにしたら現場が回らない…」
多くのクリニックの院長や事務長が、頭を抱える採用の悩みです。
しかし、少し視点を変えてみましょう。今の求職者、特に意欲の高い若手や、ブランクからの復帰を目指す優秀な人材は、何を基準に職場を選んでいるのでしょうか。
給与や待遇はもちろん重要です。しかし、それと同じくらい、あるいはそれ以上に「この職場で、自分は成長できるのか?」という点を見ています。学び続けなければ価値が陳腐化してしまう医療の世界で、これは当然の視点と言えるでしょう。
この記事では、多くの医療機関が見過ごしている、しかし非常に強力な採用戦略である『教育1日有給化』について、その絶大な費用対効果と、どんなに小さなクリニックでも無理なく導入できる具体的な方法を徹底解説します。
「人が採れない」と嘆く前に、ぜひご一読ください。
1. 「教育1日有給化」とは? –– 導入率わずか8%の差別化戦略
そもそも『教育1日有給化』とは何でしょうか。これは、法定の年次有給休暇とは別に、年に1日、教育・研修目的で休むことを認める有給の休暇制度です。
そのポイントは3つあります。
- 【法定有給とは別枠】
- 職員は、自身のプライベートなリフレッシュのための有給休暇を温存したまま、自己研鑽に時間を使えます。「勉強のために貴重な有給を消化したくない」という心理的なハードルを取り除きます。
- 【給与が支払われる「勤務扱い」】
- 休暇を取得した日は通常通り給与が支払われます。これにより、クリニックが「学びを正式な業務の一環」と捉えているという、強いメッセージを発信できます。
- 【対象は職員が希望する研修(承認制)】
- クリニックが一方的に指示する研修だけでなく、職員が自ら「参加したい」と望む学会や講習会を対象にすることで、主体的な学びを促進します。(もちろん、業務との関連性を鑑みた承認制が基本です)
厚生労働省の調査によれば、このような教育訓練休暇制度を導入している企業は、「全体のわずか8.2%」です。医療業界に絞れば、さらに低い数値が予想されます。
つまり、この制度を導入するだけで、近隣の競合クリニックをリードできる、採用市場における優れた戦略となり得るのです。
助成金活用で、初期コストを抑える
「でも、コストがかかるでしょう?」ご安心ください。
この制度導入は、厚生労働省の人材開発支援助成金「教育訓練休暇等付与コース」の対象です。所定の要件(例:3年間で5日以上の付与計画を立てる等)を満たせば、制度導入だけで「30万円(生産性要件を満たせば36万円)」が支給されます。
まずは「年1日」からスタートし、助成金を活用しながら計画的に運用していくことで、持ち出しなく始めることが可能です。
2. なぜ、これほどまでに採用と定着に効くのか?
給与を月5,000円上げるよりも、「教育有給」を年1日増やす方が、優秀な人材の心に響くことがあります。その背景にある、現場のリアルな声を見ていきましょう。
一つ目は、「学びたい、でも…」という職員の不満を解消することです。
「スキルアップしたいけど、休日に自腹で研修に行くのは正直しんどい」「時間外の勉強会が、事実上の強制参加なのに手当が出ないのは納得できない」。こうした声は、職員のエンゲージメントを静かに蝕んでいきます。教育有給化は、こうした不満を解消し、「勉強熱心な職員こそが報われる」という公正な風土を醸成します。
二つ目は、「成長実感」という最強のモチベーションを生むことです。
ある調査では、若手職員が自己研鑽をしない理由として「時間がないから」に次いで「評価されないから」が挙げられました。教育有給制度を導入し、さらに研修参加や資格取得を人事評価と連動させることで、「学べば評価される」という明確なキャリアパスを示せます。これは、日々の業務に追われがちな職員にとって、強力な動機付けとなります。
三つ目は、若手・ブランク復帰層に響く「安心感」というメッセージです。
新卒や第二新卒、そして出産・育児からの復帰を目指す層は、技術や知識に対する不安を抱えています。「このクリニックは、学び直しをしっかりサポートしてくれる」「ブランクを埋めるための勉強を応援してくれる」というメッセージは、他のどんな福利厚生よりも魅力的に映ります。求人票に「研修は勤務扱いです」と一言あるだけで、彼らが感じる安心感は絶大なのです。
実際に、看護師の離職理由を調査したデータでは、「給与への不満」や「人間関係」と並んで、「教育・研修体制の不備」が常に上位にランクインします。給与や休日数をすぐに増やすのが難しい小規模院こそ、この「教育」というカードを切ることが、持続可能な組織作りの鍵となります。
3. 先駆者たちの実例に学ぶ「伝え方」のヒント
すでに「研修=勤務扱い」を明文化し、採用力強化に成功している医療機関は規模の大小を問わず存在します。彼らのWebサイトや求人票から、「どう見せれば求職者に響くのか」そのヒントを学びましょう。
- 桂クリニック(京都府)
- 採用サイトに「研修費用は全額補助、研修日は勤務扱い」と明確に記載。学びたい人を全力でサポートする姿勢を打ち出し、安心感と信頼感を醸成しています。
- 稲毛病院(千葉県)
- 「外部研修の費用補助・交通費全額支給・勤務扱い」をアピール。特に、ブランクのある看護師向けの復職支援プログラムが充実しており、「学びながら働ける」という具体的なイメージを求職者に与えています。
- 牧田総合病院(東京都)
- 認定看護師の取得支援や学会参加を、費用負担はもちろん「勤務扱い」とすることで、職員の専門的なキャリアアップを組織として後押しするメッセージを強く発信しています。
- 小児科クリニックの求人例(大阪府)
- 「月1回の勉強会はもちろん勤務扱いです」「資格取得にかかる費用も、積極的にバックアップします!」といった親しみやすい言葉で記載。専門性を高めたいと考えるスタッフにとって、非常に魅力的なオファーです。
これらの事例に共通するのは、「“勤務扱い”という事実を、自信をもって言い切っている」ことです。この一言が、求職者の「このクリニックは、職員の成長に本気で投資してくれる」という確信に繋がるのです。
4. 気になる費用対効果は?【シミュレーションで一目瞭然】
「理想はわかるが、現実的にペイするのか?」という最も重要な疑問にお答えします。具体的なモデルケースで試算してみましょう。
【想定条件】
- クリニックの常勤職員数:12名
- 制度の利用率:70%(年間約8名が利用すると想定)
- 職員の平均時給:1,800円
- 1日の労働時間:8時間
- 法定福利費(社会保険料等の事業者負担分):給与の約15%
【年間コストの計算】
1人あたりの1日分の人件費は、 1,800円/時×8時間×(1+0.15)=16,560円 となります。
年間の総コストは、$16,560円/人 \times 12名 \times 70% = $ 約13.9万円です。
年間わずか「約13.9万円」の投資です。ここに、前述の「助成金(30万円)」を活用すれば、初年度はむしろ「16.1万円のプラス」でスタートできる計算になります。
【投資対効果(ROI)の試算】
この年間約14万円の投資が、どれだけの利益を生む可能性があるでしょうか。
- 効果1:採用コストの削減
- もし、この制度が魅力となって応募が増え、通常60万円かかる人材紹介会社を使わずに「1名採用」できた場合、それは「60万円のコスト削減」に繋がります。
- 効果2:離職コストの抑制
- もし、成長実感の高まりによって、本来なら離職していたかもしれない職員が「1人でも定着」してくれたらどうでしょう。1人の離職に伴う損失(採用費+教育費+業務停滞による損失)は、年収の50%~150%とも言われます。年収300万円の職員なら「150万円」の損失回避に繋がります。仮に「0.5人分の離職を防げた」と控えめに見積もっても「75万円」の効果です。
「年間13.9万円の投資」が、「100万円以上のリターン」を生む可能性を秘めているのです。
この数字は、まさに「費用対効果が高い」と言えるのではないでしょうか。
5. 小規模院でも現場を止めない!賢い実装5つのパターン
「制度は魅力的でも、うちのような小さなクリニックでは、1人休んだら現場が回らない…」
その懸念を解消する、賢い運用方法を5つご紹介します。複数を組み合わせることで、無理なく制度を定着させることが可能です。
- 計画的な「交代制」での取得
- 四半期ごとに取得枠を設け、部署ごとに1名ずつなど、計画的に取得してもらうルールにします。年間スケジュールに予め組み込んでしまえば、シフト調整も容易です。
- 休診日や時短診療日の有効活用
- 多くのクリニックが休診とする木曜や土曜の午後を「教育有給推奨DAY」に設定します。他の職員も休みなので、気兼ねなく研修に参加できます。
- 対象研修の「ホワイトリスト化」
- 事前に「学会」「認定資格関連」「院が指定するWebセミナー」など、勤務扱いとなる研修のリストを作成し、周知します。これにより、申請・承認のフローがスムーズになり、公平性も担保されます。
- 「代替要員プール」の確保
- 普段から付き合いのある非常勤スタッフや、短時間勤務のパートスタッフに協力を依頼し、教育有給取得者が出た日だけスポットで入ってもらう体制を整えておきます。
- 人事評価制度との接続
- 研修参加レポートの提出を義務付け、その内容を評価面談でフィードバック。優れた学びを実践した職員を表彰したり、昇給やプリセプター(新人指導係)への任用条件に組み込んだりすることで、制度利用を形骸化させません。
6. まずはここから!就業規則の規程例と求人訴求パターン
制度導入の第一歩は、就業規則への明記です。以下は、そのまま使える規程例です。
就業規則 規程例(抜粋)
(教育訓練有給休暇)
第○条
1. 従業員は、自己の職業能力の維持向上を目的として、年1日の教育訓練休暇を有給で取得することができる。
2. 本休暇は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは別に付与するものとする。
3. 休暇の対象となるのは、当院が業務に関連があると認めた講習、セミナー、学会、資格試験等とし、従業員は所定の様式により事前に院長の承認を得なければならない。
4. 従業員は、休暇取得後、速やかにその内容について報告書を提出するものとする。
求人票での訴求パターン
【本文例】
当院では、スタッフ一人ひとりの「学びたい」という意欲を何よりも大切にしています。そのため、法定の有給休暇とは別に、年1日の「教育訓練有給休暇」を制度化しました。学会への参加や資格取得のための研修は、院の承認のもとで「勤務扱い」となり、費用も全額または一部を補助します。時間外に手当なく研修を強制するようなことは一切ありません。あなたのスキルアップが、患者様への貢献、そしてクリニックの未来に繋がると信じています。
7. まとめ:小さな一歩が、5年後のクリニックを創る
この記事でお伝えしてきたことを、改めて整理します。
- 「教育1日有給化」は、導入率が低く、極めて強力な採用の差別化戦略となる。
- 助成金を活用すれば、初期コストを抑えて、むしろプラスで始めることも可能。
- 年間十数万円の投資が、採用・離職コストの削減を通じて、100万円以上のリターンを生む可能性がある。
- 交代制や休診日の活用など、工夫次第で小規模院でも全く問題なく運用できる。
人手不足が叫ばれて久しい医療業界において、「人を大切にし、その成長に投資する」という姿勢を明確に打ち出すクリニックは、必ず選ばれる存在になります。
「人が集まらない」と嘆く日々は、もう終わりにしませんか。
まずは自院でこの制度を導入した場合の費用と効果を検討することから始めてみてください。その小さな一歩が、未来のクリニックを支える優秀な人材を引き寄せる、最も確実な一歩となるはずです。






.avif)
.avif)







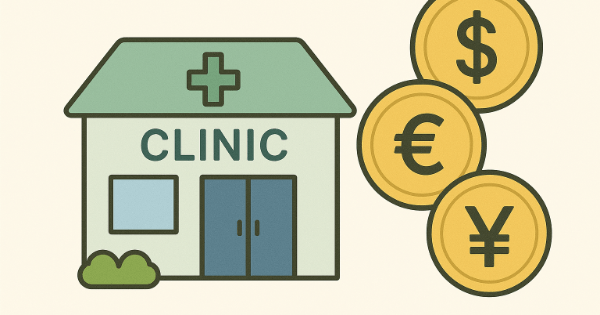
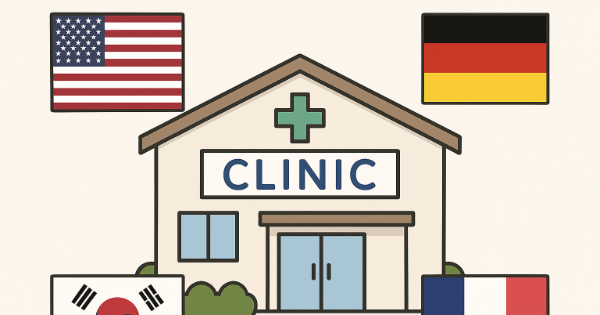
![看護師採用で“最低限ここだけ”の個人情報・マイナンバー取扱いガイド[保存期間・収集タイミング・委託時の注意点まで]](https://cdn.prod.website-files.com/640d966ca29de959e9f69b68/68d3f0cd471eb4dccfe97c23_ChatGPT%20Image%202025%E5%B9%B49%E6%9C%8824%E6%97%A5%2022_22_13-min.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
