試用期間の“3つの誤解”をいま整える
看護師を採用する際、「まずは3か月間の試用期間で様子を見る」といった運用は、多くの医療機関でごく自然に行われています。この期間は、新しい職員が組織の文化や業務に馴染めるかを見極め、また職員自身もここで働き続けられるかを判断するための大切な時間です。しかし、この試用期間の運用において、現場ではいくつかの誤解が生じやすい側面があるようです。特に、以下の3つの点は、認識の違いから思わぬトラブルにつながる可能性が指摘されています。
これらの誤解は、小さな認識のズレが、のちに職員との信頼関係を損ねたり、法的な紛争に発展したりする火種となり得ます。そこでこの記事では、医療機関で実際に導入しやすい試用期間の設計(期間設定、評価方法、具体的な文面)と、最低限押さえておくべき法的な注意点について、公開されている就業規則や判例、行政資料などを参考にしながら、具体的かつ丁寧に整理していきます。
なお、採用から定着までの一連の流れをより円滑にし、「短期間のお試し勤務から、双方納得の上で本採用へ」という仕組みそのものを強化したい場合には、看護師の短期就労から常勤雇用への移行を専門的に支援するサービスもあります。例えば、クーラのようなプラットフォームは、こうした仕組みづくりをサポートする選択肢の一つとして考えられます。ご興味があれば、こちらのページもご覧ください: https://business.cu-ra.net/
背景・課題:なぜ試用期間の設計が“揉める”のか
試用期間の運用がうまくいかず、職員との間で摩擦が生じてしまう背景には、いくつかの共通した課題が存在することが多いようです。これらは単独で存在するのではなく、互いに影響し合って問題を複雑にしています。
- 評価の基準が曖昧であること多くの医療機関で、看護師の評価項目として「コミュニケーション能力」「チーム医療における連携」「安全への配慮」などが挙げられます。これらの能力が重要であることは論を俟ちませんが、問題はその定義が評価者(例:看護師長、主任)によって異なり、個人の主観に委ねられがちな点です。例えば、ある師長は「積極的に発言すること」をコミュニケーション能力が高いと評価するかもしれませんが、別の師長は「他者の意見を傾聴し、的確に情報を引き出すこと」を重視するかもしれません。このように基準が曖昧だと、評価される側は何を改善すれば良いのか分からず、不公平感を抱く原因となります。
- 指導や評価のプロセスが記録されていないこと試用期間中の職員が、期待される業務レベルに達していない場合、通常は注意や指導が行われます。しかし、その指導がいつ、誰から、どのような内容で行われ、それに対して本人がどう反応したか、といったプロセスが客観的な記録として残っていないケースが散見されます。記録がなければ、試用期間満了時に本採用を見送る、あるいは残念ながら途中で解雇するという判断を下した際に、その判断の正当性を示すことが難しくなります。「何も指導されていないのに、突然『能力不足だ』と言われた」と職員側が主張した場合、医療機関側が適切な教育・指導の機会を提供したことを証明する手立てがなくなってしまいます。
- 就業規則や雇用契約書の記載が不十分であること試用期間に関する規定が、「採用後3か月間を試用期間とする」といった一行程度の簡素な記載に留まっている就業規則も少なくありません。これでは、試用期間を延長する可能性はあるのか、延長する場合の手続きはどうなるのか、どのような場合に本採用が見送られるのか、といった具体的なルールが不明確です。ルールが明記されていないと、いざという時に場当たり的な対応にならざるを得ず、職員に不信感を与えたり、手続きの妥当性が問われたりするリスクが高まります。
- 社会保険や各種手当の取り扱いに混乱があること前述の通り、試用期間中であっても社会保険の加入要件を満たせば加入は義務です。しかし、この認識が人事担当者や管理職の間で徹底されていない場合があります。また、夜勤手当や資格手当、危険手当といった各種手当について、「試用期間中は支給しない」「本採用後から支給する」といった運用をする場合、その根拠となる規定が明確に示されていないと、賃金に関するトラブルに発展することがあります。特に、試用期間中も同じ業務に従事しているのであれば、手当の不支給が合理的な待遇差として認められるかどうかは、慎重な検討が必要です。
これらの課題は、結果として採用した看護師の早期離職を招くだけでなく、指導する側の管理職の心理的な負担を増大させ、職場の雰囲気を悪化させることにもつながりかねません。次章からは、こうした問題を未然に防ぎ、誰もが納得感を持って働ける環境を整えるための具体的な方法を、公開されている実例を参考にしながら見ていきます。
実例紹介:医療機関の就業規則・評価運用の公開例
他院がどのように試用期間を規定し、運用しているのかを知ることは、自院の制度を見直す上で非常に参考になります。ここでは、インターネット上で公開されている医療機関の就業規則や、評価に関する考え方の例をいくつか紹介します。
病院・クリニックの「試用条項」公開例
実際に公開されている就業規則を見ると、各医療機関がどのような点に留意して条文を作成しているかが見えてきます。
- 奈良県立病院機構の例
- 地方独立行政法人奈良県立病院機構の就業規則では、試用期間について次のように定められています。「新たに採用した職員については、採用の日から起算して6箇月間の試用期間を設ける。ただし、機構長が特に認めた場合は、この期間を短縮し、又は設けないことができる。」「職員が前項の試用期間中に次の各号のいずれかに該当する場合その他職員として不適格であると認めた場合は、解雇することがある。」この規定の特徴は、6か月という比較的長い期間を設定している点と、期間の短縮や免除にも言及している点です。また、「職員として不適格」と判断する場合の例示はされていませんが、その判断をもって解雇することがある、という可能性を明確に示しています。
- 静岡市立静岡病院の例
- 静岡市立静岡病院の企業職員就業規程では、より具体的に記載されています。「新たに採用した者については、採用した日から起算して6月間を試用期間とする。」「試用期間中の者が次の各号の一に該当する場合で、企業職員として不適格であると認めたときは、解雇することができる。」として、勤務状況が著しく不良であること、心身の故障のため業務の遂行に支障があることなどを挙げています。さらに、「試用期間中に企業職員として勤務成績が良好であると認めたときは、その者を正規に採用する。」と、本採用の要件についても触れています。ここでは、本採用に至らない場合の条件を具体的に列挙することで、判断基準の透明性を高めようとする意図がうかがえます。
- 民間クリニック(フラワー皮フ科クリニック)の例
- 民間のクリニックの就業規則でも、同様の規定が見られます。例えば、ある皮膚科クリニックの公開例では、次のような条項があります。「従業員として採用した者には、採用した日から6ヶ月間の試用期間を設ける。」「試用期間中または試用期間満了時において、従業員として不適格と認めた者は解雇する。この場合、採用日から14日以内に解雇するときは予告も予告手当の支払いもしない。」この例では、期間を6か月と設定し、試用期間中または満了時に不適格と判断した場合の解雇の可能性を明記しています。また、14日以内の解雇予告除外についても言及しており、実務的な運用を意識した規定となっています。
これらの事例から分かるポイントは、単に期間を定めるだけでなく、「どのような場合に本採用に至らないか(不適格と判断されるか)」や、「期間の延長、解雇の手続き」といった、起こりうる事態を想定して、あらかじめ規程で具体的に定めておくことが、運用のブレをなくし、トラブルを予防する上で重要である、ということです。
「看護師評価シート/目標管理」公開例
試用期間を有効に機能させるためには、評価の仕組みが不可欠です。評価というと堅苦しく聞こえるかもしれませんが、これは「できていない点」を指摘するためだけのものではなく、むしろ「できている点」を認め、「これから何を身につけていけば良いか」を共有するためのコミュニケーションツールと捉えることができます。
- 人事評価・目標管理ツールの考え方
- 株式会社カオナビなどが提供する人事評価システムの解説記事では、評価項目を具体的な「行動」に落とし込むことの重要性が示されています。例えば、「協調性」という抽象的な項目ではなく、「チームの目標達成のために、自身の業務範囲を超えて他者を支援した」「カンファレンスにおいて、他者の意見を踏まえた上で建設的な提案を行った」といった、客観的に観察・評価できる行動レベルまで具体化することが推奨されています。このような行動評価は、日々の業務の中でチェックしやすく、指導やフィードバックも具体的になります。
- クリニカルラダーに準拠した目標設定の例
- 看護師向け情報サイト「看護roo!」などでは、看護師の能力開発では一般的なクリニカルラダー(臨床実践能力の段階別評価指標)に沿った個人目標の書き方や文例が紹介されています。例えば、新人(レベルⅠ)であれば、「指導者のもとで基本的な看護技術を安全に実施できる」「報告・連絡・相談の重要性を理解し、適切なタイミングで実践できる」といった目標が考えられます。中途採用者であっても、その人の経験やスキルに応じて、「〇〇(特定の看護技術)を独力で実施し、後輩にも指導できる」「病棟の課題を発見し、改善策を提案できる」といった形で、ラダーを参考に目標を設定することが可能です。
ここでのポイントは、評価項目を「行動が見える言葉」で設計することです。誰が評価しても同じような判断ができる客観的な基準を設けることで、評価の公平性が保たれ、試用期間中の指導内容と評価結果が連動しやすくなります。
法的フレームの確認(頻出論点)
試用期間を運用する上で、関連する法律の基本的な考え方を理解しておくことは、リスク管理の観点から非常に重要です。ここでは、特に問題となりやすい点に絞って確認します。
- 解雇予告の原則と例外(労働基準法第20条・第21条)
- 労働基準法第20条では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定められています。しかし、同法第21条には、この原則が適用されない例外がいくつか挙げられており、その一つが「試の使用期間中の者(14日以内に解雇する場合)」です。この条文が、「14日以内なら理由なく自由に解雇できる」という誤解の根源となっていますが、厚生労働省の資料などでも注意喚起されている通り、これはあくまで「予告手続きの免除」を定めたものに過ぎません。解雇自体が有効かどうかは、別の法律(労働契約法)の観点から判断されます。
- 解雇の合理性・相当性(労働契約法第16条)
- 労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。これは「解雇権濫用法理」と呼ばれる考え方で、判例によって確立されてきたルールを法律として明文化したものです。この規定は、試用期間中の解雇にも適用されると考えられています。つまり、試用期間中であっても、解雇するには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要なのです。ただし、判例では、試用期間が職員の適格性を見極めるための期間であるという性質から、本採用後の解雇に比べて、やや広い範囲での解雇の自由が認められる傾向にあります。それでも、使用者の一方的な都合や、些細なミスを理由とした安易な解雇は無効となるリスクがあります。
- 雇止めに関する判例の考え方
- 試用期間満了時に本採用をしないこと(本採用拒否)は、法律上は「解雇」とは少し異なる「雇止め」に近い性質を持つと解釈されることがあります。しかし、過去の裁判例(例えば、最高裁判所の判例など)では、有期雇用契約の更新が繰り返され、実質的に無期雇用と変わらない状態になっている場合などの雇止めについて、「解雇権濫用法理を類推適用すべき」という判断が示されています。試用期間の場合も、職員は本採用を期待して入職しているのが通常であるため、本採用の拒否にあたっては、解雇と同様に慎重な手続きと合理的な理由が求められる傾向にあります。安易な本採用拒否は、のちに紛争となった場合に「不当な雇止め」と判断される可能性があるため、注意が必要です。
- 社会保険の加入義務
- 前述の通り、試用期間中であっても、法律上の加入要件を満たす場合には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険への加入が義務付けられています。「試用期間だから」「短期間だから」という理由で加入させないことはできません。例えば、雇用保険の場合、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として加入対象となります。試用期間が3か月であれば、この要件を満たすことがほとんどです。これらの手続きを怠ると、遡って保険料を納付する必要が生じたり、行政からの指導を受けたりする可能性があります。
解決アプローチ:揉めない「試用期間×評価」設計の実装手順
ここからは、これまでの実例や法的留意点を踏まえ、実際に医療機関でトラブルの少ない試用期間制度を構築するための具体的な手順を提案します。規程、契約、運用の3つの層で内容をしっかりと噛み合わせることが、実効性のある制度づくりの鍵となります。
1) 規程(就業規則・諸規程)を先に固める
すべての土台となるのが、就業規則です。運用がブレないように、まずはルールブックである規程を整備することから始めます。
(a) 試用期間の長さと延長要件を明確にする
- 期間:一般的には3か月から6か月程度で設定されることが多いようです。新人看護師のように、基本的な技術習得から始める場合は3か月、専門性の高い部署(手術室、ICU、透析室など)への配属や、管理職候補としての採用など、より多角的な適性評価が必要な場合は6か月、といったように職務内容に応じて設定することが考えられます。
- 延長:期間を延長する可能性があるのであれば、その条件と手続きを明記します。「業務への習熟度が標準的なレベルに達していないと認められ、追加の教育・指導期間が必要な場合」といった合理的な理由を定め、「延長期間は最長3か月までとし、本人に書面で通知の上、同意を得る」のように、上限と手続きを具体的に記載しておくと丁寧です。
(b) 本採用に至らない場合の基準を具体化する本採用を見送る、あるいは途中で解雇する場合の判断基準を、可能な限り「行動」や「技能」に基づいた言葉で規程に落とし込みます。例:
- 正当な理由のない遅刻、早退、欠勤が複数回に及ぶなど、勤務態度が著しく不良であるとき。
- 基本的な看護技術(採血、注射、与薬管理など)について、指導を重ねても習得の見込みがないと判断されるとき。
- 医療安全に関する重要な指示・規則を繰り返し遵守せず、改善が見られないとき。
- 協調性を著しく欠き、他の職員との円滑な業務遂行が困難であるとき。
- 経歴や資格に関して、重大な詐称が判明したとき。
(c) 教育・指導に関する医療機関側の責務を盛り込む規程の中に、「試用期間中は、所属長が定期的に面談を実施し、必要な教育・指導を行う」といった一文を入れることも有効です。これは、単に職員を評価するだけでなく、組織として育成する責任があることを内外に示すことになります。こうした規定は、万が一、本採用見送りの判断に至った際にも、「組織として教育・指導の機会を十分に提供した」という事実を補強する材料となり得ます。
2) 契約(雇用契約書・内定通知)で“実務の歯車”を合わせる
就業規則で定めたルールを、個別の労働契約に反映させます。特に、入職時に書面で交付する雇用契約書や労働条件通知書は、本人との間で認識の齟齬を防ぐための最も重要な書類です。
(a) 雇用契約書・通知書に明記すべき4つのポイント
- 試用期間の具体的な長さ(例:「採用日から令和〇年〇月〇日まで(3か月間)」)と、延長の可能性があること、またその際の条件(例:「業務習熟の状況により、最長3か月まで延長することがある」)。
- 試用期間中の評価方法の概要(例:「期間中に所属長との面談を月1回実施し、評価票を用いて本採用の可否を判断する」)。
- 本採用とならない可能性があること、およびその場合の通知方法(例:「試用期間満了をもって本採用としない場合は、原則として期間満了の15日前までに書面で通知する」)。
- 試用期間中の労働条件(給与、手当、社会保険など)について、本採用後と相違がある場合は、その内容を明確に記載する。
(b) 文面例(雇用契約書・労働条件通知書の一部)以下に、契約書に記載する際の具体的な文面例を挙げます。
第〇条(試用期間)
- あなたの試用期間は、採用日から起算して3か月間(YYYY年MM月DD日まで)とします。
- 試用期間中または期間満了時において、あなたの勤務状況、業務遂行能力、適性などを考慮し、本採用の可否を決定します。
- 業務への習熟状況などにより、会社が必要と認めた場合、あなたの同意を得た上で、最大3か月を限度として試用期間を延長することがあります。
- 試用期間中であっても、健康保険、厚生年金保険、雇用保険は、法令の定める加入要件を満たす場合、採用日をもって加入手続きを行います。
- 採用後14日以内の解雇予告については、労働基準法第21条の定めに従いますが、解雇を行う場合は、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
- 試用期間満了により本採用としない場合は、原則として期間満了日の15日前までに、その理由を付して書面であなたに通知します。
3) 運用(評価・面談・記録)を“見える化”する
規程と契約という「骨格」ができたら、次はそれを動かす「筋肉」である日々の運用を設計します。ここでは、評価と面談、そしてその記録が中心となります。
(a) 30-60-90日設計(医療版)の導入試用期間(例:90日間)をいくつかのフェーズに区切り、それぞれの期間で達成すべき目標や評価のポイントを明確にする方法です。これにより、職員は見通しを持って業務に取り組むことができ、評価者も計画的に関わることができます。
(b) 評価票の項目を具体的な行動で記述する評価の客観性を高めるため、評価票の項目は「誰が見ても同じように判断できる」言葉で作成します。
- (悪い例)コミュニケーション能力が良好である。 → 評価者によって解釈が分かれる。
- (良い例)患者からの質問に対し、傾聴の姿勢を示し、不明点は医師や先輩看護師に確認した上で分かりやすく説明できる。
- (悪い例)安全管理を徹底している。 → 何をすれば徹底したことになるのか不明。
- (良い例)与薬の際は、5R(正しい患者、正しい薬剤、正しい量、正しい用法、正しい時間)を必ず指差し呼称で確認し、実施後に速やかに記録している。
(c) 面談の型と記録の徹底面談は、単なる評価の伝達の場ではなく、育成のための対話の機会です。面談記録には、以下の要素を含めると、後々のトラブル防止にもつながります。
- 観察された具体的な事実(良かった点、改善が必要な点)
- 本人からの意見や自己評価
- 合意した改善策や次の目標
- 次回の面談までの期限
- 面談者と本人の署名欄
これらの記録は、万が一、本採用見送りや解雇という判断に至った場合に、医療機関側が適切な指導・教育の機会を提供し、改善を促してきたことを示す客観的な証拠となります。
トラブルを避ける「途中解雇・本採用見送り」判断プロセス
試用期間中の解雇や本採用見送りは、非常に慎重に進めるべき手続きです。万が一、そのような判断が必要になった場合に、法的なリスクを最小限に抑え、可能な限り円満な解決を目指すためのプロセスを整理します。
過去の裁判例、例えば試用期間に関するリーディングケースとされる「三菱樹脂事件(最高裁昭和48年12月12日判決)」では、試用期間中の解約権行使は、通常の解雇よりは広い裁量が認められるとしつつも、その目的や趣旨に照らして客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される、という枠組みが示されました。この考え方は、現在の労働契約法の規定にも引き継がれています。安易な判断は避け、専門家(社会保険労務士や弁護士)に相談することも含め、慎重な対応が求められます。
よくあるQ&A
ここでは、試用期間に関して現場でよく聞かれる質問について、簡潔にお答えします。
Q1:試用期間は3か月と6か月、どちらが良いのでしょうか?A1:法律で期間の長さに決まりはありませんが、3か月から6か月が一般的です。業務内容や職責によって判断するのが良いでしょう。例えば、新人や第二新卒で、基本的な看護業務の習得から始める場合は3か月でも十分かもしれません。一方、専門性の高い部署への配属や、一定の経験を持つ中途採用者で、より広範な適性(技術、判断力、マネジメント能力など)を見極めたい場合は、6か月という長めの期間を設定することも合理的と考えられます。重要なのは、その期間設定の理由を説明できることです。
Q2:入職後14日以内であれば、本当に説明なしで解雇できるのでしょうか?A2:できません。繰り返しになりますが、14日以内の解雇は「解雇予告の手続きが不要になる」というだけで、解雇の理由が不要になるわけではありません。解雇するには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。例えば、入職直後に重大な経歴詐称が発覚した、正当な理由なく無断欠勤を繰り返した、など極めて悪質なケースに限られると考えるべきです。
Q3:試用期間中の給与を、本採用後よりも低く設定することは問題ありませんか?A3:試用期間中の給与を本採用後より低く設定すること自体は、法律上禁止されていません。ただし、そのためには就業規則や雇用契約書にその旨を明確に記載し、入職前に本人の同意を得ておく必要があります。また、減額の幅があまりに大きい場合や、最低賃金を下回るような設定は認められません。一般的には、本採用後の給与の8割~9割程度に設定する例が見られます。
Q4:評価項目は「結果」だけで評価してはいけませんか?A4:避けるべきとされています。「患者さんからのクレームがゼロだった」といった結果指標だけでは、本人のどのような行動がその結果につながったのかが分からず、適切な指導や育成につながりにくいからです。また、クレームの有無は本人の努力だけではコントロールできない外的要因も影響します。プロセス、つまり「観察可能な行動」を評価の軸に据えることで、客観的で公平な評価が可能になり、本人も何を改善すれば良いのかが分かりやすくなります。
まとめ:規程→契約→運用の“三点締め”で、納得と法適合を両立
看護師の試用期間は、単に「適性がない職員をふるい落とす」ための期間ではありません。新しい仲間が組織の一員として円滑にスタートを切り、持てる力を最大限に発揮できるよう、組織全体でサポートし、見守るための重要な「共育期間」と捉えることができます。
この期間を有効に機能させ、無用なトラブルを避けるためには、これまで見てきたように、以下のポイントを連動させることが大切です。
- 規程の整備:就業規則に、試用期間の長さ、延長の可能性、本採用見送りの基準、14日ルールの正しい理解、社会保険の取り扱いなどを具体的に明記し、制度の土台を固める。
- 契約の明確化:雇用契約書や労働条件通知書で、個別の労働条件として試用期間に関するルールを本人に書面で明示し、双方の認識を合わせる。
- 運用の徹底:30-60-90日のような計画的な評価スケジュールを立て、具体的な「行動基準」に基づいた評価と面談を定期的に実施し、そのすべてを記録に残す。
- 紛争の予防:万が一、解雇や本採用見送りという判断に至る場合は、注意指導の事実記録と改善機会の提供というプロセスを丁寧に行う。
これらの仕組みをゼロから構築するのは大変な作業ですが、他院の公開規程や、様々なメディアで紹介されている目標設定の例などを参考にすることで、自院に合った形に整えていくことができます。
採用直後のミスマッチによる離職は、本人にとっても組織にとっても大きな損失です。試用期間の設計を見直し、短期的なお試し勤務から本採用への導線をよりスムーズにしたいとお考えの場合、看護師の短期就労の設計と運用をサポートする外部サービスの活用も一つの有効な手段です。例えば、クーラのようなサービスは、現場の負担を抑えながら、柔軟な働き方を希望する看護師を受け入れる仕組みづくりを支援しています。ご興味があれば、ぜひ一度情報収集をしてみてください。→ https://business.cu-ra.net/
付録:そのまま使える「面談メモ」ひな形
このひな形は、試用期間中の定期面談で活用することを想定しています。評価票とは別に、対話の内容を記録するためのツールとしてお使いください。面談ごとに作成し、時系列で保管することで、指導と成長のプロセスが可視化されます。
参考・根拠(主要)
- 労働基準法 第20条、第21条(解雇の予告、解雇予告の除外)
- 労働契約法 第16条(解雇)
- 厚生労働省 各種資料(労働契約、就業規則に関する解説)
- 裁判例:三菱樹脂事件(最高裁判所 昭和48年12月12日判決)ほか
- 地方独立行政法人奈良県立病院機構 就業規則
- 静岡市立静岡病院 企業職員就業規程
- 各種医療機関、社会保険労務士法人が公開する就業規則モデル、解説記事






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)





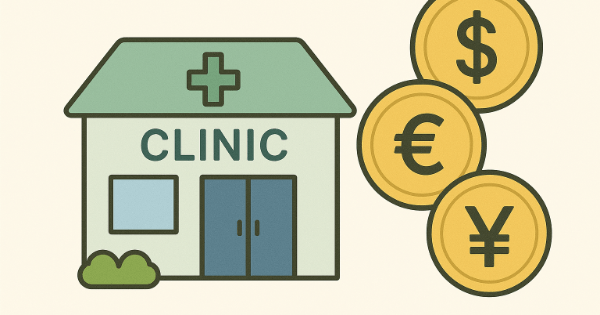
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
