採用できても“続かない”という悩み
「やっとの思いで採用できた看護師が、数ヶ月で辞めてしまった」「これまで問題にならなかったことで、急にトラブルが起きてしまい診療が滞ってしまった」
クリニックを運営される院長や事務長の方々から、このようなお話を聞くことがあります。特に、少人数で運営されているクリニックでは、一人の看護師の離職や働き方への不満が、すぐに現場の雰囲気や診療体制に影響を与えてしまいます。
この記事では、実際に公開されている様々な事例を参考にしながら、クリニックの現場で起こりやすい看護師の雇用トラブルと、その現実的な解決のヒントを整理しました。難しい法律の言葉を並べるのではなく、院長や事務長の方々が「明日から何をすれば良いか」を具体的にイメージできるよう、分かりやすく解説することを心がけています。
もし、日々の業務に加えて「スタッフの採用や管理まで手が回らず、とにかく余裕がない」と感じていらっしゃるのであれば、記事の中でご紹介する外部のサービスを検討してみるのも一つの方法かもしれません。例えば、採用候補者との相性を確かめるための短期お試し勤務や、給与・勤務時間といった条件の事前調整を外部に任せることで、採用後のミスマッチから生じるトラブルを減らす助けになる場合があります。(詳細はこちら:https://business.cu-ra.net/)
背景:なぜクリニックでは雇用トラブルが起こりやすいのでしょうか
クリニックは、大病院とは異なる特徴を持っており、その特徴が時として雇用トラブルの背景となることがあります。
一つには、就業規則や雇用契約書の整備が、大病院に比べて簡素になりがちである点が挙げられます。人事や法務の専門部署がない場合が多く、院長や事務長が診療の傍らで労務管理を担うため、細かなルール作りまで手が回らないケースが見られます。
また、スタッフの人数が少ないため、人間関係が密接になりやすいという特徴もあります。これは良い方向に働けばアットホームな職場になりますが、一方で、一度関係がこじれると小さな摩擦が大きな不満へと発展しやすい側面も持っています。院長の言動がスタッフに与える影響も、より直接的になります。
さらに、業務の範囲が曖昧になりやすい点も指摘されています。例えば、診療開始前の準備や片付け、電話対応(オンコール)、研修への参加などが、明確に労働時間として扱われていない場合、「サービス残業ではないか」という不満や、「あの人はやっていないのに」といった不公平感につながることがあります。
そして、最も大きな要因として、人員に余裕がないことが挙げられます。一人が欠けると業務が回らなくなるため、スタッフが休みを取りたいと申し出ても「忙しいから」と断ってしまったり、有給休暇の取得が制度通りに進まなかったりする状況が生まれやすくなります。
こうした状況が続くと、スタッフの退職につながるだけでなく、労働基準監督署への相談や、場合によっては訴訟といった深刻な事態に発展する可能性も否定できません。
実例紹介:クリニックで実際に起きたトラブル
ここでは、実際に報告されている様々な事例をもとに、クリニックで起こりうる雇用トラブルを具体的に見ていきましょう。それぞれの事例について、どのような点が問題となりうるのか、法律や判例ではどのように考えられているのかを解説します。
1. 更衣・準備時間は労働時間にあたるのか
北海道にある病院の事例で、看護師たちが「業務開始前の情報収集や制服への着替えは、病院からの指示で行っており労働時間にあたる」として、未払いの賃金を求めて訴訟を起こしたケースがありました(医療法人社団緑生会事件)。
この裁判で、裁判所は「労働からの解放が保障されていない時間」は労働時間であるという考え方を示しました。つまり、院長の指示によって、特定の場所で(例えば更衣室で)、決められた業務(着替えや準備)を行うことが義務付けられているのであれば、その時間は労働時間と評価される可能性が高いとされています。
クリニックの現場に当てはめてみると、
- 始業時刻前に、ユニフォームへの着替えが義務付けられている
- 朝礼の前に、その日の患者のカルテを確認するよう指示されている
- 診療で使う器具の準備や滅菌作業を行うことになっている
といった時間は、労働時間と見なされる可能性があります。これらを「自主的な準備」として扱い、賃金を支払わない運用を続けていると、後から未払い賃金を請求されるリスクがあります。
2. オンコール待機の法的な扱い
夜間や休日に、緊急の連絡に備えて自宅などで待機する「オンコール」勤務。この待機時間も労働時間にあたるのか、という問題があります。
ある介護施設では、看護師のオンコール待機が「労働時間」と認められ、施設側が1,000万円を超える未払い賃金の支払いを命じられた事例が報告されています。
裁判所などが判断する際のポイントは、「その時間がどの程度、使用者の指揮命令下に置かれているか」という点です。例えば、
- 呼び出しがあれば、必ずすぐに対応しなければならない。
- 待機中は、遠出や飲酒が禁止されるなど、行動が大きく制限されている。
- 実際に呼び出される頻度が高い。
といった状況であれば、それは単なる「待機」ではなく、使用者の管理下にある「労働時間」と判断されやすくなります。その場合、待機時間そのものに対して、通常の労働時間と同様の賃金を支払う必要が出てくることがあります。単に「オンコール手当」として1回数千円を支払うだけでは、不十分と判断される可能性があるのです。
3. 更新を重ねたパート職員の雇止め
有期雇用のパート看護師について、「また来年度もお願いしますね」といった形で契約更新を何年も続けてきた後、クリニックの都合で突然「次の更新はありません」と告げる、いわゆる「雇止め」もトラブルになりやすい問題です。
労働契約法では、有期契約であっても、何度も更新が繰り返され、スタッフ側が「このまま雇用が継続されるだろう」と期待することに合理的な理由がある場合には、簡単には雇止めができないとされています。これを「雇止め法理」と呼びます。
過去の裁判例では、雇用主が契約更新の際に「業績が悪化したら更新しない可能性がある」といった具体的な説明をせず、形式的に契約書を取り交わしていただけであった場合、労働者側の「継続への期待」が保護されるべき、と判断されたケースがあります。
クリニックでありがちな口頭での更新確認や、明確な基準がないままの契約更新は、いざという時に「話が違う」というトラブルの火種になる可能性があります。
4. ハラスメントと人間関係の悪化
院長や特定のベテラン看護師が、特定のスタッフに対してだけ厳しい態度を取ったり、無視をしたりする。こうした行為が「えこひいき」やパワーハラスメントと受け止められ、問題になることがあります。
近年、職場におけるハラスメント防止対策は、事業主の義務とされています(労働施策総合推進法)。これはクリニックも例外ではありません。「指導のつもりだった」「そんなつもりはなかった」という言い分は、法的には通用しない場合があります。
特にクリニックでは、院長の権限が強く、人間関係も固定化しやすいため、スタッフが違和感を覚えても声を上げにくい環境が生まれがちです。小さな不満や違和感が積み重なり、ある日突然、退職の申し出や外部機関への相談という形で表面化することがあります。
5. 副業による勤務への支障
看護師が、クリニックでの勤務が終わった後、夜間に別の施設でアルバイトをするなど、副業を持つケースも増えています。原則として、労働時間外の過ごし方は個人の自由であり、使用者が副業を全面的に禁止することは難しいとされています。
厚生労働省のガイドラインでも、副業・兼業を促進する方向性が示されています。ただし、副業によって、
- 本業であるクリニックの業務に、明らかに支障が出ている(遅刻が増える、勤務中に居眠りをするなど)。
- クリニックの秘密情報が漏洩するリスクがある。
- クリニックの評判を落とすような行為がある。
といった場合には、就業規則に基づいて副業を制限したり、懲戒処分の対象としたりすることが可能とされています。重要なのは、「副業をしていること」自体を問題にするのではなく、「副業が原因で、本業の業務に具体的な悪影響が出ているか」という点です。
6. 備品費用などの一方的な給与天引き
「クリニックの制服代として、毎月の給与から5,000円を天引きする」「看護師の不注意で医療機器を壊してしまったので、修理代を給与から差し引く」といった対応は、原則として労働基準法違反となる可能性があります。
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められており(賃金全額払いの原則)、使用者が一方的に給与から何かを天引きすることは認められていません。
例外として、労働組合との労働協約がある場合や、労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定(労使協定)を結んだ場合には、社宅の家賃などを天引きすることが可能です。しかし、損害賠償金を一方的に天引きすることは、たとえ労使協定があっても認められない場合が多いです。スタッフに過失があったとしても、その賠償責任の範囲をきちんと話し合い、給与とは別問題として請求・支払いを行うのが本来の手順とされています。
7. 個人情報の誤送信や紛失
患者の氏名や病状といった情報は、極めて慎重に扱うべき個人情報です。しかし、日々の忙しい業務の中で、ヒューマンエラーは起こりえます。
- 別の患者の検査結果を、違う患者に渡してしまった。
- 紹介状を入れたFAXを、違う病院に送ってしまった。
- 患者リストが記載されたUSBメモリを、どこかに置き忘れてしまった。
こうした事例は、残念ながら多くの医療機関で報告されています。個人情報保護法では、個人情報が漏洩した場合、本人への通知や個人情報保護委員会への報告が義務付けられています。小さなクリニックであっても「よくあること」では済まされず、監督官庁からの指導や、場合によっては罰則の対象となる可能性もあります。何よりも、患者からの信頼を失うことが、クリニック経営にとって大きな打撃となります。
8. 退職後のスタッフや患者の“引き抜き”
長年勤務してくれた看護師が独立したり、他のクリニックに転職したりする際に、他のスタッフを辞めるよう誘ったり、担当していた患者に「新しいクリニックに来ないか」と声をかけたりするトラブルも考えられます。
特に、透析クリニックのように患者とスタッフの関係が長期間にわたる場所では、こうした引き抜きが経営に直接的な影響を与えることがあります。
法的には、職業選択の自由があるため、転職や独立そのものを禁止することはできません。しかし、入職時に「在職中や退職後、一定期間は他のスタッフを引き抜かない」といった内容の誓約書を取り交わしている場合、その誓約に基づいて損害賠償を請求できる可能性があります。ただし、その誓約が法的に有効と認められるには、期間や内容が合理的である必要があるとされています。
9. 法律で定められた有給休暇が取得できない
「うちは小さいクリニックで、代わりの人もいないから、有給は取れないよ」こうした説明で、スタッフからの有給休暇の申請を断ってしまうのは、明確な法律違反です。
労働基準法では、労働者には年次有給休暇を取得する権利があると定められています。また、2019年からは、全ての使用者に対して、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、年に5日間は必ず取得させることが義務付けられました。
使用者側には、事業の正常な運営を妨げる場合に、休暇の時期を変更してもらう「時季変更権」が認められていますが、単に「忙しいから」「代わりがいないから」という理由だけで、恒常的に取得を拒否することはできません。「代わりがいない」のは、労働者の責任ではなく、代替要員を確保できていない使用者側の問題と判断されるためです。
解決アプローチ:トラブルを防ぐために、実際にできる工夫
これまで見てきたようなトラブルは、どれもクリニックの運営に大きな影響を与えかねません。しかし、日々の少しの工夫や準備で、リスクを大きく減らすことが可能です。ここでは、具体的な解決アプローチをいくつかご紹介します。
1. 契約書と就業規則をシンプルに整える
トラブルの多くは、ルールの曖昧さから生じます。まずは、雇用契約書と就業規則(常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成と届出の義務があります)の内容を確認し、実態に合っているかを見直すことが第一歩です。厚生労働省のウェブサイトには、モデル就業規則のひな形もありますので、参考にすると良いでしょう。
- 更衣・準備時間:雇用契約書や就業規則に「始業時刻の15分前からを準備時間とし、労働時間に含める」といった一文を加えるだけで、認識のズレを防げます。
- オンコール:「待機1回につき〇〇円の手当を支給する。緊急出動した場合は、移動時間を含め、時間外労働として別途賃金を支払う」のように、手当と出動時の給与を分けて記載すると明確になります。
- 副業:全面的に禁止するのではなく、「副業を行う場合は、所定の様式で届け出ること」という許可制(届出制)にするのが現実的です。その上で、「本業の業務に支障をきたす場合や、当院の信用を損なう場合には、許可を取り消すことがある」と定めておきます。
- 備品の弁償:制服は貸与とし、クリーニング代もクリニックが負担するのが望ましい形です。機器の破損については、故意や重大な過失がある場合を除き、スタッフ個人に全額を負担させるのは難しいと考え、保険の適用などを検討するのが一般的です。
2. 記録を残す文化をつくる
「言った、言わない」の争いを避けるためには、日々のやり取りを簡単にでも記録しておくことが非常に重要です。
- 指導の記録:スタッフの勤務態度について注意や指導を行った際は、日時、内容、相手の反応などを簡単なメモで良いので残しておきましょう。これは、万が一、試用期間満了時に本採用を見送る場合や、懲戒処分を検討する場合に、客観的な証拠として役立ちます。
- ハラスメント相談:相談があった場合は、相談者のプライバシーに最大限配慮しながら、いつ、誰から、どのような相談があったかを記録します。相談窓口は、院長だけでなく、事務長や特定の看護師など、複数の選択肢を用意しておくと、スタッフが相談しやすくなります。
3. 試用期間を有効に活用する
新しく採用した看護師とのミスマッチを防ぐために、試用期間は非常に重要な機会です。
試用期間中は、任せきりにするのではなく、定期的に面談の機会を設けましょう。例えば、1ヶ月後に「業務には慣れましたか」「何か困っていることはありませんか」と声をかけ、技術面や他のスタッフとの協調性について、クリニック側が期待する水準に達しているかを確認します。
もし、改善が必要な点があれば具体的に伝え、指導を行います。それでも改善が見られず、残念ながら本採用が難しいと判断した場合には、試用期間中に行った指導の記録が「解雇の客観的で合理的な理由」を示す上で重要になります。
4. 情報管理を“習慣”にする
個人情報の漏洩は、個人の注意深さに頼るだけでは防ぎきれません。仕組みや習慣として、クリニック全体で取り組むことが大切です。
- FAXのダブルチェック:患者情報をFAXで送る際は、必ず2名で宛先番号を確認し、送付状にもチェック欄を設ける、といったルールが有効です。
- クリアデスク・クリアスクリーン:退勤時には、机の上に患者情報が書かれた書類を放置しない「クリアデスク」や、PCの画面をログイン状態のままにしない「クリアスクリーン」を習慣づけるよう、声かけをします。
- ヒヤリハット報告:ミスには至らなかったものの「危なかった」という事例(ヒヤリTハット)を報告しやすい雰囲気を作ることも重要です。報告を責めるのではなく、再発防止策をみんなで考える機会とすることで、全体の安全意識が高まります。
5. 人員不足で工夫が難しい場合は
ここまでの対策を読んで、「理屈はわかるが、そもそも人手が足りなくて、そんな丁寧な対応はできない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。日々の診療に追われ、スタッフの労務管理まで手が回らないというのは、多くのクリニックが抱える現実的な課題です。
そうした状況では、採用のプロセスやスタッフの管理の一部を、外部の力を借りて効率化するという選択肢も考えられます。
例えば、
- 採用のミスマッチを減らす:「いきなり正社員として採用するのではなく、まずは数日〜数週間の『お試し勤務』から始めて、クリニックの雰囲気や業務内容との相性を見極めたい」
- 採用業務の負担を減らす:「求人媒体とのやり取りや、面接の日程調整といった煩雑な作業は、誰かに任せたい」
といったニーズに応えるサービスがあります。こうした仕組みを活用することで、院長や事務長は本来注力すべき診療やクリニックの運営に集中でき、結果としてスタッフが安心して働ける環境づくりにつながる場合があります。
採用の初期段階におけるミスマッチの防止や、煩雑な調整業務の負担軽減に関心があれば、一度、情報収集をしてみてはいかがでしょうか。→ クーラのサービス資料はこちらから
まとめ:文書、日々の運用、外部の活用で、安定した雇用環境を
クリニックにおける看護師の雇用トラブルは、一つの原因だけで起こることは稀です。多くの場合、日々の小さな認識のズレや、コミュニケーションの不足、そして慢性的な人手不足といった要因が複雑に絡み合って発生します。
トラブルを未然に防ぎ、スタッフが長く安心して働ける環境を整えるためには、3つの視点が大切です。
- 文書でルールを明確にする:雇用契約書や就業規則といった「文書」を整備し、給与や労働時間に関する曖昧な部分(グレーゾーン)をなくすこと。これが全ての土台となります。
- 日々の運用で不満を解消する:記録を残す、定期的に面談する、院内にルールを掲示するといった「日々の運用」を丁寧に行うことで、スタッフが抱える小さな不満が、大きな問題に発展する前に対処できます。
- 外部の力を賢く活用する:採用の見極めや日程調整など、クリニック内部だけでは手が回らない部分は、「外部の活用」を検討すること。これにより、院内の負担を減らし、より良い人材の確保と定着につなげることができます。
クリニックにとって、人材に関する最大のリスクは、ある日突然、スタッフが辞めてしまうことです。完璧な労務管理を最初から目指すのは大変ですが、できるところから一つずつ備えを進めること、そして時には外部の専門家の力を借りることで、大きなトラブルを回避し、現場を守ることにつながります。
もし「まさに今、採用やスタッフのことで頭を悩ませている」という状況でしたら、まずは外部サービスがどのようなサポートを提供しているのか、情報収集から始めてみるのも一つの有効な手段です。






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)





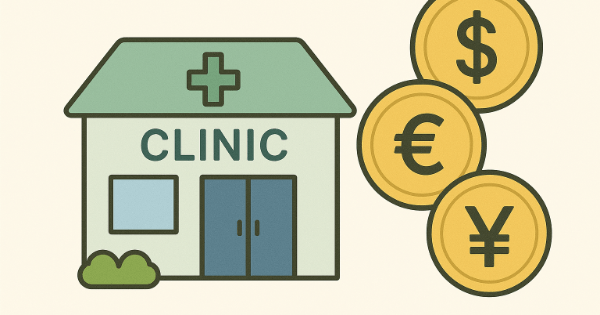
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
