この記事で伝えたいこと
訪問看護の現場で日々発生しうるヒヤリ・ハットや、スタッフ間の情報共有の齟齬。これらの原因をたどると、その多くが「記録の訂正方法」と「申し送りの形式」が事業所内で統一されていないことに起因する場合があります。特に、新しくチームに加わったスタッフが、独自のやり方で記録や報告を始めてしまうと、後々の情報確認や監査の際に大きな手戻りが発生しかねません。
そこで重要になるのが、入職後の初回研修(入職初日から初週にかけて)の段階で、事業所としての明確なルールを伝えることです。具体的には、紙の記録でも電子カルテでも等しく再現できる「中止線(二重線)を用いた訂正の運用」と、誰が聞いても同じように状況を理解できる「申し送りの標準的な文型」の2つです。この初期段階で基本的な型を定めておくだけで、その後の継続的な教育、日々の業務監査、そして何よりも医療・介護事故の予防が、格段に行いやすくなると考えられています。
この記事では、公的に発表されている各種ガイドラインや、実際に運営されている医療法人の規程、実務者向けの解説記事などを基に、初回研修で最低限押さえておくべき項目を整理しました。さらに、現場ですぐに活用できる研修台本やチェックリストの具体例もまとめています。運用方法を一から自作するのが難しい、あるいは既存のやり方を見直したいと感じている場合には、一つの参考にしていただければ幸いです。
なお、しっかりとした研修体制を整えることは、採用活動においても大きなアピールポイントになります。採用力を強化したいとお考えの場合、無料相談から始めてみるのも一つの方法です。詳細については、こちらのリンク(https://business.cu-ra.net/)からご確認いただけます。
なぜ“入職初日”に記録と申し送りのルールを決めるべきなのか
新しいスタッフを迎え入れる際、多くの研修項目がある中で、なぜ特に記録の訂正方法と申し送りの形式を最初期に徹底する必要があるのでしょうか。それは、これらが日々の業務の根幹をなし、一度「癖」がついてしまうと修正が困難で、後々大きな問題に発展する可能性があるためです。
1) 「訂正の仕方」が曖昧だと、後から全件見直しになる可能性
医療や介護の現場における公的な記録は、単なるメモではありません。それは法的な証拠性を持ち、ケアの正当性や継続性を担保する重要な文書です。そのため、一度記載した内容を修正する際には、誰が、いつ、どのように修正したのかという履歴が、第三者から見ても明確に追跡できる状態でなければなりません。修正液や修正テープで元の記載を完全に消してしまう行為は、記録の改ざんと見なされるリスクがあります。
この点について、介護・看護分野の実務者向け解説記事や、多くの医療法人が公開している内部規程では、共通して「二重線(中止線)で元の記載を残し、その上または近くに訂正印を押し、正しい内容と日付、訂正者名を記載する」という方法が推奨されています。これは、誤りを正直に認めつつ、修正の経緯を透明に保つための実務的な慣行として定着しています。
特に訪問看護指示書のように、医師の署名や押印が必要な書類の場合、訂正方法はさらに厳格さが求められます。もし誤記に気づいた場合、速やかに二重線と訂正印で修正しますが、内容によっては医師本人による再押印が必要になるケースも少なくありません。初回研修の段階で、「どの様式に、どのような訂正が必要で、その際に誰の印鑑(または署名)が必須となるのか」を一覧表などで明確に示しておかないと、個々のスタッフが自己流で対応してしまいます。その結果、月末のレセプト請求前の監査や、行政による実地指導の直前になって、大量の書類の差し替えや再発行依頼に追われるという事態が発生しがちです。
2) 申し送りの粒度が揃わないと“情報の抜け漏れ”が常態化する
申し送りは、次の担当者が安全かつ継続的なケアを提供するために不可欠な情報伝達のプロセスです。その本質は「誰に、何を、いつまでに、どのように対応してほしいか」を簡潔かつ正確に伝えることにあります。しかし、この申し送りが口頭での伝達を中心に行われていると、話す人によって情報の粒度や内容がバラバラになり、主観的な感想や憶測が混じりやすくなるという問題があります。これでは、ケア介入の客観的な根拠が記録として残らず、情報の「抜け」や「漏れ」が常態化してしまう危険性があります。
多くの看護・介護関連の実務書やウェブサイトでは、申し送りの質を担保するために、報告する項目を定型化(テンプレート化)することが推奨されています。例えば、「バイタルサイン」「観察された客観的な事実」「実施したケア」「ご家族からの伝言」「次回の課題」といった項目をあらかじめ決めておき、その順番で報告するルールを設けるのです。また、その際には「事実」と「個人の意見・評価」を明確に分けて記載・報告すること、そして「少し」「良好」といった曖昧な表現を避け、具体的な数値や観察内容で表現することが重要とされています。
3) 初回訪問での“型”が、その後の記録全体の癖を決める
訪問看護における初回訪問は、利用者様のバイタルサインの基準値、ADL(日常生活動作)のレベル、家屋環境、ご家族の介護力、緊急時の連絡手段など、その後のケア計画の土台となる重要な情報を収集する、一度きりの機会です。この非常に重要な初回訪問のアセスメントと同時に、「ご自宅に置かせていただく連絡ノートの目的と書き方のルール」や「事業所内での申し送りのフォーマット」について、新人スタッフ自身が利用者様やご家族に説明し、合意を得るプロセスを踏むことが、その後の円滑な連携の鍵を握ります。
最初にこの「型」を実践することで、新人スタッフは記録や報告の重要性を体感的に学びます。また、ご家族や連携するケアマネジャー、ヘルパーといった多職種との間での情報共有の経路も、この初回訪問の段階で確定させておくことが理想です。どのノートに、誰が、いつまでに、何を書くのか。緊急時には誰に、どの順番で連絡するのか。こうしたルールを利用者側と提供者側で共有しておくことで、その後の日々の連携がスムーズに進み、記録の質も自然と安定していきます。
このように、入職初日という、まだ業務の「癖」がついていない真っ白な状態で、記録と申し送りの「事業所の標準」をしっかりとインストールすることが、将来的なリスク管理と教育コストの削減に直結するのです。もし、こうした研修体制を整備し、採用時の魅力として伝えたいとお考えの場合、看護師採用を支援するクーラの無料相談で、他ステーションの事例などを聞いてみることも可能です。詳しくは、こちらのリンク(https://business.cu-ra.net/)からお問い合わせください。
公開情報に見る具体的な取り組み事例
記録の訂正方法や申し送りの標準化については、既に多くの医療機関や団体、公的機関が指針を示しています。ここでは、インターネット上で公開されている情報を基に、具体的な事例をいくつかご紹介します。
A. 二重線(中止線)・訂正の取り扱いに関する事例
記録の訂正に関するルールは、医療安全の基本として多くの場所で明文化されています。
- ある介護記録に関する解説サイトでは、介護記録の訂正において修正テープや修正液の使用は不適切であり、必ず二重線と訂正印を用いて誰がいつ訂正したかの履歴を残す運用が一般的であると解説されています。これは、記録の信頼性を担保するための基本的な作法と位置づけられています。(care-viewer.comの情報を参考)
- 看護記録の具体的な書き方を解説するウェブサイトでは、誤字脱字を見つけた場合は「黒のボールペンで二重線を引き、訂正印(またはサイン)と日付を記入する」、後から情報を付け加えたい場合は余白に「追記:」と明記した上で内容を記載するなど、具体的な方法が図解付きで示されている例もあります。(shigoto-retriever.comの情報を参考)
- 大手看護師向けメディアの記事でも、看護記録の基本ルールとして、改ざんを疑われないために「黒のボールペンを使用する」「間違えた箇所は二重線で消す」「記録に空白を作らないようにし、もしできてしまった場合は斜線を引くか、『〇行空白』と記載する」といった、基礎的ながら重要な点が整理されています。(ナース専科の情報を参考)
- 沖縄県にある医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院では、法人として策定した個人情報保護規程の中で、診療記録の訂正に関する項目を設けています。そこでは、訂正は二重線を引き、日付を記入し、訂正者が捺印すること、そしてそれ以外の方法による訂正は改ざんと見なされる可能性がある旨が明確に記されており、組織としてのルールが確立されています。
- 訪問看護指示書の取り扱いを解説するリハビリ専門職向けの情報サイトでは、指示書の内容に誤記があった場合は二重線と主治医の訂正印による修正が必要であること、特に主治医の捺印漏れや、保険適用に関わる指示期間の起算日・満了日の誤りには細心の注意が必要であるとされています。(pos-reha.comの情報を参考)
B. 申し送り・連絡ノートの形式に関する事例
情報の抜け漏れを防ぎ、多職種連携を円滑にするための工夫も各所で見られます。
- ある介護情報サイトでは、申し送りの基本として「いつ・誰が・何を・どのように」という要素を揃えること、内容は簡潔かつ具体的に記述し、体温や血圧などの数値や客観的な観察事実を優先して用いることの重要性が例を挙げて説明されています。また、口頭での申し送りと、連絡ノートやアプリなどの記録ツールを併用し、テンプレートを用いて情報の粒度を統一する手法が紹介されています。(care-viewer.comの情報を参考)
- 看護師向けの情報サイト「レバウェル看護」では、申し送りをスムーズに行うための具体的な項目リストが例示されています。そこには、バイタルサイン、アレルギー歴、既往歴、ADL、食事・排泄状況、実施したケア、家族からの情報、感染症対策に関する注意事項などが含まれており、報告すべき内容の標準化に役立つとされています。
- 訪問看護における連絡ノートの活用法を解説する記事では、ノートが形骸化しないために、巻頭ページに「このノートの目的」「活用方法」「関係者の連絡先一覧」「緊急時対応の手順」を明記しておくことが推奨されています。そして、日々の記録ページには「訪問日時」「ケア内容」「利用者様の様子」「特記事項・相談事項」といった定型のフォーマットを設けることで、誰が書いても運用が安定しやすくなると解説されています。(asaid.netの情報を参考)
C. 新人訪問看護師の研修フレームワークに関する事例
新人を現場に適応させるための教育プログラムにも、記録や報告に関する内容が含まれています。
- 訪問看護ステーションの管理者向け情報サイトでは、多くの事業所で新人研修のプログラムとして、入職直後のオリエンテーションに始まり、座学、同行訪問、ケーススタディなどを組み合わせ、約3ヶ月から1年程度の期間を見込んで育成計画を立てているという実態が解説されています。この中で、記録の書き方は初期に学ぶべき必須項目とされています。(ewellibow.jpの情報を参考)
- 長崎県看護協会が公開している「新人訪問看護師育成プログラム」の関連資料では、研修の具体的な流れが示されています。初回訪問への同行訪問の際に確認すべき項目、利用者様への説明内容、そして日々の業務終了後に行う振り返りの記録シート、各種様式の継続的な記載のチェックなど、評価と記録を一体とした育成の枠組みが提示されており、公的な団体が標準化を進めている事例として参考になります。
もし、ご自身のステーション向けに、これらの事例を参考にしたテンプレートを整備し、それを採用活動に活かしたいとお考えであれば、看護師採用の専門家であるクーラに相談し、採用に繋がりやすい研修体制のポイントについてアドバイスをもらうのも一つの方法です。詳しくは、こちらのリンク(https://business.cu-ra.net/)をご覧ください。
初回研修で実践する標準台本(目安:90〜120分)
以下に示すのは、入職初日に実施することを想定した、記録と申し送りに関する研修の標準的な台本です。紙媒体で運用している事業所でも、将来的に電子カルテを導入した場合でも通用する、普遍的な内容に絞り込んでいます。
1) 研修の冒頭(10分) — 目的の共有
「本日は、記録と申し送りに関する当事業所の基本的なルールについて研修します。この研修の目的は、大きく2つあります。1つは、皆さんが書く記録の『証拠性』を担保すること。もう1つは、スタッフ間の申し送りの『再現性』、つまり誰が伝えても同じ内容が正確に伝わる状態を作ることです。これらは、利用者様の安全を守り、私たち自身を守るために非常に重要です。」
「本日の研修を終えたとき、皆さんが以下の3つのことができるようになっていることをゴールとします。」
- 二重線(中止線)での訂正、訂正印、日付、署名のルールを、訪問看護記録書や指示書といった『様式別』に正しく理解し、実践できる。
- 申し送りの基本となる型(報告する項目、順番、使ってはいけない言葉)を理解し、簡単な事例で実演できるレベルになる。
- 初回訪問から次回の訪問までの間に、利用者様やご家族、主治医、ケアマネジャーとどのように情報をやり取りするのか、その『連絡経路図』を自分の手で書けるようになる。
2) 記録の訂正ルール(25分) — “どの様式で誰の印鑑が必要か”
「まず、記録を訂正する際の絶対的な原則からお話します。当事業所では、いかなる記録媒体においても、修正液や修正テープの使用を認めていません。間違えた箇所は、必ず黒のボールペンで二重線を引き、元の記載内容が読める状態を保ってください。その上で、欄外か余白に正しい内容、訂正した日付、そして訂正した本人の署名を記載します。様式によっては、これに加えて訂正印が必要となります。また、記録に空白の行ができてしまった場合は、後から追記されることを防ぐため、必ず斜線を引くか、『○行空白』と明記してください。」(shigoto-retriever.comの情報を参考)
「次に、様式ごとの具体的な違いについて、配布した一覧表を見ながら確認しましょう。」
- 訪問看護記録書IおよびII:基本は二重線と日付、署名で対応します。もし、訪問から時間が経ってから記録を追記する場合は、必ず「追記:」と時刻を明記してから内容を記載してください。(訪問看護のソフト(システム)・電子カルテはカイポケ訪問看護の解説を参考)
- 訪問看護指示書:これは医師が発行する公的な文書ですので、訂正は特に慎重に行います。誤りを発見した場合は、二重線と主治医の訂正印が原則です。ステーション側で勝手に修正することはできません。指示書を受け取ったら、まず主治医の押印が漏れていないか、指示期間の開始日と満了日に誤りがないかを必ず点検する癖をつけましょう。(pos-reha.comの情報を参考)
- ご自宅の連絡ノート:これはご家族や他のサービス事業者も見るものです。ご家族が書かれた記載を、こちらで勝手に消したり訂正したりしてはいけません。もし内容に事実誤認などがある場合は、赤ペンで下線を引くようなことはせず、新しいページや備考欄に「〇月〇日のご家族様の記載について、事実関係は以下の通りです」と、正しい情報を丁寧に追記する形で対応します。このノートの運用ルール自体を、巻頭ページに掲示しておくことがトラブル防止につながります。(asaid.netの情報を参考)
「それでは、ここで簡単な演習をしてみましょう。配布した用紙にある3つの誤記パターン(単純な誤字脱字/バイタルサインの数値の誤記/観察事実の誤認)を、今説明したルールに従って訂正してみてください。訂正が済んだら、欄外に正しい情報、日付、ご自身の署名をし、必要であれば訂正印を押してください。」(5分間演習後、解説)
3) 申し送りの型(30分) — “事実→評価→依頼”の順番を徹底する
「次に申し送りの型についてです。申し送りは、客観的な事実から伝え、最後に依頼事項で締めくくるのが基本です。配布したテンプレートを一枚見てください。この順番で報告・記録することを徹底します。」
- テンプレートの項目:
- 患者ID(または氏名)/訪問日時/担当者名
- バイタルサイン(具体的な数値を報告)
- 観察された客観的な事実(利用者の言動、皮膚の状態、家の中の環境変化など、見たまま・聞いたままを報告)
- 実施した介入・処置(何を実施し、どのような反応があったか)
- アセスメント(評価)(観察事実に基づき、前回と比較してどうか、状態に変化はあるかなどを評価)
- 次回への依頼・提案(次の担当者に何を依頼したいか、医師やケアマネに何を相談すべきか。依頼先・期限・理由を明確に)
「口頭で申し送る際の注意点です。『状態は良好です』『少し食事が摂れていません』といった主観的で曖昧な言葉は避け、具体的な表現を心がけてください。時間を伝えるとき、お名前を出すとき、数値を報告するときは、特にハッキリと先に伝えるようにしましょう。」(care-viewer.comの情報を参考)
「連絡ノートを運用する際は、巻頭ページにこのノートの目的、緊急連絡時のフロー、関係者の連絡先一覧を固定して表示しておくことが重要です。」(asaid.netの情報を参考)
「では、ここでロールプレイングを行います。3人1組になってください。配布する事例(疼痛が増悪しているケース/食事摂取量が低下しているケース/転倒リスクが上昇しているケース)について、1人が報告者、1人が受け手、1人が観察者になります。報告者は3分で口頭申し送りを行い、その後1分で要点をメモにまとめてみてください。」
「申し送りで使ってはいけない“NGワード”の例も覚えておきましょう。曖昧な言葉(少し、多め、まあまあ)、予断や憶測(~だろう、~かもしれない)、内輪でしか通じない略語などです。誰が聞いても同じ情景が思い浮かぶ言葉を選んでください。」(note(ノート)の情報を参考)
こうした申し送り用テンプレートを整備し、教育体制が整っていることをアピールすることは、採用力の向上に繋がります。採用に関するご相談は、看護師のお試し勤務・採用を支援するクーラの導入相談で承っています。ご興味があれば、こちらのリンク(https://business.cu-ra.net/)からお問い合わせください。
4) 初回訪問時の“連絡経路図”の作成(15分)
「初回訪問では、利用者様を中心に、誰と誰が、どのように繋がっているのかを可視化する『連絡経路図』を作成し、関係者で共有することが大切です。利用者様のご自宅から、私たち訪問看護ステーション、主治医、ケアマネジャー、そして場合によっては訪問リハビリやヘルパーステーションまで、情報の流れを一本の線で結んでみましょう。」
「特に重要なのが、夜間や休日といった緊急時の連絡の優先順位です。何かあったとき、ファーストコールはステーションの緊急携帯で良いのか、それとも状況によっては直接救急車を呼ぶべきか。その判断基準と連絡手順を図にして、ご家族にも説明し、合意を得ておく必要があります。」(asaid.netの情報を参考)
「ご自宅に置く連絡ノートも同様です。どこに置くのか、主に誰が書き、誰が読むことを想定しているのかを、初回訪問時にご家族としっかり合意形成しておくことが、後のトラブルを防ぎます。」(caps-plus.jpの情報を参考)
5) 訪問直後から当日内の記録タイムライン(10分)
「記録は鮮度が命です。記憶が新しいうちに記録することが、間違いを防ぐ一番の方法です。当事業所では、以下のタイムラインを推奨しています。」
- 訪問直後、車内や事業所に戻る前に、まずはメモ帳やモバイル端末に一次記録(バイタルサイン、実施したケア、特記事項など)を殴り書きで良いので残す。
- 帰所後、30分以内に正式な訪問看護記録書への二次記録を完了させる。
- その日の業務終了までに、次の担当者への申し送りを確定させ、記録として残す。
「もし、やむを得ず記録が遅れてしまった場合は、必ず『追記:』と時刻を明記してから記載するようにしてください。」(shigoto-retriever.comの情報を参考)
6) 研修の仕上げ(10分)
「最後に、本日の内容が理解できたか、簡単なチェックテスト(10問程度)を行います。二重線の引き方、訂正印が必要な場面、空白の処理方法、申し送りの正しい順序などについて確認します。」
「常に、『この記録を、全く事情を知らない第三者が見ても、ケアの経過を辿れるだろうか』という監査の視点を持つことが重要です。本日皆さんが演習で作成した訂正の用紙や申し送りのメモは、一度スキャンして保存し、来週の面談の際に個別にフィードバックします。」
実装ツール・雛形(紙でも電子でも使える)
研修で説明したルールを、日々の業務に定着させるためのツール例です。これらの雛形をステーション内の見やすい場所に掲示したり、ノートに貼り付けたりするだけで、意識づけに繋がります。ここでは、特に重要な3つのツールについて、Webflowなどのウェブサイトに埋め込んで表示できるHTML形式のサンプルコードも併せてご紹介します。
A. 1枚貼り出し用「記録訂正の基本ルール」
ステーションのスタッフルームや記録棚の前に掲示しておくためのシンプルなルール表です。
B. 申し送りテンプレート(口頭・ノート共通)
報告の順番を体に染み込ませるためのテンプレートです。
C. 連絡ノート巻頭ページの文例
利用者様宅に設置する連絡ノートの1ページ目に貼り付けておくことで、ご家族や他の事業者との認識を統一します。
こうした掲示物やテンプレートを整備することは、スタッフが安心して働ける環境づくり、ひいては定着率の向上や採用応募の増加に繋がると考えられます。採用活動を強化したい、自ステーションの魅力をどう伝えれば良いか分からない、といったお悩みについては、クーラのサイト(https://business.cu-ra.net/)からお気軽にお問い合わせください。
申し送りの品質をもう一段階上げる“3つのコツ”
テンプレートを導入した上で、さらに申し送りの質を高めるために、日頃から意識したい3つのコツがあります。
1. 「事実」と「意見」を明確に分ける
報告を聞いている側が最も知りたいのは、まず「何が起きたのか」という客観的な事実です。例えば、利用者様が不満そうな表情をしていた場合、「不機嫌でした」と報告するのは個人の意見(評価)です。そうではなく、「訪問時、眉間にしわが寄っており、こちらからの問いかけに対する発語が少なく、表情の変化も乏しかった」というように、誰が見ても同じように捉えられる事実で記述することが重要です。意見や評価を述べるのは、これらの事実を報告した後です。(note(ノート)に掲載の看護師向け記事の考え方を参考)
2. 「数値」と「比較」で具体的に語る
「食事の摂取量が少ないです」という報告では、どのくらい少ないのかが分かりません。「本日の朝食は、主食が1/3量、副菜が半分程度の摂取でした。ちなみに昨日の朝食は2/3量を召し上がっていました」というように、具体的な数値と、過去(昨日や前回訪問時)との比較で語ることで、情報の精度が格段に上がります。これにより、状態の変化を誰もが客観的に把握できるようになります。(レバウェル看護の記事の考え方を参考)
3. 「次のアクション」を明確にする
申し送りは、単なる状況報告で終わらせず、次に行うべきアクションに繋げることが目的です。そのため、報告の最後は「誰が、いつまでに、何をするのか」を明確にした依頼や提案で締めくくることが望ましいとされています。例えば、「本日、嚥下機能の低下が疑われる場面があったため、次回訪問時に再度嚥下状態の再評価を行います。その結果、必要と判断されれば言語聴覚士(ST)への介入をケアマネジャー経由で依頼する予定です(担当:A看護師/判断期限:〇月〇日)」のように、依頼先・期限・理由・担当者をワンセットで伝えることで、チーム全体で計画的に動くことができます。
よくあるNG事例と、即日で直せる是正例
新人スタッフだけでなく、経験者でも無意識に行いがちなNG事例と、その改善策をまとめました。日々の業務でのセルフチェックにご活用ください。
- NG:記録の誤りを修正テープで消して、その上から書き直してしまう。
- → 是正:必ず二重線を引いて元の記載が読めるように残し、欄外に正しい内容・日付・署名を記載します。必要に応じて訂正印も使用します。これは、記録の透明性と証拠性を保つための鉄則です。(care-viewer.comの情報を参考)
- NG:「いつも通り変わりありません」「特に問題ありません」といった、主観や推測だけの申し送りで終わらせてしまう。
- → 是正:変わりない場合でも、「バイタルは安定、表情も穏やかで、〇〇の話題で会話が弾む」など、変わりないことを示す具体的な数値を述べたり、客観的な行動や所見を伝えたりします。事実を先に述べ、その上で「特変なしと判断します」と評価を続けるのが正しい順序です。(care-viewer.comの情報を参考)
- NG:連絡ノートがただの訪問記録になっており、目的が不明確で、記載者もバラバラになっている。
- → 是正:巻頭ページに、このノートの目的、主な記載者と閲覧者、書式のルール、そして緊急時の連絡先と対応フローを明記し、固定表示します。これにより、ご家族や他の事業者が見ても、ノートの役割が一目瞭然になります。(asaid.netの情報を参考)
まとめ:初回研修で“ここだけは必ず決めておくべき”3つのこと
新しいスタッフを迎える際の初回研修は、多岐にわたる項目を教える必要があり、時間が限られています。その中でも、将来にわたる業務の質と安全性を担保するために、最低限、以下の3点だけは入職初日の段階で事業所としての統一ルールを明確にすることが推奨されます。
- 記録の訂正は「二重線+履歴」で行うこと
- 修正液や修正テープは使用せず、元の記載が読める形で訂正の履歴を残すという原則を徹底します。特に、訪問看護指示書など様式ごとに訂正印や医師の再押印の要否が異なるため、そのルールを一覧化して示すことが重要です。(医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院の規程等を参考)
- 申し送りは「定型と順序」を守ること
- 「事実→介入→評価→依頼」という標準的な順序を定め、テンプレートを活用します。報告の際は、曖昧な表現を避け、具体的な数値、固有名詞、そして次のアクションの期限を明確に伝えることを習慣づけます。(care-viewer.comの情報を参考)
- 「連絡経路図」を初回訪問で確定させること
- 利用者様を中心に、ご家族、多職種、そして夜間・緊急時の連絡の優先順位と手段を可視化し、関係者全員で共有します。連絡ノートの運用方法についても、この段階で合意しておくことが、後の連携をスムーズにします。(asaid.netの情報を参考)
この3つのポイントを入職初日に全員で共有し、実践するだけで、その後のOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)における指導が格段にしやすくなります。日々の指導では、より専門的なケース検討や同行訪問を通じたアセスメント能力の向上、利用者様とのコミュニケーション技術といった、より本質的なケアの質の向上に時間を割くことができるようになるでしょう。
しっかりとした研修体制は、採用活動における強力な武器になります。この記事で紹介したようなテンプレートを整備し、働きやすい環境を整えていることをアピールしたいとお考えでしたら、看護師のお試し勤務・採用プラットフォーム「クーラ」にご相談ください。採用のプロの視点から、貴ステーションの魅力向上と採用力強化をお手伝いします。
採用力の強化と組織作りをご検討の方へ
- 研修体制を整備して、採用応募者にアピールしたい場合:しっかりした教育体制は、求職者にとって大きな魅力です。自ステーションの強みをどう伝えれば良いか、採用のプロにご相談ください。→ クーラに相談する
- 「教育がしっかりしている」ステーションとして認知され、採用ミスマッチを減らしたい場合:お試し勤務などを活用し、実際の教育体制を体感してもらうことで、入職後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、定着率向上に繋げます。
- 働きやすい環境を整え、人材の定着と採用力向上につなげたい場合:スタッフが安心して働けるルール作りは、組織の基盤です。組織力向上と、それがどう採用に繋がるかについて、一緒に考えてみませんか。→ クーラに相談する
参考にした一般公開情報(抜粋)
- 二重線・訂正運用関連:修正テープの禁止、二重線+訂正印+日付での訂正方法に関する解説記事、実際の医療法人の院内規程、訪問看護指示書の訂正に関する実務情報。(care-viewer.com, 医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院, pos-reha.com, shigoto-retriever.com, ナース専科)
- 申し送り関連:報告項目の整理、具体的表現や数値化の重要性、口頭申し送りのコツとテンプレートの活用法。(care-viewer.com, レバウェル看護, note(ノート))
- 新人育成・連絡ノート関連:訪問看護における新人研修の一般的なフレームワーク、初回訪問の流れ、都道府県看護協会による育成プログラム、連絡ノートの効果的な運用方法。(ewellibow.jp, 長崎県看護協会, asaid.net, caps-plus.jp)
※本記事は、訪問看護ステーションにおける記録・申し送りの運用方法に関する一般的な理解を深め、現場の皆様が安心して業務に取り組める環境づくりを支援することを目的としています。最終的な様式の決定や押印の要否については、必ず貴ステーションの内部規程、連携する主治医の運用方針、そして所轄の行政機関からの指導内容に沿ってご判断ください。






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)





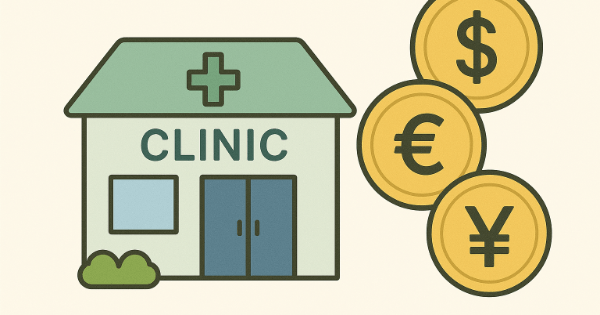
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
