いま、なぜ「インバウンド診療」を整えるべきか
訪日外国人客の数は、回復という段階を越え、月次で過去の記録を更新する勢いを見せています。例えば、日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2025年8月の訪日外客数は342.8万人に達し、前年の同じ月と比較して16.9%の増加となりました。特に、夏休みシーズンと重なるこの時期は、東アジアや欧米豪からの旅行者が増加の主な要因となっていると分析されています。
この大きな流れは、観光業界に限った話ではありません。旅行先での急な体調不良への対応、皮膚科や歯科での予期せぬトラブル、婦人科や小児科に関する相談、あるいは健康診断や美容医療を目的とした来院など、クリニックの現場においても「インバウンド需要」の確かな手応えを感じる機会が増えているのではないでしょうか。
このような状況を受け、国や地方自治体も後押しを始めています。厚生労働省やJNTO、各都道府県では、外国人患者を受け入れる医療機関の情報を多言語で検索できるウェブサイトを整備・公開しています。これらの公的な情報提供サイトに自院の情報を正確に掲載し、検索された際に見つけてもらえる状態を作るだけでも、新たな患者さんの流れを生み出すきっかけとなり得ます。
この記事では、大規模な病院でなくとも、クリニック単位で現実的に取り組むことが可能な「集患」と「診療単価の最大化」に向けた具体的な方法を、実際の事例を交えながら一つひとつ解説していきます。読み進めながら、ご自身のクリニックで何から始められるか、応用できそうな部分はないか、という視点でご覧いただければ幸いです。
クーラの詳細・導入に関するご相談はこちら: https://business.cu-ra.net/
背景・課題:「外国人患者」対応の“つまづき”はどこに出るか
外国人患者の受け入れを始める、あるいは既に始めているものの、現場で様々な課題に直面しているというお話はよく耳にします。具体的に、どのような点が業務の妨げになりやすいのでしょうか。いくつかの典型的な例を見ていきましょう。
よくある課題となりやすい点
- 初動の言語の壁電話での予約や問い合わせの段階で、症状や希望する日時、保険の有無といった基本的な情報がうまく伝わらず、受付業務が滞ってしまうケースです。窓口での直接のやり取りでも同様に、緊急性の判断やトリアージに時間がかかり、他の患者さんをお待たせしてしまう原因にもなり得ます。
- 決済・料金説明の煩雑さ日本の医療保険制度に馴染みのない方へ、自由診療の料金体系を説明するのは簡単ではありません。特に、どの範囲が「初診料」で、どこからが「検査料」「処置料」になるのか、といった見通しが不明瞭だと、患者さんの不安につながります。また、支払い方法として普段利用しているクレジットカードや電子決済(例えば中国で普及している銀聯カードなど)が使えるかどうかは、患者さんにとって非常に重要な情報です。この確認と説明に手間取り、会計がスムーズに進まないことも少なくありません。
- 院内案内の不統一院内で使用する書類の言語対応が、診療科ごと、あるいは担当者ごとに異なっているケースも見受けられます。例えば、内科では英語の問診票があるのに、皮膚科には用意がない。あるいは、Aという医師は多言語の同意書を使っているが、Bという医師は口頭での説明のみ、といった状況です。アフターケアの説明書なども含め、提供する情報が標準化されていないと、患者さんの混乱を招き、後々のトラブルの原因となる可能性があります。
- 受け入れ情報の露出不足最ももったいないのが、せっかく外国人患者を受け入れる体制を整えたにもかかわらず、その情報が必要な人に届いていないケースです。多言語対応が可能であること、利用できる決済方法、診療科目などが、患者さんが医療機関を探す際に見るであろうウェブサイトや地図アプリに掲載されていなければ、存在しないのと同じになってしまいます。
なぜ「公的導線」を押さえると効くのか
こうした課題に対して、まず着手しやすいのが公的な情報導線を活用することです。厚生労働省やJNTOは、外国人患者の受け入れが可能な医療機関のリストを、英語、中国語、韓国語をはじめとする複数の言語でウェブサイト上に公開しています。
これらのリストには、各都道府県が中心となって選定した「外国人患者受入れ拠点的医療機関」のような大規模な病院だけでなく、地域の診療所や歯科診療所も登録・検索が可能です。掲載にあたっての要件や、どのような診療カテゴリで登録されているかといった考え方も明記されています。自院の情報をこれらの公的リストに正確に掲載し、常に最新の状態に保つことは、「いざという時に頼れるクリニック」として、外国人旅行者や在留者に見つけてもらうための、信頼性が高く効果的な第一歩となると考えられています。
実例紹介:成功パターンを具体的に見る
ここでは、実際に外国人患者の受け入れに取り組んでいる医療機関の事例をいくつかご紹介します。すべてを真似する必要はありませんが、自院の状況に合わせて参考にできるヒントが見つかるかもしれません。
- 静岡県・森町家庭医療クリニックの取り組みこのクリニックでは、当初、現場での会話対応に苦労があったと報告されています。そこで活用されたのが、医師賠償責任保険に付帯していた医療通訳サービスや、静岡県が提供する電話医療通訳サービスでした。県のサービスは最大31言語に対応しており、これらを組み合わせることで、高額な初期投資をして多言語対応スタッフを常時雇用することなく、段階的に受け入れ体制を整備することに成功しました。結果として、職員の負担が軽減され、外国人患者さんからも安心して受診できると評価されたそうです。この事例は、既存の外部サービスをうまく組み合わせることで、クリニックの規模でも無理なく対応体制を構築できることを示唆しています。
- 東京都の情報導線(Tokyo Himawariなど)東京都では「東京都保健医療情報センター(愛称:ひまわり)」を通じて、外国人向けの医療情報サイトを運営しています。このサイトでは、救急車の呼び方といった基本的な情報から、対応可能な医療機関の検索、日本の医療制度の解説まで、多言語で詳細な情報が提供されています。特に、東京のような大都市を訪れる旅行者が、体調を崩した際に最初に検索してたどり着く可能性の高い公的情報源です。そのため、自院のウェブサイトや窓口で案内する内容を、「ひまわり」に掲載されている情報と整合性を取っておくことで、患者さんの混乱を防ぎ、スムーズな受診につなげやすくなります。
- 歯科診療所の知見(中目黒・山手デンタルクリニックの発表資料より)ある歯科診療所の発表資料では、外国人患者の具体的な来院経路や診療内容について報告されています。患者さんがクリニックを知るきっかけは、インターネット検索が最も多く、次いで知人からの紹介、加入している海外旅行保険会社や自国の大使館からの紹介、学会でのつながりなど、多岐にわたります。診療内容の多くは、痛みや詰め物が取れたといった緊急対応が中心の保険診療ですが、一部の国からの患者さんや在留資格によっては、審美歯科やインプラントなどの自費診療の割合が高くなる傾向も見られるとのことです。現場での苦労としては、やはり電話での氏名の聞き取りや、言語の壁による受付の混乱が挙げられており、多くのクリニックで共通する課題であることがわかります。
- 医療通訳サービスの活用(株式会社メディフォン社の「mediPhone」など)医療に特化した遠隔通訳サービスも、有効な選択肢の一つです。例えば「mediPhone」というサービスは、電話やビデオを通じた人力の通訳と、タブレットなどで利用できる機械翻訳を組み合わせて提供しています。来院前の電話での問い合わせ対応から、受付、診察室での医師との対話、会計時の説明、さらには院内掲示物の翻訳まで、一貫して支援する体制をうたっています。全国で8万以上の医療機関への導入実績があると公表されており、自治体や消防機関との連携も進んでいます。こうした外部サービスを利用することで、院内に通訳スタッフがいなくても、必要な時に必要なだけ専門的な言語サポートを得ることが可能になります。
- JMIP(外国人患者受入れ医療機関認証制度)という選択肢JMIPは、第三者機関が外国人患者の受け入れ体制を客観的に評価し、一定の基準を満たしていると認めた医療機関を認証する制度です。この認証を取得する過程で、院内のマニュアルや案内表示、スタッフの教育体制などを見直すことになり、組織全体で受け入れ体制を向上させる共通の目標ができます。また、認証を取得していることは、対外的に「外国人患者が安心して受診できる医療機関」であることの証明となり、信頼性の向上に繋がるとされています。厚生労働省もこの制度を推進しており、ウェブサイトなどで認証取得医療機関のリストを公開しています。
解決アプローチ:小さく始めて、確実に伸ばす5ステップ
外国人患者対応は、最初から完璧な体制を目指す必要はありません。できることから着実に進めることが大切です。ここでは、クリニック規模でも取り組みやすい5つのステップをご紹介します。
科目別の着眼点:どこを整えると単価が上がるか
診療科の特性によって、外国人患者が求めるものや、満足度を高めるポイントは異なります。ここではいくつかの科目を例に、診療単価の向上にもつながる工夫のヒントをご紹介します。
露出強化:患者が探す“場所”に正しく載る
受け入れ体制を整えたら、次はその情報をいかにして必要とする患者さんに届けるか、という段階です。
公的サイト・認証を使う
- JNTOの受け入れ医療機関検索への対応JNTOが運営する「Japan, Safe travels」などのウェブサイトには、外国人患者が日本の医療機関を探すための検索ページがあります。自院がここに掲載されているか、掲載されている情報(対応言語、診療科目、決済方法など)が最新かつ正確であるかを確認し、必要であれば情報の更新を行いましょう。
- 都道府県の医療情報サイトの参照東京都の「ひまわり」のように、各都道府県でも外国人向けの医療情報提供を行っている場合があります。こうしたサイトでどのような情報が求められているか、どのような医療機関が「拠点医療機関」として紹介されているかなどを参照し、自院の情報提供のあり方を改善していくヒントにすることができます。
- JMIP認証による信頼性の獲得前述のJMIP認証を取得することは、院内体制の標準化と継続的な改善を促すだけでなく、対外的にも「外国人患者の受け入れに積極的で、体制が整っている医療機関」としてのアピールになります。認証マークをウェブサイトなどに掲載することで、患者さんの信頼を得やすくなるという効果が期待されます。
民間サービスで“初動”を切り抜ける
mediPhoneのような遠隔通訳と機械翻訳を組み合わせたサービスは、言語の壁に起因する様々な問題を解決する助けになります。来院前の電話問い合わせから、診察、会計、アフターケアの説明まで、患者さんと医療機関の間のコミュニケーションが滞りがちなポイントを、外部の専門家の力で補うことができます。これにより、院内スタッフは本来の業務に集中しやすくなります。
現場オペのコツ:トラブルを未然に防ぐチェックリスト
日々の業務の中で、少しの準備や工夫で未然に防げるトラブルは少なくありません。ここでは、すぐにでも確認・実践できるチェックリストをご紹介します。
繁忙日にだけ看護師の人数を増やしたい、あるいは、英語が話せるスタッフに頼るのではなく、他のスタッフでも円滑に業務を回せるようにしたい、といった場合、1日単位で看護師の応援を頼める体制は有効な選択肢となります。試験的な勤務から依頼できるクーラのようなサービスは、導入の心理的なハードルが低く、運用体制を構築する上での「最初の一歩」として検討しやすいかもしれません。 https://business.cu-ra.net/
まとめ:完璧を目指さない。まず「見つけてもらい、誠実に案内する」
外国人患者の受け入れ体制整備は、壮大なプロジェクトに感じられるかもしれませんが、重要なのは、完璧な状態を一度に作り上げようとしないことです。以下のポイントを参考に、できるところから始めてみてください。
- まずは公的な導線(JNTOや都道府県の医療情報サイト)に掲載されている自院の情報を最新に保ち、“探される場所”に正しい情報が載っている状態を作ります。
- 多言語の問診票テンプレートや遠隔通訳サービスといった初動を助けるツールを導入し、受付や診察が言語の壁で滞るのを防ぎます。
- 料金や利用可能な決済手段に関する情報を透明化することで、患者さんの金銭的な不安を減らし、信頼関係を築くことが、結果的に満足度と単価の両立につながります。
- 診療科ごとの需要の違いを意識してウェブサイトの情報を整え、地図アプリや口コミサイトにも英語で対応することで、検索からの流入を増やします。
- すべてを院内の人材だけで賄おうとせず、必要な時に外部の力を柔軟に借りる仕組みを整えます。特に、業務量の波に合わせて短時間・短期で看護師のサポートを得ることは、無理なく継続していくための有効な手段です。
インバウンド診療は、何か特別な集患施策というよりも、「探している人に、自院の情報を見つけてもらう」ことと、「安心して受診できる体制があることを、分かりやすく伝える」ことの、地道な積み重ねです。ぜひ、今日からできる範囲の一歩を踏み出してみてください。
受付業務の負担を軽減したい、繁忙期に合わせて一時的に看護師を増員したい、といった具体的な課題をお持ちの場合は、1日単位の短期・お試し勤務から始められるクーラの活用をご検討ください。
お問い合わせはこちら: https://business.cu-ra.net/
付録:検索に強い見出しのサンプル(自院サイト向け)
自院のウェブサイトやブログ記事を作成する際に、以下のような英語の見出しを使うと、外国人患者が検索した時に見つけてもらいやすくなる場合があります。
「外国人患者 受け入れ」向けH2/H3見出しの例
- English-speaking doctor available in [Area Name]|[地名]で英語対応可能な医師が在籍
- Credit cards and UnionPay accepted|各種クレジットカード・銀聯カードが利用可能です
- For Travelers in Japan: Urgent Care & General Medicine|旅行中の方向け:急な発熱・腹痛・皮膚トラブルに対応
- How to visit our clinic: For International Patients|外国人患者さんへ:持ち物・予約方法・費用の目安
- Medical interpretation service available|電話・ビデオによる医療通訳サービスに対応しています
検索結果に表示されやすいスニペットの例文(英語ページの概要欄など)
“Same-day consultation available for travelers in [City Name]. Please bring your passport and travel insurance documents. We accept major credit cards and UnionPay for your convenience.”([都市名]にご滞在の旅行者向けに、当日診療が可能です。パスポートと海外旅行保険証書をお持ちください。主要クレジットカードおよび銀聯カードをご利用いただけます。)
引用・参考リンク(主要)
- 訪日外客数関連データ:日本政府観光局(JNTO) 月次発表資料
- 外国人患者受け入れ医療機関の情報:JNTOウェブサイト、厚生労働省「医療機能情報提供制度」、各都道府県の医療情報サイト(例:東京都保健医療情報センター「ひまわり」)
- 多言語説明資料:厚生労働省「外国人向け多言語説明資料一覧」
- 医療通訳サービス事例:株式会社メディフォン「mediPhone」
- 医療機関認証制度:日本医療教育財団「外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)」
- クリニックの取り組み事例:特定非営利活動法人 日本医療政策機構(HGPI)「在留外国人への医療提供に関する研究」報告書内、森町家庭医療クリニック(静岡県)の事例、山手デンタルクリニック(東京都)の発表資料など
この記事を読み終えた今が、小さな一歩を踏み出す良い機会です。まずは、ご自身のクリニックの情報が「探される場所」に正しく掲載されているかを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。そして、業務の負担を分散させたいと感じた時には、クーラのようなサービスで看護師の短時間サポートを組み合わせ、無理なく続けられる土台を作ってください。

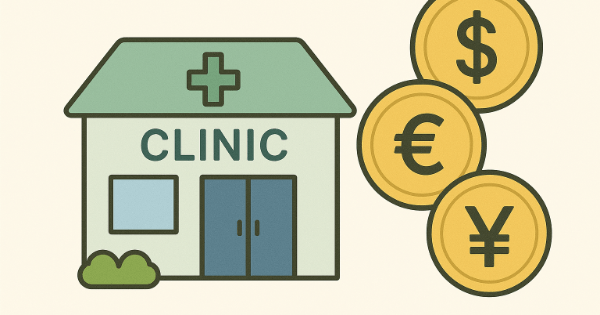





.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
