魅力的な言葉「だけ」を並べると、かえってコストが上がってしまうかもしれません
採用案内用のウェブページやパンフレットに、「働きやすい職場です」「スタッフの人間関係は良好です」「お休みが取りやすい環境です」といった魅力的な言葉だけを並べる。これは、医療業界の採用活動でよく見られる光景かもしれません。しかし、もし実際に入職された方が「聞いていた話と少し違うな」と感じてしまったら、どうなるでしょうか。その小さな違和感が、早期の離職や職場全体への不信感につながってしまうことがあります。そうなると、再び人材紹介会社に手数料を支払ったり、求人広告を出し直したりする必要が生じ、結果的に採用にかかる費用は、想定していた以上になってしまう可能性があります。
実際に、日本看護協会が公開している調査によると、2023年度における正規雇用看護職員の離職率は11.3%、新卒ではない、いわゆる既卒で採用された看護師の年度内離職率は16.1%にのぼるとされています。これらの数字は少しずつ改善する傾向にはあるものの、決して小さな数字とは言えない状況です。
この記事では、あえて入職後に「ここは少し大変かもしれません」と感じられやすい部分、例えば「特に忙しくなる時間帯」「お掃除や片付けといった業務」「お問い合わせの電話が多い窓口」「オンコールの実際のところ」「院内の通りにくい動線」などを、先にお見せするという少し変わったアプローチをご紹介します。この目的は、採用の指標となる数字を追いかけることではなく、応募を検討してくださる方々に、職場への深い「理解」と「納得」、そして「安心感」を提供することにあります。
なお、採用活動の基本的な部分から見直したい、あるいは短期間で試せるような新しい取り組みを探しているという場合には、外部の求人サービスとご自身の医療機関の採用窓口をうまくつなぐ仕組みを整えることが効果的な場合があります。必要に応じて、看護師の「お試し勤務」という仕組みを持つ「クーラ」のようなサービスの導入も、選択肢の一つとしてご検討いただくのも良いかもしれません。https://business.cu-ra.net/
背景・課題:求職者が知りたいことと、施設側が見せたい情報の「ズレ」をどう埋めるか
看護師が転職を考える理由と、入職後のギャップの関係
民間の調査会社などが公開しているアンケート記事を参照すると、看護師の方が転職を考える理由として、「業務の負担が大きいこと」「職場の人間関係」「聞いていた情報とのギャリプ」といった点が、しばしば上位に挙げられています。表面的な、聞こえの良い情報だけが並んだ採用ページは、かえって求職者の方の警戒心を強めてしまうことがあります。本当に知りたいと思っている「実際の忙しさ」「当直やオンコールの実態」「身体の清潔を保つケアや採血の担当体制」「電子カルテ入力の具体的なルール」「業務の引継ぎは丁寧に行われるか」といった、現場の細かな情報に届きにくくなってしまうのです。
採用にかかる費用は、この「ギャップ」を埋めるための対価になりやすい
医療業界では人材不足が続いており、特に人材紹介会社を介した採用にかかる費用は、依然として高い水準にあると言われています。あるクリニック向けの解説記事によれば、看護師1名を人材紹介で採用した場合の紹介手数料は、年収の20%から30%が目安とされており、かなりの金額になることが指摘されています。そのため、自院のウェブサイトなどを通じて直接応募を獲得することの重要性が、多くの場で語られています。
つまり、入職後のギャップが原因で離職者が出てしまい、再び募集をかけたり、紹介を依頼したりすることが増えるほど、経営的な負担は大きくなっていきます。今回ご紹介する、あえて「大変な部分」を先に見せるアプローチは、応募者の数をとにかく最大化するというよりも、応募してくださる方の「覚悟」や「理解」の質をそろえ、入職後の早期離職を減らすことで、長期的なコスト削減に貢献する可能性がある考え方です。
実例紹介:小さな現場の「正直さ」が、良い結果につながったパターン
ここでは、抽象的な理論だけでなく、実際に公開されているウェブページや記事の中で、現場の大変さや実態をあえて正直に書いている事例をいくつかご紹介します。大規模な病院よりも、訪問看護ステーションや介護施設、クリニックといった、比較的小さな現場の例を中心に集めてみました。
1) 訪問看護の「大変さ」を先に言葉にして伝える
訪問看護の現場では、ご利用者様のご家族とのコミュニケーション、一人で判断を下さなければならない責任の重さ、そしてオンコール(待機・緊急呼び出し)の負担などが、離職の理由になりやすいと言われています。例えば、神奈川県にある「訪問看護ステーションウィリング」のウェブサイトでは、経験者の声として、やりがいと共に仕事の大変さについて率直に触れています。採用を考えるウェブページでも、単に「オンコールがあります」と書くだけでなく、「オンコールの平均的な頻度」「実際に出動するかどうかの判断基準」「困ったときに相談できるバックアップ体制(例えば、管理者や先輩看護師に電話で相談できる仕組み)」といった点まで具体的に示すことで、入職後の「こんなはずではなかった」というギャップを小さくすることができます。
また、愛知県の「ファミリークリニックこころ」のブログ記事などからも、訪問看護のやりがいと同時に、日々の業務の大変さを隠さずに伝えようとする姿勢がうかがえます。もし、こうした姿勢を採用ページに応用するのであれば、「ある一日の、実際の訪問ルートを示した地図」「雨や雪など天候が悪い日の対応フロー」「訪問に使う車や自転車の点検・管理ルール」といった、具体的な運用の様子がわかる「現物」を写真や図で掲載すると、求職者にとって働く姿をイメージしやすくなるかもしれません。
2) 介護施設の採用では「働き方への不安」に寄り添うことが鍵
介護や福祉の分野における採用活動を解説する情報サイト「地方採用ワークス」の記事では、応募が集まりにくい原因の一つとして、求職者が抱く「過重労働への不安」を挙げています。だからこそ、採用情報のページで、具体的なシフトの組み方、新人スタッフへの教育制度、休憩時間をきちんと確保するためのルールなどを具体的に示し、安心材料として提供することが大切だと述べられています。
また、介護・福祉業界向けのホームページ制作を手がける「らっくうぇぶ」の解説ページでも、職場の実際の雰囲気や、その施設ならではのユニークな取り組みを、自前のウェブサイトで詳細に発信する必要性が強調されています。特に、スタッフの写真や仕事風景の動画、施設見学の案内などを丁寧に整備することは、今回ご提案する「正直な情報開示」と非常に相性の良い取り組みと言えるでしょう。
3) クリニックの採用では「仕事内容を細かく分けて、はっきりと示す」ことが有効
医療機関専門のホームページ制作会社「ヒーローイノベーション」が運営するブログでは、クリニックが採用活動を行う際に、看護師、医療事務といった職種ごとに、仕事内容、給与などの待遇、応募に必要な条件を、丁寧に分かりやすく明記することの重要性が解説されています。この考え方をさらに一歩進めて、「正直な情報開示」を行うのであれば、「午前中の外来が最も混雑する時間帯の、平均的な待ち人数」「採血や注射が多くなる曜日の傾向」「院内の清掃や片付けの分担表」といったことまで、写真やグラフを添えて公開すると、現場の様子が一気に具体的になり、求職者の理解を助けます。
実際に、採用サイトの活用に成功した事例として、ある医療法人が自院のサイト経由での直接応募を増やし、求人媒体への依存度を低下させたと報告されています(メディカルリンク社の事例より)。これは、求職者が知りたい「本音の情報」にアクセスしやすい導線を用意したことが、「この病院で働きたい」という、いわゆる「指名応募」を増やした良い例と言えるでしょう。
4) 等身大の「しんどさ」を伝えても、応募はきちんと来る
看護師向けの情報メディア「レバウェル看護」に掲載された記事では、老年看護の現場で働く看護師が体験する「正直、しんどいと感じる瞬間」について、率直に語るコンテンツが多くの共感を得ています。このように、仕事の「しんどさ」を隠さないことで、むしろその仕事への適性がある人や、課題解決にやりがいを感じる人が集まりやすくなる傾向は、採用のためのウェブページ作りにも十分応用できる考え方です。
こうした「現場の大変な部分」を先に開示する姿勢は、結果として、応募者自身が「自分にこの職場は合っているだろうか」と考える機会、つまり一種の「自己選別(セルフスクリーニング)」を促すことにつながります。これは、最終的にスタッフの定着率を改善することに寄与する可能性があり、業界全体の離職率のデータを鑑みても、理にかなったアプローチと言えるかもしれません。
解決アプローチ:「正直さ」を伝えるためのウェブページの作り方
看護師採用ページに入れたい「正直セクション」の具体例
ピーク時間帯と「混み合いやすい場所」を地図やグラフで見せる
受付、採血室、処置室、レントゲン室の前など、患者様やスタッフの動きが集中して「混み合いやすい」場所を、院内の簡単な動線図で示します。
これに加えて、「混雑時には、受付スタッフが看護師に応援を頼む合図を決めています」「患者様の動線が交差しないよう、床に案内テープを貼っています」といった、具体的な対策も箇条書きで添えます。これを先に見せることで、忙しい状況でも落ち着いて対処できる方や、チームで協力して働くことにやりがいを感じる方にとって、魅力的な情報となり得ます。
身体的な負担が伴う作業は、写真付きで事前に公開する
身体の清潔ケア、嘔吐物の処理、医療器具の洗浄、リネン類の交換といった、体力的・精神的な負担が伴う作業について、その頻度や担当のローテーションを簡単な表にまとめます。また、個人防護具(PPE)がどこに置かれているか、使用後の片付けはどのような手順で行うかなども、文章だけで説明するよりも、実際の写真を掲載したほうが、はるかに伝わりやすくなります。
オンコールや夜間出動の「現実」を、具体的な数字で示す
もしオンコール体制がある場合は、その実態をできるだけ正確に伝えます。
- 看護師一人あたりの、月平均の当番回数
- 電話がかかってきたうち、実際に出動する割合
- 電話での指示だけで対応が完了する割合
- 出動した場合の、移動距離の平均や中央値
特に訪問看護の現場では、「オンコールが大変そう」という声が多く聞かれるため、サポート体制を分かりやすく図で示すことが安心につながります。
電子カルテの運用に関する「細かい決めごと」
- 一日の記録を入力する締め切りの時間
- よく使う言葉を登録しておく、単語登録やショートカット機能の有無
- 夕方の忙しい時間帯に、まとめて入力作業をしても良いか
- 院内で使用できる端末の台数や、院外への持ち出しの可否
- 自宅などから記録を閲覧・入力できる場合のルール
こうした細かいルールを事前に明文化しておくことで、入職後のスムーズな業務遂行を助けます。
新人教育と業務引継ぎの「最初の1ヶ月ロードマップ」
入職してから独り立ちするまでの、具体的なスケジュール感を示します。
- 1週目:先輩スタッフとペアになって、一日の流れを覚える期間
- 2週目:一部の業務を一人で担当し始める、半独り立ちの期間
- 3週目:比較的限定された範囲の業務から、主担当として受け持つ期間
- 4週目:独り立ちする前に、管理者や先輩が最終的な確認を行う期間
さらに、評価の際にどのような点を見るのか(例えば、ミスが起こりやすい手技、患者様への声かけのタイミング、カルテ記録の詳しさなど)をまとめた評価観点表を、PDFファイルなどでダウンロードできるようにしておくと、教育体制の透明性が高まります。こうした「正直な情報開示」は、特に介護施設や訪問看護ステーション、クリニックの採用において、求職者が抱きやすい「過重労働」「職場の雰囲気が分からない」「教育体制が整っているか不安」といった懸念に対する、有効な答えとなり得ます。
ウェブページの構成案(そのまま使える文章の例)
ページの冒頭部分
- 見出しコピーの例:「私たちは、良いことだけを書きません。職場の忙しさも、大変な作業も、すべて先にお見せします。」
- サブコピーの例:「それでも『ここで働きたい』と思ってくれる方と、一緒に仕事がしたいからです。」
- 最初に促すアクション:「まずは見学(30分)から/お試し勤務(半日〜)」
- ポイントは、いきなり「応募」のボタンを押させようとしないことです。まずは短時間の見学や、半日程度の「お試し勤務」へ誘導します。看護師の「お試し勤務」の仕組みを持つクーラのようなサービスを併用すると、この部分の設計がスムーズに進みます。 https://business.cu-ra.net/
大変さが伝わる場所のマップ(写真や簡単な動画で)
- 例:「午前10時頃は、採血の患者様が集中します」「この廊下は、配膳車が通ると少し狭くなります」「リネン類の回収は、午後2時にピークが来ます」
- ここでも、「だから、こうやって工夫しています」という対策ルールをセットで表示することが大切です。単に「大変さ」を紹介するだけで終わらせないようにします。
オンコールや残業に関する「数字」
- 具体的な数字の例:月平均の当番回数、電話後の出動率、電話のみで完了する割合、30分を超える残業が発生した月間回数の分布など。
- メッセージ:「この数字を見て、ご自身の働き方と合うかどうか、じっくりご検討ください。」と、正直な姿勢を伝えます。
1ヶ月の育成ロードマップと評価の観点
- 「ここまでできれば独り立ち」というラインを、あらかじめ示しておくことで、選考過程の透明性を担保します。
- 丁寧な教育体制があることは、介護施設や訪問看護の採用においても、大きな安心材料となります。
「しんどい瞬間」の体験談(先輩スタッフへのインタビュー3本)
- 老年看護、小児外来、訪問看護など、それぞれの部署で働く先輩の「大変さ」を率直に語ってもらいます。成功体験だけでなく、失敗談や、それをどう乗り越えたかという「工夫」の話を添えると、より人間味のある内容になります。
よくある質問(あえて聞きにくい質問への回答)
- 「嘔吐物の処理は、主に誰が担当しますか?」→「日中は手の空いているスタッフが協力し合いますが、基本的には発見者が対応します。夜間は当直看護師と看護補助者の2名で対応するルールです。」
- 「電子カルテの入力は、いつまでに終えなければいけませんか?」→「原則として勤務時間内の18時までです。やむを得ない場合は、上長にチャットツールなどで報告すれば、時間外での入力も可能です。」
- 「オンコールで判断に迷う、怖いと感じた時はどうすれば?」→「すぐに管理者にセカンドコールしてください。一人で判断させません。判断を助けるためのフローチャート(画像リンク)も用意しています。」
見学 → “お試し勤務” → 応募、という三段階の導線
- 「最初は応募ボタンを押させない」という考え方で導線を設計します。短時間でも実際に職場の空気に触れたり、仕事を体験したりした人の方が、入職後の定着率が高い傾向は、多くの現場で実感されているようです。実際に、自院のウェブサイトを通じて直接応募した人の方が、採用の質が高まったという報告事例もあります。
ここまでの骨組みを、今お持ちのウェブサイトに少しずつ足していくだけでも、「正直な採用ページ」への第一歩を踏み出すことができます。もし、これらの実装にご不安があったり、「お試し勤務」の仕組みを外部の力を借りて手軽に導入したいと考えたりする場合には、専門のサービスを利用するのが近道です。https://business.cu-ra.net/
言葉選びとデザインの注意点
- 見出しには、「看護師 採用」「クリニック 求人」「訪問看護 オンコール」「介護施設 採用サイト」といった、求職者が検索する際に打ち込みやすい具体的な言葉を入れることをお勧めします(この記事の見出しの構成も、そのまま参考にしていただけるかと思います)。
- 掲載する写真は、プロが撮った綺麗なものよりも、実際の院内の様子がわかる写真(例えば、実際の動線図、器具棚の様子、個人防護具の置き場所、休憩室の椅子の数など)の方が、信頼性が高まります。フリー素材の多用は、かえって「間に合わせ」の印象を与えてしまう可能性があります。
- 「職場の良い点」と「大変な点」を、同じくらいの情報量で伝えるように心がけます。良い点の説明が厚すぎると、宣伝のように見えてしまい、正直さが伝わりにくくなります。
- 応募の前に、小さな約束を提示することも有効です。例えば、「初回は30分、院内を見学するだけでお帰りいただいて大丈夫です」「無理に話さなくても大丈夫な“無言見学”も歓迎します」といった一言が、心理的なハードルを下げます。
- もし他の求人媒体も利用している場合は、そこからのリンク先を、ただトップページに飛ばすのではなく、この「正直な採用ページ」の該当セクションへ直接リンクさせると、より効果的です。
- 費用の話に触れるのであれば、「一般的に、人材紹介に頼る採用はコストが高くなる傾向があり、自院のウェブサイトで直接応募していただくことの重要性が増しています」といった形で、客観的な事実として淡々と伝えるのが良いでしょう。
まとめ:「正直さ」は応募者を減らすためではなく、「選び合い」の関係を築くための設計です
大変な部分を先にお見せすることは、応募者を減らすための施策ではありません。むしろ、「この大変さを理解した上で、それでもここで働きたい」と思ってくれる方を増やし、結果として現場の満足度と定着率を高めるための取り組みです。
オンコール、特定の時間帯の忙しさ、身体的な負担が伴う作業、教育方針の細かな部分など、入職後のギャップになりやすい要素を、写真や図、具体的な数字で公開してみましょう。訪問看護ステーションや介護施設、クリニックなどの公開情報や解説記事が、こうした情報開示の透明性が持つ価値を裏付けています。
また、自院のウェブサイト経由での直接応募は、求人媒体や人材紹介会社への依存を減らし、採用コスト全体を抑制しやすいという報告もあります。
この取り組みの第一歩は、応募のハードルを「応募」から「見学」や「お試し勤務」へと、小さく分解することです。これにより、応募者の心理的な負担を下げつつ、ご自身で職場との相性を見極めてもらう機会を提供できます。
現場の「生の実態」を先に見せるこのアプローチは、短期的な応募者数の増減に一喜一憂するのではなく、長期的な離職率の低下、すなわち採用と育成にかかる総コストの最適化に効果を発揮すると考えられます。ぜひ、最新の離職率データなども参考にしながら、お互いが納得して選び合えるような採用活動へと、舵を切ってみてはいかがでしょうか。
クーラ導入のご案内(自然に添える形で)
「見学」から「お試し勤務」、そして「正式応募」へとつながる三段階の導線を、今お使いの求人媒体やご自身のホームページに簡単に付け加えたい、とお考えの場合、「クーラ」を導入することで、その設計が非常にスムーズになります。短時間の「お試し」から始めることを前提としたサービスのため、今回ご紹介した「正直な採用ページ」との相性が良いのが特徴です。https://business.cu-ra.net/
外部の求人情報と自院の採用ページを併用したり、短期間のトライアルを前提とした面談フローを組んだりと、「最初からすべてを決めきらない、柔軟な採用」を設計することが可能です。まずは見学や「お試し」を受け入れる枠組み作りだけでも効果が期待できるため、小規模なクリニックや訪問看護ステーションでも導入しやすい仕組みと言えるでしょう。https://business.cu-ra.net/
付録:そのまま使える「正直な採用ページ」の見出しセット
看護師採用で伝えるべき「忙しさ」の中身(時間帯・動線・役割)
- 午前外来の採血ピークは何時ごろ?(曜日と時間帯の混雑グラフ)
- 受付から処置室、そして会計までの「混み合いやすいポイント」を地図で公開します
- 院内の片付け、リネン回収、器具洗浄の頻度と担当ローテーションについて
オンコールや残業の「本当のところ」を数字で示します
- 一人あたりの月間当番回数と、実際の出動率、そして判断基準のフローチャート
- 30分を超える残業の月間発生回数と、翌日のシフトへの配慮ルール
- 夜間に働くスタッフのための安全対策(セカンドコール体制、タクシーチケットの利用、緊急連絡手段)
電子カルテの運用ルールを、入職前にすべてお見せします
- 記録の入力締め切り時間と、記載内容の標準的な詳しさについて
- 院内で使用できる端末の台数、便利な辞書機能やテンプレートの有無
- 新人スタッフが「つまずきやすい」ポイントの記録(よくある入力ミスとその回避策)
最初の30日間のロードマップ(見学からお試し、そして独り立ちまで)
- 独り立ちの判断基準となる「評価観点表」をPDFで公開します
- 先輩たちが語る「しんどい瞬間」とその乗り越え方(実例紹介)
- 困ったとき、助けを求めるための「ヘルプの合図」(チャットの定型文、口頭での合図など)
よくあるご質問(あえて聞きにくいことにもお答えします)
- 身体的な負担のある作業は、誰が、どれくらいの頻度で担当しますか?
- 患者様からのクレーム対応、最初の一次受けの手順はどうなっていますか?
- 見学だけで帰っても失礼にあたりませんか? 「無言見学」は可能ですか?
これらの見出しは、そのまま採用ページの構成として配置することで、求職者が検索する言葉(例:「看護師 採用」「訪問看護 オンコール」「クリニック 求人」など)との関連性も高めやすくなります。様々な解説記事が示すように、情報の「具体性」が、信頼を得るための鍵となります。
最後に
「正直な採用ページ」は、ご自身の職場の弱みをただ晒す行為ではありません。それは、「大変な部分も含めて、それでも一緒にやっていけるだろうか」という点を、応募者と医療機関側が、対等な立場で確かめ合うための設計です。入職後のギャップになりやすい点を先にお見せすることで、誠実な期待値の調整ができ、応募の質とスタッフの定着が、静かに、しかし着実に向上していくことが期待できます。その導入への最も早い道は、まず「見学」と「お試し勤務」の受け皿を用意することです。もしその運用を外部の仕組みに任せたい場合は、「クーラ」も有力な選択肢の一つとなるでしょう。https://business.cu-ra.net/







.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



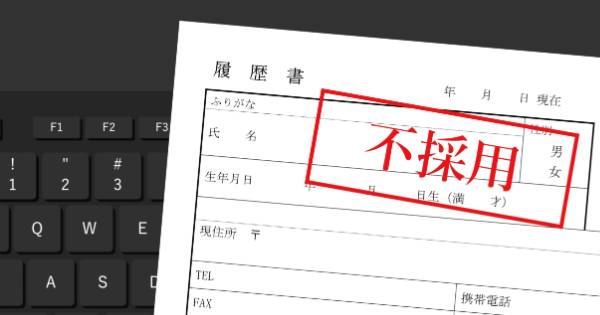
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
