はじめに
採用活動において、内定を出す応募者よりも、不採用となる応募者の方が多くなるのは自然なことです。だからこそ、その大多数を占める方々への不採用連絡の対応が、施設の評判を大きく左右する可能性があります。この記事は、看護師の採用に携わる院長、看護部長、理事長、事務長、人事担当者の皆様に向けて、不採用連絡の際に「最低限これだけは守りたい」というポイントを、分かりやすく整理したものです。各種の法令やガイドラインに触れつつ、特に小規模な病院やクリニック、訪問看護ステーション、介護施設といった現場でも実践しやすい、具体的な進め方や文例を紹介します。
なぜ「不採用連絡の作法」が重要視されるのか——その背景と課題
近年、採用候補者一人ひとりとの向き合い方が、これまで以上に施設の将来を左右する要素となっています。なぜ不採用の連絡方法にまで配慮が求められるようになったのか、その背景にあるいくつかの理由を見ていきましょう。
応募者の体験が、そのまま施設の評判につながる時代
医療や介護の分野は、地域社会との結びつきが強く、利用者やその家族、そして働くスタッフからの「口コミ」が非常に大きな影響力を持つとされています。特に、インターネットやSNSが普及した現代では、個人の体験談が瞬く間に広がる可能性があります。選考過程での不誠実な対応や、ぞんざいな不採用連絡は、応募者に悪い印象を与え、それが思わぬ形で外部に伝わってしまうことも考えられます。
例えば、応募者が転職支援サイトのレビューや個人のSNSで「あのクリニックは連絡がとても遅い」「不採用の連絡すらなかった」といった内容を投稿した場合、それを見た他の求職者が応募をためらう要因になりかねません。
看護職の労働市場は、依然として売り手市場が続いています。日本看護協会が2024年に発表した「2023年 病院看護実態調査」によると、2023年度の正規雇用看護職員の離職率は11.3%と報告されており、人材の確保と定着は多くの施設にとって重要な経営課題です。このような状況下で、一人でも多くの優秀な人材に興味を持ってもらうためには、応募から選考、そして結果連絡に至るまでの一連の体験を、誠実で丁寧なものにしていくことが大切です。
法令や公的なガイドラインの基本線を踏まえる必要性
採用選考は、応募者の適性と能力を基準に行われるのが大原則です。厚生労働省が示す「公正な採用選考の基本」では、採用選考時に配慮すべき事項として、本人に責任のない事柄や、本来自由であるべき事柄(思想・信条など)を採用基準にしないよう呼びかけています。
具体的には、以下のような項目に関する質問は、就職差別につながるおそれがあるとして避けるべきとされています。
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観・生活信条などに関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
これらの項目は、面接時だけでなく、不採用理由を伝える際にも関連してきます。「家庭の状況から、当院のシフトには合わないと判断しました」といった伝え方は、たとえ配慮のつもりであっても、応募者のプライベートな事柄を理由にしたと受け取られかねず、不適切な場合があります。
個人情報の取り扱いを誤らないための知識
応募時に提出される履歴書や職務経歴書は、個人情報保護法のもとで厳格に管理されるべき情報です。これらの書類は、あくまで「採用選考」という目的のために収集したものであり、本人の同意なく他の目的で利用したり、第三者に提供したりすることは原則として認められていません。
例えば、不採用になった応募者の情報を、本人の同意を得ずにグループ内の別の施設に共有したり、将来の欠員募集のために無期限に保管し続けたりすることは、目的外利用にあたる可能性があります。応募書類の保管期間、返却または破棄の方法といった方針は、応募時にあらかじめ明示しておくことが、トラブルを未然に防ぐ上で重要です。
補足として、こうした応募者情報の管理や連絡、帳票の取り扱いに関する業務負担を軽くしたい場合には、適切な管理ポリシーに沿って設計されたツールの活用も一つの方法です。実務の見直しを検討されている場合は、例えば「クーラ(法人向け)」のような採用管理システムの運用設計が参考になるかもしれません。(リンク先: https://business.cu-ra.net/)
具体的な事例紹介——クリニックや小規模施設に見る「よい不採用連絡」の型
理論だけでなく、実際にどのように運用されているのか、公開されている情報からいくつかの事例を見てみましょう。
例1:歯科クリニックにおける端的で誠実な不採用メールの文例
歯科医院向けの採用支援サイトなどでは、書類選考後や面接後の不採用通知に関する文例が紹介されていることがあります。そうした文例に共通する特徴として、以下の4つの要素が挙げられます。
- 選考結果を明確に伝えること
- 応募してくれたことへの感謝を伝えること
- 預かった応募書類の扱い(返却するのか、施設側で責任をもって破棄するのか)を明記すること
- 応募者の今後の活躍を願う言葉で締めくくること
これらの要素は、非常にシンプルですが、応募者に対する誠実な姿勢を示す上で基本となるものです。もちろん、これは歯科領域に限らず、医科クリニックや訪問看護、介護施設などでも広く応用できる考え方です。
例2:応募者データの取り扱い方針を応募時に明記する事例
ある企業の採用サイトでは、採用活動を通じて得た個人情報の取り扱いについて、具体的な方針をプライバシーポリシーとして明記しています。そこには、「取得した個人情報は採用可否の判断という目的のためにのみ利用し、本人の同意なく目的外利用や第三者への提供は行わない」といった主旨が記載されています。さらに、不採用となった応募者の情報については、「一定期間保管した後、適切な方法で破棄する」という規定を設けている例もあります。このように、情報の扱い方をあらかじめ透明化しておくことは、応募者に安心感を与え、施設の信頼性を高めることにつながります。
例3:転職関連サイトの口コミから見る応募者の視点
看護師専門の転職情報サイトや口コミサイトを調べてみると、応募者側からの様々な声を見つけることができます。特に、「面接後の連絡が指定された期日を過ぎても来ない」「不採用の連絡がメール一通だけで、あまりにも定型文すぎる」といった連絡の遅さや誠実さの欠如に対する不満は、多く見受けられるようです。
逆に対応が丁寧で迅速な施設に対しては、たとえ不採用という結果であっても、「今回はご縁がありませんでしたが、丁寧に対応していただき感謝しています」といった好意的な感想が寄せられることもあります。こうした一つひとつの積み重ねが、長期的に見て施設の評判を形作っていくと考えられます。
ここで紹介したのはあくまで公開情報に基づく事例であり、各施設の規模や方針に応じて、最適な方法を調整していくことが大切です。
不採用連絡の基本原則——文面・時刻・連絡手段
では、具体的にどのような点に気をつければよいのでしょうか。ここでは、不採用連絡を行う際の基本的な5つの原則を解説します。
これらの実務を効率化するためには、応募者データに関する同意管理や、複数人への一括通知機能などが役立つ場合があります。運用の土台から見直したい場合は、クーラ(法人向け)のような採用管理システムがどのような機能を提供しているか、その運用事例を確認してみるのも一つの手です。(リンク先: https://business.cu-ra.net/)
そのまま使える「不採用メール」のひな形(医科・歯科・訪問看護・介護で共通化可能)
ここでは、実際に使えるメールの文例を紹介します。施設の状況に合わせて適宜修正してご活用ください。
件名:選考結果のご連絡(〇〇クリニック/看護師採用担当)
〇〇 〇〇 様
〇〇クリニック 採用担当の△△です。この度は、数ある求人の中から当院の看護師募集にご応募いただき、誠にありがとうございました。また、先日はお忙しい中、面接にお越しいただき重ねて御礼申し上げます。
〇〇様にご応募いただいた件につきまして、慎重に選考を進めてまいりましたが、誠に残念ながら、今回はご期待に沿えない結果となりました。貴重なお時間をいただいたにもかかわらず、このようなご連絡となりますことを、大変心苦しく思っております。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、お預かりいたしました応募書類(履歴書・職務経歴書)につきましては、当院の個人情報保護方針に基づき、責任を持って破棄させていただきます。(※返却の場合は「ご登録の住所へ郵送にて返却いたします」などに変更)
誠に勝手ながら、今回いただいた個人情報につきましては、今後の欠員募集や新たな求人が発生した際などに、当院からご連絡をさせていただく目的で、一定期間保管させていただきたく存じます。もし、今後のご連絡を希望されない場合は、お手数ですが本メールへのご返信にてその旨をお知らせください。ご希望されない方にご連絡を差し上げることは一切ございません。
末筆ではございますが、〇〇様の今後のご健勝と、より一層のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
本件に関しましてご不明な点がございましたら、以下の連絡先まで遠慮なくお問い合わせください。
――――――――――――――――〇〇クリニック 採用担当:△△住所:〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇1-2-3電話:03-xxxx-xxxxメール:recruit@xxxx.jp受付時間:平日 9:00–17:30――――――――――――――――
文例のポイント解説
- 「返却/破棄」の部分は、施設の実際の方針に合わせて書き換えてください。どちらの方針でも法的な問題はありませんが、応募時に明示した方法と一貫させることが重要です。
- 将来の案内(タレントプール)に関する記述は、必ず任意で同意を得る形にしてください。「希望されない場合はお知らせください」というオプトアウト形式でも運用は可能ですが、「希望される場合はお知らせください」というオプトイン形式の方が、より丁寧な印象を与えやすいとされています。
SMS・電話で連絡する場合の短いスクリプト
状況に応じて、SMSや電話で連絡する際の文例も用意しておくと便利です。
SMS(メールを送った後の補助連絡として)
「〇〇クリニック採用担当の△△です。先日はご応募ありがとうございました。選考結果のご案内を、本日ご登録のメールアドレスにお送りいたしました。もしメールが届いていない場合は、お手数ですが当院(03-xxxx-xxxx/平日9:00–17:30)までご連絡ください。」
電話(本人が出た場合)
「もしもし、〇〇様のお電話でいらっしゃいますか。わたくし、〇〇クリニックで採用を担当しております△△と申します。今、少しだけお時間よろしいでしょうか。先日の面接、ありがとうございました。本日は、その選考結果のご連絡でお電話いたしました。詳細につきましては、後ほどメールでもお送りいたしますが、今回につきましては、誠に残念ながら見送らせていただく結果となりました。ご応募いただきましたこと、心より感謝申し上げます。」
留守番電話(結論を音声に残さない)
「〇〇様、〇〇クリニック採用担当の△△です。先日の面接、ありがとうございました。選考結果のご案内でお電話いたしました。詳しいお話をさせていただきたく、大変お手数ではございますが、ご都合のよろしい時に、当院の採用担当(03-xxxx-xxxx)まで折り返しのお電話をいただけますでしょうか。受付時間は平日の9時から17時半までとなっております。よろしくお願いいたします。」
これは避けたい、NGになりやすい表現や運用の注意点
良かれと思って行った対応が、かえって応募者に不信感を与えてしまうこともあります。ここでは、特に注意したい点をいくつか挙げます。
- 採否理由として不適切な属性に触れること前述の通り、人格、家族、本籍、信条、健康状態の詳細など、本人の適性・能力と関係のない事柄を示唆するような表現は、書面・口頭を問わず絶対に避けるべきです。例えば、「他にご応募いただいた方の方がお若かったので」「ご家庭の事情を考えると、うちのシフトは難しいかと思いまして」といった言い方は、差別的と受け取られる可能性があります。
- 同意なく応募者情報を他へ共有することたとえ同じ医療法人のグループ内であっても、応募者の情報を本人の同意なく別の施設や部署に共有することは、個人情報の目的外利用にあたる場合があります。「こちらのクリニックでは不採用ですが、グループの〇〇病院で人を探しているので、情報を回しておきますね」といった対応は、必ず本人の許可を得てから行いましょう。
- 連絡する時間帯への配慮を欠くこと連休前夜や深夜、早朝といった時間帯の不採用通知は、受け取った側の心理的な負担を大きくする可能性があります。機械的な一斉送信を行う場合でも、送信予約機能を活用するなどして、時間帯には配慮したいところです。
- 連絡期日を伝えない、または守らないこと(通称:サイレントお祈り)面接の際に「結果は1週間以内にご連絡します」と伝えたにもかかわらず、期日を過ぎても連絡がなかったり、結局何の連絡もないまま終わってしまったりするケースは、応募者の不満に最もつながりやすい対応の一つです。約束した期日は必ず守る、もし遅れる場合はその旨を正直に連絡する、という基本的な姿勢が信頼関係の土台となります。
現場の業務に落とし込むための「3つの解決アプローチ」
日々の業務に追われる中で、こうした丁寧な対応を継続していくのは簡単ではないかもしれません。そこで、現場で無理なく実践するための仕組みづくりのヒントを3つご紹介します。
こうした一連の運用を、手作業ではなく仕組みで解決したいと考える施設にとっては、一括連絡機能や文例管理、候補者ごとの同意状況を管理できるフラグ機能などが備わった採用管理システムの導入が、結果的に近道になることもあります。参考として、クーラ(法人向け)のサイトでどのような運用が可能かを見てみるのもよいでしょう。(リンク先: https://business.cu-ra.net/)
よくある質問(看護師採用の現場視点から)
Q1:不採用の理由を聞かれたら、どこまで答えるべきですか?
A1:応募者の人格や能力そのものを否定するような伝え方は避け、「募集している職務要件との適合度」という枠組みで説明するのが基本です。例えば、「今回は、外来での実務経験が豊富な方を優先して採用することになりました」「夜勤にも対応可能な方を募集しておりましたが、その枠が充足してしまいました」といったように、あくまで今回の募集条件との兼ね合いで説明し、個人属性には触れないようにしましょう。
Q2:応募書類は返却すべきでしょうか?破棄してもよいのでしょうか?
A2:法律上、応募書類の返却は義務付けられていません。したがって、返却・破棄のいずれを選択しても問題ありません。大切なのは、どちらの方針なのかを応募時にあらかじめ明示し、その方針通りに一貫して運用することです。破棄する場合は、シュレッダーにかける、溶解処理するなど、個人情報が漏洩しないよう確実な方法で行う必要があります。
Q3:連絡は電話だけで済ませても構いませんか?
A3:トラブル防止の観点から、原則としてメールや書面など、記録が残る手段で連絡することをお勧めします。電話での連絡は、あくまで補助的な手段と位置づけるのが安全です。特に、留守番電話に不採用という結論をメッセージとして残すのは、応募者の気持ちを考えると避けるべきでしょう。
Q4:看護補助者や短時間パートの応募者でも、対応は同じようにすべきですか?
A4:はい、同じように対応することをお勧めします。雇用形態に関わらず、応募してくれた方一人ひとりに対して誠実に対応するという姿勢を一貫させることが、施設の信頼につながります。パートの応募者が、将来的に常勤での応募を考えてくれる可能性や、地域の口コミに影響を与える可能性も十分に考えられます。
まとめ——「結論は早く、配慮は厚く、記録は正確に」
不採用連絡は、採用活動におけるいわば「お見送り」の作法です。その対応一つで、施設の印象は大きく変わります。最後に、これまでのポイントをまとめます。
- 速さ:面接後、遅くとも72時間以内には結論を伝える。もし難しい場合は、必ず中間連絡を入れる。
- 配慮:連絡する時間帯は平日の日中に。手段は記録の残るメールを基本とし、電話は補助的に使用する。
- 法令遵守:不適切な質問を避け、個人情報は目的の範囲内でのみ利用し、同意管理を徹底する。
- 文面の構成:結論 → 感謝 → 書類の扱い → 今後の案内(同意ベース)→ 問い合わせ窓口、という順番を意識する。
- 運用の仕組み化:院内ルール、ひな形、チェックリスト、記録の徹底で、対応の質を安定させる。
応募者との良好な関係を築くことは、将来的な人材確保、紹介による応募、再応募といった形で、必ず施設の力になります。日々の実務をよりシンプルに、かつ確実に行うための仕組みづくりを検討されている場合は、クーラ(法人向け)のようなツールの活用事例や機能を確認してみてはいかがでしょうか。(リンク先: https://business.cu-ra.net/)
付録:最短で実践するための「不採用連絡チェックリスト」
明日からの実務にすぐ使えるチェックリストです。
参考資料(公開情報)
- 日本看護協会:「2023年 病院看護実態調査」報告書
- 厚生労働省:「公正な採用選考の基本」
- 各都道府県労働局のウェブサイト(不適切な質問の具体例などが掲載されています)
- マイナビ研修サービス:「応募書類の保管期間とは?履歴書の取り扱いについて解説」
- Guppy:「なるほど!デンタル人事」などの医療系求人関連記事
この記事は、一般に公開されている情報をもとに、クリニックや小規模病院、訪問看護、介護施設などの現場で活用しやすいように情報を整理したものです。最終的な運用にあたっては、各施設の就業規則や個人情報保護方針に沿って適切に調整してください。

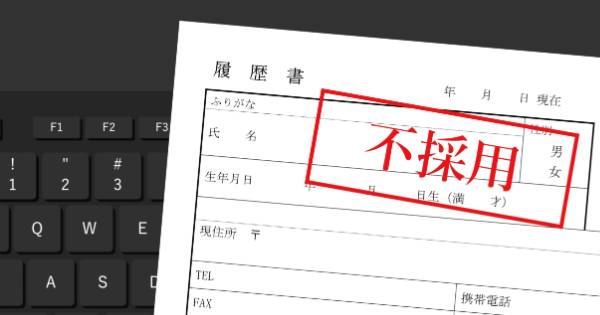





.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
