週に1日や2日、あるいは半日といった短時間勤務の看護師パートは、クリニックや病院のシフトの隙間を埋めたり、特定の忙しい時間帯の対応力を高めたりする上で、有効な選択肢の一つとされています。一方で、採用や管理に携わる方々からは、「短時間勤務で採算は合うのだろうか」「社会保険料の負担や教育にかかる時間まで考慮すると、かえってコストが増えるのではないか」といった懸念の声も聞かれることがあります。
この記事では、クリニックや小規模な病院で実際に活用できる、短時間パート看護師の損益分岐点の考え方と、現場で円滑に業務を回していくための具体的な方法について、公開されているデータや実際の求人事例などを参考にしながら、現実的な視点で解説を進めていきます。
先に結論の要点をお伝えすると、週1〜2日・半日勤務のパート看護師の活用は、いくつかのポイントを押さえることで、採算性を確保しやすくなると考えられます。具体的には、
- 患者さんが最も集中する時間帯を見極め、その時間に合わせて勤務してもらうこと
- 担当してもらう業務範囲をあらかじめ絞り込み、教育にかかる負担を最小限に抑える仕組みを整えること
- 社会保険の加入条件や扶養内で働きたいという希望について、施設側が正確な情報を提供し、誤解なく案内することこの3点が重要になります。記事の途中では、具体的な数値を交えたシミュレーションや、現場での運用事例も紹介していきます。
なお、もし「院内の繁忙な時間帯の可視化」や「短時間パートの勤務を前提とした業務フローの再設計」などを体系的に進めたいとお考えの場合は、私たちが提供している看護人材プラットフォームの事業者向け案内がお役に立てるかもしれません。ご興味がありましたら、https://business.cu-ra.net/ より詳細をご確認ください。ご登録やご相談は無料です。
短時間パートが活きる「時間」と「業務」を特定する
短時間パートの方に最大限の力を発揮してもらうためには、まず「いつ」「何の業務を」担当してもらうかを戦略的に特定することが不可欠です。漠然と人手を増やすのではなく、最も効果的な一点にリソースを集中させるイメージです。
外来の繁忙帯に合わせる(午前ラッシュ/夕方ラッシュ)
多くのクリニックや外来部門では、一日のうちで患者さんが集中する時間帯、いわゆる「ラッシュ」が存在します。例えば、午前診の受付開始から、採血や点滴、処置が次々と発生する時間帯。あるいは、学校や仕事が終わる夕方の時間帯などです。
このようなピークタイムに、短時間パートの看護師に1コマ(例えば3〜4時間)入ってもらうだけでも、患者さんの待ち時間を大きく減らす効果が期待できます。待ち時間の短縮は、患者満足度の向上に直結するだけでなく、結果として一日に対応できる患者数、つまり処置の回転数を高めることにも繋がります。
実際に、看護師の勤務シフトは、もともと「日勤」「準夜勤」「夜勤」といったように、時間帯で役割を明確に分けるのが一般的な運用です。そのため、特定の時間帯に特定の業務を集中させるという考え方は、看護業務の特性とも相性が良いと言えるでしょう。ある医療機関向けのコンサルティングサービスを提供する企業の情報によれば、多くのクリニックが午前中のピークタイム対策としてパート採用を検討しているというデータも見られます。
「ボトルネック業務」をパート帯にまとめる
院内の業務フロー全体を見渡したときに、流れが滞りがちな部分、いわゆる「ボトルネック」となっている業務はないでしょうか。多くの場合、医師の診察そのものがボトルネックになることもありますが、その前後の工程が滞ることで、結果的に医師の時間を奪っているケースも少なくありません。
例えば、採血、点滴の準備、処置の介助、患者さんへの各種説明、診察前の簡単な問診(トリアージの前工程)といった業務は、看護師が担うことで医師がより診察に集中できる環境を作ることができます。これらの業務を短時間パートの方の勤務時間帯に意図的に集約させることで、施設全体の対応能力、ひいては売上の向上が見えやすくなります。
具体的な例としては、「午前9:00から12:30の勤務で、主な担当は採血、処置、そして患者さんへの説明です」というように、採用時点から役割を明確に限定することが挙げられます。こうすることで、教える側もその範囲に集中して指導すればよく、新しく入った方も比較的早く業務に慣れ、戦力化しやすくなるという利点があります。
損益分岐の考え方:式→目安→注意点
短時間パートの採用が経営的にプラスに働くかどうかを判断するために、簡単な損益分岐の考え方を整理しておきましょう。複雑な会計知識は不要で、あくまで現場で使えるシンプルな計算で考えていきます。
基本的な考え方
短時間パートの看護師に1コマ(仮に3.5時間とします)勤務してもらうことで、どれくらいの利益が増え、どれくらいの費用がかかるのかを比較します。
この式を満たすことが、採算が取れる一つの目安となります。特に重要なのは「増分粗利」をいかにして生み出すか、そして「間接コスト」をいかにして抑えるか、という点です。
時給の目安と仮置き
人件費を計算する上で基本となる時給は、地域や業務内容によって幅があります。公表されている複数の求人情報サイトのデータを参考にすると、看護師(正看護師)のパート時給は、全国平均で1,600円〜2,200円程度の範囲に分布しているようです。特に東京都などの都市部では平均時給が1,800円前後から2,000円を超える募集も多く見られます。例えば、大手看護師専門の求人サイト「看護roo!」などで実際の募集内容を確認すると、クリニックの外来補助や処置のサポート業務で、時給2,000円前後の設定が散見されます。
社会保険ラインの扱い
短時間パートを雇用する上で、社会保険の加入義務は必ず理解しておくべき重要なポイントです。「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金が8.8万円以上」といった複数の条件を満たす場合、パートタイマーであっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要となり、保険料の約半分を事業主が負担することになります。
この制度をめぐっては、働き手である看護師側にも「扶養の範囲内で働きたい」という希望を持つ方が少なくありません。そのため、募集や面接の段階から、施設側として2つの選択肢を用意しておくのが現実的な対応とされています。
- 扶養内希望者向けの「週20時間未満」の勤務枠を設ける。
- 戦力としてより長い時間勤務してくれる方には、社会保険加入を前提とした条件を提示し、安定したシフトの中核を担ってもらう。
特に、2016年以降、社会保険の適用対象が段階的に拡大されてきた経緯があり、今後も従業員数が少ない事業所への適用が広がる可能性があります。人事担当者は、厚生労働省が公表している最新の情報を確認し、応募者からの質問に対して正確に説明できるように準備しておくことが、後のトラブルを避ける上で大切です。
よくある落とし穴
短時間パートの活用がうまくいかないケースには、いくつかの共通したパターンが見られます。
- 「なんとなく午前中が忙しそうだから」と、データに基づかずにパートを入れてしまう。→ これでは、パートの方が勤務しても期待したほど患者さんの回転数が上がらず、人件費だけがかさんでしまう可能性があります。まずは、曜日別・時間帯別の患者数や待ち時間を可視化し、最も効果的な時間帯を見極めることが重要です。
- 短時間パートの方にも、常勤と同じように全ての業務を教えようとしてしまう。→ 限られた時間で働く方に、広範囲の業務を習得してもらうのは非効率的です。前述の通り、担当業務を限定し、段階的に業務範囲を広げていく方が、教える側の負担も少なく、早期の戦力化につながります。
- とにかく早く人を集めたい一心で、相場より高い時給を提示して求人広告のクリック単価(CPC)を上げてしまう。→ 高い時給で応募は集まるかもしれませんが、現場の受け入れ態勢が整っていないと、採用してもすぐに活躍してもらえず、人件費だけが先行してしまいます。求人媒体のクリック課金広告は、一般的に入札制で表示順位などが決まるため、単価を上げるよりも、まずは募集原稿の中身を充実させ、業務内容や働きやすさの魅力を具体的に伝えることで、費用対効果の高い採用を目指すのが賢明です。
事例で考える:求人市場と現場運用のヒント
次に、実際のデータや市場の動向から、短時間パート活用のヒントを探っていきましょう。
求人プールの実感値
実際に大手求人情報サイトで検索してみると、「看護師 パート 週1日」「午前のみ」といった条件での募集が、特に都市部を中心に相当数存在することがわかります。「Indeed」や「ジョブメドレー」といったプラットフォームで東京都内の求人を見てみると、「週1日からOK」「扶養内勤務を考慮」「半日勤務可」といった文言を掲げるクリニックや病院の募集が多数見つかります。
これは、子育て中の方や、一度現場を離れてブランクがある方、あるいは他の仕事と両立したい方など、求職者側に「短い時間で働きたい」という強いニーズがあることの表れです。つまり、施設側が週1〜2日・短時間の受け皿を柔軟に用意できれば、それだけ多くの応募者と出会える可能性が高まる、ということを示唆しています。
離職率データの示唆
公益社団法人日本看護協会が毎年公表している「病院看護実態調査」によると、正規雇用看護職員の離職率は、近年わずかに改善傾向にあるとされていますが、依然として一定数の離職者が発生している状況です。特に、一人の常勤スタッフが抜けた際の現場へのダメージは小さくありません。
短時間パートをうまく活用することは、こうした常勤スタッフの負担を軽減する効果も期待できます。例えば、残業が発生しがちなピークタイムの業務をパートの方に分担してもらうことで、常勤スタッフの過重労働を防ぎ、働きやすい職場環境を維持することにつながります。これは、結果的に常勤スタッフの離職を防ぎ、採用難の時代における人材確保という点でも間接的に貢献する可能性があります。
具体的な損益シミュレーション(外来クリニック想定)
では、ここまでの情報を基に、具体的な数値を当てはめて簡単なシミュレーションをしてみましょう。あくまで一つのモデルケースとしてお考えください。
前提条件(例):
- 平日の午前(9:00〜12:30、実働3.5時間)に、看護師パートを1名追加で配置する。
- 時給は2,000円、交通費は1日あたり500円とする。
- 担当業務は、採血、点滴、患者説明、院内の動線整理に限定する。
- このパート看護師の配置により、「採血+処置+説明」の一連の流れがスムーズになり、1時間あたりに対応できる患者数が平均して3件増加すると仮定する。
- 患者1件あたりの実質的な粗利(保険点数や自費診療の売上から、薬剤や材料費などを差し引いた、おおよその利益)を1,200円と仮置きする。
計算:
- 売上側の増加分(増分粗利)
- 3件/時 × 3.5時間 × 1,200円/件 = 12,600円
- この勤務によって、1コマあたり約12,600円の粗利が上積みされるという見立てです。
- 費用側の増加分
- 人件費(時給): 2,000円/時 × 3.5時間 = 7,000円
- 交通費: 500円
- 間接コスト(教育・引継ぎなど): 最初のうちは負担が重いですが、数ヶ月で慣れていくことを考慮し、1コマあたり500円〜800円相当と見積もります。
- 費用の合計 ≒ 8,000円 〜 8,300円
損益:
- 12,600円(売上増) - 8,300円(費用増) = +4,300円
この前提であれば、パート看護師に1コマ入ってもらうことで、4,000円程度の利益的な余剰が生まれる計算になります。もちろん、この数字は地域や診療科、設定する業務内容によって大きく変動します。しかし、「患者が集中するラッシュの時間帯に配置する」「医薬品などの材料ロスが少ない業務を中心に担当してもらう」「患者さんへの説明や会計前の待ち時間を短縮する」といった、回転率と満足度を同時に高められる業務に絞り込むことで、採算性を確保できる可能性は十分にあると言えるでしょう。
※ なお、このシミュレーションは社会保険料の事業主負担を含んでいません。週20時間以上や月額賃金の要件を満たし、社会保険への加入が前提となるような長時間のパート勤務に移行する場合は、事業主負担分(およそ賃金の15%程度)を費用に加味して再計算する必要があります。最新の保険料率や適用要件は、厚生労働省や年金事務所の案内をご確認ください。
週1〜2日パートを円滑に「回す」ための設計:5つの型
採用した短時間パートの方にスムーズに現場に溶け込んでもらい、継続して活躍してもらうためには、受け入れる側の「設計」が非常に重要になります。ここでは、具体的な5つの方法をご紹介します。
募集原稿と露出:クリック単価よりも「中身」で惹きつける
良い人材と出会うためには、募集原稿の工夫と、それを適切な場所に届けるための考え方が重要です。
原稿の核となる文言
求職者が最初に目にするのは、勤務条件に関するキーワードです。以下のような、働きやすさを具体的に伝える言葉を明確に記載することが効果的とされています。
- 「週1日から勤務OK/半日だけの勤務も可能です」
- 「扶養範囲内での勤務、歓迎します」
- 「担当業務を限定:採血、簡単な処置準備、患者説明が中心です」
- 「ブランクのある方も歓迎します/丁寧な研修とマニュアルがあります」
- 「勤務曜日は固定、または相談に応じます。お子様の学校行事なども配慮します」
前述の通り、実際の求人市場には「週1日・半日OK」の募集は多く存在します。そのため、これらのキーワードは、求職者が検索する際の最初のフィルターとして機能し、記載がないだけで候補から外れてしまう可能性さえあります。
露出の考え方
多くのオンライン求人媒体では、広告の表示順位などがクリック単価(CPC)の入札によって決まる仕組みが採用されています。しかし、やみくもに単価を上げて露出を増やすことだけが正解ではありません。
それよりも、募集原稿の中身を充実させ、業務範囲の具体性、勤務時間の柔軟性、教育体制の手厚さ、院内の動線の良さといった「働きやすさ」を丁寧に伝えることで、広告がクリックされた後の応募率を高める方が、結果的に一人あたりの採用コストを抑えることにつながりやすいと言われています。求人サービス「エンゲージ」などの媒体情報によれば、クリック課金は幅広い単価で設定が可能と案内されており、まずは控えめな単価で試し、原稿の改善を優先するアプローチも考えられます。
教育・マニュアル:「3点セット」で立ち上がりを早める
短時間パートの方は、常勤スタッフと比べて勤務時間が短く、院内にいる時間も限られます。だからこそ、短時間で効率的に情報をキャッチアップできる仕組みが不可欠です。そのために、「3点セット」のツールを用意することをお勧めします。
短時間パートの方にとって、出勤した「その日」の情報が何よりも重要です。事前にマニュアルのテンプレートを渡しておき、初日の勤務は「見学30分+実働3.5時間」といった流れにすると、心理的な不安を和らげる効果も期待できます。
なお、こうした教育用のマニュアル雛形や、当日の情報共有メモのテンプレートについては、私たちがご提供している事業者向けのページでも具体的な事例として紹介しています。導入に関するご相談は、https://business.cu-ra.net/ からいつでもお気軽にお寄せください。
社会保険・扶養の説明を「誤解なく」伝える
採用面接や説明会の場で、応募者から最も多く寄せられる質問の一つが、社会保険や扶養に関するものです。「月にいくらまでなら扶養を外れませんか」「週に何時間から社会保険に入ることになりますか」といった内容は、働き方を決める上で非常に重要な要素です。
先にも触れましたが、現在の制度では、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの要件を満たす場合に加入対象となります。施設側がこれらの条件を丁寧に説明し、応募者の希望(扶養内で働きたいのか、社会保険に加入して安定して働きたいのか)に合わせて、複数のシフトパターンを具体的に提示できると、認識のズレによる採用後の離脱を防ぐことができます。厚生労働省のウェブサイトには、パート・アルバイトの社会保険適用拡大に関する詳しいリーフレットなどが掲載されており、こうした公的な資料を基に説明するのも良い方法です。
品質と安全:短時間パートでも「ここだけは外さない」という共通認識
短時間パートは、現場の業務を「省力化」し、効率を高めるための一つの手段ですが、医療の根幹である品質と安全が損なわれては本末転倒です。だからこそ、パート、常勤といった立場に関わらず、全員が守るべき最低限のルールを明確にしておく必要があります。
- 患者さんの取り違え防止(名前のフルネームでの声出し確認、手首のバンドやラベルとの二重確認、指差し呼称など)
- 血液曝露や針刺し事故を防止するための手順と、万が一発生した場合の報告・対応フローの共有(当日の変更点メモに緊急連絡先も明記しておく)
- 患者さんへの説明内容の標準化(重要なポイントをまとめた説明シートを印刷して渡し、要点をチェックしながら説明する)
- 判断に迷った際の相談先リスト(この内容は医師に、この内容は受付に、と問い合わせ先を明確にした一覧表を用意する)
品質や安全に関する基本的なルールは、常勤スタッフが中心となって守り、維持していくべきものです。その上で、短時間パートの方がチームに合流した際に、迷わずそのルールを守れるような「道筋」を付けておくことが、受け入れ側の重要な役割と言えるでしょう。
まとめ:損益分岐は「時間を当てる×教育を絞る×制度を説明」で乗り越えられる
この記事では、週1〜2日・短時間パートの看護師を雇用する際の損益分岐の考え方と、現場での具体的な活かし方について解説してきました。最後に、要点を改めて整理します。
- 施設の最も繁忙な時間帯に、半日単位の勤務を戦略的に配置することで、患者さんの回転率向上を売上の増加として捉えることが可能です。
- 担当してもらう業務をあらかじめ限定し、段階的に業務範囲を広げることで、教育にかかるコストと時間を最小限に抑えられます。
- 週20時間という社会保険加入の一つの目安や、月額賃金の要件などを、施設側が正確に理解し、応募者に誤解なく伝えることが信頼関係の構築につながります。
- 募集の際は「週1日OK」「半日可」「扶養内歓迎」といったキーワードを明確に打ち出し、広告単価の競争よりも、原稿の具体性で応募者の関心を引くことを目指しましょう。
- 短時間パートの活用は、直接的な戦力となるだけでなく、常勤スタッフの残業時間を減らし、負担を軽減することで、離職抑制にも間接的に貢献する可能性があります。
これらのポイントを一つひとつ丁寧に積み上げていくことで、週1〜2日・短時間勤務のパート看護師の活用は、施設にとって十分に採算の合う、価値ある選択肢となり得ます。
看護人材プラットフォーム「クーラ」のご案内
- 短時間パートの勤務を前提とした、「業務を限定した求人原稿」のテンプレートや、現場の動線設計の雛形などをまとめてご確認・ご相談いただけます。詳しくは
https://business.cu-ra.net/をご覧ください。 - 「午前中だけ」「週に1日だけ」といった希望を持つ看護師の方々にも届きやすい求人の出し方や、勤務初日の教育で使えるチェックリストなどもご紹介しています。
参考にした公開情報(例)
- 看護職の離職率の動向について:公益社団法人日本看護協会 「2023年 病院看護・外来看護実態調査」
- 求人広告のクリック課金(CPC)の仕組みについて:エン・ジャパン株式会社「エンゲージ」などのサービスガイド
- パート・アルバイトの社会保険適用拡大について:厚生労働省ウェブサイト「社会保険適用拡大特設サイト」






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)





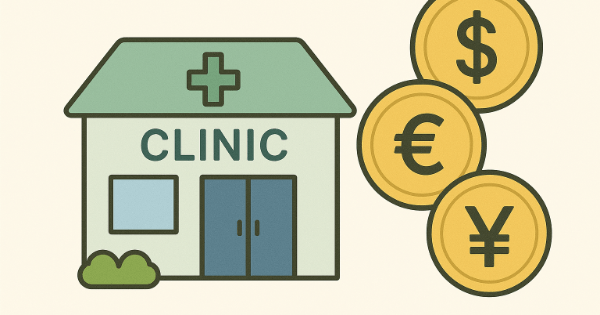
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
