はじめに:固定曜日シフトは「人が集まる仕組み」になります
子育てやご家族の介護、あるいは専門性を活かした副業など、多様なライフスタイルと仕事を両立したいと考える看護師の方は少なくありません。現場の管理者様にとっても、そうした方々が働きやすい環境を整えることは、人材確保の重要な鍵となります。
しかし、毎週決まった曜日に勤務する「固定曜日シフト」に対して、「毎月のシフト調整が逆に難しくなるのではないか」「特定の曜日だけ人手が足りなくなったらどうしよう」といった懸念から、導入に慎重な現場もあるかもしれません。
この記事では、固定曜日シフトは適切な「運用の仕組み」さえ整えれば、むしろ離職の予防と採用力の向上の両方に貢献しうる、という考え方をご紹介します。具体的な医療機関の事例を交えながら、導入から運用、そしてリスク管理の要点を、順を追って解説していきます。
働き手が「ここでなら長く続けられそう」と感じ、結果として人材が集まり定着する。そんな好循環を生み出すための一つの選択肢として、固定曜日シフトの可能性について、一緒に考えていければと思います。
ここで、固定曜日シフトに対する一般的なイメージと、適切な運用によって得られる実態について、簡単な図で整理してみましょう。
背景と課題:なぜ固定曜日シフトは難しく見えるのでしょうか
「硬直的で穴が埋まらない」という誤解について
固定曜日シフトを検討する際、まず懸念されるのが「いつも同じ曜日・同じ時間帯に欠員リスクを抱えることになる」という点です。確かに、特定の曜日の担当者が急に休むことになれば、その穴を埋めるのは大変だ、と感じられるかもしれません。
しかし、見方を変えると、これは「どの曜日に、どれくらいの人手が必要か」をあらかじめ計画しやすくなる、ということでもあります。
例えば、月曜の午前は新患が多くて忙しい、木曜の午後は手術や検査が集中する、といったように、業務量には曜日ごとの波があるのが一般的です。この波に合わせて、あらかじめ曜日ごとに必要な人員数やスキルを設計し直すことができれば、固定曜日シフトはむしろ「計画的で読みやすい人員配置」の土台となります。
業務の流れを曜日ごとに整理し、平準化できる作業は他の曜日に移す、といった工夫をすることで、特定の曜日に過度な負担がかかるのを防ぐことも可能です。問題は固定曜日シフトそのものではなく、業務の繁閑に合わせた人員配置計画が、シフト制度と連動しているかどうかにある、と考えられます。
「生活の安定」が応募を呼ぶという事実
看護職は、その専門性の高さにもかかわらず、勤務の不規則さが離職の一因となることがある、と指摘されています。特に育児中の方にとっては、子どもの保育園の送迎時間や学校行事など、決まった時間に動かなければならない場面が多くあります。希望休制度だけでは、毎月シフトが確定するまで予定が立てられず、心理的な負担を感じるケースも少なくありません。
固定曜日シフトは、この「予定の立てづらさ」という悩みを直接的に解消する働き方です。働く曜日と時間が決まっていることで、生活の見通しが立ちやすくなります。これは、子どもの送迎時間を確保したい方、家族の介護で定期的な通院の付き添いが必要な方、あるいは別の仕事(副業)との両立を目指す方にとって、非常に魅力的な条件となります。
実際に、看護師専門の転職支援サービスなどでも、「曜日固定」の求人は、家庭の事情を抱える看護師からの需要が高い条件の一つとして紹介されています。働く側が「この曜日なら働ける」と明確に意思表示できることは、応募へのハードルを下げ、これまでアプローチできなかった層からの応募を掘り起こすきっかけにもなり得ます。
(もし、固定曜日で働きたいパート看護師の募集や、短期間の「お試し勤務」から長期雇用へとつなげる仕組みづくりにご関心があれば、看護師のマッチングサービスであるクーラが、相性の良い選択肢の一つになるかもしれません。→ https://business.cu-ra.net/)
実例紹介:医療現場における曜日ごとの役割分担と柔軟な働き方
固定曜日シフトは、決して机上の空論ではありません。すでに多くの医療機関で、多様な働き方を支える仕組みとして導入・運用されています。ここでは、公的な資料などで紹介されている具体的な事例をいくつか見ていきましょう。
複数の職員で一人の常勤業務を分担する「ワークシェアリング」
厚生労働省がまとめた「医療機関の勤務環境改善の好事例」の中では、一人の常勤職員が行っていた業務を、複数の短時間勤務職員で分担する「ワークシェアリング」という考え方が紹介されています。
例えば、神奈川県川崎市にある社会医療法人財団石心会 川崎幸病院では、多様な勤務形態の導入に積極的に取り組んでいます。その一環として、常勤職員1名分の業務を、短時間勤務の職員2名で分担するような働き方が考えられます。具体的には、「Aさんは月曜日と火曜日を担当し、Bさんが水・木・金曜日を担当する」といった曜日ごとの分担です。
このように曜日で担当を区切ることで、それぞれの職員は固定曜日で勤務することが可能になります。さらに、出勤時間を30分や60分ずらす「短時間差出勤」といった制度と組み合わせることで、朝の忙しい時間帯だけ人員を厚くするなど、より柔軟な配置が実現できます。この事例から学べるのは、「曜日ごとに業務と責任の範囲を明確に区切る」という設計が、固定曜日シフトを機能させる上での核になるということです。
クリニックにおける「定休日+固定休日」の運用
外来診療が中心のクリニックでは、「日曜・祝日+木曜日」のように、特定の曜日を定休日とする運営形態が広く浸透しています。この「曜日の型」を、スタッフの勤務体系にも応用している事例が見られます。
例えば、あるクリニックでは、週休2日に加えて、さらに特定の曜日を固定休とする「週休3日制」に近い働き方や、午前のみ・午後のみといった短時間勤務を積極的に導入し、人材確保につなげている取り組みがあります。
「休みの曜日」が固定されていることは、働く側にとって「出勤する曜日」が固定されることと表裏一体です。クリニックのような比較的小規模な組織では、スタッフ一人ひとりの希望と、診療の繁閑を組み合わせた「曜日の型」を作りやすいという利点があります。これにより、子育て世代の看護師などが、家庭と両立しながら働き続けられる環境を提供しているのです。
訪問看護における固定曜日パートの活用
訪問看護の分野では、パートタイム職員の勤務形態として、週に2〜3日、決まった曜日に勤務する形が一般的な選択肢の一つとして紹介されています。例えば、「毎週火曜日と金曜日の9時から16時まで」といった働き方です。
この背景には、訪問看護特有の事情があります。利用者様へのケアは、継続性が重要です。毎週同じ曜日に同じ看護師が訪問することで、利用者様との信頼関係が築きやすくなり、状態の変化にも気づきやすくなります。
また、訪問ルートも曜日ごとに固定化できるため、移動の効率が上がり、業務計画が立てやすくなるという運営上のメリットもあります。このように、利用者様のケアの質を安定させ、働く側の家庭の事情にも配聞する、という二つの目的を両立させる仕組みとして、固定曜日シフトが有効に機能している事例です。
週休3日制や短時間勤務制度との組み合わせ
近年、働き方改革の流れの中で注目されている「週休3日制」や「短時間正社員制度」も、固定曜日シフトと非常に相性の良い制度です。
例えば、東京都八王子市にある医療法人社団KNI 北原国際病院では、看護師を含む職員を対象とした多様な勤務形態を導入しています。その中には、1日の労働時間を延ばす代わりに休日を増やす「変形労働時間制」を活用した週休3日制などが含まれます。こうした制度では、出勤する曜日を固定しやすいため、職員はプライベートの予定を長期的に計画できます。
これらの事例が示しているのは、「固定曜日=硬直的で融通が利かない」という考え方ではなく、「曜日ごとに責任と業務量を可視化し、計画的に人員を配置する手法」として捉えることの重要性です。曜日という明確な区切りがあるからこそ、かえって柔軟な働き方を設計しやすくなる、という側面があるのです。
(固定曜日の募集要件を作成したり、求人票のテンプレートを準備したりする作業は、クーラの導入支援サービスをご利用いただくことで、短時間で効率的に整備することが可能です。→ https://business.cu-ra.net/)
解決アプローチ:固定曜日シフトを機能させるための具体的な設計方法
固定曜日シフトを円滑に導入し、持続可能な制度として定着させるためには、いくつかの設計上のポイントがあります。ここでは、その具体的なステップを8つに分けて解説します。
1. 需要の「曜日プロファイル」を可視化する
まず最初に行うべきは、自院の業務量が曜日や時間帯によってどのように変動しているかを、客観的なデータで把握することです。感覚的に「月曜は混む」と理解しているだけではなく、具体的な数値で可視化します。
- 来院・在宅需要の曜日別データの洗い出し:外来であれば、曜日ごとの来院患者数、新患と再診の比率。病棟であれば、入退院や手術の件数。訪問看護であれば、訪問件数や移動距離など、曜日による業務負荷の偏りを数値で確認します。
- 業務の分解と必要なスキルの棚卸し:看護業務を、採血、点滴、検査介助、患者説明、記録、物品管理といった具体的な作業(タスク)に分解します。そして、それぞれの作業について、どの曜日のどの時間帯に、どれくらいの人数と、どのようなスキル(例:採血の経験が豊富な人、特定の機器を扱える人など)が必要かを整理します。
この作業によって、「曜日×時間帯×必要スキル(人数)」を一覧にした表が完成します。これは、人員配置を考える上での設計図となります。この表の上に、現在の常勤スタッフの配置を重ねてみることで、どの曜日のどの時間帯に人手が不足しているのか、つまり、どのような条件で固定曜日パートの募集をかければよいのかが、一目でわかるようになります。
2. 「曜日ごとの役割」を定義する
次に、可視化した需要に基づいて、「曜日ごとの役割(曜日ロール)」を明確に定義します。これは、単に「月曜担当」とするのではなく、その役割が担う具体的な業務内容を定めることを意味します。
- 役割に名前をつける:例えば、「火曜午前・採血専門担当」や「金曜午後・処置室および物品管理担当」のように、業務内容がイメージできる名前をつけます。
- 業務範囲と終了時の作業を明文化する:その役割が担当する業務の範囲(どこからどこまでか)と、一日の業務の終わりに必ず行うべきこと(次の担当者への引き継ぎ内容、記録の締め切り、物品の補充ルールなど)を文章にしておきます。
- 必要な経験やスキルを明確にする:その役割を担うために必要な経験の目安(例:1日あたり30件程度の採血に対応できる)や、特定の機器の操作スキルなどを具体的に示します。これにより、募集時のミスマッチを防ぎ、採用後の教育計画も立てやすくなります。
ここでのポイントは、「人に仕事をつける」のではなく、「定義された役割(仕事)に、適した人をつける」という考え方です。役割が明確であれば、担当者が変わっても業務の質が維持しやすく、交代や代替もスムーズに行えます。
3. 「二重のゆとり」をあらかじめ確保する
計画通りに物事が進まないのが、医療現場の常です。予期せぬ緊急入院や、患者様の状態の急変などに対応するためには、シフトに「ゆとり(バッファ)」を組み込んでおくことが不可欠です。
- 曜日ごとのゆとり:特に混雑が予想される曜日や時間帯には、理論上の必要人数ぴったりではなく、少し手厚めに人員を配置します。常勤スタッフに加えて固定曜日パートに入ってもらうことで、ピーク時の負荷を軽減します。
- 人員としてのゆとり:各曜日のシフトの中に、特定の業務に固定されない「浮動枠」のような役割を1枠設けることを検討します。この担当者は、急な欠員が出た際の補充要員となったり、普段は手が回らない業務改善のための作業(マニュアル作成、物品整理など)に取り組んだりすることができます。学生実習の指導担当など、日によって発生する業務に対応する役割としても機能します。
目安として、最も忙しい時間帯の必要人数に対して、プラス0.5〜1.0人分(短時間勤務なども活用)の「吸収枠」を設けておくと、現場の心理的な安心感につながり、突発的な事態にも対応しやすくなります。
4. 欠員時の「代替ルート」を最初から組み込んでおく
固定曜日シフトを運用する上で最も重要なのが、欠員発生時の対応策をあらかじめ複数用意しておくことです。誰かが休んだ時に、その場しのぎで対応するのではなく、決められた手順に従って動けるようにしておきます。
- 代理担当者を指名しておく:同じ役割を担う人を複数育成し、「火曜担当のAさんが休んだ場合は、同じ業務ができる木曜担当のBさんが第一候補」というように、あらかじめ代理の順序を決めておきます。
- 緊急時の連絡・判断ルールを決める:どのような状況になったら、誰(医師や看護師長など)に、どのタイミングで連絡・相談すべきかを明確にします。また、どうしても人手が足りない場合に、どの対応を優先するかの順位も決めておきます(例:1.外部の応援スタッフを探す、2.翌週以降に業務を分散させる、3.一部の予約を調整する)。
- 相互補完の状況を一覧にする:誰がどの曜日の役割を代替できるのかを一覧表にして、定期的に更新します。これにより、いざという時にスムーズな協力体制が築けます。
5. 「固定シフト×短時間勤務」を積極的に組み合わせる
固定曜日シフトは、フルタイム勤務だけでなく、短時間勤務と組み合わせることで、さらに効果を発揮します。
- 保育園の送り迎えなどに合わせた時間設定:例えば、「10時から16時まで」といった勤務時間は、子育て中の方にとって非常に働きやすい選択肢です。中抜けしがちな時間帯をピンポイントで補強できるため、現場にとってもメリットがあります。
- 業務を切り出して短時間化する:物品の補充、リネンの交換、翌日の準備など、必ずしも就業時間全般にわたって必要ではないものの、誰かがやらなければならない業務は多くあります。こうした業務を切り出して、2〜3時間の短時間・固定曜日の役割として募集することも有効です。
- 午前のみ・午後のみの組み合わせ:「午前担当」と「午後担当」のパート職員を組み合わせることで、常勤スタッフ一人が担っていた業務を分担し、全体の負荷を軽減することができます。
(短時間・曜日固定といった条件で、すぐにでも勤務を試せる人材の選択肢を広げたい場合には、多様な働き方を希望する看護師が登録しているクーラの「お試し勤務」の仕組みが活用しやすいかもしれません。→ https://business.cu-ra.net/)
6. 「公平感」を大切にするための設計
固定曜日シフトを導入すると、希望が集中しやすい曜日(例えば、金曜日)とそうでない曜日が出てくる可能性があります。また、シフトが固定されている職員と、毎月変動する職員との間で、不公平感が生じないような配慮も必要です。
- 定期的な見直しの約束:特定の曜日に人気が偏る場合は、希望者が複数いることを全体に伝え、半年や一年に一度、担当を見直す機会を設けることをあらかじめ約束しておきます。
- 変動シフトメンバーへの配慮:毎月シフトが変わる常勤スタッフなどには、希望休を優先的に取得できるようにしたり、研修や勉強会への参加機会を優先的に提供したりするなど、貢献に報いる仕組みを用意します。
- 固定曜日メンバーの協力体制:固定曜日の担当者には、担当外の曜日に急な欠員が出た際に、協力してくれた場合のインセンティブとして、時間外手当とは別に少額の「代替協力手当」のような制度を設けることも考えられます。
7. コミュニケーションの「定期点検」を行う
制度は作って終わりではありません。運用しながら、現場の実態に合わせて改善していくことが重要です。そのためには、定期的なコミュニケーションの機会を設けることが効果的です。
- 毎月の短い振り返り会:月に一度、15分程度の短い時間で構わないので、曜日ごとの担当者が集まり、業務負荷に偏りはなかったか、やりにくい点はなかったかなどを話し合う場を設けます。
- 業務の移管を提案制にする:振り返りの中で、「忙しい月曜に行っているこの作業は、比較的余裕のある木曜に移せないか」といった改善提案を歓迎する雰囲気を作ります。
- 教育項目のチェックリスト化:新しい医療機器の導入や、業務手順の変更があった際に、固定曜日の担当者全員がその情報を確実に習得できているかを確認するためのチェックリストを用意し、教育漏れを防ぎます。
8. 募集・採用・定着を一体で考える
固定曜日シフトの導入は、採用活動のあり方にも影響します。
- 求人票の工夫:募集をかける際は、単に「パート募集」とするのではなく、「【火曜・金曜担当】外来の採血・処置介助スタッフ募集」のように、曜日と主な役割を明確に記載します。勤務時間、想定される業務量、教育体制が整っていることなども明記すると、応募者は働くイメージを持ちやすくなります。
- 面談での丁寧な説明:面談の場では、なぜその曜日に人員を強化したいのか、という背景(曜日プロファイルなど)を説明し、採用される方がチームにとってどのような貢献を期待されているのかを伝えます。これにより、仕事への意欲を高めることができます。
- 入職後のフォロー体制:新しい職場と仕事に慣れるまでの最初の4週間が、定着のための重要な期間です。週に一度は面談の時間を設け、業務負荷は適切か、人間関係で困っていることはないか、家庭との両立はうまくいっているかなどを丁寧にヒアリングし、不安を早期に解消することが大切です。
運用細目:固定曜日シフトの「型」となる文書やルール
制度を円滑に運用するためには、いくつかの文書(テンプレート)を整備し、ルールを明確にしておくことが役立ちます。
見える化のためのテンプレート(抜粋)
- 曜日×時間帯×必要スキルの一覧表
- 各曜日役割(ロール)ごとの主要業務と終了時業務のリスト
- 欠員発生時の代替担当者と連絡の優先順位を示した表
- 補充が困難な場合の対応優先順位(例:1.応援要請、2.予約調整、3.当日業務の縮小)
- 新規採用者向けの教育項目チェックリスト
- 月次レビュー会議の議事録(改善提案と実施結果を記録)
欠員リスクへの具体的な対応策
- 「浮動枠」の活用:当日の急な欠員は、まず「浮動枠」の担当者が吸収します。それによって遅延した本来の業務は、翌週に人員を増やすなどして回収します。
- 代理担当者の一時的な役割変更:固定曜日の担当者が病気などで連続して休む場合は、あらかじめ決めておいた代理担当者が、一時的にその役割を引き継ぎます。
- 業務量の平準化:医師のスケジュール変更や、特定の検査が集中する日をあらかじめ予測し、月単位で業務量が平準化されるよう、人員配置を調整します。
部署ごとの使い分けのヒント
- 病棟(2交代・3交代制との組み合わせ):病棟における固定曜日シフトは、日勤帯の業務強化に適しています。特に、入退院の対応、処置、物品管理、患者指導といった、日中に集中する業務に組み込みやすいです。夜勤の責任体制は常勤スタッフで固めつつ、固定曜日パートには「日中の業務の底上げ」を担ってもらう、という役割分担が考えられます。
- 外来・検査部門:特定の曜日に内視鏡検査が集中したり、特定の医師の外来日は混雑したり、といった傾向が強い外来・検査部門では、その繁閑に合わせて固定曜日シフトを組むことが非常に効果的です。物品の準備や滅菌、患者様の案内といった業務を、毎週同じ担当者が行うことで、習熟度が上がり、業務の質とスピードの向上が期待できます。
- 訪問看護:前述の通り、利用者様との関係構築や訪問ルートの効率化の観点から、固定曜日シフトとの親和性が非常に高い分野です。「9時から16時まで(実働6時間)×週2日」といった、家庭と両立しやすい勤務パターンは、潜在的な看護師資格保持者へのアピールにもつながります。
よくある懸念と、その現実的な対応策
Q1:小規模なクリニックや事業所では、固定曜日にすると他の曜日が回らなくなるのでは?
A:むしろ、小規模だからこそ、曜日ごとの業務量を正確に把握し、計画的に人員を配置することが重要になります。まずは、曜日ごとの必要人員を丁寧に見直し、本当にぎりぎりの人数で運営していないかを確認することから始めます。その上で、例えば週に1枠だけでも短時間の「浮動枠」を設けることができれば、急な事態への対応力が格段に向上します。混雑する曜日の業務がスムーズになれば、残業が減ったり、患者様の待ち時間が短縮されたりといった効果も期待でき、結果として全体の満足度が上がるケースも少なくありません。厚生労働省の好事例集でも、短時間勤務や週4日勤務といった柔軟な働き方を拡大する取り組みが、組織の規模を問わず紹介されています。
Q2:スタッフ間の公平感は本当に保てますか?
A:公平感を保つためには、「制度の透明性」と「納得感のある仕組み」が鍵となります。まず、固定曜日の担当は永続的なものではなく、半年や一年といった期間で見直す可能性があることを、全員に伝えておきます。その上で、変動シフトで協力してくれているスタッフには、希望休の優先的な取得や、外部研修への参加機会といった、目に見える形でのメリットを提供します。また、固定曜日の担当者にも、他の曜日での欠員発生時に協力してくれた際には、それを評価する小さな手当などを設けることで、「お互い様」という意識を醸成することが大切です。
Q3:担当者が固定されると、教育の機会や業務の品質にばらつきが出ませんか?
A:逆の側面もあります。同じ曜日に同じ業務を繰り返し担当することで、その業務への習熟度は深まり、むしろ品質は安定しやすくなります。問題は、その担当者しかできない「業務の属人化」が起こることです。これを防ぐために、曜日ごとの役割(ロール)ごとに手順書を整備し、業務の進捗や品質を測る簡単な指標(例:処置準備にかかる平均時間、採血のエラー発生率など)を設けます。そして、月次のレビューで、他の曜日の担当者と情報共有し、手順の改善などを話し合うことで、全体の品質を均一に保ち、向上させていくことができます。
まとめ:固定曜日は「安定採用」「離職予防」「業務平準化」を同時に目指す手法です
これまで見てきたように、固定曜日シフトは、適切に設計・運用することで、多くのメリットをもたらす可能性を秘めた制度です。
- 働く側の「生活の安定」が担保されるため、育児や介護、副業など、様々な事情を抱える看護師からの応募が増え、採用力が向上します。
- 「曜日ごとの役割」を定めることで、業務内容が明確になり、作業の平準化が進みます。これにより、教育がしやすくなり、サービスの品質も安定します。
- 欠員発生時の代替ルートをあらかじめ計画に組み込めるため、突発的な事態にも慌てず、組織的に対応することができます。
実際の医療現場の事例や、公的な資料においても、曜日ごとの分担や短時間勤務、週4日勤務といった柔軟な働き方の成功例は、数多く報告されています。
もし、「どの曜日に、何人、どのようなスキルを持つ人材を配置すれば最適なのかを、手早く整理したい」とお考えの場合や、固定曜日パートの募集を「お試し勤務」からスムーズに本格採用へとつなげたい、とお考えの場合は、多様な働き方を希望する看護師が登録しているクーラのようなサービスが、その一助となるかもしれません。
まずは、皆様の職場における業務の「曜日プロファイル」を大まかに整理し、どこに人材を投入すれば最も効果的かを見極めることから、始めてみてはいかがでしょうか。→ https://business.cu-ra.net/
付録:導入ステップの簡易チェックリスト
固定曜日シフトの導入を検討される際に、ご活用いただける簡易的なチェックリストです。
(具体的な求人票のテンプレート、「お試し勤務」の運用サンプルなどは、クーラの支援メニューの中で、まとめてご提供することも可能です。→ https://business.cu-ra.net/)
参考にした公開情報(一部)
- 厚生労働省「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」掲載の「医療機関の勤務環境改善の好事例」および関連資料。
- 訪問看護におけるパートタイム勤務の実態に関する紹介記事(nurses.works 等)。






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)





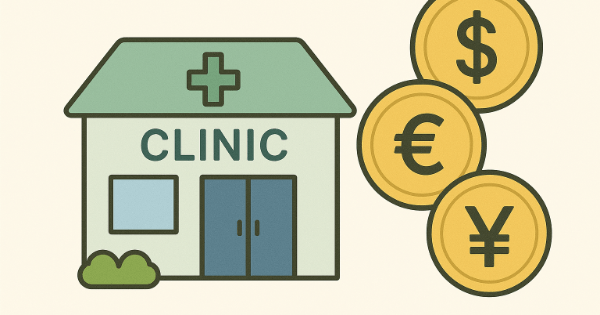
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
