はじめに:受け入れを「特別なこと」にしないために
看護師不足が日本の医療現場における共通の課題となるなか、「外国人看護師の受け入れ」を具体的な選択肢として検討する病院やクリニックが増えているように感じられます。しかし、実際に検討を始めると、在留資格の種類の複雑さ、採用後に任せられる業務の範囲、そして日本の看護師国家試験に合格するまでの支援体制の構築など、確認すべき点が多岐にわたることに気づかされます。
この記事では、制度に沿って一つひとつ準備を進めることで、外国人看護師の受け入れは決して“特別扱い”が必要なものではなく、通常の人材育成の延長線上で捉えることができる、という視点をご提案します。外国人材の受け入れが初めての施設でも、実務で迷いやすいポイントに絞って、制度の全体像、就労前後の業務範囲の明確化、そして現場での指導体制の具体的な設計方法について、公表されている事例を交えながら整理していきます。
この記事が、貴院の多様な人材活用の一助となれば幸いです。
背景・課題:複数の制度、押さえるべき3つの要点
現在、日本の病院が外国籍の方を「看護師」として雇用するためのルートはいくつか存在しますが、制度が少し複雑に見えるかもしれません。ここでは、主要なルートを整理し、特に病院での就労における要点を3つに絞って解説します。
- EPA(経済連携協定)に基づく受け入れこれが、外国籍の方が日本の看護師資格取得を目指すための、国が設けた主要なルートの一つとされています。インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国から、「看護師候補者」として来日します。候補者は、日本の医療機関で看護補助業務に従事しながら、日本語研修や国家試験対策の学習を進めます。そして、日本の看護師国家試験に合格し、看護師免許を取得した後に、正規の「看護師」として就労を開始する、という二段階の仕組みになっています。この制度の調整機関は、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が担っています。
- EPA以外の在留資格を持つ方の雇用すでに日本に居住している外国籍の方で、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」といった、活動に制限のない在留資格をお持ちの場合、日本人と同様に看護師や看護助手として採用することが可能です。また、留学ビザで来日し、日本の看護師養成校を卒業して国家試験に合格した方は、在留資格を「医療」に変更することで、看護師として就職できます。ただし、これらのケースは、能動的に海外から人材を募集するというよりは、日本国内にいる応募者の中から採用する形が中心となります。
- 介護分野の制度との違い近年、「特定技能」や「技能実習」、「介護」といった在留資格で来日する外国籍の方も増えています。これらの制度は、主に介護施設での介護業務を担う人材を対象として設計されています。そのため、病院における「看護助手」としての業務を主目的に、これらの在留資格で広く人材を受け入れることは、制度の趣旨と異なる場合があるため注意が必要です。厚生労働省も、「看護助手」という業務内容を主目的として新たに付与される在留資格はない、という点を明確にしています。個別のケースで雇用が可能かどうかは、出入国在留管理庁や専門家への確認が推奨されます。
以上の点を踏まえると、海外から人材を募集し、将来的に貴院の看護師として活躍してもらうことを目指す場合、EPA(経済連携協定)の枠組みが、現在最も確立されたルートであると言えるでしょう。この記事では、このEPAの制度を中心に、具体的な受け入れプロセスと現場での工夫について掘り下げていきます。
ここで、EPA制度の全体像を視覚的に理解しやすくするために、他の在留資格との比較を簡単な表にまとめました。
実例紹介:受け入れ現場の工夫と成果
ここでは、公表されている資料や研究報告から、実際に外国人看護師候補者を受け入れている医療機関の具体的な取り組みをいくつかご紹介します。特定のやり方が唯一の正解というわけではなく、「このような工夫をしている事例がある」という参考情報としてご覧ください。
事例1:医療法人社団錦水会 山口リハビリテーション病院の報告
国際厚生事業団(JICWELS)が公開している説明会資料によると、こちらの病院では法人グループ全体で連携した支援体制を構築している様子がうかがえます。特筆すべきは、複数の施設を持つ医療法人の利点を活かし、住居の提供や生活面での細やかな指導、さらには異文化理解を促進するための学習機会の提供など、包括的なサポートを行っている点です。国家試験の勉強と日々の就労を両立させるためには、職場だけでなく生活基盤の安定が不可欠であるという考えに基づいた取り組みとされています。
事例2:医療法人常磐会 常磐病院(ときわ会グループ)の発表資料
こちらの病院の事例で特徴的なのは、候補者の最大の目的は「日本の看護師国家試験に合格すること」であると明確に位置づけ、就労計画そのものを学習時間の確保を最優先に設計している点です。具体的には、学習時間を勤務シフトに組み込む、日本語能力のレベルに合わせた業務内容の調整などが行われているようです。また、職員向けのニュースレターを発行して、院内での相互理解を促進したり、賃金や住居に関するルールを事前に明確に定めたりするなど、候補者が安心して日本での生活と仕事に集中できるような環境づくりへの配慮が見られます。細かなルールの積み重ねが、信頼関係の構築につながっている事例と言えるかもしれません。
事例3:社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院の取り組み
こちらの法人は、早くから外国人材の受け入れに積極的で、EPA看護師候補者だけでなく、介護福祉士候補者なども含めた多国籍の職員が活躍しています。ウェブサイトや広報誌で公表されている情報によれば、専門の部署を設置し、日本語教育や国家試験対策はもちろんのこと、文化や習慣の違いから生じる戸惑いを解消するためのメンタルサポートにも力を入れているようです。また、地域社会との交流を促進するイベントを企画するなど、職場への定着だけでなく、地域の一員として生活できるよう支援する視点も持たれています。
事例4:国家試験合格後の日本語能力の維持・向上に関する研究報告
ある学術研究(J-STAGEで公開)では、EPA看護師が国家試験に合格し、正規の看護師として働き始めた後も、日本語能力の向上が続くプロセスが報告されています。特に効果的だったとされるのが、日々の業務に組み込まれた学習支援です。例えば、患者さんへの説明でわからない点があれば、その都度、先輩看護師が繰り返し確認する、看護記録の書き方を具体的に添削・指導する、といった現場での地道な関わりが、実践的な日本語能力の向上に大きく寄与したと分析されています。座学だけでなく、実践を通じた学習がいかに重要かを示す事例です。
参考:自治体による支援制度の活用
個別の医療機関の取り組みに加えて、自治体が提供する支援制度を活用する動きも見られます。例えば、神奈川県の公式ウェブサイトでは、外国人看護師候補者を受け入れる施設に対して、日本語学習の費用や資格取得にかかる経費の一部を補助する制度があることが案内されています。県や市町村によっては、このような公的な支援スキームが用意されている場合があるため、自院が所在する自治体の情報を確認してみることも有効なアプローチです。
解決アプローチ:制度・実務・育成の“三層設計”
外国人看護師の受け入れを成功に導くためには、「制度の正確な理解」「日々の実務における安全管理」「長期的な視点での育成計画」という3つの層を、それぞれ丁寧にかつ連携させながら設計していくことが大切です。
1) 制度理解:EPAの基本的な仕組みを正確に把握する
EPAによる受け入れを検討する上で、まず押さえるべきは、その制度的な枠組みです。ここは自己流の解釈を避け、公式な情報源に基づいて進めることが不可欠です。
受け入れの唯一の窓口はJICWELS
EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者の受け入れは、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入れ調整機関として定められています。受け入れを希望する病院は、まずJICWELSに求人登録を行うところから始まります。募集から候補者とのマッチング、入国前後の研修の案内、在留資格に関する手続きのサポートまで、制度運用における中心的な役割を担っています。受け入れのスケジュール、施設が満たすべき要件、必要となる費用などは、年度ごとに更新されるため、常に最新の「受入れの手引き」を確認することが、間違いのない準備への第一歩です。
在留資格:「特定活動(EPA看護師候補者)」とは
EPAで来日する候補者は、「特定活動」という在留資格が付与されます。この資格は、活動内容が「日本の看護師資格を取得するための知識の修得及び関連する業務への従事」に限定されています。具体的には、受け入れ施設での看護補助業務と、国家試験合格に向けた研修が活動の二本柱となります。この在留資格にはいくつかの重要な前提条件があります。例えば、受け入れ先の施設を原則として変更することはできません。また、家族を日本に呼び寄せること(家族帯同)も認められていません。これらの条件は、候補者の生活設計だけでなく、受け入れ施設側の長期的な人員計画にも影響を与えるため、事前にしっかりと理解しておく必要があります。なお、訪問看護ステーションなど、在宅看護の領域は現在の制度では対象外とされています。
看護師国家試験の合否について
EPA制度が始まった当初、国家試験の合格率は伸び悩む時期もありましたが、JICWELSが公表しているデータによれば、近年は日本語教育や学習支援のノウハウが蓄積され、合格率は改善傾向にあると報告されています。厚生労働省が発表する統計資料でも、EPA候補者の受験状況や国別の合格者数の推移などが整理されており、客観的なデータとして参考にすることができます。合格は決して簡単な道のりではありませんが、適切な支援体制を構築することで、多くの候補者が目標を達成しているのが現状です。
ここで一つ、運営上の視点をご提案します。EPA候補者は、国家試験合格という明確な目標があるため、特に試験直前期には学習に集中できる環境を整えてあげることが重要になります。その期間、一時的に病棟の人員配置が手薄になる可能性も考えられます。そのような時に、短期的な人材サービスを「緩衝材」として活用するのも一つの方法です。例えば、看護補助業務や外来の繁忙な時間帯に、数日間から看護職を依頼できるクーラ(医療機関向け)のようなサービスを併用することで、現場の運営を安定させながら、候補者の学習時間を確保しやすくなるという考え方もできます。
2) 実務:業務範囲の線引きと安全管理の徹底
候補者が来日し、現場での就労が始まると、最も重要になるのが「どこまでの業務を任せて良いのか」という業務範囲の明確化と、それに伴う医療安全の管理です。
候補者期間に任せられる業務(看護補助)
JICWELSの資料では、候補者の業務は「看護師の指示・監督のもとで行う看護補助業務」と明確に定められています。具体的には、以下のような業務が挙げられます。
- 療養環境の整備(ベッドメイキング、清掃など)
- 身体の清潔に関するケア(清拭、入浴介助、陰部洗浄など)
- 排泄の介助(おむつ交換、ポータブルトイレの補助など)
- 食事の介助(配膳、下膳、食事摂取の補助など)
- 移乗・移動の介助(車椅子への移乗、歩行の付き添いなど)
- 医療機器や物品の準備、片付け、補充など
一方で、採血、注射、点滴の管理、薬剤の投与といった侵襲的な医療行為や、患者の状態をアセスメントして対応を判断するような、看護師としての専門的な判断を伴う行為は一切認められていません。この線引きを曖昧にせず、病棟の全スタッフが共通の認識を持つことが、医療安全の観点から極めて重要です。
国家試験合格後の業務(看護師)
無事に国家試験に合格し、日本の看護師免許を取得した後は、他の日本人看護師と同様に、看護師としての業務に従事することができます。ただし、免許を取得したからといって、すぐに一人前の看護師として全ての業務をこなせるわけではありません。多くの施設では、新人看護師と同様の導入研修を改めて実施したり、特に医療安全や感染対策、看護記録の様式など、その施設独自のルールについて再教育の機会を設けたりしています。この移行期間を丁寧に設計することが、その後のスムーズな定着につながります。
在留資格や配属に関する注意点
前述の通り、候補者期間中の受け入れ施設の変更は、倒産などやむを得ない事情がない限り認められていません。これは、同じ医療法人内の別の病院や施設への異動(横滑り)も原則として対象外です。安易な異動は出入国管理及び難民認定法に抵触するリスクがあるとJICWELSも注意を促しています。そのため、最初の受け入れ計画の段階で、配属先の病棟や指導体制を慎重に検討し、長期的な視点で固定することが前提となります。また、在留期限の更新手続きなども発生するため、人事・総務部門と現場が連携し、手続きのスケジュールを管理することも重要です。
「看護助手」としての採用に関する誤解を避けるために
時折、「EPAではなく、最初から看護助手として外国人を直接雇用できないか」という相談が聞かれます。この点について、厚生労働省は注意喚起の文書を公表しており、「看護助手」として就労することのみを目的とした在留資格は、現状では付与されていないという点を明確にしています。身分系の在留資格を持つ方などを除き、安易に「看護助手」として外国人を雇用しようとすると、不法就労助長罪に問われるリスクもあります。採用時には、必ず在留カードを確認し、就労が認められている資格かどうか、その活動範囲は何かを厳格に確認する責任が病院側にはあります。
在留資格の適合性チェックや、候補者の学習計画によって一時的に生じる病棟シフトの穴を埋める際には、柔軟な人材活用が有効な場合があります。例えば、面談や見学を経て、まずは1〜4シフト程度の「お試し勤務」から始められるクーラ(医療機関向け)のような仕組みは、本格的な採用の前にミスマッチを防いだり、EPA候補者の学習時間を確保するための臨時的な人員補充として活用したりするのに適しているかもしれません。
3) 育成:日本語・学習時間・メンタルの三本柱
EPA候補者の受け入れは、単なる労働力の確保ではなく、「日本の看護師を育てる」という育成プロジェクトです。その成功の鍵は、「日本語能力の向上」「学習時間の確保」「精神的な安定」という3つの柱を、バランスよく支えていくことにあります。
日本語と実務を同時に学ぶ環境づくり
多くの成功事例で報告されているのが、日々の業務を通じて日本語を学ぶ「現場参加型」の学習です。机上の勉強だけでは身につかない、医療現場特有の言い回しやコミュニケーションの機微は、実践の中でこそ習得されます。具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
- 反復確認の徹底:指示が正確に伝わったか、曖昧な表情をしていないかを確認し、わからなければ何度でも違う言葉で説明する。
- 記録の共同作業と添削:最初は一緒に看護記録を書き、徐々に本人に任せ、書いた内容を教育担当者が確認・添削する。「てにをは」の間違いや、より適切な専門用語の使い方を具体的にフィードバックする。
- 用語の使い分けの解説:患者さんへの説明で使う「やさしい言葉(和語)」と、スタッフ間で使う「専門用語(漢語・外来語)」の違いを、場面ごとに教えていく。
学習時間を「聖域」として守る仕組み
候補者にとって、日々の業務と並行して国家試験の勉強時間を確保することは、想像以上に大変なことです。現場が忙しいと、つい学習時間が後回しにされがちになります。そこで、個人の努力任せにするのではなく、組織として学習時間を守る仕組みを作ることが重要です。ある病院の事例では、
- 勤務表を作成する段階で、あらかじめ「週10時間の学習時間」などを固定の枠として組み込んでしまう。
- 早出や遅出勤務が続くと生活リズムが崩れ、学習時間が確保しにくくなるため、慣れるまでは日勤帯を中心としたシフトにする。
- 夜勤についても、回数や組み合わせを段階的に調整し、学習への影響を最小限に抑える。といった工夫が紹介されています。
生活面・精神面のサポート体制
慣れない異国での生活は、仕事のストレス以上に大きな負担となることがあります。職場外の生活が安定して初めて、仕事や勉強にも集中できるものです。受け入れ施設ができるサポートとしては、
- 住居の手配:アパートの契約や、家具・家電の準備などを法人が支援する。
- 生活ルールの明文化:ゴミの出し方、騒音の問題、地域の慣習など、日本で暮らす上での基本的なルールをまとめた資料を用意する。
- 精神的なケア:定期的な面談の機会を設け、仕事の悩みだけでなく、生活の不安や孤独感についても話を聞く。同じ出身国の先輩や、地域に住む同国人のコミュニティと繋ぐ「ピアサポート」の機会を作ることも有効とされています。
- 文化交流:季節の行事(お花見、夏祭りなど)への参加を促し、日本文化への理解を深め、職場に溶け込むきっかけを作る。
自治体の補助金などの活用
前述の通り、自治体によっては、外国人材の受け入れにかかる費用を補助する制度を設けている場合があります。日本語学習の教材費、模擬試験の受験料、外部講師への謝礼などが対象となるケースが多いようです。申請手続きなどの事務作業は発生しますが、費用対効果の高い取り組みとなり得るため、一度、自院が所在する都道府県や市区町村の担当部署に問い合わせてみる価値はあるでしょう。
特に、模擬試験の集中期間や、日本語研修で候補者が職場を離れる日など、あらかじめ人員が手薄になることが分かっている日があります。そうした日に合わせて、短時間・日勤のみといった条件で外部から応援を依頼できると、現場の負担を大きく軽減できます。必要な時に必要な分だけ人材を確保できるクーラ(医療機関向け)のようなサービスは、こうした学習計画の調整弁として、非常に相性が良いと考えられます。
実装の型:最初の90日間で受け入れの“土台”を作る
EPA候補者の受け入れが成功するかどうかは、最初の3ヶ月、約90日間の初期対応でその後の流れが大きく決まると言われています。この期間に、業務のルール、学習の習慣、そして人間関係の土台をしっかりと作ることが重要です。ここでは、最初の90日間をいくつかのフェーズに分け、具体的なアクションプランを時系列で整理しました。
特に、模擬試験の週や、苦手分野を克服するための集中学習期間には、病棟の他のスタッフに負担が偏りがちです。そのような時に、クーラ(医療機関向け)のようなサービスを活用し、「日勤だけ、数シフトだけ」といった形で応援の看護職を確保できると、学習時間を犠牲にすることなく、現場の運営も円滑に進めることができます。
よくある質問(Q&A):採用設計でつまずかないために
ここでは、外国人看護師の受け入れを検討する際に、多くの担当者様が疑問に思われる点や、誤解しやすい点について、Q&A形式でまとめました。
Q1:EPA候補者には、具体的にどこまでの業務を任せても良いのでしょうか?
A:候補者期間中の業務は、あくまで「看護補助業務」に限定されます。採血や注射といった侵襲的な処置や、患者さんの状態を見て次のケアをどうするかといった独自の判断を伴う業務は任せることができません。安全を確保するため、病棟や部署ごとに「任せられる業務リスト」を文書で作成し、それを基に指導することが推奨されています。また、業務の指示は必ず受け持ちの看護師や教育担当者から行うなど、指示系統を明確にすることも重要です。詳細はJICWELSが発行する手引きに明記されています。
Q2:採用後、同じ法人内の別の病院や施設に異動させることは可能ですか?
A:原則として、できません。EPA候補者の在留資格「特定活動」は、最初に入国管理局に届け出た受け入れ施設でのみ活動が許可されています。法人の経営状況の著しい悪化など、やむを得ない事情がある場合に限り、JICWELSと出入国在留管理庁の許可を得て変更が可能になることがありますが、極めて例外的なケースです。そのため、最初の受け入れ計画の段階で、数年単位でその候補者が働くことになる配属先を慎重に決定する必要があります。
Q3:EPA以外に、「看護助手」として外国人を採用できる在留資格はありますか?
A:「永住者」や「日本人の配偶者等」のように、日本での活動に制限がない身分系の在留資格をお持ちの方であれば、日本人と同様に看護助手として採用することが可能です。しかし、海外から「看護助手」として働くことだけを目的として、新たに在留資格が付与されることはないと厚生労働省から周知されています。介護分野の「特定技能」なども、主たる業務は介護であり、病院での看護補助業務を広く想定した制度ではないため、採用時には在留資格の適合性を厳格に確認する必要があります。
Q4:EPA候補者の国家試験合格率は、あまり高くないと聞いたのですが…
A:制度開始当初は、言語の壁などから合格率が低い時期もありました。しかし、JICWELSが公表している近年のデータを見ると、日本語教育や学習支援のノウハウが蓄積された結果、合格率は改善傾向にあると報告されています。特に、受け入れ施設側の支援体制(日本語教育、学習時間の確保、生活支援)が三位一体となって機能している場合に、合格率が高まる傾向があるとされています。国別の合格率の推移なども公表されているため、最新の情報を確認することをお勧めします。
Q5:受験手続きや書類の管理で、施設側が特に注意すべき点はありますか?
A:受験手続き自体はJICWELSがサポートしてくれますが、施設側で注意すべき点として、JICWELSは「受験資格認定書」の取り扱いを挙げています。これは、母国での看護師免許などを基に日本の受験資格を証明する大変重要な書類で、候補者本人が所有するものです。施設が預かる場合でも、雇用契約が終了した際には必ず本人に返却するよう、手引きの中で明記されています。紛失や返却トラブルを避けるため、管理方法をあらかじめ決めておくことが大切です。
まとめ:EPA受け入れを「採用×育成×運営」の一体設計で捉える
外国人看護師、特にEPAの枠組みによる受け入れは、単なる人材採用活動ではありません。それは、一人の専門職を育成し、チームの一員として共に働き、日々の病院運営を安定させるという、「採用・育成・運営」を一体で設計する長期的なプロジェクトです。
本稿でご紹介したポイントを改めて整理します。
- 制度の理解が全ての土台:EPAが看護師を目指す上での主要なルートであり、候補者期間は看護補助、合格後は看護師という二段階の構造を理解することが基本です。JICWELSの公式情報に基づき、在留資格の前提条件から逸脱しない計画を立てることが重要です。
- 安全管理の徹底:業務範囲を文書で明確にし、院内の全スタッフで共有すること。そして、指示系統をシンプルにすることで、医療安全上のリスクを最小限に抑えることができます。
- 三位一体の育成支援:日本語能力の向上、学習時間の確保、そして生活・精神面のサポート。この3つは相互に関連しており、どれか一つが欠けても国家試験合格と職場定着は難しくなります。組織として支援する仕組みを構築することが求められます。
- 公的支援の活用:JICWELSのサポートはもちろん、自治体が提供する補助金なども積極的に情報収集し、活用することで、受け入れにかかる費用や人的な負担を軽減できる場合があります。
- 運営の柔軟性:候補者の学習計画と、病棟の繁忙期が重なることもあります。そのような場合に、短期的な外部人材を「緩衝材」として柔軟に活用する視点を持つことで、現場の負担を平準化し、持続可能な受け入れ体制を築きやすくなります。
EPAによる受け入れは、一つひとつの手順を丁寧に踏み、制度の枠組みの中で、現場の安全と候補者の成長を両立させる仕組みを設計すれば、決して特別なことではありません。むしろ、新人看護師を育成するプロセスを、文化や言語の背景が異なる方に対して、より丁寧に、より構造的に実践するものと捉えることができます。
最後に:貴院のチームの一員として、長く働ける仲間を増やすために
候補者の学習日や、模擬試験が続く週には、どうしても現場のシフトが手薄になりがちです。そのような一時的な人員の谷間を埋めるために、日勤のみ、週に数回だけといった柔軟な働き方が可能な看護職を、外部から応援として呼べるとしたら、現場の負担感は大きく変わるのではないでしょうか。
クーラ(医療機関向け)では、必要な時に、必要な期間だけ、看護職の人材を確保するお手伝いができます。見学や「お試し勤務」から始めることもできるため、本格的な採用の前に、お互いの相性を見極めることが可能です。これにより、定着前のミスマッチを減らし、常勤スタッフがEPA候補者の育成に集中できる環境を整えやすくなります。
まずは無料で求人を掲載し、貴院の近隣にどのようなスキルを持った登録看護師がいるのか、その稼働状況を把握するところから始めてみませんか。制度の理解と、日々の運営の工夫を重ねることで、EPAで来日した方々が、貴院にとってかけがえのないチームの一員となるはずです。そのプロセスを、私たちも少しでもお手伝いできれば幸いです。
参考リンク・出典(一般公開情報)
- 公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者の受入れ調整機関。制度の概要、各種手引き、説明会資料、過去の事例などが網羅的に掲載されています。
https://www.jicwels.or.jp/ - JICWELS「経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師候補者受入れの手引き」在留資格、活動内容、施設変更の原則禁止、家族帯同の不可、受験資格認定書の取り扱いなど、受け入れに関する詳細なルールが記載されています。年度ごとに更新されるため、最新版をご確認ください。
- 厚生労働省看護師国家試験の実施概要や、過去の試験の合格発表資料(EPA候補者の受験状況を含む)などが公開されています。また、在留資格と看護助手業務の取り扱いに関する注意喚起などの情報も発信されています。
https://www.mhlw.go.jp/ - J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)職場における日本語学習支援の実践に関する研究報告など、学術的な観点からの論文が検索・閲覧できます。
https://www.jstage.jst.go.jp/ - 神奈川県公式サイト自治体による外国人材受け入れ支援制度の一例として。各都道府県や市区町村で同様の制度がないか、確認の起点となります。
https://www.pref.kanagawa.jp/

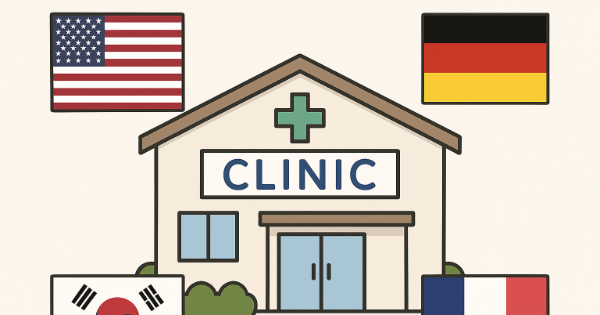





.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
