看護師の採用を進める中で、「人材紹介の手数料が経営の負担になっている」「気づけば、採用のほとんどを紹介会社に依存してしまっている」と感じる場面は、多くの医療機関で共通する悩みかもしれません。人材紹介は、スピーディーかつ確実に採用を決定しやすいという大きな利点がある一方で、その手数料は採用する看護師の想定年収の2割から3割が一般的とされています。採用が一人、また一人と重なるほど、その費用負担は決して小さなものではなくなります。
この記事では、人材紹介の持つ「早く決まる」という長所はそのまま活かしながら、より長期的な視点で採用の費用対効果を高めていくための「併用設計」という考え方について、具体的な事例を交えながら、分かりやすく整理していきます。ここで紹介する数値や事例は、公に発表されている調査や記事、各機関の取り組み事例などを基にしています。採用活動の新たな選択肢を考えるきっかけとして、お役立ていただければ幸いです。
なぜ“紹介に頼りきり”の状況が生まれるのか(背景と課題)
多くの医療機関が人材紹介サービスを中心に採用活動を行っているのには、構造的な背景があります。なぜ特定の手段に偏りがちになるのか、その理由と課題を整理してみましょう。
看護師採用が持つ構造的な難しさ
医療の現場は、常に人手不足のリスクと隣り合わせの状態にあると言えるかもしれません。年度末の退職者が思ったより多かった、新しい病棟やサービスを立ち上げることになった、産休や育休に入る職員が重なった、夜勤体制を少し変更した、といった些細な変化が、あっという間にシフトの逼迫に繋がることは珍しくありません。
こうした状況では、どうしても「時間」が最優先されます。数ヶ月かけてじっくり採用活動を行う余裕がなく、「1ヶ月以内にあと2名、なんとか確保したい」といった緊急性の高い募集が多くなりがちです。そうなると、多くの登録者の中から条件に合う人材を迅速に提案してくれる人材紹介サービスが、最も頼りになる選択肢に見えてきます。この「スピードを重視せざるを得ない状況」が、結果として紹介への依存度を高める一因となっているようです。
手数料は“時間と確実性”への対価
人材紹介サービスを利用する際に発生する手数料は、一般的に採用者の理論年収の20%から35%程度が相場とされています。仮に年収500万円の看護師を採用した場合、100万円から175万円前後の費用が発生する計算になります。
この金額は、単に人を紹介してもらうことへの対価だけではありません。自院で募集広告を出し、多数の応募書類に目を通し、面接日程を調整し、条件交渉を行う、といった一連の採用業務にかかる時間と労力を代替してくれることへの費用、いわば「時間と確実性を購入する」ためのコストと捉えることができます。特に採用担当者が他の業務と兼務していることが多い中小規模の医療機関にとっては、この価値は非常に大きく感じられることでしょう。しかし、その手軽さゆえに、採用が重なるとコストが際限なく膨らんでしまうという側面も持っています。
離職やミスマッチがもたらす影響
採用にかかる費用は、入職時に支払う手数料だけで終わりではありません。もし、採用した人材が早期に離職してしまった場合、投じた採用コストは回収できないばかりか、再度同じポジションを募集するための採用活動費と、その間現場の職員にかかる負担、そして新しい人材への教育コストが二重、三重にのしかかってきます。
日本看護協会が公表している「2024年 病院看護実態調査」によると、2023年度の正規雇用看護職員の離職率は全体で11.3%でした。内訳を見ると、新卒採用者が8.8%であるのに対し、既卒採用者は16.1%と高い傾向が見られます。これは、既卒採用者が自身のキャリアや働き方に対する明確な考えを持っていることの表れとも言えますが、同時に、入職前のイメージと入職後の現実との間にギャップが生まれやすいことの示唆でもあります。
採用単価の高さだけでなく、入職後の定着までを視野に入れた「トータルの費用対効果」を考えなければ、人材紹介に偏った採用活動は、想定以上に割高なものになってしまう可能性があるのです。
紹介+ダイレクト応募+求人広告の“併用”が有効な理由
そこで考えたいのが、人材紹介だけに頼るのではなく、他の採用手法を戦略的に組み合わせる「併用設計」です。これにより、それぞれの弱点を補い合い、採用活動全体の質と効率を高めることが期待できます。
1)アプローチできる母集団の性質が異なる
それぞれの採用手法は、アプローチできる看護師の層(母集団)が異なります。それぞれの特徴を理解し、使い分けることが重要です。
2)募集のタイミングと難易度に応じた“適材適所”の使い分け
すべての募集を同じ方法で行う必要はありません。募集するポジションの緊急度や専門性に応じて、最適な手段を使い分けることで、全体の効率は大きく向上します。
- 緊急の欠員補充や、高度な専門スキルが求められる認定看護師などの募集は、人材紹介のスピードとマッチング精度を活用するのが合理的かもしれません。
- 一方で、通年で行う病棟看護師の募集や、将来的な増員を見越した採用活動は、求人広告やダイレクトリクルーティングで、時間をかけて自院のファンとなる「常温の見込み層」を育てていくアプローチが有効です。
- 特に、夜勤専従や訪問看護といった、一般的に敬遠されやすいとされる条件の募集では、単に紹介を待つだけでなく、求人票の表現を工夫したり、面談前にオンラインで不安を解消する機会を設けたりすることで、直接応募の数を増やす取り組みが効果を発揮することがあります。
3)“紹介コストの年間上限”を自然に作れる
併用設計の最大のメリットの一つは、採用コストのコントロールがしやすくなることです。求人広告や自院の採用サイトから、年間を通じて一定数の直接応募が安定して入る仕組みができていれば、人材紹介に依頼する求人を「本当に急いでいるもの」「自力では見つけにくい専門職」だけに限定することができます。
これにより、自然と年間の人材紹介の利用比率に上限が設定され、採用費全体の大きな変動を抑えることができます。計画的な予算執行が可能になり、経営の安定にも繋がるでしょう。
実例で学ぶ:費用対効果を高めた具体的な取り組み
抽象的な理屈だけでなく、実際に他の医療機関がどのように採用手法を組み合わせて成果を出しているのか、公表されている事例をいくつか見てみましょう。
- 事例1:運用型広告で応募単価を安定させたクリニックの例求人検索エンジンIndeedの活用レポートなどでは、看護職の採用において、クリック単価が100円台から200円台、応募単価が1万円から2万円の範囲で成果を出している事例が紹介されています。具体的には、求人票に「残業月平均5時間以内」「有給消化率90%以上」といった具体的な数字を入れたり、院内の和やかな雰囲気が伝わる写真を複数掲載したりすることで、応募者の関心を引き、結果として紹介会社への依存度を下げながら、面談に繋がる質の高い応募を確保できた、という内容が見られます。
- 事例2:小規模医療機関が“原稿見直し”で応募を回復させた例ある求人広告代理店の公開事例では、これまで紙媒体や従来の求人サイトで募集をかけても全く応募がなかった小規模な医療機関が、Indeed PLUSの導入を機に求人原稿を根本から見直したケースが紹介されています。例えば、「未経験者やブランクのある方でも安心な研修内容」を具体的に列挙したり、「院長が大切にしている患者さんへの想い」といった人柄が伝わる文章を加えたり、院内の設備やスタッフの働く様子がわかる写真を活用したりしたそうです。その結果、応募単価約4,000円で4件の応募を獲得するなど、劇的な改善が見られたと報告されています。急な欠員が出た際に、最短即日で掲載できるスピード感も、選択肢として有効に機能したようです。
- 事例3:理念への共感で“カルチャーフィット”を高めた医療法人の例ダイレクトリクルーティングの成功事例として、SNSなどを積極的に活用し、法人の掲げる理念や、現場で働くスタッフの生の声を丁寧に発信し続けた医療法人の話があります。日々の何気ない職場の風景や、患者さんとの心温まるエピソード、研修で成長していく若手スタッフの様子などを継続的に伝えることで、その法人の「文化」や「空気感」に共感した求職者が集まるようになりました。こうした採用は、給与や待遇といった条件面だけでなく、価値観のマッチングを重視するため、入職後の定着率が高く、現場の満足度向上にも繋がったとされています。
- 事例4:紹介手数料の考え方と総額コントロールの重要性医療機関向けのコンサルティング会社などが発信する情報では、看護師の紹介手数料について、過去のアンケート調査を基に「看護師1名あたり平均約76万円」といった具体的な数字が示されていることがあります。高年収の役職者や、複数名を同時に採用する場合には、この費用インパクトはさらに大きくなります。だからこそ、一つの手段に依存するのではなく、複数の採用手法を組み合わせて年間の採用コスト総額を平準化していく、という経営的な視点が重要であると示唆されています。
併用設計の考え方:順番と配分で“効率”を作る
実際に採用手法の併用を始めるにあたり、どのような手順で考え、実行していくと良いのでしょうか。3つのステップで整理してみます。
“応募が集まる”求人票の要点(広告・直接応募の質を高める)
直接応募を増やす上で、最も重要なのが「求人票」そのものの魅力です。求職者の視点に立ち、少しの工夫を加えるだけで、応募数は大きく変わることがあります。
検索で見つかりやすい言葉を先頭に置く
求職者が仕事を探すとき、多くの場合「地域名」「診療科」「働き方」などをキーワードにして検索します。そのため、求人票のタイトルや見出しのできるだけ前半に、これらの言葉を具体的に入れることが有効とされています。
例えば、「看護師募集」というだけのタイトルよりも、「【渋谷駅徒歩5分】皮膚科クリニックの外来看護師|日勤のみ・残業ほぼなし」とした方が、検索結果に表示されやすくなりますし、一目で自分に関係のある求人だと認識してもらえ、クリック率の向上に繋がります。
写真は“働く自分”を想像できる構図を選ぶ
写真は、文章の何倍もの情報を伝える力を持っています。Indeed PLUSのような新しいサービスでは、複数の写真を掲載できることが特徴として紹介されています。単にスタッフの集合写真を一枚載せるだけでなく、様々な角度から職場の魅力が伝わる写真を用意しましょう。
- ナースステーションの様子や、病棟の廊下の雰囲気
- 実際に使っている電子カルテの画面や医療機器
- 休憩室で談笑しているスタッフの自然な表情
- 院長や看護部長が笑顔で話している場面
正面を向いたかしこまった写真だけでなく、業務に集中している真剣な横顔や、患者さんと接している優しい後ろ姿など、「ここで働く自分」を具体的に想像できるような写真が、求職者の心に響きやすいようです。
不安を先回りして解消する情報を提供する
転職を考えている看護師が応募をためらう理由の多くは、「新しい職場に馴染めるだろうか」「業務についていけるだろうか」といった不安です。求人票の中で、これらの不安を先回りして解消してあげるような情報を提供できると、応募へのハードルはぐっと下がります。
- 入職初日はどのようなスケジュールで動くのか
- 導入している電子カルテのメーカー名と、操作に慣れるまでのサポート体制
- 夜勤時の看護師・介護士の人数体制
- オンコールの所持頻度と、実際に呼び出しがある頻度の目安
- 子育て中のスタッフが何名在籍し、どのようにシフト調整をしているか
- 正式な面接の前に、まずは職場見学だけでも可能かどうか
特に、「見学→面談→おためし勤務」といったように、段階的に関わりを深められる選択肢を用意しておくことは、直接応募の心理的な壁を取り払う上で非常に効果的だとされています。
“直接応募が増えるほど紹介が効く”という逆説
直接応募を増やすための努力は、人材紹介の利用と矛盾するように感じられるかもしれません。「直接応募で充足できれば、紹介は不要になるのでは?」と考えるのは自然なことです。しかし、実際には逆の現象が起こることがあります。
求人広告や自院の採用サイト経由で、基礎的な人員、つまり通年で募集しているようなポジションが安定して採用できるようになると、人材紹介の価値はむしろ高まります。なぜなら、人材紹介を「急募のポジション」「専門性が高く代替不可能な人材」といった、本当にピンポイントで助けが必要な場面に集中して活用できるようになるからです。
その結果、一件一件の紹介依頼の目的が明確になり、支払う手数料が「効かせたい場所にだけ」投下されるようになります。採用活動全体で見たときに、年間の総コストは抑制され、かつ採用の質も担保される、という理想的な状態に近づけるのです。
失敗しやすいポイントとその回避策
併用設計を試みる際に、陥りがちな落とし穴がいくつかあります。事前に知っておくことで、無駄な時間やコストをかけずに済みます。
- 求人広告を“掲載するだけ”で放置してしまうありがちなのが、一度求人広告を出稿したら、あとは応募が来るのを待つだけ、という状態です。求人原稿の言葉が抽象的だったり、写真が不足していたり、タイトルが「看護師募集」のような一般的な言葉だけだったりすると、数多の求人情報の中に埋もれてしまいます。広告代理店の事例などを見ると、少なくとも2週間から1ヶ月に一度は応募状況のデータを確認し、タイトルの文言を修正したり、新しい写真に差し替えたりといった見直しを行うことが推奨されています。
- スカウトの文面が“お願い”調になっているダイレクトリクルーティングで候補者に送るスカウトメールが、「ぜひご応募ください」「お待ちしております」といった、一方的なお願いのメッセージになっていると、返信率は上がりにくいようです。なぜあなたに声をかけたのか、あなたのどのような経験に魅力を感じたのか、といった個別性の高いメッセージを添えることが大切です。また、いきなり「選考」に誘うのではなく、「まずはオンラインで30分、私たちの理念についてお話しできませんか?」といったように、心理的なハードルが低い入り口を用意することが成功の鍵とされています。
- 紹介会社に伝える要件が“漠然と”している人材紹介会社に依頼する際に、「経験3年以上で、協調性のある方」といったように、曖昧な条件だけを伝えてしまうと、紹介会社も候補者も、本当にその職場で活躍できるかどうかの判断が難しくなります。夜勤の具体的な人数体制、月の平均的なオンコール頻度、休み希望の通しやすさ、院内で使っている電子カルテの種類、といった「現場のリアルな情報」を事前に詳しく開示することで、ミスマッチのリスクを大幅に減らすことができます。
シミュレーション:紹介比率を変えずに“総額”を抑える考え方
ここで、簡単なシミュレーションを用いて、併用設計がコストにどう影響するかを見てみましょう。
もちろん、これは単純化したモデルであり、施設の規模や立地、求める人材の要件によって実際の数値は変動します。しかし、ここでのポイントは、「緊急性の高い採用は人材紹介のスピードを活かし、通年採用は広告やスカウトでコストを抑える」という役割分担をすることで、採用のスピード感を損なうことなく、年間の総額をコントロールできる可能性がある、という考え方そのものです。
“紹介×広告×スカウト”を現場で動かす具体的な順番
では、明日から具体的にどのように動けば良いのでしょうか。現実的なアクションの順番を考えてみましょう。
- 急な欠員募集は“二刀流”でスタートする現場から「急いで1名補充してほしい」という依頼が来たとします。その場合、まずは人材紹介会社へ求める人材の要件を伝えるのと同時に、その日のうちに求人広告の出稿準備も進めましょう。Indeed PLUSのようなサービスは最短1日で掲載が開始できる例もあるため、スピード感を持って並行して動くことが可能です。「紹介で早期に1人目を確保しつつ、広告でもう1名の応募を待つ」といった並走戦略が、最も現実的で効果的な打ち手となることが多いです。
- 通年募集は“常時掲載×月1回の点検”を習慣にする病棟の常勤・非常勤看護師や、日勤のみ・夜勤専従といった定番の募集職種については、求人広告を常に掲載しておく「常時掲載」を基本とします。そして、月に1回、カレンダーに予定を入れるなどして、応募数やクリック数といったデータを確認し、タイトルの文言や写真、仕事内容の説明文を見直す「点検日」を設けましょう。応募単価の目安として1万円から2万円といった数値を参考にしながら、必要に応じて露出を強めたり、訴求内容を調整したりする地道な改善が、安定した直接応募に繋がります。
- スカウトは“母集団の温度差”を埋めるために使うSNSや特定のスキルを持つ人材が集まるプラットフォームなどを活用し、自院の理念や教育制度、働き方の魅力などを丁寧に発信していきます。すぐに転職を考えていない潜在層に対して、「私たちの想い」を伝えることで、少しずつ興味を持ってもらう活動です。返信のハードルを下げるために「まずは見学だけでもいかがですか?」と気軽に誘ったり、面接の前にオンラインで現場の看護師と話す機会を設けたりと、小さなステップをたくさん用意することで、応募への橋渡しをしていきます。
直接応募をさらに伸ばすための“院内の3つの仕掛け”
採用担当者だけの努力だけでなく、院内全体で協力体制を築くことで、直接応募の数はさらに増え、質も向上していきます。
- 見学希望への“即レス”体制を組む採用サイトや求人票から「見学希望」の問い合わせがあった際に、当日か、遅くとも翌営業日には返信する。ただこれだけのことで、候補者が抱く印象は大きく変わります。迅速な対応は、歓迎されているというメッセージになります。事務長と看護師長などで担当者を決め、「見学希望のメールが来たら、このテンプレートを使って、まずはこの時間に返信する」といった簡単なルールを決めておくだけで、取りこぼしが格段に減ります。
- 初日の不安を解消する“A4一枚の紙”を用意する応募を検討している人が最も知りたいことの一つが、「入職初日の流れ」です。タイムスケジュール、電子カルテへのログイン方法、担当する業務範囲、申し送りの流れ、休憩を取るタイミングや場所、といった情報をA4一枚にまとめておき、見学や面接の際に渡すだけで、応募前の不安を大きく和らげることができます。
- “おためし勤務”制度を明文化するいきなり常勤で入職することに不安を感じる方は少なくありません。そこで、数日から1週間程度、有償で実際の業務を体験できる「おためし勤務」や「トライアル勤務」といった制度を正式に用意し、求人票にも明記します。これにより、現場の雰囲気や業務内容を肌で感じてもらうことができ、求職者と現場双方にとっての「こんなはずではなかった」というミスマッチを、入職前に防ぐことができます。
こうした直接応募を増やすための地道な取り組みは、一見遠回りに見えるかもしれませんが、巡り巡って人材紹介の費用対効果をも引き上げます。なぜなら、紹介に頼るべき場面が「急ぎで、かつ専門性の高いポジション」に限定され、一件あたりの手数料の価値が最大化されるからです。
まとめ:紹介は“効かせる場所”に。併用設計で採用コストを整える
人材紹介サービスは、決して否定されるべきものではありません。むしろ、その価値を正しく理解し、最も効果的な場面で活用することで、採用活動の強力な武器となります。
- 人材紹介は、緊急性が高く、見つけるのが難しい人材の採用において、特にその強みを発揮します。
- 求人広告やスカウト活動によって直接応募の土台が厚くなるほど、人材紹介を「ここぞ」という場面に集中投下できるようになり、結果として年間の採用コスト総額が安定します。
- 求人票のタイトル、言葉の選び方、写真の工夫、そして求職者の不安を先回りして解消する情報の提供によって、広告経由の応募単価は安定させやすい、という事例が多く報告されています。
- 年間の採用計画を立てる際に、「紹介手数料の上限目安」をあらかじめ設定し、もしそれを超えそうになったら広告やスカウト活動に予算を振り分ける、といったルールを決めておくことが、計画的な採用活動に繋がります。
読み終えた後に試したい、実務に役立つ小さな一歩
この記事を読んで、何か一つでも行動に移すことが、採用活動を改善する上で最も重要です。ぜひ、以下の小さなステップから始めてみてください。
- まず、現在募集中の求人、あるいは今後募集する可能性のある求人を、「急ぎ×難易度高」「準急ぎ×一般」「通年×将来」の3つの区分に分類してみる。
- 今出している求人広告のタイトルを見直し、先頭に「駅名×診療科×勤務形態」を入れてみる。そして、掲載している写真を3枚から5枚に増やしてみる。
- 見学希望の問い合わせに迅速に対応するため、事務長や看護師長と相談し、簡単な「返信担当表」や「返信テンプレート」を作成してみる。
すぐにでも採用活動を動かしたいと感じた方へ
もし、「継続的に出し続ける求人原稿の整備から始めたい」「おためし勤務を入り口にした新しい応募フローを作りたい」といった、直接応募を増やすための具体的な仕組みづくりに関心をお持ちでしたら、外部の専門サービスの力を借りるのも一つの有効な手段です。クーラでは、数日間の「おためし勤務」から始められる応募の導線づくりと、看護師の心に響く求人情報の整備を、まとめて支援するサービスを提供しています。ご興味があれば、ぜひ一度ご覧ください。https://business.cu-ra.net/
「今月は緊急の欠員補充があるが、年間の採用コストはできるだけ抑えたい」というジレンマを抱えている状況であれば、人材紹介と求人広告を並行して進めることに加え、クーラが提供するような「短期雇用からのスタート」という選択肢を組み合わせることで、費用の負担を平準化しやすくなるかもしれません。
「給与や待遇だけでなく、法人の理念や働きがいへの共感で応募者を集めたい」とお考えの場合は、写真や文章で職場の魅力を具体化し、「まずは見学から」という気軽な入り口を設計することが第一歩です。求人原稿の作成や応募フローの整備を外部に任せることで、院内の皆様は面接や現場の受け入れ準備といった、本来注力すべき業務に集中することができます。クーラの支援内容の詳細は、下記にまとまっています。https://business.cu-ra.net/
参考にした公開情報(例)
- 日本看護協会「2024年 病院看護実態調査」:2023年度の正規雇用看護職員の離職率(全体11.3%、新卒8.8%、既卒16.1%)など。
- 看護職の人材紹介手数料に関する一般的な相場(年収の20%〜35%程度)や、平均的な費用感について解説している記事。
- 運用型求人広告(Indeed/Indeed PLUS)における、看護職の応募単価やクリック単価、具体的な活用事例に関する求人広告代理店などの公開記事。
- ダイレクトリクルーティングやSNS活用によって、理念に共感する人材の母集団形成に成功した医療法人のケーススタディ。






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



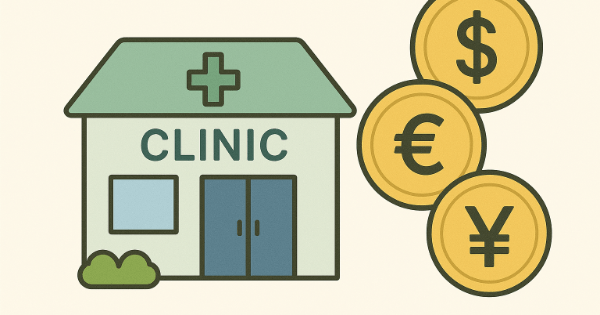
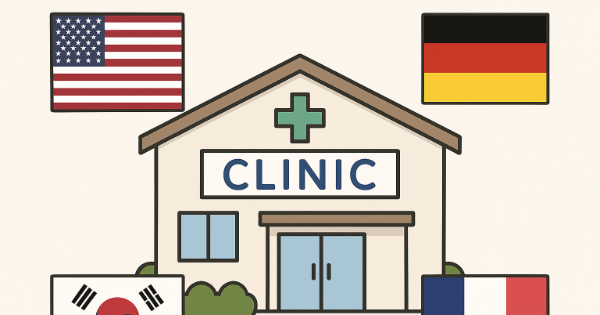
![看護師採用で“最低限ここだけ”の個人情報・マイナンバー取扱いガイド[保存期間・収集タイミング・委託時の注意点まで]](https://cdn.prod.website-files.com/640d966ca29de959e9f69b68/68d3f0cd471eb4dccfe97c23_ChatGPT%20Image%202025%E5%B9%B49%E6%9C%8824%E6%97%A5%2022_22_13-min.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
