はじめに:採用の壁は「仕事」より「暮らし」の不安
全国の医療機関が、それぞれの地域で、熱意ある看護師や医師を求めています。その採用活動は、今や病院の近隣地域だけにとどまりません。インターネットを通じて、北海道に住む看護師が沖縄の病院に興味を持つことも、ごく当たり前の時代になりました。
しかし、遠い場所にある病院で働くことを、自分自身の立場として想像してみてください。そのとき、私たちの心をよぎるのは、新しい職場での仕事内容への期待よりも先に、暮らしに対する現実的で、切実な不安ではないでしょうか。
「知らない土地で、安心して住める場所はすぐに見つかるだろうか」「引っ越しには、どれくらいのお金がかかるんだろう。今の貯金で足りるだろうか」「毎日の通勤は、ストレスなくできるだろうか。車は必要なんだろうか」「もし家族も一緒なら、子どもの学校や保育園は?パートナーの仕事は?」
候補者が応募の一歩手前で立ち止まってしまうとき、その理由の多くは、給与の額面や仕事のやりがいといった専門的な問題ではありません。見知らぬ土地で、ゼロから生活を再構築することへの、あまりにも自然で、人間的な不安です。
この記事は、そうした候補者の不安にどう寄り添えるかを考えるための一助です。財務的な話や制度の複雑な解説に終始するのではなく、一人の新しい仲間を、そして時にはその家族を、地域の一員として温かく迎え入れるために、私たちができる具体的なサポートの形について、現場の声も交えながら、ゆっくりとお話ししていきたいと思います。
1. 新しい生活を支える、3つの柱
遠くから来てくれる仲間を支えるために、まず考えたい具体的なサポートは、大きく分けて3つの柱があります。それは「通勤」「住まい」そして「初期費用」です。これらは、新しい生活を始める上での物理的・経済的な土台となります。
柱1:毎日の「通勤」を、ストレスのない時間に
新しい職場での生活は、毎日の通勤から始まります。一日の始まりと終わりを過ごすこの時間を、少しでも安心できるものにすることは、基本的な配去の一つです。特に、土地勘のない場所での通勤ルートを考えるのは、想像以上にストレスがかかるものです。
公共交通機関を利用する場合は、最も合理的で経済的な経路の実費を支給するのが一般的です。大切なのは、事前に分かりやすくその旨を伝えることです。
自動車での通勤を考える仲間もいるでしょう。その場合は、駐車場の有無や場所、利用料金といった情報が非常に重要になります。また、通勤距離に応じて非課税で手当を支給する国の制度があり、多くの病院で活用されています。具体的な金額は以下の通りです。
こうした制度があること、そして申請手続きが煩雑でないことを伝えるだけで、日々の生活への不安を少し和らげることができます。
柱2:生活の基盤となる「住まい」を用意する
見知らぬ土地での家探しは、おそらく新しい生活を始める上で最も心労の大きい作業です。その負担を軽くすることは、遠方採用において最も喜ばれるサポートかもしれません。
方法の一つは、家賃の一部を補助する「住宅手当」です。これは、職員が自分で住む場所を選びたい場合に適しています。相場は地域によって異なりますが、月1.5万円から2.5万円程度が一般的です。大切なのは、支給対象や条件を明確にし、職員間の公平性を保つことです。
もう一つ、より直接的で心強いサポートが、病院が用意した「社宅」や「借り上げ社宅」です。これは、病院が所有している、あるいは民間のアパートやマンションを借り上げて、職員に安価で提供する仕組みです。
社宅の最大のメリットは、土地勘のない場所で、時間と労力をかけて家を探す必要がないことです。特に、家具や家電(ベッド、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、カーテンなど)を備え付けておけば、採用が決まった仲間は、文字通りスーツケース一つで新生活をスタートできます。
家賃も、市場価格の半額程度の負担で住めるように設定している病院が多く、これは職員にとって大きな経済的メリットになります。実務的な話をすると、職員の家賃負担を市場家賃の半分程度以上に設定することで、家賃差額が給与として課税されるのを避けることができます。これは、職員の実質的な手取り額を増やすことにも繋がる、大切な配慮です。
場所の選定も重要です。病院のすぐ近くで通勤の利便性を重視するのか、少し離れた静かな住宅街でプライベートな時間を大切にしてもらうのか。スーパーや商店街、公園などが近くにあるか。そうした視点で物件を選ぶことも、温かい心遣いの一つです。
柱3:最初の大きな壁、「初期費用」を乗り越える手伝い
新しい生活を始めるには、まとまったお金が必要です。敷金・礼金、仲介手数料、そして引越し業者への支払いなど、数十万円が必要になることも珍しくありません。この初期費用をサポートすることは、転職を決断する際の最後のひと押しになります。
一般的なのは、引っ越しにかかった費用を、領収書に基づいて後から精算する方法です。規程で上限額(例えば20万円など)を設けつつ、その範囲内で実費を支給します。
しかし、より丁寧なのは、職員の当座の負担をゼロにする工夫です。例えば、病院が提携する引越し業者に直接支払いを行ったり、敷金・礼金などを病院が一時的に立て替えたりする方法です。入職前の、ただでさえ物入りな時期に、大きなお金を用意しなくて済むという安心感は、計り知れません。
大切なのは、「入社お祝い金」として一律の金額を渡すことと、引っ越しの実費をサポートすることの違いを理解することです。前者は給与として課税されますが、後者は原則として非課税です。つまり、実費をサポートするほうが、同じ金額でも職員の手元により多くを残すことができるのです。「引っ越しという現実的な課題を一緒に解決する」という姿勢を示すことは、金銭的な価値以上のメッセージを伝えます。
大切なのは、制度の裏側にある心遣い
制度をただ用意するだけでなく、その伝え方や使い方に少しの配慮を加えるだけで、温かみは大きく変わります。形だけの福利厚生ではなく、「あなたを歓迎しています」という気持ちを伝えるための、小さな工夫の積み重ねが重要です。
例えば、内定を伝えた後、社宅に決まった部屋の写真を何枚かメールで送ってみる。「窓からの景色はこんな感じですよ」「近くに美味しいパン屋さんがあります」といった一言を添えるだけでも、新しい生活への期待は膨らみます。
病院の周りにあるスーパーや、おすすめの定食屋さん、子どもが遊べる公園などをまとめた手作りの地図を渡すのも、素晴らしい歓迎の形です。既存の職員にアンケートを取って、「私のおすすめスポット」を集めてみるのも良いでしょう。
入職前に、地域の不動産屋さんを回ったり、役所の手続きをしたりするために、半日程度の特別休暇を認める、という配慮も非常に喜ばれます。
こうした小さな心遣いが、「この病院は、一人ひとりの職員の生活まで考えてくれる場所なんだ」という信頼に繋がり、入職後のエンゲージメントを高めるのです。
現場の声が語る、サポートの本当の意味
実際に、こうしたサポートは現場でどのように受け止められているのでしょうか。様々な立場の職員の声に、耳を傾けてみましょう。
ある病院の院長は、採用活動の哲学をこう語ります。「採用活動は、単なる労働力の確保ではありません。私たちの仲間になってくれる人を、家族も含めてこの地域に迎え入れる活動だと考えています。だから、まず私たちがその人の生活に責任を持つ姿勢を見せることが、信頼関係の第一歩なんです。」
子育てをしながら働く看護師は、こんな話をしてくれました。「子どもの急な病気は、働く母親にとって何よりの心配事です。この病院では、地域の病児保育サービスと法人契約をしてくれていて、いざという時に頼れる場所があるんです。この安心感がなければ、私は仕事を続けられなかったかもしれません。金銭的な支援だけでなく、働き続けられる環境を本気で考えてくれていることが、本当に嬉しいです。」
最近、遠方から転職してきたばかりの若い医師は、こう言います。「正直、知らない土地での一人暮らしには不安しかありませんでした。でも、病院が家具付きの社宅を用意してくれていて、引越しの費用も立て替えてくれたおかげで、お金の心配をせずに済みました。何より、入職前に担当の方が『何か分からないことがあったら、いつでも連絡してくださいね』とこまめに連絡をくれたのが、精神的に一番の支えになりました。」
看護師採用における「離職防止」×「応募増加」を両立させる福利厚生施策の具体例
❶ 入職前の金銭不安を解消する「前貸し制度」
ある地方の総合病院では、採用時に最大20万円までの前貸し制度を導入しています。これは引越しや制服代など、入職前後の突発的な支出に備える仕組みで、入職3か月以内に領収書で精算する形式を採用。病院が金銭を立て替えるのではなく、一時的な“立替の器”を提供するという形です。
実際にこの制度を利用した20代の看護師は、面接時にこう話しました。
「転職したかったけど、引っ越し代と数日分の生活費が足りなくて諦めかけていた。前貸し制度を紹介されて、『あ、ここなら来られる』と思えた」
この制度により病院は人材紹介会社を使わずに採用でき、紹介料100万円のコスト削減にもつながりました。人材確保と採用コスト削減の両立ができた好例です。
❷ 単身者・遠方出身者の応募を促進する「社宅+住宅手当セット」
首都圏のある中規模病院では、病院敷地のすぐ隣にワンルームの社宅を10部屋整備。加えて、通勤距離に応じて最大2万円の住宅手当を支給する制度を設けています。
この取り組みで特に変化があったのは、「地元を離れたいけれど、金銭面の不安がある地方在住の若手看護師」からの応募数です。
「駅近でキレイな社宅に、月3万円台で住めるなら挑戦してみようかなと。しかも生活家電付きで、カバン一つで引っ越せました」
— 新卒で北海道から上京した23歳の看護師
結果として、地方からの応募数が3倍に増加し、長期的に定着する人材の確保につながっています。社宅を「使わないと損」なものに設計した点がポイントです。
❸ 離職を防ぐ「勤務時間の可視化×柔軟シフト」
ある内科系クリニックでは、残業を減らすためにタイムカード連携型の勤怠管理アプリを導入。毎月の残業時間を数値で把握し、早番・遅番のバランスを勤務表で可視化するようにしました。
この取り組みの結果、「残業が少ない職場」という口コミが自然に広まり、地域のSNSやナース専用掲示板でも話題に。2024年後半には、求人を出して3日で10件の応募が集まりました。
「働いてみて本当に定時で帰れて驚いた。家庭との両立ができてありがたい」
— 育休復帰した30代女性看護師
「働きやすさ」を言葉で語るのではなく、数値で見せることが信頼獲得に繋がった事例です。
❹ 育児世代の離職を防ぐ「子連れ出勤&病児保育補助」
神奈川県内のある療養型病院では、敷地内に保育施設を設置。さらに、急な病児対応のためのベビーシッター費用を月5,000円まで補助する制度も導入しています。
とくに反応が大きかったのが、「保育園に預けられない日でも相談できる」という安心感です。
「子どもが熱を出しても、院内保育室で様子を見てもらえたり、補助が出てシッターさんに頼れたりと、とにかく続けやすい」
— 常勤で復職した元・非常勤看護師
病院としては、時短勤務でもシフトに入ってくれる貴重な人材の確保につながり、パートから常勤への移行も進みました。
❺ 施策導入のポイント:単なる制度で終わらせない「伝え方」
どの病院でも制度そのもの以上に重要なのが、伝え方と導線です。
- 求人票やホームページに「住宅手当あり」ではなく、「月3万円台で住める社宅+通勤費手当で実質家賃ゼロ」などと具体的に表記する
- 面接や電話時に「引越し不安ありますか?実は前貸し制度があって…」と悩みに寄り添う形で提示する
- LINEやメール配信では、「こんな制度あります」ではなく、「過去にはこんな方が利用して入職しています」という事例付きで紹介
いずれも、「制度のスペック」ではなく、「看護師が感じている不安に対して、どう効いたか」を軸に伝えることで、応募率も入職率も大きく変わってきます。
まとめ:仕事だけでなく、仲間を迎えるということ
遠くから来てくれる仲間を迎えるために、私たちにできることは何でしょうか。
通勤、住まい、初期費用。こうした生活面の不安を丁寧に解消する福利厚生は、確かに応募や定着に大きく影響します。
しかし同時に、「いきなり長期契約で働く」こと自体への心理的なハードルも、候補者を遠ざける大きな要因です。
実際、面接だけでは職場の雰囲気や人間関係は分かりません。看護師にとっても「ここで続けられるだろうか」という不安は消えないままです。
そこで有効なのが クーラのお試し勤務 です。
- まずは1〜4回の短期勤務から始められる
- 面接なしで「実際に働いてみる」機会を提供できる
- 適性や人柄を現場で見極められる
- 条件通知や帳票作成はシステムで自動処理
病院にとっては「応募の間口が広がる」「採用リスクを最小化できる」、看護師にとっては「気軽に応募できて、納得してから継続できる」という双方にメリットのある仕組みです。
福利厚生制度を一から整えるのは時間もコストもかかりますが、クーラを導入するだけで、応募数増加と定着率向上を同時に実現できます。
遠方からの応募や、復職を考える看護師に「まずは試してみませんか?」と伝えられることが、最大の安心材料になるのです。






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

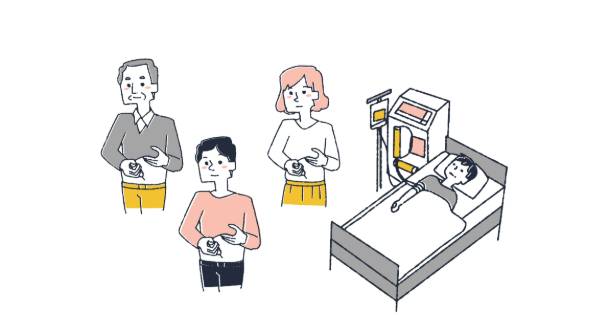




.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
