応募が集まる“院内公式”の顔をつくる
看護師の応募が集まりにくいと感じる時、新たな求人媒体を増やす前に、一度見直してみたいのが「自院の採用LP(ランディングページ)」です。採用LPとは、採用情報に特化して作られた、1枚の長いウェブページのことを指します。応募を検討している方は、多くの場合、求人媒体で貴院を見つけた後、公式サイトを訪れ、さらに詳しい情報を求めて採用LPを確認するという順序で情報を集め、最終的な判断を下す傾向が見られます。この採用LPの内容が不十分だと、どれだけ多くの求人媒体で告知を行っても、最後の段階で関心を失わせてしまう可能性があります。
この記事では、医療機関が採用LPを作成する上で必要となる要素と、すぐに活用できる構成のテンプレートをご紹介します。一般に公開されている事例や調査データを参考に、具体的な取り組みの例も挙げながら、院内でスムーズに採用ページを形にできるよう、順を追って解説します。
なお、短期の勤務や「お試し勤務」といった、まず数日間だけ働いてもらってから本採用を検討する、という採用フローを導入される場合には、外部のサービスを併用することで、日程調整などの手間を軽減できる場合があります。例えば、「クーラ」というサービスは、数日単位のスポット勤務から長期の勤務までを想定して設計されており、応募への入り口を増やすという点でも活用が考えられます。この記事の中でも、宣伝色を強くすることなく、自然な流れでこうしたサービスの活用場面にも触れていきます。詳細については、こちらのリンク(https://business.cu-ra.net/)からご確認いただけます。
背景・課題:応募者が知りたいのに、載っていない情報とは
よく見られる採用ページの課題点
採用LPを作成する上で、意図せず応募者の求める情報が欠けてしまうことがあります。例えば、以下のような点です。
- 仕事の具体的なイメージが見えない:配属される可能性がある診療科、担当する業務内容、シフトの詳細、使用している電子カルテや医療機器の種類といった情報が曖昧なケース。
- 人間関係や教育体制の実像が不明:新人、経験者、ブランクからの復帰者、それぞれの状況に合わせた導入プログラムの内容や、現場での教育(OJT)の担当者、評価や面談の頻度などが具体的に書かれていないケース。
- 日常の“時間割”がわからない:一日の業務の流れ、夜勤の具体的な体制、オンコールの有無や当番の設計など、日々の働き方を想像するための記述が不足しているケース。
- 写真や動画から働く姿を想像しにくい:院内の写真が、どこかで見たことのあるような一般的な素材画像のようで、自分が「ここで働く姿」を具体的にイメージしにくいケース。
- 応募や見学への手続きに心理的な“段差”がある:見学の申し込みが電話に限られていたり、面談の予約カレンダーがなかったり、LINEでの気軽な質問や簡易的なエントリーフォームが用意されていなかったりするケース。
データが示す“安心できる情報”の重要性
公的な調査からも、応募者がどのような情報を求めているかを推察することができます。例えば、日本看護協会が定期的に公表している「病院看護実態調査」では、看護職員の離職率(2023年度の正規雇用看護職員の離職率は11.3%、うち新卒は8.8%、既卒は16.1%)などのデータが公開されています。こうしたデータは、多くの医療機関が働きやすさの向上や定着支援の取り組みに力を入れていることの表れとも言えます。
このことから、応募を検討している看護師は、「勤務形態の柔軟性」「教育やサポート体制の充実度」「休暇の取得しやすさの実情」といった、安心して長く働けるかどうかを判断するための具体的な情報を強く求めている、と考えることができます。
実例紹介:採用LPで情報を“わかる化”している事例
ここでは、一般に公開されている情報の中から、採用ページの作り方や情報の見せ方について参考になる点をいくつかご紹介します(ここでの解釈は、本記事の筆者によるものです)。
1. レイアウトと情報の見せ方の順序
ウェブサイト制作会社などがまとめている記事では、クリニックから総合病院まで、様々な医療機関の採用サイトの事例が紹介されています。それらの多くに共通しているのは、訪問した人が迷わないように、情報の順番が整理されている点です。例えば、「最初に病院全体の雰囲気が伝わる写真やメッセージを見せる → すぐに募集職種一覧へ移動できるリンクを置く → 教育体制や福利厚生の詳しい説明 → 実際に働くスタッフの声 → 応募や見学への入り口」といった流れが、一つの型として見られます。これは、応募者が知りたい情報の流れに沿った、親切な設計と言えるでしょう。(参考:株式会社ワードの制作事例紹介記事など)
2. “働く人の声”の具体性
採用サイトのサンプルページなどを見てみると、単に「やりがいがあります」といった感想だけでなく、勤続年数や所属部署を明記した上で、具体的なエピソードを交えて紹介している例が多くあります。例えば、「入職3年目・循環器内科病棟」といった情報と共に、「この職場で成長できると感じた理由」が短い文章で具体的に語られています。スタッフの声だけでなく、その人が働く部署で使われている機器の種類や、受けた教育プログラムの内容などを近くに配置することで、応募者は自分の働く姿をより鮮明に想像しやすくなります。(参考:hr-symphony.co.jpのサンプルLPなど)
3. 求人媒体との役割分担を意識する
転職情報サイトの比較記事などを読むと、求人数の多さやキャリア相談サポートの手厚さなど、媒体ごとの強みがあることがわかります。医療機関の公式採用LPは、そうした求人媒体には載せきれない、より詳細な一次情報を掲載する場所として機能させることが効果的です。例えば、各病棟の詳しい特性、夜勤形態やオンコール当番の具体的な運用ルール、一日の業務の流れをタイムラインで示す、院内の様子が伝わる多くの写真や動画を掲載するなど、「ここにしかない情報」で媒体の情報量を補完し、応募者の最終的な判断を後押しする役割が期待されます。(参考:株式会社Method innovationなどの転職サイト比較記事)
4. 病院広報の視点から学ぶ
病院の広報活動を専門とする方の発信する情報の中には、「採用ウェブサイトの目的をはっきりさせる」「応募者に敬遠されがちなホームページの特徴を理解する」といった、採用活動の基本となる考え方が整理されています。特に、「誰が、どんな不安を感じているのかを想像し、その不安をどの順番で解消していくか」という設計の視点は、看護師採用LPを作る上でも非常に参考になります。(参考:noteなどで発信されている病院広報専門家の記事など)
解決アプローチ:そのまま使える“構成テンプレート”
以下に、1ページで完結する採用LPの標準的な構成案を示します。この順番で各ブロックを配置していくことで、応募者が抱える疑問や不安を自然な流れで解消していくことが期待できます。
1. ファーストビュー:写真と一文で“働く実感”を伝える
ページの最上部には、現場の様子が伝わる写真を配置します。個人が特定されないよう配慮しつつ、スタッフの笑顔や真剣な眼差し、病棟の空気感が伝わるような一枚が理想的です。キャッチコピーは、大げさな表現を避け、事実と病院の姿勢を簡潔に伝えます。例:「内科・整形外科の混合病棟/二交代制・仮眠室あり/ブランクのある方も歓迎します。まずは見学にお越しください。」そのすぐ下に、応募者が次の行動をすぐに起こせるよう、「病院見学の予約」「募集中の求人一覧」「LINEで相談」といった3つのボタンを設置します。もし、短期のお試し勤務を導入している場合は、ここに「数日からの体験勤務も可能です」といった一文を小さく記載し、詳細はページの下部で説明する形が良いでしょう。こうした「心理的な段差が低い」入り口を自院で用意するのが難しい場合は、クーラのような外部サービス(https://business.cu-ra.net/)を活用して、応募の入り口を別に設けるのも一つの現実的な方法です。
2. 募集職種スイッチャー:看護師・准看護師・外来看護・訪問看護など
応募者が自分の希望する職種の情報をすぐに見つけられるように、タブやページ内リンクを使って、各職種の詳細情報へすぐに移動できるようにします。各職種情報の先頭には、勤務形態(例:常勤/夜勤専従パート/週1日からのパート/スポット勤務)をはっきりと記載します。可能であれば、シフトの例(二交代・三交代の具体的な時間割や、オンコールの分担方法など)を図で示すと、より分かりやすくなります。
3. 業務と1日の流れ(診療科別)
具体的な業務内容を箇条書きで示します。使用している電子カルテのメーカー名や医療機器の機種名、主な患者さまの層や、よく行う処置などを記載すると、応募者が自分の経験を活かせるか判断しやすくなります。一日の流れをタイムライン形式で紹介します。(例:早番の場合…、夜勤の場合…)。夜勤やオンコールの運用ルールは特に詳しく説明します。当番の分担方法(一次対応は誰か、バックアップ体制はあるか)、平均的な呼び出し件数の目安、オンコールを免除される条件など、具体的な情報が安心につながります。混合病棟の場合は、日中と夜間の人員配置や、休憩・仮眠がどのように確保されているかを明記します。夜勤やオンコールの実態は、応募者が就職先を決める上で非常に重要なポイントとなることが多く、この部分の情報を率直に開示することが、入職後のミスマッチを防ぎ、定着率の改善にも結びつくとされています。(参考:日本看護協会「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」など)
4. 教育・支援:経験者・ブランク復帰・新卒それぞれの“入口”を分ける
応募者の経験や状況に合わせて、入職後の流れを分けて説明します。例えば、「オリエンテーション(初日)→ 現場でのOJT → 定期的な面談」という流れを三段階で図示するなど、視覚的に分かりやすく伝えます。電子カルテの操作は、多くの方が不安に感じる点です。その負担を軽減するための工夫(例:機種別の早見表を用意、操作方法の動画マニュアルを作成、最初の数日間は先輩が隣でサポートする回数を明記)を具体的に紹介します。経験者やブランクからの復帰を考えている方には、診療科ごとの「復職パス」のようなモデルプランを提示すると親切です(例:2週間のモデルスケジュールなど)。資格取得支援や外部研修への参加支援については、支援の上限額や対象となる資格・研修などを具体的に記載します。
5. 働きやすさ・制度(休暇、シフト希望、託児、住宅など)
休み希望の通りやすさ(例:「毎月3日まで希望休が出せます」「子どもの学校行事などは優先的に調整しています」など)、休憩室や仮眠室の設備、時短勤務や曜日固定シフトの可否といった、日々の働きやすさに関わる情報を開示します。院内託児所や保育費の補助、住宅手当や職員寮、通勤の負担を軽減するための制度(駐車場完備、送迎バスなど)についても詳しく説明します。可能な範囲で、有給休暇の平均的な消化率など、実際の取得実績を示すことも、信頼性を高める上で効果的です。
6. 数字で見る職場(“一般公開の調査”も参考に)
客観的なデータを用いて、職場の特徴を伝えます。例えば、看護師の平均年齢、常勤と非常勤の比率、可能であれば離職率の推移などを公開します。自院のデータだけでなく、日本看護協会などが公表している全国的な調査結果(例:看護職の離職率の全国平均)を併記し、自院の取り組みがどのような位置づけにあるかを説明することも、客観性を高める一つの方法です。(参考:日本看護協会「病院看護実態調査」)
7. 働く人の声と写真:経験年数・所属・働き方の“幅”を見せる
経験年数や所属部署、働き方(常勤、パート、子育て中など)が異なる3〜5名のスタッフに登場してもらい、「この病棟で働いていて嬉しかった瞬間」「成長を実感した場面」などを、短い言葉で語ってもらいます。長文よりも、15〜30秒程度の短い動画の方が、職場の雰囲気が伝わりやすい場合があります。その際、話す内容は簡潔にまとめます。複数のスタッフのコメントを、写真と共にタイル状に並べるレイアウトは、多くの情報をコンパクトに見せることができ、読みやすいとされています。(参考:hr-symphony.co.jpのサンプルLPなど)
8. よくある質問(応募前の実務的な不安を解消する)
応募を迷っている方が抱きがちな、実務的な疑問に先回りして答えます。例:「見学だけでも大丈夫ですか?」「子育て中の時短勤務は、どこまで相談可能ですか?」「夜勤はいつ頃から入ることになりますか?」「オンコールの当番を免除してもらうことはできますか?」など。見学当日の持ち物や服装、駐車場についての案内まで記載しておくことで、問い合わせの電話を減らし、応募者と自院双方の負担を軽減できます。
9. 応募・見学の入口(心理的な段差の低い選択肢を用意)
応募への最終的な入り口は、複数の選択肢を用意することが望ましいです。例えば、「見学予約カレンダー」「LINEでの相談窓口」「エントリーフォーム」の3つを基本とし、メールや電話での問い合わせ先も併記します。スポット勤務やお試し勤務といった制度を導入したい場合、クーラのようなサービス(https://business.cu-ra.net/)と求人掲載を連携させることで、候補日の調整などをスムーズに行うことができます。求人媒体経由で応募してきた方に対しても、「まずは見学から」「短期勤務を試してから」といった、リスクの低い選択肢を提示しやすくなります。
看護師採用サイトの作り方(実装の順番と注意点)
写真・動画は“今日の現場”の空気感を大切に
プロのカメラマンに依頼しなくても、院内の様子は十分に伝えられます。大切なのは、自然光が入る時間帯に撮影された、ありのままのナチュラルな写真を用意することです。撮影の際は、個人が特定されないように配慮することが不可欠です。マスクの着用や名札のぼかし、患者さまの情報が写り込まないように、細心の注意を払ってください。15〜30秒程度のスマートフォンで撮影した縦長の動画を3本ほど用意するのも効果的です。例えば、スタッフが行き交う病棟の廊下、ナースステーションでのやり取りの様子、休憩スペースの雰囲気などが伝わると、働くイメージが湧きやすくなります。
文章は、具体的な“行動の変化”がわかるように書く
抽象的な表現は避け、具体的な行動がイメージできる言葉で説明することが大切です。「教育に力を入れています」と書くよりも、「入職後のOJTは、最初の1ヶ月で3回、2ヶ月目に1回の面談を行います。電子カルテの操作は、初日に30分間の実践的な研修を実施します」と書く方が、応募者は入職後の自分の姿を想像しやすくなります。二交代・三交代制の具体的な勤務時間や、オンコールの運用ルールについても、可能な範囲で具体的に記載します。
求人媒体と公式サイトの役割分担
求人媒体の役割は、まず貴院の求人を「検索で見つけてもらう」ことです。そして、公式サイト・採用LPの役割は、そうして訪れた方に、媒体には載せきれない「一次情報の倉庫」として、より深く、安心できる情報を提供し、応募への最後の一押しをすることです。様々な求人媒体の比較軸(求人数、サポート体制、連絡の手段など)を理解した上で、公式サイトでは「ここでしか得られない情報」で応募者の不安を解消していく、という役割分担を意識すると良いでしょう。(参考:株式会社Method innovationなどの転職サイト比較記事)
検索で見つけてもらいやすくするための見出しサンプル(コピーして使用可)
採用LPに掲載する各項目の見出しは、応募者が検索する際に使いそうな言葉を意識すると、より見つけてもらいやすくなります。以下にサンプルを挙げます。
- 看護師採用の病院見学について|当日の服装・所要時間・持ち物・流れ
- 二交代制と三交代制の違い|夜勤回数の目安・仮眠・休憩室の環境について
- オンコール当番の分担方法|呼び出し頻度の目安と免除ルール
- ブランクのある看護師の方へ|2週間の復職研修プログラム例と評価シート
- 電子カルテの研修について|初日の操作研修と動画マニュアルのご案内
- 院内託児所・時短勤務・固定シフトの可否|子育て中の働き方相談窓口
- 先輩看護師の声|経験年数・所属部署・働き方の違いがわかるコメント集
- 見学申し込み・LINE相談|最短での応募ステップと所要時間
ワイヤーフレーム(文章だけで作れる“骨組み”)
ウェブページの専門的な設計図がなくても、以下の項目の順番を文章で書き出すだけで、ページの骨組みは作れます。
- ヒーローセクション:現場の写真1枚+キャッチコピー(診療科・勤務形態・見学への案内)
- 職種スイッチャー:看護師/外来看護/訪問看護/夜勤専従
- 1日の流れ・業務内容:診療科別の図解+電子カルテ・使用機器の名前
- 教育・復職支援:入職初日から2週間程度の研修メニュー
- 働きやすさ:休み希望のルール、仮眠、託児、住宅、通勤について
- 数字で見る職場:平均年齢・勤務形態の比率・離職率の推移(公開可能な範囲で)+一般公開されている調査の参考値(参考:日本看護協会)
- 働く人の声:経験年数と所属部署を明記して3〜5名(参考:hr-symphony.co.jp)
- よくある質問:応募前の実務的な不安を網羅
- 行動喚起(CTA):見学予約/LINE相談/応募フォーム
- ※スポット勤務や“お試し勤務”の制度を併設すると、応募への心理的なハードルが下がります。運用面の負担が懸念される場合は、クーラのエントリー連携機能などを活用することで、候補日の調整や短期就労に関わる手続きを簡略化できます。(
https://business.cu-ra.net/)
テキスト例(そのまま参考に書き換え可)
ファーストビューの文章例
「内科・整形外科の混合病棟です(二交代制/仮眠室あり)。私たちは、患者さん一人ひとりに向き合う丁寧な看護を大切にしています。病院見学は30分から受け付けておりますので、まずはお気軽な気持ちでお越しください。」
1日の流れ(早番の一例)
「8:30 申し送り → 9:00 検温・処置 → 12:00 休憩 → 13:30 点滴・記録 → 16:30 申し送り・退勤。電子カルテについては、初日に操作ガイドをお渡しし、二日目の朝に10分間の復習時間を設けています。」
教育・復職支援の文章例
「経験者やブランクのある方には、2週間の復職支援プログラムをご用意しています。初日はオリエンテーションと電子カルテの操作説明、二日目から現場でのOJTを開始し、週末に振り返りの面談を行います。配属先は、ご本人の希望とこれまでの経験を丁寧にお伺いした上で、無理のない範囲で調整いたします。」
応募・見学の文章例
「病院見学は、平日の10:00〜、または16:00〜の時間帯で、30分から受け付けております。土曜の午前中をご希望の場合もご相談ください。服装は自由、履歴書も不要です。お子さまとご一緒の下見も歓迎しています。」
写真・FAQ・応募ボタンの作り分け(現場でのコツ)
- 写真:病棟の全体像、ナースステーション、休憩室、病院の外観など、応募者が出勤してから退勤するまでの「動線」を意識して写真を並べると、働く姿を想像しやすくなります。
- FAQ(よくある質問):応募をためらう理由になりがちな不安(オンコール、夜勤回数、時短勤務、曜日固定シフト、配属先の決定方法など)について、正直に回答します。
- CTA(応募ボタンなど):ページの途中にも、控えめなサイズで見学案内のボタンを複数配置しておくと効果的です。そして、ページの最後に「見学」「LINE」「応募」の3つの選択肢を横並びで提示します。
求人媒体から訪れる人の“最後の一押し”をつくる
看護師向けの転職サイトは情報量が豊富ですが、院内の細かな実情(夜勤体制やオンコール当番の具体的な分担、使用している機器や電子カルテの機種、写真や動画で伝える職場の雰囲気)は、公式サイトの採用LPでしか詳細に語ることができません。各種媒体の強み(求人数の多さ、サポート体制、連絡手段など)を理解しつつ、公式サイトは「一次情報」で不安を解消する、という役割分担が有効とされています。(参考:株式会社Method innovationなど)
また、「短期の体験勤務から始めて、相性が合えば継続・常勤へ」という、応募者と病院側の双方にとってリスクの低い導線を用意することも、応募の増加につながる場合があります。手続きや連絡、日程調整の業務量が増えることが気になる場合は、クーラのようなサービス(https://business.cu-ra.net/)を部分的に併用することで、見学から短期勤務、そして本採用へという滑らかな流れを、既存の運用に無理なく付け加えることが可能です。
まとめ:大切なのは、情報の順番と“安心の濃度”です
1ページで構成された採用LPでも、その内容を工夫することで、応募者が抱える不安を大きく減らすことができます。大切なのは、情報を見せる「順番」と、一つひとつの情報の「安心できる濃さ」です。
- 写真とキャッチコピー → 2. 募集職種一覧 → 3. 業務内容と1日の流れ → 4. 教育・復職支援 → 5. 働きやすさ・制度 → 6. 数字で見る職場 → 7. 働く人の声 → 8. よくある質問 → 9. 心理的な段差が低い応募の入り口。
この型に沿って情報を整理するだけでも、求人媒体から訪れた方が「応募する」という次の行動に移りやすくなることが期待できます。自院の採用業務のリソースに不安がある場合には、見学の予約受付や短期勤務の希望者との日程調整といった業務の一部を、外部のサービスに任せるという考え方も現実的です。クーラは、数日からの勤務を経て継続雇用へ、という流れを前提に設計されているため、既存の求人募集と並行して運用しやすい仕組みと言えます。まずは自院の採用LPの最後に、「短期勤務から試してみる」という選択肢を一つ加えることで、応募への段差を少し下げてみることから始めるのも良い方法でしょう。(https://business.cu-ra.net/)
参考(一般に公開されている情報)
- 日本看護協会「病院看護実態調査」:離職率や勤務実態に関する近年の傾向がわかります。(出典:日本看護協会ウェブサイトなど)
- 制作会社の事例まとめ記事:採用サイトのレイアウトや情報の見せ方のヒントになります。(出典:株式会社ワードのウェブサイトなど)
- サンプルLPの“働く人の声”の構成:短いコメントと所属情報の組み合わせ方が参考になります。(出典:hr-symphony.co.jpのウェブサイトなど)
- 媒体比較系の公開記事:求人媒体の強みを理解し、公式サイトで一次情報を補完するという視点の参考になります。(出典:株式会社Method innovationのウェブサイトなど)
このテンプレートをたたき台として、まずは写真の更新や「1日の流れ」の項目から着手してみてはいかがでしょうか。大がかりなウェブサイトの改修を行わなくても、情報の順番と濃度を整えるだけで、応募への“最後の一歩”を後押しできる可能性があります。






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



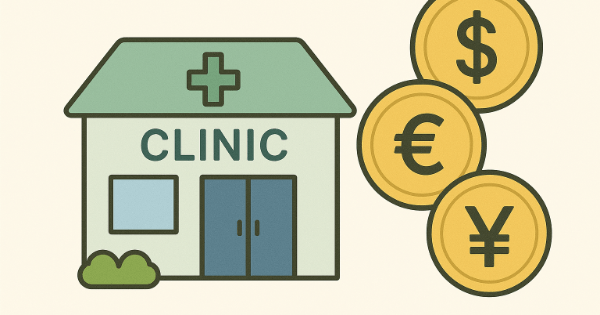
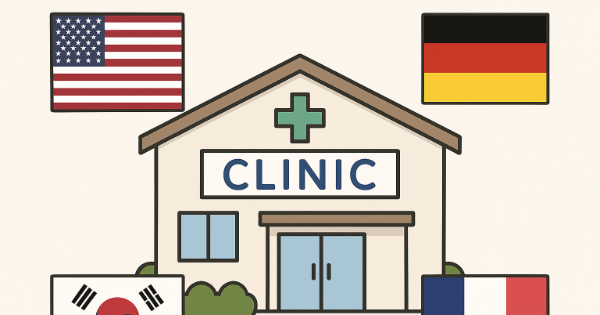
![看護師採用で“最低限ここだけ”の個人情報・マイナンバー取扱いガイド[保存期間・収集タイミング・委託時の注意点まで]](https://cdn.prod.website-files.com/640d966ca29de959e9f69b68/68d3f0cd471eb4dccfe97c23_ChatGPT%20Image%202025%E5%B9%B49%E6%9C%8824%E6%97%A5%2022_22_13-min.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
