なぜ「副業のルール化」がいま必要か
看護師の働き方は、近年大きく変化しています。「空いた時間を有効活用して単発で働きたい」「現在の職場では経験できない領域でスキルを磨きたい」「収入の柱を複数持ちたい」といった、多様なニーズが現場から生まれています。このような状況は、多くの医療機関の管理者様にとっても無視できない変化と言えるでしょう。
一方で、院内では「副業による疲労が、本業である看護の質に影響しないだろうか」「患者様の個人情報や院内の機密情報が、外部で不適切に扱われるリスクはないか」「すぐ近隣の競合する医療機関で働かれると、人材の引き抜きや患者様の移動につながらないか」といった、もっともな懸念の声が根強くあることも事実です。
こうした背景を受け、厚生労働省はモデル就業規則の見直しやガイドラインの改定を重ね、企業に対して原則として副業や兼業を認める方向性を示しています。しかし、無条件にすべてを認めるということではありません。ガイドラインでは同時に、本業の労務提供に支障がある場合、業務上の秘密が漏洩するリスクがある場合、競業によって自院の利益が害される場合、そして自院の名誉や信用を損なう行為がある場合には、副業を制限できるとしています。
この「原則容認」と「制限可能」という二つの側面を、いかに自院の状況に合わせて具体的に運用していくか。ここに、多くの医療機関が頭を悩ませるポイントがあります。単に「副業は原則禁止」あるいは「許可なく行ってはならない」という一文を就業規則に設けるだけでは、実態に即した運用は難しく、かえって無許可の副業を増やしてしまう可能性も否定できません。
そこで重要になるのが、「どこまでを許可し、どこからを制限するのか」という具体的な線引きを明確に言語化し、ルールとして整備することです。明確なルールがあれば、職員は安心して副業の相談ができ、管理者は一貫性のある判断を下すことができます。結果として、職員の多様な働き方を支援しつつ、組織としてのリスクを管理することが可能になります。
本稿では、実在する医療機関が公開している資料や、一般に公開されている調査、専門家の解説などを参照しながら、副業を容認する際の現実的で再現しやすい「ルールの設計例」を提示します。特に、「診療科の組み合わせ」「時間帯の線引き」「守秘義務と競業避止の取り決め」という三つの重要な観点から、具体的な規程の作り方を丁寧に解説していきます。
(院内で短期的な人材不足に対応したり、副業希望の看護師をスポットで受け入れたりする体制を整える際には、看護師の登録が多い「クーラ」のようなサービスを併用することも有効な選択肢の一つです。副業ルールの整備と合わせて、外部人材の活用方法を検討する際に役立つ情報も提供しています。詳しくは https://business.cu-ra.net/ をご覧ください。)
背景と課題:法令の方向性と実務現場のギャップ
看護師の副業を考える上で、まず押さえておくべきは、所属する医療機関の設置主体による違いと、国が示すガイドラインの内容、そして現場で実際に起こりうるトラブルです。
公務員看護師と民間病院看護師での大きな違い
看護師の副業に関するルールは、まずその身分によって大きく異なります。
国立病院機構や都道府県立病院、市立病院、保健所などで働く看護師は、多くが公務員または準公務員という身分です。国家公務員法や地方公務員法では、職員が営利企業の役員を兼ねたり、自ら営利企業を営んだりすること(自営兼業)、あるいは報酬を得て事業や事務に従事すること(他社勤務)は、原則として禁止されています。許可を得れば例外的に可能になる場合もありますが、そのハードルは一般的に高いとされています。これは、公務員には職務専念義務があり、公共の利益のために働くことが求められるためです。
一方、医療法人や社会福祉法人、個人が開設するクリニックなど、民間医療機関で働く看護師には、これらの法律は直接適用されません。適用されるのは労働基準法であり、労働時間外の過ごし方、つまり副業をどうするかは、基本的には個人の自由とされています。そのため、民間医療機関では副業を全面的に禁止するケースは少なく、多くは「事前の許可制」を前提として運用しているのが実情です。
厚生労働省ガイドラインが示す「容認の原則」と「制限の条件」
国は働き方改革の一環として、副業・兼業の普及促進を図っています。厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、その中心的な指針となるものです。このガイドラインでは、裁判所の判断例などを踏まえ、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由」であるという考え方を明確に示しています。
つまり、企業が労働者の副業を一方的に、かつ全面的に禁止することは、特別な理由がない限り難しいというのが現在の法的な解釈の主流です。
ただし、同ガイドラインは、企業が自社の利益を守るために、以下のような場合に副業を制限または禁止することが許容されるとしています。これらの条件は、医療機関が副業規程を作成する際の根幹となる部分です。
同時に、ガイドラインは企業側(医療機関側)の留意点として、労働時間の管理と健康への配慮、そして秘密保持の徹底についても明記しています。これらの条件や留意点を踏まえて、自院のルールを構築することが求められます。
実務で起こりがちなトラブル
「原則禁止」という規程だけでは、現場で起こる個別のケースに対応しきれないのが実情です。例えば、以下のような事例は、多くの法律事務所のウェブサイトなどで、労務トラブルの代表例として解説されています。
- 「夜間に飲食店でアルバイトを始めた職員の、日勤中の居眠りや業務中のミスが明らかに増えた。注意をしても改善が見られない」
- 「退職した職員が、在職中に副業で関わっていた訪問看護ステーションに、担当していた患者様の情報を持ち出して引き継いでいたことが発覚した」
- 「近隣のクリニックで看護師として働き始めたが、業務内容が自院の診療と競合するのかどうか、判断の基準が曖昧で対応に困っている」
- 「SNSで個人のアカウントを使い、美容関連商品の宣伝販売を副業として行っていたが、その投稿内容に病院名を記載し、特定の治療法を推奨するかのような表現があった」
これらの事例が示すように、問題が発生してから対応するのでは手遅れになることがあります。事前に「許可と禁止の具体的な線引き」「申請から許可までの流れ」「ルールに違反した場合の対応」までを明確に言語化し、職員に周知しておくことが、トラブルを未然に防ぐ上で不可欠です。
実例紹介:日本の医療機関における「兼業・副業」の公開ルール
実際に、日本の医療機関ではどのように副業・兼業のルールを運用しているのでしょうか。ここでは、ウェブサイトで一般に公開されている資料から、いくつかの事例を紹介します。設置主体や組織の規模によって表現は異なりますが、「事前の許可申請」「所定の様式」「提出期限の設定」「よくある質問(FAQ)の公開」といった、実務的な運用の骨格が共通して見られます。
公立系の事例:東京都立駒込病院
東京都立病院機構に属する駒込病院では、兼業を希望する外部の関係者(依頼者)向けに、手続きをウェブサイトで明示しています。兼業依頼の手順、必要となる書類、郵送先、そして問い合わせの多い事項をまとめたFAQが整理されています。特に、事前審査のために提出を求める書類が具体的で、「病院長宛の依頼状(原本)」「兼業の内容が分かるプログラムやパンフレット」「依頼元の団体概要が分かる資料」、そして依頼元が製薬会社などの場合は「透明性ガイドラインに関する資料」まで求められています。これは、兼業の内容を多角的に審査し、適切性を判断するための仕組みと言えます。
公立系の事例:地方独立行政法人 大阪市民病院機構
大阪市民病院機構では、職員の兼業に関する手続きを詳細に公開しています。「兼業依頼状(許可申請書・許可書)」のテンプレート(ひな形)を配布し、その記入例や手続きの要綱をまとめたPDF、さらにはQ&Aまでウェブサイトで提供しています。各病院の総務課に書類を提出し、審査を経て許可が下りるという流れが明確に示されており、回答書が必要な場合の取り扱いや、申請から許可までの標準的な期間など、実務の細部にまで配慮された運用がなされています。
国立大学病院系の事例:東北大学病院
東北大学病院も、兼業依頼に関する手続きをウェブサイトで公開しています。特徴的なのは、提出期限を「兼業許可を希望する日の2週間前まで」と具体的に設定している点です。これにより、事務手続きや審査に必要な時間を確保し、計画的な運用を可能にしています。また、「大学として職員を派遣する形式をとることで、兼業の許可回答とみなす」といった回答の考え方も明示されており、申請者と病院側の認識のズレを防ぐ工夫が見られます。
公立系の事例:地方独立行政法人 神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立医療センター中央市民病院では、「許可希望日の3週間前までの提出」をルールとし、依頼状をメールで提出することも可能としています。注目すべきは、FAQの中で「学会や研修会への参加・聴講は兼業には当たらない」という線引きを明確にしている点です。これにより、職員の自己研鑽を目的とした活動を萎縮させることなく、管理が必要な「報酬を伴う業務」に絞って申請を求めるという、効率的で合理的な運用を行っていることがうかがえます。
民間医療機関の一般的な傾向
民間医療機関の場合、公立病院のように手続きを詳細に外部公開しているケースは多くありません。しかし、各種の調査や転職情報サイトの解説、看護師の体験談などを総合すると、副業を全面的に禁止している施設は少なく、許可制を前提に容認する方向へ進んでいる傾向が見られます。一方で、公務員身分の看護師が働く病院では、法律により原則禁止という大きな枠組みが存在するという棲み分けが、依然としてあるようです。例えば、介護・医療系の単発バイトを紹介するサービス「カイテク」などの利用者が増えている背景にも、こうした民間病院での副業容認の流れが関係していると考えられます。
ルール設計の参考になる公的資料
自院でルールを設計する際には、これらの実例に加え、公的な指針を参照することが重要です。
- 副業・兼業の促進に関するガイドライン(厚生労働省): 副業を認める際の基本的な考え方、制限が可能な場合の要件、労働時間管理のあり方などが網羅されています。
- 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(厚生労働省): 特に、副業における情報漏洩リスクを管理する上で参照すべき指針です。電子カルテのアクセス記録(ログ)の管理、USBメモリなどの可搬型記録媒体(可搬媒体)の取り扱い、個人所有のスマートフォンやPCの業務利用に関するルールなどを定める際の基準となります。
- 秘密保持に関する誓約書のひな形: 多くの法律事務所や社会保険労務士事務所が、ウェブサイトで医療機関向けの誓約書のサンプルを公開しています。これらを参考に、自院の実情に合わせた誓約書を作成することができます。
これらの公開事例や公的資料は、これから副業規程を整備しようとする医療機関にとって、非常に有益な羅針盤となるでしょう。
解決アプローチ:副業容認の「線引き」をどう作るか
それでは、具体的にどのようなルールを設ければよいのでしょうか。ここでは、民間病院やクリニックでの現実的な運用を想定した、副業規程の設計例を項目別に提案します。これらの案を参考に、各医療機関の規模、診療科の特性、地域の状況に合わせて取捨選択し、就業規則や内規、誓約書、申請様式などに反映させてみてください。
1) 診療科ベースの線引き:競業・守秘義務の観点から
方針例A:同一の診療圏・同じ患者層を対象とする「直接的な競合」は原則として許可しない
- 具体的なルール: 自院が整形外科の外来診療を中心に行っている場合、半径数キロメートル以内にある、同じく整形外科の有床クリニックで夜間診療のアルバイトを行う、といったケースは制限の対象に含めることを検討します。この「半径○km」という地理的な範囲や、「同一の主要な診療機能」という定義をあらかじめ定めておくと、判断基準が明確になります。
- 考え方: これは、厚生労働省のガイドラインが示す「競業により自社の利益が害される場合」に該当する可能性を考慮したものです。ただし、職員の職業選択の自由を過度に制限しないよう、配慮も必要です。例えば、「別の診療科であれば問題ない」「エリアが異なれば許可する」といった代替案を示せるようにしておくと、職員の納得感を得やすくなります。
方針例B:守秘義務のリスクが高い領域は「業務内容を限定」または「匿名化」を前提とする
- 具体的なルール: 集中治療室(ICU)、救急救命室(ER)、感染症専門病棟、希少疾患の研究センターなど、患者様の症例が特殊であったり、プライバシーへの配慮が特に求められたりする部署については、副業の許可にあたり条件を付すことが考えられます。例えば、「副業先での業務は、採血や身体の清拭などの基本的な処置に限定し、カルテの記録やサマリーの作成は行わない」といった業務範囲の限定や、「研究発表や講演活動で症例を用いる際は、個人が特定できないよう厳格に匿名化処理を行う」といった条件を設けます。
- 考え方: 患者様の機微な情報が、意図せず漏洩することを防ぐための措置です。厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考に、電子カルテへのアクセス記録の管理、USBメモリなどの使用ルール、個人所有のスマートフォンでの業務データ扱いの禁止などを院内の規程に明記し、副業の許可条件と結びつけることが有効です。
方針例C:研修、講演、学会への参加は「兼業に当たらない」という扱いを検討する
- 具体的なルール: 神戸市立医療センター中央市民病院の事例にもあるように、「報酬が発生しない学会や研修会への参加・聴講は、自己研鑽の一環とし、兼業の申請は不要」とFAQなどで明示します。一方で、製薬会社などから依頼されて行う講演のように、有償の活動については申請の対象とし、その内容が分かる資料(プログラムやスライドなど)の提出を許可の条件とします。
- 考え方: これにより、職員の学習意欲を妨げることなく、管理が必要な業務に絞って手続きを求めることができます。事務的な負担を軽減し、本来注力すべきリスクの高い副業の審査に時間を割くことにもつながります。
2) 時間帯の線引き:疲労と労働時間管理の観点から
方針例D:本業の勤務開始前および終了後の一定時間は、他の就労を制限する
- 具体的なルール: 「本業の勤務が終了してから次の副業を開始するまでに、少なくとも○時間の休息時間を設けること」「本業の勤務開始前○時間は、副業に従事しないこと」といったルールを設けます。特に、夜勤明けにそのまま別の施設で日勤業務を行うといった、明らかに休息が不足する働き方は、原則として許可しない方針が望ましいでしょう。
- 考え方: これは、職員の健康を守るための安全配慮義務の観点から非常に重要です。厚生労働省のガイドラインでも、使用者の健康管理責任が強調されています。申請時に、副業を含めた1週間のスケジュールを提出してもらい、十分な休息が確保されているかを確認するプロセスを設けることが有効です。
方針例E:週40時間を超える労働が見込まれる場合は「面談」を必須とする
- 具体的なルール: 労働基準法では、副業・兼業先の労働時間は通算して管理することが原則とされています。しかし、他の医療機関での正確な労働時間を自院で完全に把握することは実務上困難です。そこで、代替策として、副業の申請時に本人が想定する1週間の総労働時間を自己申告させ、その時間が週40時間を大幅に超えるような場合は、看護部長や人事担当者との面談を設定し、健康状態や業務への影響についてヒアリングを行う、という仕組みが考えられます。また、自院の就業規則で定める夜勤の連続回数の上限や、勤務間インターバルのルールを、副業を行う職員にも改めて周知徹底します。
- 考え方: 強制的な労働時間の管理は難しくても、対話を通じて過重労働の兆候を早期に発見し、本人に注意を促すことは可能です。これは、職員を守ると同時に、医療安全を確保する上でも重要な取り組みです。
3) 守秘・競業の取り決め:誓約書と具体的な行動規範の2本立てで
方針例F:秘密保持誓約書に、具体的な行動レベルの禁止事項を盛り込む
- 具体的なルール: 入職時に取り交わす誓約書とは別に、副業を許可するタイミングで、専用の秘密保持誓約書に署名を求めます。その中には、「患者情報や経営情報をいかなる形式でも外部に持ち出さない」という一般的な内容に加え、「個人所有のスマートフォンで患者情報を撮影しない」「SNSに職場で見聞きした症例や人間関係について投稿しない」「休憩中や退勤後の雑談であっても、患者様が特定できるような形で症例の話をしない」といった、具体的な行動レベルでの禁止事項を明記します。
- 考え方: 「秘密を守る」という抽象的な理念だけでなく、やってはいけないことを具体的に示すことで、職員の意識を高め、無自覚な情報漏洩を防ぐ効果が期待できます。社会福祉法人浴風会のウェブサイトで公開されているような、具体的な誓約書の文例も参考になります。
方針例G:競業を回避するための「地理的範囲」と「機能的範囲」を定義する
- 具体的なルール: 方針例Aとも関連しますが、競業避止義務の範囲を客観的に定義します。「半径○km以内」といった地理的範囲と、「同じ主要な診療機能(例:急性期、回復期、慢性期、在宅、外来透析など)を持つ」という機能的範囲を掛け合わせて、「自院から半径5km以内の急性期病院での、病棟看護師としての勤務は原則として許可しない」のように具体化します。
- 考え方: 職員の転職の自由や職業選択の自由を不当に制限しないよう、競業とみなす範囲は、自院の利益を守るために合理的に必要な範囲に限定することが大切です。広すぎる範囲を設定すると、法的に無効と判断される可能性もあります。
4) 申請・許可・更新の流れ
方針例H:許可は「案件ごと」かつ「年単位での更新制」とする
- 具体的なルール: 副業を始める際には、必ず所定の様式で申請させます。申請書には、①副業先の名称・所在地・連絡先、②従事する具体的な業務内容、③勤務する時間帯や頻度、④雇用形態(アルバイト、業務委託など)と報酬の有無、⑤患者情報などの個人情報にアクセスする可能性の有無、⑥副業を含めた想定総労働時間と休息の確保計画、といった項目を盛り込みます。そして、一度出した許可は永続的なものではなく、有効期間を最長1年などと定め、毎年更新手続きを行うようにします。また、許可の条件としていた業務内容や勤務時間が途中で変わる場合は、その都度再申請を義務付けます。さらに、「本業への支障が見られる場合や、守秘義務違反の疑いがある場合には、許可を取り消すことがある」という条項も明記しておくことが重要です。
- 考え方: 大阪市民病院機構などが公開している依頼状や許可書のひな形を参考に、自院に必要な項目を盛り込んだ申請様式を整備します。更新制にすることで、職員の状況の変化を定期的に把握し、形骸化した許可が続くことを防ぎます。
方針例I:申請の提出期限を明確に定める(例:2〜3週間前ルール)
- 具体的なルール: 東北大学病院や神戸市立医療センター中央市民病院の事例のように、「副業を開始したい日の2週間前(または3週間前)までに申請書を提出すること」を就業規則や内規に明記します。
- 考え方: 直前の申請では、内容を十分に審査する時間がありません。事前に期限を区切ることで、管理部門は余裕をもって申請内容を確認でき、申請者本人も計画的に準備を進めることができます。
5) 点検・記録:負担を増やさず「最低限」を仕組み化する
- 具体的なルール: 事務的な負担を増やしすぎないよう、点検の仕組みはシンプルにします。例えば、「四半期に一度、簡単な報告書で、実際の労働時間や業務内容に変更がなかったかを自己申告してもらう」「産業医や保健師との定期面談の際に、希望者や長時間労働が懸念される職員に対して、副業による心身の負担がないかヒアリングを行う」「副業先で経験したヒヤリハット事例など、院内全体の医療安全に貢献する学びがあれば、個人名や施設名を伏せた上で報告してもらう」といった取り組みが考えられます。また、前述の通り、参加・聴講のみの学会などは申請不要とすることで、許可対象を絞り、運用負荷を下げます。
6) ケース別の「許可・保留・不可」の具体例を示す
規程や申請書とあわせて、具体的な判断例をあらかじめ示しておくことで、職員の理解は格段に深まります。
7) 書式・誓約書の準備
これらのルールを運用するために、以下の書式を準備しておくとスムーズです。
- 兼業依頼状/許可申請書: 病院長(または理事長)宛ての正式な申請書。
- 業務内容を証明する資料: 副業先が発行する雇用契約書や、業務内容がわかるパンフレットなど。
- 副業先の団体概要がわかる資料: 会社のウェブサイトのコピーや定款など。
- 秘密保持に関する誓約書: 副業に特化した内容を盛り込んだもの。
これらの提出物や提出期限、許可・不許可の回答方法などを、院内のイントラネットや職員に配布する資料で明確に案内しておくことが、円滑な運用の鍵となります。
まとめ:現場が安心できる「3つのセット」の整備
これまで見てきたように、看護師の副業を適切に管理し、職員と組織の双方にとって良い形で運用していくためには、単なる精神論や曖昧な禁止規程では不十分です。現場の職員も管理者も安心して制度を利用できるようにするには、以下の「3つのセット」を整備することが効果的です。
- 線引きの言語化: 「どの診療科」「どのエリア」「どの時間帯」「どの情報」が制限の対象となりうるのか。競業や守秘義務に関するルールを具体的に文書に落とし込むこと。
- 申請・許可・更新の型(プロセス)の確立: 誰が見ても分かる申請様式、明確な提出期限、そして許可の有効期間と更新手続き、さらには問題発生時の許可撤回条項まで、一連の流れを仕組み化すること。
- 点検の最小限の仕組み: 職員の負担を増やしすぎない範囲で、定期的な自己申告や必要に応じた健康面談、ヒヤリハットの共有など、状況を把握し続けるための簡単な仕組みを設けること。
これらの要素を、数ページの簡潔な内規と、1枚の誓約書、1〜2枚の申請様式に落とし込む。たったこれだけの準備で、現場の「どうすればいいのだろう」という不安は大きく軽減され、看護師の柔軟な働き方を、組織として前向きに後押しできるようになります。
重要なのは、厚生労働省のガイドラインが示す「容認の原則」と「制限の合理性」のバランスです。職員のキャリア形成や生活を不当に縛るような過度に広い禁止規程や、ルールはあるものの実際には誰も申請しないような骨抜きの運用になることを避け、自院の実情に合った、現実的で公平なルール作りを目指しましょう。
クーラの導入:副業人材の受け入れと自院職員の働き方の選択肢として
院内の副業ルールを整備する過程で、短時間勤務やスポット勤務といった柔軟な働き方へのニーズが、自院の職員からも上がってくるかもしれません。また、急な欠員補充や繁忙期の増員のために、外部から短期的に人材を受け入れたいと考えることもあるでしょう。
このような、短時間・スポットでの人材活用を検討する際に、整備した副業の枠組みと相性が良いのが、外部の看護師に単発で業務を依頼できるサービスです。中でも「クーラ」は、短期・単発で働きたい看護師が多く登録しており、自院で定めた副業ルール(勤務可能な時間帯、守秘義務や競業避止の条件など)を求人の募集要件に具体的に落とし込みやすいという特長があります。
初めて外部のスポット人材を受け入れる際の求人票の作り方や、注意すべき点の書き方など、導入時のサポートも充実しています。院内の働き方改革と、外部からの柔軟な人材確保を同時に進めるための一つの選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは https://business.cu-ra.net/ をご覧ください。
また、求人票に「副業可」と明記することで、応募者の数が増える傾向があると言われています。ただし、その際には必ず「ただし、院内規程に基づく事前申請・許可を必須とします」「競業避止、情報管理に関するルールあり」といった条件を明文化しておくことが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。「クーラ」の求人作成支援サービスでは、そうした自院のルールを反映した求人原稿の文言テンプレート作成なども相談できます。こちらも、詳しくは https://business.cu-ra.net/ をご確認ください。
付録:雛形として使える「就業規則の条文化メモ」(抜粋案)
以下に、就業規則や内規に副業に関する条文を追加する際の参考として、簡単な条文案を記載します。注意:これはあくまで一般的な案です。そのまま使用するのではなく、必ず自院の実情に合わせて内容を修正し、顧問の社会保険労務士や弁護士にご確認の上でご利用ください。
第○条(副業・兼業の原則)
- 本院は、職員がその勤務時間外において、他の会社等の業務に従事すること(以下「副業・兼業」という)を、本条の定めに従い、原則として容認する。これは、職員の主体的なキャリア形成、新たなスキルの習得、自己実現の追求を支援する観点からのものである。
- 前項の定めにかかわらず、職員は副業・兼業を行うにあたり、本業である当院の業務への誠実な遂行義務を疎かにしてはならない。
- 職員が従事しようとする副業・兼業が、以下の各号のいずれかに該当すると本院が判断した場合、本院は当該副業・兼業を許可しない、又は付与した許可に条件を付し、あるいはこれを取り消すことがある。(1) 副業・兼業による心身の疲労等により、本院における労務の提供に支障が生じるおそれがある場合(例:頻繁な遅刻、欠勤、業務中の集中力低下など)(2) 職務上知り得た患者の個人情報、本院の運営・技術・人事に関する情報その他一切の業務上の秘密が漏えいするおそれがある場合(3) 副業・兼業の内容又は場所が、本院の事業と競合し、本院の正当な利益を害するおそれがある場合(例:本院と同一の診療圏内における、同一の主要診療機能を有する医療機関での恒常的な就労)(4) 副業・兼業の実施により、本院の名誉または社会的信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為にあたるおそれがある場合
(解説)この条文は、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の考え方を基にしています。原則として容認する姿勢を示しつつ、制限が可能な4つのケースを具体的に列挙することで、判断基準を明確にしています。
第○条(申請および許可手続き)
- 副業・兼業を希望する職員は、原則として副業・兼業を開始しようとする日の3週間前までに、所定の「兼業許可申請書」を所属長経由で人事担当部署に提出し、本院の事前の許可を得なければならない。
- 申請後、その内容に変更が生じた場合、または許可された副業・兼業を更新しようとする場合も、前項と同様の手続きを要する。
- 本院からの許可の有効期間は、原則として許可日から1年以内とする。期間を超えて継続を希望する場合は、期間満了前に更新の申請を行うものとする。
(解説)東北大学病院などの公的機関の事例を参考に、具体的な申請期限(例:3週間前)を設けています。これにより、手続きの形骸化を防ぎ、計画的な運用を促します。また、許可を更新制にすることで、状況の変化に対応できるようにしています。
第○条(労働時間管理および健康配慮)
- 職員は、副業・兼業を行う場合、本院における労働時間と副業・兼業先の労働時間とを通算した時間外労働が、法令の定める上限を超えないよう、自己の責任において管理しなければならない。
- 職員は、本院からの求めに応じ、四半期ごとに副業・兼業における労働時間の実績を自己申告するものとする。
- 本院は、職員の申告内容や勤務状況に基づき、その健康状態に懸念があると判断した場合は、当該職員と面談を行い、副業・兼業の頻度や時間について指導を行うことがある。特に、本院の夜勤勤務終了直後に、十分な休息なく他の施設で日勤業務に従事することは、原則として認められない。
(解説)ガイドラインが求める安全配慮義務と健康管理の考え方を反映した条文です。労働時間の完全な把握が難しい実態を踏まえ、自己申告を基本としつつ、健康への配慮という観点から病院が関与する仕組みを設けています。
第○条(秘密保持義務および情報管理)
- 職員は、副業・兼業の許可の有無にかかわらず、在職中および退職後において、本院の業務上知り得た一切の秘密情報を、副業・兼業先を含むいかなる第三者にも開示または漏えいしてはならない。
- 副業・兼業の許可を受ける職員は、別途定める「副業・兼業に関する秘密保持誓約書」に署名の上、これを提出しなければならない。
- 電子カルテの記録、患者の画像データ、その他業務に関する情報の取り扱いについては、別途定める「情報セキュリティ管理内規」を遵守しなければならない。特に、個人所有の情報端末(スマートフォン、PC等)の業務利用や、許可なき記録媒体の使用は固くこれを禁ずる。
(解説)厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などを念頭に、情報管理の重要性を強調しています。誓約書や別内規への言及により、具体的なルールを別途定められるようにしています。
第○条(競業の回避に関する事項)
- 本院が別途定める範囲(例:半径○km以内)で、本院と同一の主要診療機能を有する医療機関等において、恒常的に有償で就労することは、本院の正当な利益を害する競業行為にあたる可能性があるため、原則として許可しない。
- ただし、地域医療への貢献など、特段の事情があると本院が認めた場合は、審査の上で例外的に許可することがある。
(解説)競業とみなす範囲について、具体的かつ合理的な定義が必要であることを示唆する条文です。「原則」とすることで、個別の事情に応じた柔軟な判断の余地を残しています。
第○条(研修、講演、学会等への参加)
- 職員が、自己の知識・技術の向上のために、報酬の発生しない学会、研修会、セミナー等に参加または聴講することは、本条に定める副業・兼業には該当せず、事前の申請を要しない。
- 外部からの依頼に基づき、講演、研修指導、執筆活動などを行い、これによって報酬を得る場合は、申請の対象とする。
(解説)神戸市立医療センター中央市民病院の事例を参考に、職員の自己研鑽活動を萎縮させないための線引きを明確にしています。これにより、管理コストを削減し、本当に審査が必要な案件に集中できます。
おわりに
看護師の副業を、これまでの「黙認」や「一律禁止」の状態から、ルールに基づいた「設計と運用」の段階へと進めること。そのために必要なのは、複雑な理論ではなく、具体的な線引きと言語化、そして最小限の運用プロセスです。これらを整えるだけで、職員の多様なキャリアプランを応援しながら、組織としてのリスクを管理し、現場の漠然とした不安を和らげることができます。結果として、それは職員の定着や満足度の向上にもつながる可能性があります。
副業を希望する職員を受け入れる、あるいは自院の職員に許可するということは、短時間勤務やスポット勤務といった、より柔軟な働き方を組織として受け入れる体制を整えることでもあります。その第一歩として、外部の短期・単発の人材を試しに受け入れてみるという方法も有効です。
看護師専門のスポットワークサービス「クーラ」であれば、そうした短期からの受け入れ設計を、求人作成の段階からサポートすることが可能です。自院のルールに合わせた人材を、必要な時に必要なだけ確保する新しい採用の形について、一度情報を集めてみてはいかがでしょうか。導入の流れや他院での活用事例は、公式サイト https://business.cu-ra.net/ にてご確認いただけます。
(本稿の作成にあたり参考にした一般公開情報:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、各国公立病院のウェブサイトで公開されている兼業依頼に関する手続き案内・様式、各種法律事務所や社会保険労務士法人が公開する秘密保持誓約書例、民間調査会社のレポート、医療・介護系情報メディアの記事など)






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



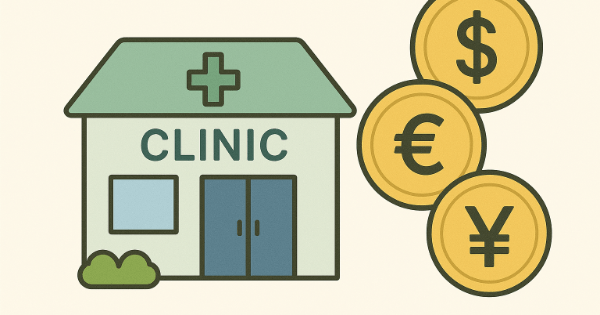
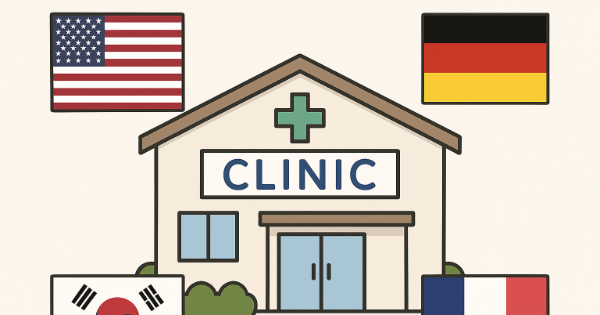
![看護師採用で“最低限ここだけ”の個人情報・マイナンバー取扱いガイド[保存期間・収集タイミング・委託時の注意点まで]](https://cdn.prod.website-files.com/640d966ca29de959e9f69b68/68d3f0cd471eb4dccfe97c23_ChatGPT%20Image%202025%E5%B9%B49%E6%9C%8824%E6%97%A5%2022_22_13-min.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
