毎週の小さな発信が、応募を検討するきっかけに
「SNSを更新したいけれど、ネタが思いつかずに続かない」「院内ブログを始めてみたものの、何を書けば応募につながるのか分からない」。看護師の採用や定着に関わる院長、看護部長、事務長、人事担当者の方々から、このようなお悩みを伺うことがあります。
実は、採用候補者の関心を引く情報は、特別なイベントの中だけではなく、日々の業務や環境の中に多く存在します。週に1回から2回、無理のない範囲で更新を続け、現場の雰囲気、教育体制、働きやすさの実際をありのままに伝えていく。こうした地道な情報発信が、「一度、見学してみたい」「まずは短期間だけでも働いてみたい」といった、応募前の大切な一歩につながっていく事例が見られます。
この記事では、看護師採用の観点から有効とされる情報発信の「定常ネタ」を30個、具体的な事例を交えながらご紹介します。日本の医療機関で実際に行われている発信の例も取り上げながら、現場で取り組みやすいと思われる順番で解説を進めます。記事の最後では、短期のお試し勤務の受け入れを通じて応募のハードルを下げる「クーラ」の活用についてもご案内します。(クーラのサービス案内: https://business.cu-ra.net/ )
なぜ「日常の断片」を発信することが採用につながるのか
看護師の方々が転職や復職を考える際、その意思決定は給与や通勤時間といった条件面だけで決まるわけではない、とされています。むしろ、「どのような人たちと働くのか」「どのような教育を受けられるのか」「実際のところ、どのくらい忙しいのか」といった、求人票の文字だけでは伝わりきらない情報が、最終的な判断を大きく左右することがあります。
だからこそ、SNSや院内ブログといった媒体を通じて、継続的に院内の様子を可視化していくことが有効なアプローチとなり得ます。
国内の医療機関における発信事例
日本国内でも、看護部のブログやInstagramなどを採用活動に活用する医療機関が増えています。
例えば、看護部の教育研修や院内行事をこまめに記事にしている病院があります。こうした発信は、その病院の雰囲気や、職員をどのように育てていこうとしているのかという姿勢を伝える上で役立ちます。一例として、姫路聖マリア病院の看護部ブログでは、「3年目看護師事例発表会」の様子が記録されています。発表を終えた看護師の表情や、学んだことについてのコメントが添えられており、教育環境の実際や成長の節目を具体的に知ることができます。このような記事は、候補者が抱く「ここではきちんと成長できるだろうか」という不安を和らげる材料になると考えられます。
また、福井赤十字病院の看護部サイトも参考になる事例です。各部署の紹介や教育システムの全体像をウェブサイト上に分かりやすく整理して掲載しつつ、日々の活動の様子をブログで更新しています。これにより、候補者は「もしここで働くことになったら、自分はどのような環境で、どのようにキャリアを重ねていくのだろうか」と、自身の将来を具体的に想像しやすくなるのではないでしょうか。
一方で、専門の広報部署を持たない地方の病院や中小規模の病院でも、工夫次第で成果を上げているケースが報告されています。ある取材記事では、TikTokやInstagramといったツールを採用活動に活用し、他の業務と兼務しながらも看護師の採用につながった事例が紹介されていました。これは、必ずしも大規模な体制がなくとも、「小さく始めて、地道に続ける」ことで効果が得られる可能性を示唆しています。
訪問看護の分野では、Instagramに採用専用のアカウントを設けて運用する事業所が多数見られます。日々の投稿を通じて、拠点の和やかな雰囲気や、直行直帰が可能な柔軟な働き方などを伝えています。プロフィール欄には勤務エリアや応募方法への導線を明確に記載し、関心を持った人がすぐに行動に移せるような工夫がされています。
これらの事例に共通しているのは、特別な出来事だけを発信するのではなく、「日常の断片」を丁寧に、そして継続的に伝えようとする姿勢です。そうした情報が、候補者にとって何より信頼できる情報源となるのかもしれません。
国内の医療機関に学ぶ「淡々と続ける」ための発信テーマ
ここでは、実際に国内の医療機関が行っている発信のテーマと、そこから読み取れるポイントをいくつかご紹介します。詳細な運用方法というよりは、「どのような情報であれば、現場の負担を抑えながら継続できるか」という視点で参考にしてください。
- 教育行事の記録(事例発表会・ケース検討会)看護師の成長の節目となる出来事を、1枚か2枚の写真と短い文章で記録する形です。前述の姫路聖マリア病院の「3年目看護師事例発表会」のように、発表を終えた後の達成感に満ちた表情や、学びに関する具体的な言葉が伝わる記事は、その病院が持つ教育環境への安心感を育むことにつながると言えるでしょう。
- 部署紹介や教育システムの情報を整理し、日々の活動を追記する福井赤十字病院のウェブサイトのように、部署ごとの特徴や教育システムの全体像をまず固定ページとして作成し、それとは別に、ブログで日々の研修や勉強会の様子を更新していく方法です。情報が整理されているため、候補者は自分の知りたい情報にたどり着きやすく、迷うことがありません。
- 新人研修の様子をスナップ写真で紹介毎年行われる新人研修の様子を、数日間のダイジェストとしてまとめる記事です。研修内容が多岐にわたる場合でも、それぞれの場面を写真と一言コメントで紹介するだけで、研修の雰囲気や手厚さを十分に伝えることができます。これは、急性期、慢性期、あるいはクリニックといった場の特性を問わず有効な手法とされています。千葉メディカルセンターの看護部ブログなどでも、こうした形式の投稿が見られます。
- 大規模グループ病院における各院からのローカルな発信徳洲会グループや済生会グループのような大規模な医療法人に所属する病院でも、各施設が独自に情報発信を行っています。例えば、白根徳洲会病院のブログでは、院内で行われた教育行事やイベントの様子が記録されています。こうした地域に根差した情報は、全国規模の広報とは別に、その地域で働きたいと考える候補者にとって、より身近で重要な情報となります。
- 慢性期医療や地域包括ケアの魅力を短い動画で伝える近年、慢性期病院がSNSを活用して人材確保に成功した経緯を紹介する取材記事が増えており、その中でTikTokなどの短尺動画の活用にも言及されることがあります。「患者さん一人ひとりと、ゆっくり向き合うことができる」といった慢性期医療ならではの価値は、文章だけよりも、穏やかな現場の様子を切り取った短い動画の方が伝わりやすい場合があります。
- 訪問看護の採用に特化したInstagramアカウント多くの訪問看護ステーションが、採用専用のInstagramアカウントを運用しています。そこでは、「当直やオンコールの分担はどのようになっているか」「直行直帰の際の1日の流れ」といった、働き方の実際に関する情報が継続的に発信されています。プロフィール欄に応募への導線を明確に示しておくことも、効果的な運用方法の一つです。
- Instagramと求人媒体を連携させた運用ある訪問看護事業者のインタビュー記事では、Instagramの運用と一般的な求人媒体をうまく使い分けることで採用成果を上げた経験が語られています。SNSでは事業所の雰囲気やスタッフの人柄といった定性的な情報を伝え、求人媒体では給与や休日といった条件面を正確に提示する、という役割分担が紹介されており、参考になります。
- 地方のステーションにおける応募増加のレポート地方都市の訪問看護ステーションが、スタッフの顔が見える日常的な投稿を続けた結果、短期間で応募が増加したというレポート記事も公開されています。プロが撮影したような綺麗な写真でなくとも、スタッフの素朴な笑顔や、ありのままの職場の様子を伝えるキャプションでも、十分に効果が期待できることを示唆しています。
- 病院広報や看護管理者が語るSNS活用の考え方看護管理者向けのウェブサイトなどでは、「現場の声をSNSに載せる」ことの重要性を論じる記事が見られます。看護という「実践の場」でスタッフが何を感じ、何を考えているのかを拾い上げ、発信していくという視点は、採用を目的とした広報活動にも応用できる考え方です。
- 地域の中核病院による「看護部の今」を伝えるまとめ記事能登総合病院の看護部ブログのように、その年度に行われた交流会や行事を淡々と記録し続けるだけでも、応募を検討している人にとっては貴重な情報源となります。特別なイベントがなくとも、定期的な情報発信そのものが、応募前の不安を少しずつ解消していく材料になるのです。
明日からでも始められる「定常ネタ」30選
以下に、現場のスタッフが他の業務と兼務しながらでも続けやすいと思われる情報発信のネタを30種類、具体的な書き方のヒントと合わせてご紹介します。どのネタも、「写真1枚から3枚程度」と「200文字から500文字程度の本文」があれば十分に成立します。
例えば、「月曜日は教育関連、水曜日は人や雰囲気、金曜日は働きやすさについて」というように、曜日ごとにテーマを固定すると、ネタ探しに悩む時間を減らし、運用上の負担を軽くすることができます。
1. 教育・成長が伝わるネタ(応募の不安を和らげる)
- 新人研修の1週間ダイジェスト
- 写真:技術演習の様子、プリセプターと振り返りをしている場面など、真剣な中にも和やかさが感じられるもの。
- 本文:その週に学んだ具体的な内容(例:採血、記録の書き方など)と、次週の目標などを簡潔に記します。「〇〇の演習では、同期と教え合いながら理解を深めました」といった一文を加えると、協力的な雰囲気が伝わります。
- 事例発表会の舞台裏
- 写真:発表している風景、使用したスライドの一部(個人情報が映らないように配慮)、発表を終えてほっとした表情など。
- 本文:発表されたテーマの一覧を紹介し、「発表者からは〇〇という学びが共有されました。この経験を、来年の新人教育にも活かしていきたいと考えています」といった、組織としての学びや将来への展望に触れると、教育への真摯な姿勢が伝わります。
- 病棟内ミニ勉強会
- 写真:勉強会で使ったホワイトボードや資料の一部。
- 本文:その日のテーマ(例:新しい医療機器の使い方、口腔ケアのポイントなど)と、所要時間(例:「お昼休みの10分間」)、参加者からの簡単な感想などを記載します。頻繁に学びの機会があることを示すことができます。
- 部署紹介シリーズ(週替わり)
- 写真:部署のスタッフステーションの様子、スタッフ紹介ボード(個人名はぼかす)、デイルームの雰囲気など。
- 本文:その部署の主な患者層、1日の業務の流れの概要、教育面で特に力を入れているポイントなどを解説します。これにより、候補者は配属後のイメージを具体的に持つことができます。
- 専門・認定看護師の活動日記
- 写真:カンファレンス(打ち合わせ)の様子、専門分野に関する資料など。
- 本文:その日にどのような活動をしたか、どのような相談を受けたか、関わった事例から得られた学びなどを、専門的になりすぎない言葉で一言添えます。専門性を高められる環境であることをアピールできます。
- 新人の1年間の振り返り
- 写真:入職時と現在の写真(本人の許可を得て)。後ろ姿や手元などでも構いません。
- 本文:本人への簡単なインタビュー形式で、「この1年でできるようになったこと3つ」や「一番うれしかったこと」などを紹介します。成長の軌跡が可視化され、新人が着実にステップアップできる環境であることが伝わります。
- 先輩からのメッセージ
- 写真:仕事中や休憩中の自然な笑顔。必ずしも白衣である必要はありません。
- 本文:華やかな成功体験だけでなく、「入職当初はこんな失敗もしたけれど、先輩のフォローで乗り越えられた」といった等身大の経験談を紹介すると、親近感が湧き、職場のサポート体制が伝わります。
- 外部研修・学会参加レポート
- 写真:配布された資料の表紙や、会場の看板など。
- 本文:研修の概要を長々と書くのではなく、「今回の学びで、現場に持ち帰りたいポイントは〇〇です」というように、要点を三行程度でまとめます。職員のスキルアップを支援する風土があることを示すことができます。
- 看護補助者や事務職との学び合い
- 写真:多職種が連携して業務にあたっている様子。
- 本文:看護師の視点から、「看護補助者さんの〇〇という動きに助けられた」「事務の方のこの一言で業務がスムーズに進んだ」といった、具体的なエピソードを紹介します。チーム医療を大切にしている姿勢が伝わります。
- プリセプター(新人指導担当者)の座談会
- 写真:数人のプリセプターが輪になって話している様子。
- 本文:「新人指導で大切にしている声かけは?」「自分が新人だった頃を思い出して気をつけていることは?」といったテーマで、座談会形式の短い記事を作成します。指導する側の想いが伝わることで、新人は安心して入職を検討できます。
2. 人と雰囲気が伝わるネタ(「見学したい」気持ちを育む)
- ランチ紹介(職員食堂、売店、周辺のお店など)
- 写真:トレーに乗せられた1食分のランチ。
- 本文:メニュー名、価格、混雑する時間帯、おすすめのポイントなどを記載します。福利厚生だけでなく、職員の日常という「生活感」が伝わると、候補者は職場をより身近に感じやすくなります。
- 病棟の小さな工夫
- 写真:情報共有に使っているホワイトボード、スタッフが手作りした掲示物、整理整頓された物品棚など。
- 本文:「忙しい時でも、この一言を添えるようにしています」「この掲示物のおかげで、情報共有がスムーズになりました」など、業務を円滑にするための小さなルールや工夫を紹介します。職場の協調性や問題解決への意識が伝わります。
- ユニフォームやナースシューズ事情
- 写真:ユニフォームのデザインが分かる写真(スタッフの後ろ姿など)、足元だけの写真。
- 本文:ユニフォームが貸与か個人購入か、クリーニングのルール、ナースシューズに関する補助の有無などを具体的に記載します。些細なことですが、働く上での現実的な情報として重宝されます。
- お祝いや表彰の文化
- 写真:誕生日や資格取得を祝うメッセージカード、院内の表彰状など。
- 本文:職員の頑張りや記念日を、みんなで称え合う小さな習慣を紹介します。「今月は〇〇さんが資格試験に合格したので、ささやかなお祝いをしました」といった投稿は、温かい職場の雰囲気を感じさせます。
- シフトの組み方の考え方
- 写真:個人情報をぼかした勤務表のフォーマット。
- 本文:休み希望の提出方法や提出時期の目安、夜勤回数の平均、連続勤務日数への配慮など、シフト作成に関する基本的な考え方を説明します。ワークライフバランスを重視する候補者にとって、非常に重要な情報です。
- 子育てや介護との両立の工夫
- 写真:更衣室に貼られた時短勤務のタイムスケジュール、子育て中のスタッフ同士の談笑風景など。
- 本文:子どもの急な発熱などでお迎えが必要になった際、部署内でどのように連携・協力しているか、具体的なエピソードを交えて紹介します。「お互い様」の精神が根付いていることを伝えることができます。
- オンコール分担の実際
- 写真:PHSや連絡用のスマートフォンのみをシンプルに撮影。
- 本文:オンコールの当番回数の目安、担当する曜日の決め方、どうしても対応できない場合の代替ルールなどを説明します。特に訪問看護などでは、候補者が最も気にする点の一つであり、透明性の高い情報提供が安心につながります。
- 夜勤の前後での過ごし方
- 写真:仮眠スペースの様子、夜食として人気のカップ麺やお菓子など。
- 本文:夜勤中の仮眠の取り方や休憩時間のルール、夜勤明けの過ごし方(例:「明けで同僚とランチに行くのが楽しみです」など)を紹介します。過酷なイメージのある夜勤について、現実的な情報を伝えることで不安を軽減します。
- 文章だけでは伝わりにくい部分は、実際に働いて理解してもらうのが確実です。クーラなら短期のお試し勤務からスタートできます(https://business.cu-ra.net/)。
- 徒歩や自転車通勤の実際のところ
- 写真:病院の駐輪スペース、近隣の風景など。
- 本文:職員の通勤手段の割合や、雨の日の対策(例:更衣室にカッパを干すスペースがあるなど)、近隣の交通事情などを紹介します。地域に密着した生活情報が、候補者の入職後の暮らしをイメージさせます。
- 休憩の取り方を見直した話
- 写真:休憩室に貼られた新しいルールに関する掲示物。
- 本文:「以前は忙しくて休憩が取りづらい時もありましたが、〇〇というルールを決めたら、全員がしっかり休憩を取れるようになりました」といった、職場改善の取り組みを紹介します。職員の健康や働きやすさを大切にしている姿勢が伝わります。
3. 仕事の中身が伝わるネタ(業務のイメージを具体化)
- 1日のタイムライン
- 写真:時計のアイコン画像や、個人情報を消したスケジュール表の一部など。
- 本文:急性期、慢性期、外来、訪問看護など、部署ごとの代表的な1日の業務の流れを紹介します。特に、業務が集中する時間帯と、比較的落ち着いている時間帯を記載すると、働く上でのリズムがイメージしやすくなります。
- 電子カルテ「最初の壁」の乗り越え方
- 写真:操作マニュアルの表紙や、教育用のPC画面(ダミーデータ)。
- 本文:中途採用者が最初につまずきやすい電子カルテの操作について、「入職後の最初の1週間で、まず覚えてもらう操作はこの3つです」というように、教育のポイントを絞って紹介します。独自のシステムに対する不安を和らげることができます。
- 物品カートの定位置ルール
- 写真:整理整頓された物品カートの引き出しを少し開けた状態。
- 本文:「新人の頃は、物品の場所が分からず焦ることがありました。当院では、写真付きのラベルを貼るなど、新人が迷わない工夫をしています」といった紹介をします。業務効率化への意識と、新人への配慮が伝わります。
- 申し送りの進め方
- 写真:カンファレンス風景(顔がはっきり映らないように配慮)。
- 本文:申し送りを行う時間、場所、参加する職種、申し送りの標準的なフォーマットなどを説明します。情報共有の仕組みが整っていることは、医療安全の観点からも候補者に安心感を与えます。
- 急変対応の標準的な手順
- 写真:院内の壁に貼られた急変対応フローチャートの一部(ぼかしを入れるなど配慮)。
- 本文:急変が起きた際の第一報の方法、スタッフの役割分担など、初動で迷わないための基本的なルールを簡潔に紹介します。「いざという時も、手順が決まっているので落ち着いて行動できます」といった一言を添えると、教育体制の信頼性が増します。
- 患者さん・ご家族への説明で心がけていること
- 写真:説明時に使用する資料やメモ帳。
- 本文:患者さんやご家族からよく受ける質問と、それに対する標準的な回答例、説明の際に大切にしている心構え(例:「専門用語を避け、分かりやすい言葉で伝える」など)を紹介します。看護の質や、患者さんへの向き合い方が伝わります。
- 感染対策の「季節のお知らせ」
- 写真:院内に設置されたアルコールディスペンサー、感染対策ポスターなど。
- 本文:「今月はインフルエンザ対策を重点的に行っています」というように、季節に応じた感染対策の取り組みを発信します。職員と患者さんを守るための基本的な姿勢を示すことにつながります。
- 離床や口腔ケアで効果があった工夫
- 写真:ケアに使用する物品の置き方、安全な介助のための配置など。
- 本文:「このクッションの使い方を工夫したところ、褥瘡のリスクが減らせました」といった、日々のケアの中で生まれた小さな成功事例や工夫(ベストプラクティス)を共有します。看護の専門性を追求する姿勢が伝わります。
- 退院支援における連携先とのやりとり
- 写真:地域連携室の掲示板や、連携先リスト(施設名はぼかす)。
- 本文:退院支援の際に、地域のケアマネジャーや訪問看護ステーションとどのように情報を共有し、連携しているのか、その流れを説明します。病院内だけでなく、地域全体で患者さんを支える視点を持っていることを示せます。
- 訪問看護の「1日の持ち物」紹介
- 写真:訪問バッグの中身を並べた写真。
- 本文:血圧計や聴診器といった医療機器から、書類、衛生用品、さらには「夏場の暑さ対策グッズ」といった個人的なアイテムまで、訪問看護師のリアルな持ち物を紹介します。これは、訪問看護ステーションの採用Instagramアカウントでよく見られる人気の投稿で、仕事の実際が具体的にイメージでき、応募前の不安を下げる効果があるとされています。
投稿を作成する際の基本的な考え方
ここまで30個のネタをご紹介しましたが、実際に投稿を作成する際には、いくつかの共通したポイントがあります。
- 書式はいつも同じ型にする毎回構成に悩まなくて済むように、基本的な型を決めておくと負担が軽くなります。例えば、「タイトル(何についての話か具体的に分かる言葉)」「本文(結論を先に書き、次にその理由や具体例を続ける)」「最後の締め(見学や問い合わせへの案内)」といったシンプルな構成で十分です。案内の一文は、「ご興味のある方は、いつでも見学にいらしてください」のように、押し付けがましくない表現を心がけると良いでしょう。
- 写真は個人情報が映らないように工夫するスタッフや患者さんの顔がはっきりと映り込む写真は、本人の許可なく使用することは避けるべきです。後ろ姿や手元、掲示物の一部、風景などを活用しましょう。また、名札に書かれた名前や、書類に記載された個人情報などが意図せず写り込んでいないか、投稿前に必ず確認する習慣が大切です。
- ハッシュタグは検索されやすい言葉を選ぶ投稿の末尾には、関連するハッシュタグをいくつか付けると、関心のある人の目に留まりやすくなります。例えば、「#看護師募集」「#看護部ブログ」「#新人看護師研修」「#夜勤」「#訪問看護」といった一般的なキーワードに加え、「#横浜市看護師求人」「#福井県病院」のように、地域名を入れることも効果的です。
- 週2回更新なら曜日ごとにテーマを固定する前述の通り、「月曜日は教育関連」「水曜日は職場の雰囲気」「金曜日は働きやすさ」というように、曜日ごとに発信する情報の柱を決めておくと、運用がスムーズになります。ネタ探しに迷うことが減り、継続しやすくなります。
- 動画は10秒から30秒程度の短いもので十分動画を作成する場合、長時間の凝った編集は必要ありません。例えば、慢性期病棟での穏やかな時間の流れや、患者さんとゆっくり向き合う様子などは、BGMをつけた短い動画だけでも十分に伝わると言われています。スマートフォンのアプリなどで簡単に作成できる範囲で試してみるのが良いでしょう。
事例から学ぶ、継続のための小さな設計
ここまで紹介してきた国内の医療機関の事例には、いくつかの共通点が見られます。それは、「等身大であること」「過度に飾り立てないこと」「毎週同じような型で継続していること」の3点です。
- 教育体制の見える化多くの候補者、特に新卒や経験の浅い看護師は、「入職後にきちんと教えてもらえるだろうか」という不安を抱えています。事例発表会や新人研修の様子、部署ごとの教育方針などを記事として継続的に発信し、ウェブサイト上に「教育」という棚を用意してそこに情報を蓄積していくことで、その不安に先回りして応えることができます。
- 現場スタッフの一次情報理事長や看護部長といった管理職の理念やメッセージも大切ですが、それと同じくらい、現場で働くスタッフの短いコメントや等身大の声は、候補者にとって信頼できる情報となります。看護の実践の場で、スタッフが何を感じ、何を学んでいるのかを拾い上げて発信していく視点が重要だと指摘する論考も見られます。
- 地方や訪問看護ならではの強みは「生活導線」の情報特に地方の事業所や訪問看護ステーションの場合、通勤手段、直行直帰の可否、休憩の取り方、日々の持ち物といった、より生活に密着した情報が候補者の関心を引くことがあります。これは、地方の訪問看護ステーションが日常的な投稿を続けた結果、応募が増加したという公開記事の内容とも一致しており、生活者としての視点を大切にすることが有効と考えられます。
- SNSと求人媒体の役割分担SNSでは、文章や写真、動画を通じて、人や現場の雰囲気といった定性的な魅力を伝えます。一方で、給与、休日、福利厚生といった条件面は、求人媒体や公式サイトの募集要項に正確かつ詳細に記載します。この両輪をうまく連携させることで、採用成果につながったというインタビュー記事もあり、それぞれの媒体の特性を理解して使い分けることが大切です。
よくあるつまずきとその対処法
情報発信を始めると、いくつかの壁に突き当たることがあります。ここでは、よくあるつまずきの例と、それに対する具体的な対処法をご紹介します。
- つまずき1:ネタが尽きてしまう
- 対処法:この記事で紹介した30のネタの中から、自分たちの職場で発信しやすいテーマの「柱」を3つ程度選びます。そして、月に一度、5分から10分程度の短い打ち合わせの時間を設け、翌月分の投稿タイトル(仮で構いません)だけをいくつか決めておきます。本文は後からで良いので、まず見出しだけリストアップしておくことで、日々のネタ探しへの心理的な負担が大幅に軽減されます。
- つまずき2:投稿に使える写真がなかなか撮れない
- 対処法:「写真当番制」を導入し、「担当者は1週間のうちに2枚だけ、職場の様子が分かる写真を撮る」といった簡単なルールを決めるのがおすすめです。その際、個人情報保護の観点から、「遠くから引きで撮る」「手元だけを撮る」「掲示物の一部を切り取って撮る」といった撮影方法の例を共有しておくと、担当者も安心して取り組めます。
- つまずき3:続けていても成果が見えない
- 対処法:SNSやブログ発信の成果を、すぐに応募者数の増加だけで測ろうとすると、途中で心が折れてしまうことがあります。まずは、「見学の予約が入った」「問い合わせフォームからの連絡があった」「面接に来た人が『ブログを見ています』と言ってくれた」といった、応募の前段階における小さな変化に注目しましょう。SNSのダイレクトメッセージでのやり取りが苦手な場合は、ブログの記事から公式サイトの問い合わせフォームへ誘導する流れを作るのが良いでしょう。
- つまずき4:忙しくて更新が止まってしまう
- 対処法:完璧を目指さず、「毎週決まった曜日に、決まったテンプレートを使って投稿する」ことを最優先します。もし本当に時間がなければ、写真1枚と「今日は部署内で〇〇の勉強会がありました。学びの多い時間でした。」といった、5分で書けるような「ひとこと日誌」でも構いません。更新が完全に止まってしまうより、短い内容でも継続することの方がはるかに重要です。地方の中小病院のSNS活用事例でも、「兼務でも続けられる小さな仕組み作り」の重要性が語られています。
まとめ:等身大の情報の積み重ねが、応募前の不安を解消する
採用のための情報発信に、特別なキャッチコピーや、プロが作成したような美しいコンテンツが必ずしも必要というわけではありません。
新人研修の一場面、休憩室で見つけた小さな工夫、夜勤前後の過ごし方に関する知恵。こうした一つひとつの等身大の情報の断片を、毎週同じ型で、ウェブサイトやSNS上に積み重ねていく。それだけで、応募を検討している候補者は、「もし自分がここで働いたら」という未来を、より具体的に、そして肯定的に想像することができるようになります。
そして、もし「ウェブサイトの情報だけではまだ不安、という方のために、まずは短期間だけでも現場を体験してもらい、その上で長期的な勤務を検討してもらいたい」とお考えでしたら、短期のお試し勤務を受け入れやすい仕組みを整えることが有効な手段となります。
クーラは、「1日から数回程度の、有給でのお試し勤務」に特化した採用の仕組みを提供しています。SNSや院内ブログで関心を持ってくれた看護師の方々が、応募という高いハードルを越える前の「最初の一歩」として、気軽に現場を体験する機会を作ることができます。ご興味がありましたら、ぜひクーラのサービス案内をご覧ください。
クーラ導入のご案内: https://business.cu-ra.net/
月間投稿カレンダー(サンプル)
参考にした公開事例・記事
本記事を作成するにあたり、以下の公開情報や事例を参考にさせていただきました。
- 姫路聖マリア病院 看護部採用ブログ:教育の節目となるイベントを具体的に記録し、可視化することの重要性を示唆しています。
- 福井赤十字病院 看護部サイト:ウェブサイト上で情報を整理し、候補者が必要な情報にアクセスしやすい導線を設計している好例です。
- 慢性期病院におけるSNS活用に関するレポート記事:短尺動画などを活用し、文章だけでは伝わりにくい職場の魅力や雰囲気を伝えるアプローチが紹介されています。
- 地方・中小規模の病院におけるSNS活用に関する実務記事:広報専門の担当者がいない中でも、工夫次第で継続的な運用が可能であることを示しています。
- 訪問看護ステーションの採用専用Instagramアカウント(例:Recovery International株式会社など):採用に特化したアカウントの作り方や、日常の様子を発信する投稿内容の参考になります。
- Instagramと求人媒体の連携に関するインタビュー記事:各媒体の特性を理解し、役割を分担させることの有効性が語られています。
- 地方の訪問看護ステーションにおける応募増加に関する公開記事:スタッフの顔が見える、生活感のある日常的な投稿が、候補者の信頼感や親近感を醸成する効果について触れられています。
- 看護管理者によるSNS活用の考え方に関する記事:採用広報においても、現場で働くスタッフの声を拾い上げ、発信していくことの重要性を示唆しています。
- 能登総合病院 看護部ブログ:特別なイベントがなくとも、年度ごとの行事などを淡々と記録し続けることが、候補者にとっての安心材料になることを示しています。
日々の現場で起きていること、行われている工夫は、それ自体が十分に魅力的なコンテンツです。まずは、小さく、等身大の情報を、決まった型で発信し続ける。来月からの1か月間だけでも、ぜひ試してみてください。きっと、見学や問い合わせをしてくる方々の反応に、これまでとは違う変化が生まれるはずです。その際には、関心を持ってくれた方々の「次の一歩」を後押しするために、「お試し勤務」という選択肢を用意しておくことも、有効な方法の一つと考えられます。
クーラの導入に関する詳細はこちら: https://business.cu-ra.net/






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



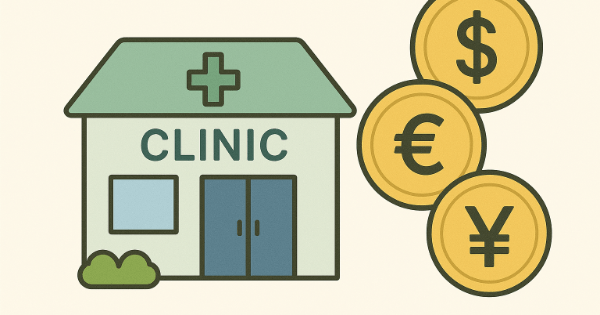
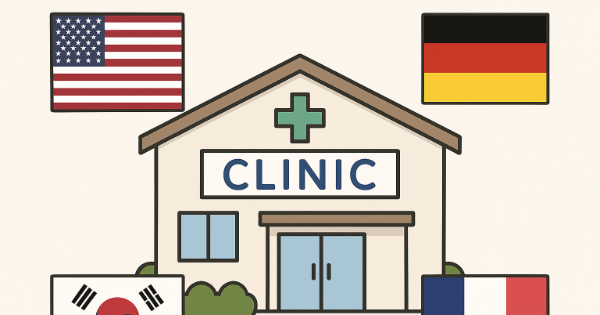
![看護師採用で“最低限ここだけ”の個人情報・マイナンバー取扱いガイド[保存期間・収集タイミング・委託時の注意点まで]](https://cdn.prod.website-files.com/640d966ca29de959e9f69b68/68d3f0cd471eb4dccfe97c23_ChatGPT%20Image%202025%E5%B9%B49%E6%9C%8824%E6%97%A5%2022_22_13-min.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
