「地域に根ざす×短時間で働ける」から応募が動く
小規模クリニックの採用活動において大切なのは、広範囲から多くの人を集めることよりも、「ここなら通えそう、働けそう」と感じる近隣の人材を的確に呼び込むことです。看護師の有効求人倍率は、他の多くの職種と比較して高い水準で推移している状況が報告されています。日々の診療で忙しく、採用活動に多くの時間を割くことが難しいクリニックほど、求人票の書き方や勤務シフトの設計といった少しの工夫で、応募状況が目に見えて変わることがあります。
本稿では、地域に密着した視点と、「午前のみ」「週1日から」「1日3時間から」といった柔軟な働き方の枠組みを組み合わせることで、現実的に人材を募集するための要点を、公開されている様々な事例を交えながら整理していきます。厚生労働省が公表する「職業別一般職業紹介状況」などを見ても、医師・看護師等の保健医療職の有効求人倍率は、全職業計の数値を上回る傾向が続いています。
このような状況下で、いきなり常勤での採用を目指すのではなく、まずは短時間の“お試し勤務”から始めることで、お互いのミスマッチを減らす運用も一つの有効な手段とされています。もし「面接だけで採用するのは少し不安がある」「まずは数回、試しに勤務してほしい」といったご要望があれば、クーラのようなサービスを通じて短期の就業から始める方法は、現場の負担を大きく増やすことなく試せる選択肢の一つです。この点については、記事の最後で改めてご案内します。
背景・課題|なぜ「地域×時短」が効くのか
看護職の採用は“量”よりも“適合”
看護職全体の離職率は、年度によって多少の増減はありますが、日本看護協会の「2023年 病院看護・外来看護実態調査」によると、2022年度の正規雇用看護職員の離職率は11.8%と報告されており、依然として二桁台の水準です。特に、経験の浅い新人看護師だけでなく、中途採用者の比較的早い段階での離職も、多くの医療機関にとって課題とされています。このことは、採用の段階でいかに職場の実情と応募者の希望をすり合わせ、適合度を高める工夫ができるかが重要であることを示唆しています。
生活圏と時間帯の「制約」が応募を決める
看護師資格を持つ方の中には、子育てや家族の介護といった家庭の事情により、フルタイム勤務や夜勤、オンコール対応が難しいという方が少なくありません。こうした潜在看護師と呼ばれる層は、全国に多数存在すると言われています。そのため、「午前のみ」「1日4時間から勤務可能」「週1日、扶養の範囲内で」といった柔軟な勤務条件を提示するだけで、これまで応募に至らなかった層からの関心を引き出すことが可能になります。
実際に、医療系の求人情報サイトを見ると、「午前のみOK」「扶養内考慮」といった検索条件が標準的に用意されており、多くのクリニックがその条件で募集をかけている実態があります。例えば、ある求人サイトで東京都内のクリニックの看護師求人を検索すると、「午前のみ」という条件だけで数百件の募集情報が見つかることも珍しくありません。
また、子育てをしながらクリニックで働く看護師の方々の声として、ウェブ上の記事やブログなどでは、「夕方の診察が長引いて、子どものお迎えに間に合うかいつも心配」「子どもの急な発熱の際に休みが取りにくい雰囲気がある」といった、現実的な悩みや制約が語られています。採用する側が、こうした不安を先回りして解消するような情報、例えば「当院の午後の診療は平均して18時には終わります」「お子さんの急な体調不良の際は、他のスタッフでカバーする体制があります」といった具体的な情報を提示することが、応募への心理的なハードルを下げることにつながると考えられます。
地域施策や福利厚生の後押し
都市部か地方かを問わず、多くの自治体や医療機関が、看護職の人材確保のために住まいや保育に関する支援制度を設けています。これらの制度は、応募者にとって実質的な“通いやすさ”や“働きやすさ”に直結します。
例えば、公的な事例として、多くの都道府県では看護師等修学資金貸与制度を設け、特定の地域や診療科で一定期間勤務することを条件に返還を免除する取り組みを行っています。また、自治体によっては、市内の医療機関に就職する看護師に対して、転居費用の一部を補助したり、家賃補助を行ったりする制度もあります。
病院単位の事例では、大規模な病院グループなどが独自に職員用の寮や院内保育所を整備しているケースは広く知られています。愛知県がんセンターのように、敷地内に24時間対応の院内保育所を設置し、病児・病後児保育にも対応することで、子育て中の職員が安心して働き続けられる環境を提供している例もあります。
小規模なクリニックで同様の設備を整えることは難しいかもしれませんが、これらの考え方を応用することは可能です。例えば、「近隣の提携保育園の情報をリストアップして提供する」「家賃補助として、少額でも近隣居住手当を支給する」といった形であれば、比較的小規模な組織でも導入を検討できるかもしれません。
実例紹介|公開情報から学べるポイント
1)「午前のみ」「土曜午前のみ」で応募の母集団を増やす
求人媒体を調査すると、「土曜午前のみ」「午前診察の時間帯だけ」といったパートタイムの募集は、常に一定数見られます。これらの求人は、特定の時間帯に限定して働きたいと考えている層に的確に届きやすい特徴があります。
例えば、ある求人情報サイトでは、関西圏の婦人科クリニックが「土曜午前のみ、9時から13時まで」「駅直結で通勤が便利」「扶養内での勤務も可能」といった条件を明確に掲げた募集を出していました。業務内容も「主に医師の診療補助と採血業務」と具体的に示し、1名体制で担当する役割であることを明記していました。このように、勤務時間、場所、業務範囲が限定された“ピンポイント”の求人は、平日は別の仕事をしている方や、週末だけ少し働きたいと考える方の応募を後押しする効果が期待できます。
2)在宅・地域連携の職種で「家庭と両立」を打ち出す
近年需要が高まっている在宅医療の領域でも、柔軟な働き方の事例が見られます。訪問看護などでは、オンコール対応が前提となる常勤のイメージが強いかもしれませんが、日中の短時間勤務の求人も存在します。
ある在宅療養支援診療所のインタビュー記事では、病院の病棟勤務から、地域連携を担う看護師に転職した方の事例が紹介されていました。その方は、子どもの成長に合わせて働き方を見直し、夜勤のない日中の仕事、特に多職種と連携して患者さんの在宅生活を支えるコーディネート業務に魅力を感じて転職を決めたと語っています。
この事例から、クリニックにおいても、例えば「地域連携室の補助業務」「在宅患者さんへの電話連絡や書類整理」といった、直接的なケア以外の役割を短時間勤務の業務として切り出す設計は、一つのヒントになります。患者さんと直接対面する時間以外にも、看護師の知識や経験が活かせる場面は多く、それらをパートタイムの仕事として設定することは、新たな人材活用の可能性を開くかもしれません。
3)短時間正職員制度を参考に、クリニックでも「時短だけど主力」の位置づけに
比較的規模の大きな病院では、「短時間正職員制度」の導入が進んでいます。これは、フルタイム勤務はできないものの、正規職員として責任ある業務を担いたいというニーズに応えるための制度です。大分県立短期大学が発表した研究報告など、この制度に関する学術的な調査も行われており、時短勤務者が組織の中でどのように活躍し、評価されているかの実践例が蓄積されています。
こうした考え方は、診療所のパートタイム雇用のあり方にも応用できます。パートタイム勤務というと、どうしても“補助的な業務”というイメージを持たれがちですが、必ずしもそうである必要はありません。例えば、外来診療における一連の流れ(受付からの誘導、問診、検査の補助、処置の準備、電子カルテの入力補助、診療後の片付けなど)をいくつかのパートに分解し、そのうちの特定の範囲を責任をもって担当してもらう、という形も考えられます。業務内容を手順化・明確化することで、「短時間勤務であっても、クリニックの重要な戦力である」という位置づけにすることが可能です。
4)地方の人材確保では「住宅・赴任支援+柔軟シフト」が相性の良い組み合わせ
特に地方や郊外において看護師を確保する上では、通勤の利便性や住居に関する支援が重要な要素となることがあります。看護師専門の人材紹介サービスなどのウェブサイトでは、地方の医療機関の求人情報として、赴任手当や住宅支援、転居費用の一部補助といった優遇施策がセットになっている例がしばしば紹介されています。
クリニックの規模で、高額な赴任手当や寮の提供は現実的ではないかもしれません。しかし、その考え方を応用し、簡易的な形で支援を提示することは効果的な場合があります。例えば、「自家用車での通勤を想定し、一般的な交通費の上限額を引き上げる」「近隣に住む場合に、月数千円程度の近隣居住手当を支給する」といった方法です。
これに加えて、「毎週水曜日の夜間診療だけ」「週に1回、訪問診療の同行だけ」といった、曜日や業務を限定した柔軟なシフトを組み合わせることで、地域に住む潜在的な労働力にアプローチしやすくなる可能性があります。
解決アプローチ|“地域×時短”を設計する5つの手順
ここでは、これまでの事例を基に、実際に“地域×時短”の求人を設計するための具体的な5つの手順を提案します。
“地域×時短”の求人コピー例
ここでは、上記の5つの手順を踏まえて作成した、そのまま使える求人票の文面例を紹介します。
地域類型別・時短設計の考え方
クリニックが立地する地域の特性によって、効果的なアプローチは少しずつ異なります。ここでは3つの類型に分けて、時短設計の考え方を整理します。
面接・見学の受け入れ方|“短時間で現場が見える”導線
応募があった後の面接や見学のプロセスも、ミスマッチを防ぐ上で非常に重要です。短時間勤務を希望する応募者に対しては、受け入れ側も効率的に、かつ具体的に仕事のイメージが伝わるような工夫が求められます。
- 30分から60分程度のショート見学:実際の勤務時間帯に、受付から診察室、処置室といった患者さんの動線に沿って院内を案内します。スタッフが実際にどのように動いているかを見てもらうのが効果的です。
- スキル確認は「今日の外来で使うもの」に限定:ブランクのある方などに対して、全てのスキルを一度に確認しようとするのではなく、「今日は採血と心電図の業務が中心です」というように、その日の業務に必要な手技に絞って経験の有無を尋ねます。
- 終了後5分の相互確認:見学と面接の最後に、「今日見ていただいた中で、できそうだと感じたこと、逆に少し不安に感じたことはありますか」と尋ねる時間を作ります。応募者の不安を口頭で整理し、それに対してクリニックとしてどのようなサポートができるかを伝えることで、信頼関係の構築につながります。
見学の段階で、応募者が担当することになる“時短枠の中で始まり、終わる仕事”の範囲を具体的に示すことが、採用後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを減らす上で有効です。前述の短時間正職員制度の実践報告においても、役割の明確化や評価の工夫が、制度定着の鍵であるとされています。この考え方は、診療所のパートタイム雇用の運用にも十分応用可能です。
ブランク・復職支援の取り込み
看護師の資格を持ちながらも、出産や育児などを機に一度現場を離れている、いわゆる潜在看護師の方は多く存在します。こうしたブランクのある方の復職を後押しすることも、地域の人材確保において重要な視点です。
各都道府県の看護協会や、ナースセンターでは、復職を目指す看護師のための再就職支援研修が定期的に開催されています。研修では、最新の医療知識の確認、採血や注射といった基礎的な看護技術の再確認、最新の医療機器の操作方法の習得などが行われます。
募集要項の中に、「ブランクのある方、歓迎します」「各都道府県の復職支援研修を修了された方、歓迎します」といった一文を明記することで、復職に不安を感じている方々に対して、応募の間口を広げることができます。さらに、採用後の初回勤務時には、「最初の30分は業務説明の時間とします」「まずは午前診察の見学から始めましょう」といった、段階的な導入プランを提示すると、より安心して仕事を始めることができるでしょう。具体的な研修の開催案内は、各都道府県の看護協会のウェブサイトなどで確認することが可能です。
給与・手当の考え方(時短ならではの設計)
短時間勤務の求人において、給与や手当の設計は応募を左右する重要な要素です。
- 時給は地域の相場を意識しつつ設定:時給の金額そのものも重要ですが、「駅からの近さ」「午前のみで終わる」といった、お金には換算しにくい“条件の良さ”を、金額の魅力だけに頼らず、求人票の中でしっかりと伝えることが大切です。通勤時間や保育、家事との両立で得られる時間的な余裕も、応募者にとっては非金銭的な価値となります。
- 家賃や交通費の“ミニ補助”を検討:大規模病院の充実した家賃補助制度などを参考にしつつ、クリニックの規模で可能な範囲での支援を考えます。例えば、「交通費の上限を少し引き上げる」「近隣のコインパーキング代を一部補助する」「自転車の整備費用として年一回手当を支給する」など、薄く広く、しかし応募者にとって少し嬉しいと感じるような制度設計が考えられます。
- 処置手当は“件数の目安”とセットで:例えば、「1日の採血件数が〇件を超えた場合は、1件につき〇円の手当を支給」といったように、短時間勤務の中でも達成可能な目標と連動した手当を設定することで、仕事へのモチベーションにつながる場合があります。
よくあるつまずきと対処
- 「午前だけの募集では、なかなか人が来ないのでは?」
- 実際には、医療系の求人サイトでは午前のみのパート求人は非常に多く掲載されており、その働き方を希望する層は一定数存在します。検索条件としても定着しているため、勤務時間や業務内容といった条件の提示が明確であれば、応募につながる可能性は十分にあります。
- 「ブランクが長いことを心配して、応募がない」
- 前述の通り、看護協会などが実施する復職支援研修の存在を求人票で知らせたり、採用後の研修体制や、見学時の丁寧な説明をセットで記述したりすることで、応募者の安心感を高めることができます。
- 「家庭の事情による急な欠勤に対応できるか心配」
- あらかじめ、看護スタッフが複数名いる体制で、お互いにシフト交換が可能であるといったルールや、学校行事などの際の休日取得ルールを明示しておくことが有効です。また、当日の連絡方法(まずは電話、その後チャットツールで詳細を共有するなど)のフローを具体的に決めておくと、現場の混乱を最小限に抑えられます。
- 「短時間勤務のスタッフには、責任ある業務を任せにくい」
- 病院における短時間正職員制度の事例が参考になります。3〜4時間といった短い時間の中でも完結する“ひとまとまりの仕事”として業務を切り出し、その役割と責任範囲を明確にすることで、短時間でも主力として活躍してもらうことが可能です。
まとめ|“来やすさ”を設計し、言葉にする
採用活動は、単に人を募集することではなく、クリニックの“働きやすさ”を設計し、それを的確な言葉で伝えるプロセスです。
- 地域:駅からの距離、利用できる路線、学童保育施設との位置関係、駐輪・駐車の可否といった、物理的な“来やすさ”を求人票の冒頭で具体的に示します。
- 時短:午前のみ、土曜午前、週1日から、といった柔軟な勤務枠を設け、担当する業務の具体的な件数や、一日の仕事の流れまでを言語化します。
- 両立:学校行事や子どもの急な発熱といった、家庭を持つ人が直面する現実的な課題に対し、職場のルールとしてどのように対応するかを、事前に提示します。
- 支援:住宅、保育、移動といった側面で、大規模な福利厚生は難しくても、小規模な“ミニ補助”を用意することで、応募を後押しします。
- 復職:公的な復職支援研修の存在を伝え、採用後の受け入れ体制を丁寧に説明することで、ブランクのある方の不安を和らげます。
採用は“量”よりも“適合”です。応募者の持つ、時間、生活、通勤といった現実的な制約を理解し、そこに適合するような働き方の選択肢を提示できれば、小規模なクリニックであっても、必要な人材を確保することは十分に可能だと考えられます。看護職員の離職率や有効求人倍率といった統計データが示す採用環境の厳しさは、一つの事実として存在しますが、自院の採用活動における設計と、それを伝える記述の工夫によって、応募者の働く動機を喚起することはできるはずです。
クーラ導入誘導|“まずは数回のお試し勤務”から始める
面接だけで採用を決めることに不安がある場合や、まずは実際の職場の雰囲気や業務の流れを体験してもらってから本格的な採用を考えたい、というケースもあるかと思います。クーラは、そのようなニーズに応えるためのサービスです。
- 面接だけで決めない採用:まずは1回から4回程度の短期アルバイトとして“お試し勤務”をしてもらうことができます。実際の仕事ぶりや他のスタッフとの相性などを確認した上で、その後の長期的な継続勤務について相談することが可能です。
- 時短・午前のみからの設計:午前診察の時間帯だけ、土曜日の午前中だけ、といったように、応募者の生活事情に合わせた短時間の枠を最初から設定しやすいため、お互いのミスマッチが起きにくい運用が期待できます。
- 現場の負担を増やさない受け入れ:受け入れ時の業務は、通常の外来業務の流れに沿って、短時間で完結するように設計できます。ブランクのある方の受け入れにも適しています。
地域に根ざした短時間勤務の採用を、実際の勤務を通じて、無理なくスムーズに始めたいとお考えの際は、クーラの“お試し勤務”からのスタートを検討してみてはいかがでしょうか。より詳しい情報やお問い合わせについては、下記のクーラの事業者向けページをご覧ください。
参考にした公開情報(抜粋)
- 医療業界の有効求人倍率の概況:厚生労働省「一般職業紹介状況」、株式会社レイヤード
- 地方都市の雇用環境や優遇制度の紹介:Nurses Works
- 看護職員の離職率など:日本看護協会「2023年 病院看護・外来看護実態調査」
- 「午前のみOK」等の求人掲載の実態:コメディカルドットコム
- 子育て中の看護師の働き方・クリニック勤務の実情:医療21、訪問看護ステーション みもざ
- 住宅・保育等の福利厚生事例(病院・自治体):愛知県がんセンター
- 短時間正職員制度の実践報告:大分県立短期大学紀要
- 看護師の復職支援研修に関する情報:各都道府県看護協会ウェブサイト






.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)



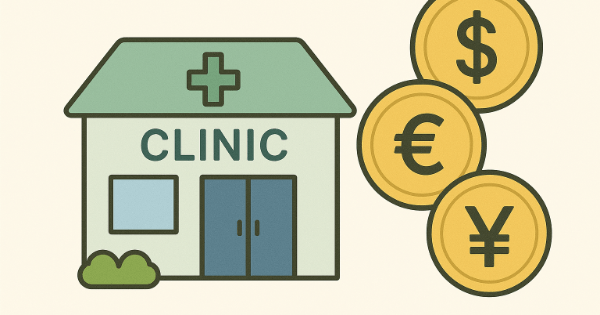
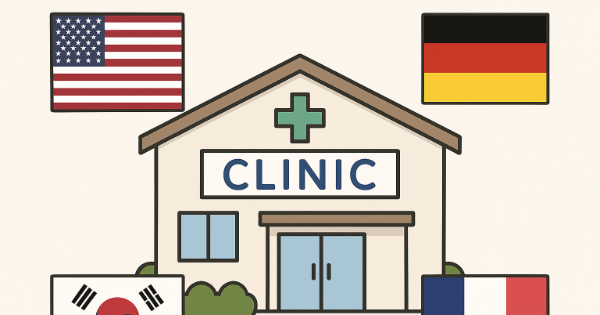
![看護師採用で“最低限ここだけ”の個人情報・マイナンバー取扱いガイド[保存期間・収集タイミング・委託時の注意点まで]](https://cdn.prod.website-files.com/640d966ca29de959e9f69b68/68d3f0cd471eb4dccfe97c23_ChatGPT%20Image%202025%E5%B9%B49%E6%9C%8824%E6%97%A5%2022_22_13-min.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
%201.png)
